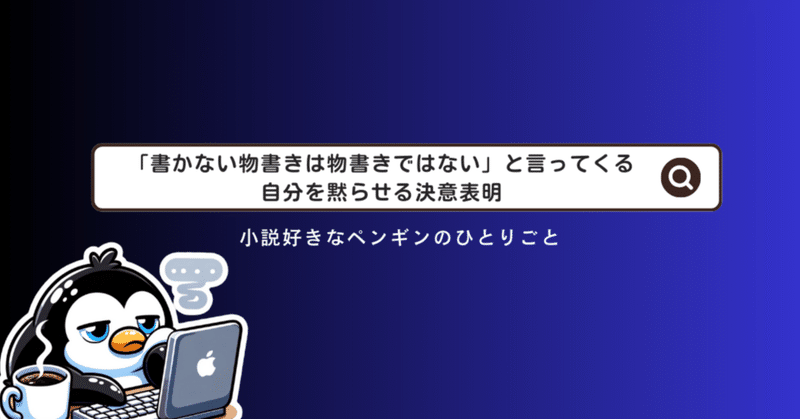
「書かない物書きは物書きではない」と言ってくる自分を黙らせる決意表明
そういうことを思いました。
※本記事は私の思考の整理のために書かれたものです
おはようございます。りさきりです。最近は会社でもすっかり「りさきりといえばペンギンだよね」という共通認識になってきており、私のデスク周りはちょっとした南極になっている訳で。
すこし脱線(レールは地続き)
別にペンギン好きキャラで売り出していたつもりはないけれど、方々でペンギンの話をしたり「確認しました」のスタンプがペンギンだったためにそうなってきたのかなと思っています。
ですが、もっとも重要なことは私は無類のペンギン好きではないという事実ではないでしょうか。
ペンギンをアイコンにしているのは、辛い時にペンギンの笑い声が放たれる動画にお腹がよじれるほど笑わせてもらったからで、それ以降ペンギンを見ると大抵の事は笑い飛ばせるようになるんだろうなって思い出せるからで。
認識は自由でいい。けれど……
話が脱線しましたが、核心はといえば「会社の皆さんの中にある私の好きなもの」と「私が心の内だけで知っている私の好きなもの」にギャップが生じていることです。
認識の齟齬と表現すればちょっと仰々しいですが、この構造は中身を変えても成立しえると思います。
たとえば「私は私を無類のペンギン好きだと思っている」と主張していても、会社の方たちが私のことを「あいつは無類のペンギン好きを自称しているが、でもペンギンのことほとんど知らないよね」という認識を持つようになれば、自意識と他者の認識にギャップが同様生まれます。
これを受けて、「それでもペンギン好き」って名乗って良いじゃないか!というのが最近の風潮でしょうか。
りさきりも思います。好きに生じる差は程度でしかないですし、その基準は個人に委ねられるべきものだと思うからです。
しかし、これが小説に――あるいは物書きとしての存在の話になってくると、私の立場は一転します。
自己に内在するただ一人の辛口なファン
先の構図を引っ張り出してきて、その対立をいずれも私の意識に置換します。するとこういうことが起きる訳です。
私は「自分のことを物書きだと思っている」が、一方で「理由はあれど書いていないのだから物書きではない」
言わば、ここに存在する確からしい私という自意識と、それを手厳しくジャッジする辛口なファン。それらが混在し、やがて明確に分離して一方が一方の主張を粉々に踏み砕いていく。
物書きであることは私であり、使命であり、人生である――。
自我は確かにそう鳴いている。
けれど現実は耳を塞ぐように蓋をしようとする。私が私であることを拒み続け、平然と命を奪おうとしてくる。
だから物書きたちは抗う。戦う。書きたいのに何らかの事情で書けなくなっていく。人生に孕まれた矛盾に葛藤を抱える。自分の胸倉を掴みたくなる。
そうして疲弊してきたところで、冷静なもう一人の自我がこう言うのだ。
「お前はもう物書きではない。だって書いていないんだから」
この過程、あるいは事象が、私にはどうしても辛かった。
書けずに奥歯を噛んでいるのは他でもない私自身なのに、そんな私にさえ私は現実で叩きのめすのかと。
「そうしなければいい」
ええ、ごもっともです。それができるなら最初からそうするでしょう。
でも私は、物書きという内側の私が現実と相対している時は、真実から目を背けることはありません。
目標が数値で出るのなら、目標は達成か未達かのいずれかでしかない話と似ています。
結局は「程度」に対する認識の問題
とはいえ、ここで「誰がなんと言おうが私は物書きである!」と言えたらそれでいいのです。書いていなかろうが原稿が進まなかろうが物書きであると胸を張って言えるのであれば何も問題はないのです。
本来であれば、これだって「好き」と同様、程度の話でしかないはずでしょうから。1日原稿から離れれば物書き失格だと考える人もいれば、10年後でも書くことをやめていなかったら物書きであると考える人もいる。そういう話に過ぎません。
つまるところ、私は「私自身に求める物書きの在り方」と、それを許さない現実との間に生じる歪に苦しんでおり、その歪をつついて「お前は物書きじゃない」とキックしてくる『辛口なファン』を受け入れるしかないほど、執筆活動に資源を投下できていない現状に見舞われているのです。
長いお付き合いになりそう
さらに重要なことは、その現状を受け入れたくない私がいることです。
でなければ苦しみませんし、こんなnote書かずにベッドでスヤスヤ寝ていることでしょう(時刻6:49)
けれど、できることは限られていて、現実は簡単には変わりません。
仕事をすぐに辞めてしまうのも、生活をほっぽりだすのも、地元に帰って部屋に引きこもるのも。
やろうと思えばできますが、それをしてもさまざまな問題に直面し、結局は執筆活動を断念せざるを得なくなることも理解しています。
だからこそ、私は、私たちは、その問題の原因を解消できるようにアクションしていかなければなりません。
求める作家像に近づくために、求める物書き像に近づくために、そして最たる目的――小説を書き続けるために。
私は、今日の私にできる精一杯をしようと思います。
長くなりましたが――そんな決意表明でした。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
