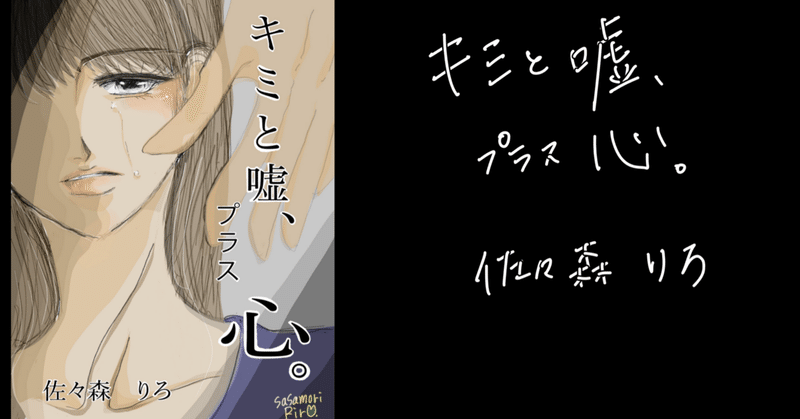
キミと嘘、プラス心。11
第十一章 明かされる
喫茶店「鈴蘭」でキヨミを初めて見た時、どこか寂しげで悲しそうな雰囲気を纏った、とても綺麗な女の子だと思った。
カウンターの椅子に慣れないように座ってから、マスターの言葉に耳を傾けている。
出されたコーヒーを砂糖もミルクも入れずに口にしたけれど、苦そうにはしていない。普段から飲み慣れているのだろう。そう感じた。
不思議な雰囲気の彼女から、目が離せなくなってしまっている自分に驚いた。
父からされる婚約の話から逃げるように電車を乗り継ぎ、こんな何のゆかりもない場所まで一人で来てしまっていた。
引き寄せられるように入ったこの喫茶店「鈴蘭」はとても落ち着けた。なんとか、仕事のことを冷静に考えられるくらいまで頭が働くようになった。
マスターにお礼を言って店を出る。窓際の席に移動した彼女の姿が外からぼんやりと見えた。
もうここへ来ることもないだろう。
彼女に会うこともないだろう。
そう思うと、少しだけ寂しいなんて気持ちが、心の片隅に落っこちてきた。
マスターの人柄の良さに感謝しつつ、僕は東京へと戻った。
冬が過ぎ、春が来た。
相変わらず父の決めた婚約者の江莉から食事の誘いが来る。断り続けても良くないと何度か会ったりもした。けれど、その度に浮かんでくるのは、あの時会った彼女の寂しげな横顔だった。
彼女は今も、寂しそうにしているのだろうか? どうして、あんなに悲しい目をしていたのだろうか。
考え始めると、途端に頭の中を彼女が支配してくる。なにも分からない、たった一度だけ、見知らぬ土地で顔を合わせただけなのに。
また、あの時と同じ季節がやってくる。
仕事終わりに車で移動中、車窓から見えた光景に僕は思わず息を呑んだ。慌てて運転手に車を止めるように頼む。
あの時の彼女と似た、空を見上げる横顔を見つけた。
この広い世界で、行き交う人の多い都会で、ただ一人、キミだけが、僕には輝いて見えた瞬間だった。
きっと、この再会には意味がある。
そう思いたかった。偶然なんかじゃなくて、必然なんだと、ずっと思っていた。
あの日以来の再会に、僕のことを覚えている保証なんてどこにもないから、キミに対してどう接したら良いのか分からなかった。だけど、そんな僕に、キミは戸惑いつつも、優しい笑顔をくれた。
ガラの悪い男に絡まれていたキミを助けようと警察を呼ぶ。すぐに逃げていった男に安心していると、踵を返していってしまおうとするから、思わず呼び止める。
けれど、全く振り向いてもらえない。やっぱり、キミは僕のことを覚えてはいなかったんだと、ガッカリした。
だけど、この再会を無にしたくなくて、キミを追いかけた。
朝からろくにご飯も食べずに仕事に明け暮れていたから、情けないことにキミとちゃんと話す前にお腹の虫が鳴る。呆れたような顔をして笑った君が、僕にくれたのはすぐそばにあったコンビニから買ってきた、熱々の肉まんだった。あまりにも熱くて、なによりも美味しかったのを今でも忘れない。
キミと過ごすようになってからは、キミが作ってくれたご飯がとても美味しかったのを思い出す。毎日、僕のマンションの広い部屋で一人待っていてくれるキミに、早く会いたくて、抱きしめたくて、時には仕事さえも忘れてしまうほどにキミに夢中になった。
大好きだった。
だから、キミと生きることを、僕は選んだんだ。この先もずっと一緒にいたい。なにがあっても、そばにいてほしい。
僕がキミのことを、一生かけて、守っていきたいと、心からそう思ったんだ。
「ユウくん、ごめんね」
真っ白な霧の中、キヨミが涙を流しながら遠くなっていく。追いかけても、追いかけても、追いつくこともキミを抱きしめることも、触れることすらも出来ずに、ただ、あの時と同じ。
さみしそうに、悲しそうに、キミは泣いているんだ。
勢いよく目を見開いて上体を起こした。
全身ぐっしょりと汗が滲む体が小刻みに震える。
ポタリと頬を伝って、流れた汗が布団に落ちてシミを作った。
もう何度目だろうか、この夢を見るのは。
キヨミに会いたくて、会いたくて。
どうしようもなくて。キミに一目でも会うことができたなら、この気持ちも諦めることができるのかもしれないのに。
夢の中のキミは、どうしてそんなに悲しんでいるんだ。僕と離れて幸せならそれで良いのに。こんな夢を見せられてしまうと、キミにどうしようもなく会いたくなる。
「僕に、その涙を拭ってあげることはできないのか……」
額に手を当てて、悔しくて涙が込み上げてくる。
深いため息を吐き出してカーテンを開けた。
沈みきった気持ちとは裏腹に、空は清々しいほどに晴れ渡っている。
昨日会ったキヨミの弟のことを思い返した。
奥田グループに勤めていたとは、世の中本当に狭いものだ。
ベタつく体をシャワーで洗い流して、適当な朝食を取る。キヨミがいたころには色とりどりの野菜サラダやフルーツ、日替わりのスープ、厚切りトーストにたっぷりのチーズとハムを乗せて食べたり、ご飯に焼き魚や卵焼きと和食だったり。キヨミは料理が上手だった。幼い頃に母親を亡くして父親と二人。父親が仕事で遅くなることはしょっちゅうだったから、キヨミはご飯の支度をするのが当たり前だったようだ。
キヨミの作った料理が食べたい。素直にそう思いながら、なにものせることのないトーストを齧る。
キミと過ごした夏を、思い出してみようとする。けれど、忙しさを理由に僕はただキミが笑って家の中で待っていてくれることだけが、幸せだと思っていた。だから、夏だからと言って特別になにかをしたかなど、正直覚えていない。
唯一、「今日は暑いから食欲もないし、私は先に軽く済ませたの。ユウくんは仕事で頑張ってきたんだから、たっくさん食べてね」そう言って、少し青白い顔をしていたキヨミのことを思い出す。
心配はしたけれど、元気に見せてくれる振る舞いに、僕は安心していた。
あの時、なにか不安でもあったのだろうか?
今となって聞いてみればよかったなど、後悔しても、もう遅い。
僕になにか非があったのかもしれない。
僕はキミに不満など、なに一つなかった。
優しすぎるほどに、キミは僕のことを優先して考えてくれていたから。その優しさに、ずっと甘えていた。
まさか、キミがここから出ていくことになるだなんて、考えもしなかったんだ。あの頃は。
思い返せば、キミの横顔がまた悲しみの色を纏い始めていることに、僕は気が付いていたはずだ。
気が付いていたはずだったのに。
キミはもうどこにも行かないと、僕の手の内にずっといるんだと、なんの根拠も確信もないのに、自信過剰になっていたんだ。
こんなに未練がましいなんて、キミが知ったら呆れられてしまうのかもしれない。だけど、僕はキミのことを心から、愛しているから。
一口だけ口にしたトーストを皿に戻すと、スマホに入っていた仕事のメールを確認する。
と、同時に、江莉からのメッセージが届いていることに気が付いて、ため息を吐き出した。
》おはようございます。
今晩、優志さんのお父様と一緒に食事会を予定しております。ぜひ、優志さんもいらしてください。よろしくお願い致します。
毎回、丁寧な言葉を並べてくる。
僕は、キヨミのフレンドリーな話し方が好きだ。僕のことを決して大企業の息子だと一線を置いたりしない。コンビニの肉まんも、自動販売機の缶コーヒーも、全部キヨミが教えてくれた。
僕はキミよりもずっと年上なはずなのに、たまに説教だってされた。だけど、キミは怒っていても僕のことを想ってくれていたし、最後は必ず笑顔をくれるんだ。
また今日も、キヨミが笑ってくれた。それだけで、僕の生きている意味がある気がして、幸せだった。
突然、スマホのコール音が鳴り始めた。
画面を見れば〝父〟の文字。こんな朝早くに珍しい。
パタッバタバタッ……と、同時に、大きめの雨粒が窓枠を叩き出した。先ほどまで清々しいほどに晴れていた青空が、いつの間にか薄暗い灰色に支配されている。
胸騒ぎがする。不安が募り始める着信に、ゆっくりと僕は応答した。
「おはようございます。優志です」
冷静に、落ち着いて、いつも通りに言葉を発する。
「おはよう。優志、この前お前の話していた、女性の名前を……教えて、欲しい」
スマホの向こうの父の声の方が、震えている気がした。
「……え、キヨミのこと、でしょうか?」
父にキヨミのことを聞かれるなんて、思ってもみなくて驚いたと同時に、嬉しくもある。
「昨日、奥田グループの社員が持ってきた封筒の中に、その女性のことが書かれた記事や資料が入っていたんだ。優志はこのことを、知っているのか?」
「……え?」
昨日の封筒。孝弥くんが持ってきたもののことだろうか。それなら、中身など確認していないし、そもそも、奥田グループとの関わりなどキヨミは一切ないはずだ。それなのに、キヨミの資料? どういうことだ?
「永田キヨミさん、二十八歳。六月に交通事故で死亡しているようだ」
父から出たキヨミの名前。年齢。そして、交通事故で、死亡……? キヨミが、亡くなっている?
「嘘……です、よね……」
一気に全身の力が抜ける。手にしていたスマホがフローリングに真っ逆様に落ちていった。脱力した体は椅子に座ったまま動くことができなくなる。
スマホからわずかに父の声が聞こえてくる気がした。そんなことよりも、今は。
「どうして⁉︎ なんでだよ‼︎ どういうことだ⁉︎」
頭の中が混乱する。
今まで発したことのないくらいに大きな声が喉の奥から湧いて出た。
ぐるぐるとこれまでの記憶をかき混ぜられている気分だ。僕はなにをしている。
どうして、キヨミに会いたいと思うばかりで、キヨミに会えずに今日まで来てしまったんだ。キヨミの事故は六月? 何日だ? どうしてそうなった? 誰が関わっている? 単独か? 巻き込まれか? 事故か? 事件か?
渦巻く思考に耐えられずに、頭を両手で抱え込んで叫んだ。
「あああぁぁぁぁぁっっ」
──キヨミさんは、ちょっと遠くに行くって、当分帰らないって言ってましたよ
──あんな田舎の女なんて、どこが良いんですか? 百代の方がまだマシです
── 言っておきますから、任せてください
あれは、みんな嘘だったのか?
どうして? 雨宮さんも、江莉も、孝弥くんも、どうしてみんな嘘をつく?
どうして……?
意識的に、拳を振り上げて一気に叩き落とした。鈍い音を立ててトーストの乗った皿が割れた。指の間から、血が滴り落ちて来る。感覚だけは、感じている。
呼吸が早く短くなる。苦しい。考えれば考えるほどに分からなくなる。
ただ一つだけ。父の言葉が本当なら、キヨミはもう、この世には、いない。
前回までの話はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

