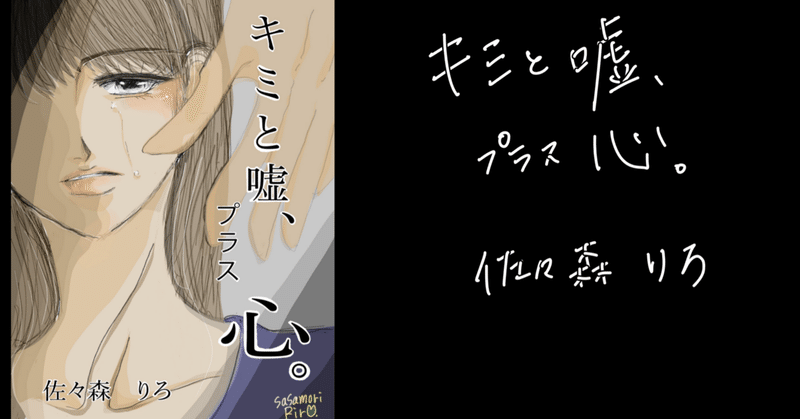
キミと嘘、プラス心。16
第十六章 再会の日
自分がこの先どうしたいのかとか、何をしたいのかとか、考えてみても何も思い浮かばなくて、途方に暮れるばかりだった。
母を小さい頃に亡くして、父と二人暮らし。そんな父も母のことを忘れてしまったのか、別の女の人と結婚すると言い出した。別に反対はしなかった。父は優しいし、その女の人といると幸せそうに見えたから。その人には、私と同じように連れ子がいた。
孝弥はとても素直で元気がよくて、私に懐いてくれた。かわいい弟ができたことは日々の救いだった。
そんな折、どこか、私のことを誰も知らない場所に行きたい。
ふと、そう思うようになった。
ふらりと正気を失ったように歩き続けていた私は、何かに導かれるように町外れの草が蔦のように生えて絡まる、ブロック塀の前で立ち止まった。看板や表札などないけれど、同じように蔦が絡みついた柵に視線が止まる。片方だけが開いていて、まるで入っておいでと誘っているような入り口門に、迷うことなく足を踏み入れた。
周りは蔦だらけだけれど、足元の石畳はきちんと奥の玄関まで綺麗に整備されていた。途中で、蔦が絡まった看板が目に入る。
鉄製のアンティークな模様で囲われた看板には〝喫茶 鈴蘭〟と描かれているのがなんとか読み取れた。
ようやく見えたのは、小さな洋館のような佇まいの建物。
重そうな木の扉を引いてみると、すぐに目に入ったのは白髪まじりの長髪を後ろで一つに結んだおじいさんと呼ぶにはまだ若いような男性マスター。
「いらっしゃいませ」
にっこりと微笑まれて、思わず顔に熱が上がってしまう。
どうしてここへきたのかも分からないくらいに、無意識に足が向いていた。入ってしまったからには、今更出て行くことも出来ない。
「今日はめずらしい。こんな寂れた喫茶店にお若い方が二人もいらっしゃるだなんて」
嬉しそうにマスターが言った。「どうぞ」とカウンター席へと手を差し出されて、私は素直にそこへ座った。
「お二人は知り合いでは?」
先に来ていたスーツ姿の男性が、奥の席に座ってコーヒーカップを持ち上げたところだった。
お互いに目が合って、見知らぬ顔に同時に「いえ」と首を振る。
スーツ姿で働く男性に知り合いなんていない。私は即答だった。きっと、彼もまた、制服姿の女子高生など、知り合いなはずがないとでも言うように、困った顔で笑っていた。
「おっと、それは失礼いたしました。まぁ、でもこれも何かの縁かもしれません。今日の出逢いに私から一杯ご馳走させてください」
にっこりと笑って、マスターはコーヒーを入れ始めた。
穏やかな音楽がようやく聞こえてきた頃、スッと差し出されたコーヒー。お砂糖とミルクのポットが横に添えられた。
「ありがとうございます」
小さく頭を下げて、私はお砂糖もミルクも入れないままカップを口に運ぶ。
酸味のある苦さがゆっくり細く喉を通っていく。
いつからか、コーヒーにはお砂糖もミルクも入れなくなっていた。
自分を甘やかしたくなかったから。
苦味には慣れたけれど、コーヒーを飲むと無性に寂しくなってしまう心はいつになっても消えない。
亡くなった母が飲んでいたことを、思い出すからかもしれない。
もう少し落ち着いていたいと思い、カウンター席からおりて、窓側の外が見える席に変えてもらった。
先ほどいた男の人は、私が席を移動する時に帰って行った。柔らかい笑顔をする、どこか都会っぽい洗練された雰囲気を纏っていて、この辺りでは見かけない人だと思った。それが、とても格好いいとも思った。
ゆっくりと時間が過ぎていく。
何も考えなくていい。誰にも邪魔をされない。ぼうっと、ただ時を過ごすのにとても有意義な時間だった。
東京にでも、出てみようかな。
なんの気無しだった。目標も目的もなく。ただの好奇心だけだった。
父も母も一度は止めたけれど、賛成してくれた。孝弥にも、笑って送り出された。
私は初めて、一人になった。
誰にも頼れずに、周りは知らない人ばかりで、すれ違っても挨拶どころか目も合わない。
華やかなのは街の明かりと騒がしい雑踏。こんなにたくさんの人で溢れかえっているのに、寂しい場所だと思った。
ピッ。機械音と取り繕われた笑顔の店員。毎日会っているはずなのに、心が通うことはない。あの人は、ロボットなんじゃないだろうか。なんて想像して、一人スーパーからの帰り道を歩く。吐き出す息が随分とつめたくなった。
上京してきて初めての冬。
東京でも、雪は降るらしい。
見上げたけれど、その先が空なのかビルの壁なのかがよく分からない。
「ねぇ、お姉さん」
立ち止まっていた私に声をかけてきたのは、ジャラジャラと鎖のようなアクセサリーを身に纏った見るからに危険信号が点滅し出す人物だった。
「ここ行きたいんだけどさぁ、道に迷っちゃって、一緒に連れてってくんない?」
くしゃくしゃになった変なチラシをちらつかせて、男が迫ってくる。
上京したての私に道を聞くことが間違いだ。この人の方が、絶対に私なんかよりもこの辺に詳しそうな風貌だ。
聞くのはいいけれど、一緒に行くなど意味がわからないし、そもそもどこかも分からない。
右や左を向いても、道ゆく人は目的に向かって一心に足早に去っていく。とても「助けて」なんて言える状況ではない。
こんなところで、立ち止まっていた私が悪かったんだ。
「え、と。私上京したてでこの辺りがよく分からなくって、すみませんが別の方か警察に……」
「は!?」
一刻も去りたい一心で向きを変えた私の腕を、男が掴んできた。
「いっ……!!」
ギリリと食い込むように掴まれて、痛さと恐怖で声も出てこない。
湧き上がる涙が溢れそうになった瞬間、急に男は私の手を離して舌打ちをすると、どこかへ走り去って行ってしまった。
訳がわからずに俯いていた顔を上げると、スーツ姿の男の人が数人、私を取り囲っていた。
まるで、守ってくれているみたいに見える。
「もう大丈夫ですよ。警察呼びましたから」
にっこり笑いかけてくれる男の人に、私は見覚えがある気がした。
「もしよければ送りましょうか?」
道路に横付けされた、見るからに高そうな車と護衛のような人たち。明らかに普通じゃない状況にまたしても恐怖を覚えた。
「い、いえ、大丈夫ですので」
買い物袋を持ち直して、私は歩き出す。
ガラの悪い人は確実に怖いけれど、今の人だって良さそうな顔をしていても、あれじゃあやっていることが一緒だ。車に乗ったら最後。どこに連れて行かれるか分からない。
しばらく歩いてから、ふと立ち止まった。
後ろからの足音も、同時に止まる。
再び歩き出すと、後ろの足音も聞こえ出す。
え、ちょっと待って。これって、絶対につけられてる?
一気に心拍が上昇して、早足になった。だけど、これじゃあ家まで持たない。息切れし出した呼吸に胸を掴み、思い切ってそのままの勢いで振り返った。
「わ!」
やっぱり! さっきの男の人が後ろにいて、背筋がゾッとしてしまう。
「なんなんですか! ついてこないでください!! あなたこそ警察呼びますよ!!」
大きな声の私に慌て近づいてくる男。恐怖とずっと緊張しながら早足で歩いてきていたからか、もう膝がガクガクしてしまって動けない。
「す、すみません……でも、僕っ」
目の前まできて立ち止まった男のお腹の音だろうか? ぐうぅぅぅぅっと、鳴り響いたのが耳に入ってきて、私は大きなため息を吐き出した。
「ちょっと待っていてください」
飼い犬に待てをするような感覚で手のひらを突き出すと、近くのコンビニへと入った。ちょうど私もお腹が空いていたし。
レジに並んで肉まんを二つ注文する。
外に出ると、さっきと全く同じ場所に彼は立って待っていた。
「はい」
「……え?」
「これ、さっき助けてくれたお礼です。これあげるから、もうついてこないでください」
いつまでもぽかんとして肉まんを受け取らないから、イラっとして開いた口に突っ込んでやった。
「ふぁ!?」
「では」
「え、あ、ちょっと、ま、あっつ!」
深々頭を下げて去ろうとする私を、引き止めようとする彼の慌てた姿に、思わず笑いが込み上げてきてしまう。
「うっわ、美味しい。これ、めちゃくちゃ美味しい!」
振り返ってみると、肉まんの湯気の間から、満面の笑みで興奮するようにはしゃぐ彼の表情に、堪えきれずに笑ってしまった。
「ただの肉まんですよ」
「へぇ」
へぇって。
物珍しそうに手にしている肉まんを眺めている目の前の人に不思議に思うけど、なぜだろう、不信感が薄れていく。
「あの、鈴蘭で一度お会いしてますよね?」
「……え?」
「きっと、キミから貰ったものだから、こんなに美味しく感じるんだ」
道の真ん中。嬉しそうに肉まんにかぶりつく彼の姿は、私にしか見えていないんじゃないかと思うくらいに、明るく輝いて見えた。
これが、私とユウくんの再会の日。
私は、この日からどうしようもないくらいに彼に惹かれていった。
私と彼が釣り合わないことなどとっくに知っていたから、ただそばにいられたらそれで良かった。私はそれが幸せだった。
ユウくんのそばにいられたことが、一番の幸せだったんだよ。だから、私はあなたから離れたことを、後悔していない。
第十七章に続く↓
前回までの話はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

