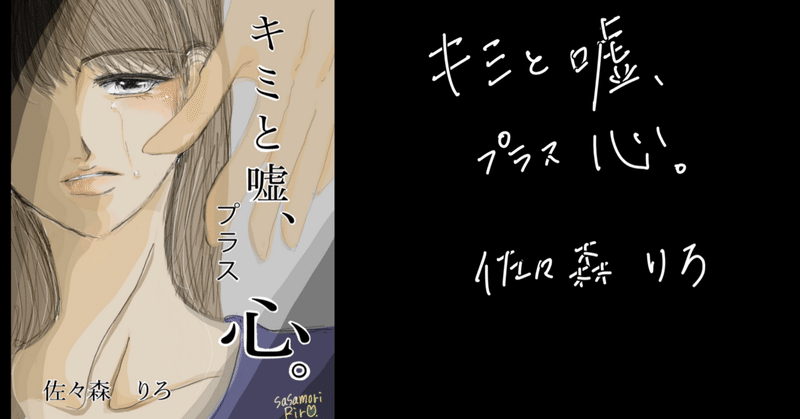
キミと嘘、プラス心。12
第十二章 接触
不穏な空気が流れる空間で、あたしは空を見上げた。真っ黒に渦巻く雲は狭い空でも存在感を目立たせている。
モヨも孝弥も、キヨミさんという大切な人を失った悲しみは同じなんだと思う。大切な人を失う悲しみ。
ふと、凌二のことが頭によぎった。
大切だった。とても。本当に大好きだと思っていた。それなのに、また会いたいとは、思わない自分がいる。
薄情だろうか? 他に好きな人ができた凌二が悪いんだと凌二のせいにして、自分には非がないと思い込んでいた。
そのうち、思い出すこともやめた。そうしたら、気持ちが軽くなったんだ。こうしてたまに思い出してしまうのは仕方がない。脳内には記憶があるから、少しずつ新しい記憶を更新していけばいい。前向きになるって、そういうことなんじゃないかと思った。
モヨも孝弥も、きっと同じ場所から前に進めていない気がする。
あたしの失恋とは、訳が違う。
孝弥にとっては大切な家族。モヨにとってはかけがえのない自分を認めてくれた人。
想いが強すぎて、あたしにはなにもかけてあげられる言葉がない。
絶望にも似た考えにため息を吐き出すと、テーブルの上に置いていたスマホが震え出した。すぐに視線をそこに落として着信表示に現れた名前に驚いた。
それは、孝弥も同じ。向かい合っていた孝弥から、あたしのスマホの画面がよく見えたらしい。目元を拭いながら、驚いたように、怪訝な表情をむけてくる。
「ちょっと、出てくる……ね」
スマホを手にして、あたしは席を立った。
表示されていたのは、沖野さんの名前。入り口付近の空きスペースに立ち、あたしは着信に応えた。
「はい、雨宮です」
着信が切れる前に通話に出たつもりだったけれど、向こうからはなにも聞こえてこない。入り口の開け閉めで、聞こえてくる雨音の方がうるさいくらいに耳に響く。
「……あの、沖野さん? ですよね」
恐る恐る、尋ねてみると、ようやくわずかに声が聞こえてきた。
『……っ』
聞き取れないくらいの声量に「え?」と聞き返すと、ようやくなにを言っているのかが分かった。
『今日、すぐにでも、会えません……か?』
「え……」
『東京にはもう着いていますか? もし着いていましたら迎えに行きますので。駅でも、どこでも、雨宮さんのいる場所さえ教えてくださればすぐに向かいますから、だから──』
「え、あ、沖野さんちょっと……」
どうしたんだろう。落ち着いて見えていた姿からは想像もできないくらいに取り乱しているような声に、あたしは怖くなる。
本当にこの人は、沖野さんなのだろうか? とまで、疑ってしまいたくなるほどに。
『今、どちらにいらっしゃいますか? 教えてください。お願いします……』
捲し立てる様に話し出したかと思えば、今度は消えそうなほどに弱々しい声で悲願してくる。こちらまで、胸が掴まれた様に苦しくなった。
通話を終えて二人の所へと戻ると、深刻な表情で会話をしているのは変わらないけれど、先ほどまであった不穏さは、和らいでいるような気がした。
今の着信が沖野さんからだということを知った孝弥は、あたしが元の席に座ると落ち着かないように視線を泳がせている。
「今のって、優志さんからだったの?」
モヨが孝弥の代わりに聞いてくるから、あたしは小さく頷いた。
「今から、会えないかって」
「……え」
「なんだか、ひどく混乱しているような感じだった」
姿が見えないのに、声だけで伝わってくる、なにかあったんじゃないかと思わせるくらい悲痛な声色。
もしかしたら、キヨミさんの死を知ってしまったんではないだろうか? 瞬時に頭の中をよぎった。それしか、あの人をあそこまで動揺させるようなことはないのではないかと、胸が騒ぐ。
「え、会うの?」
モヨが戸惑って俯いてしまったあたしに聞いてくるから、また無言のまま小さく頷く。
「ここの場所、さっき教えたら迎えにくるって」
「え……ここに、来るってこと?」
「……たぶん」
あたしが今いる場所、このお店の名前がフレーバフルだと伝えると「向かいます」と一言発して、沖野さんとの通話は終了した。
のんびり紅茶を飲んで、ケーキを食べている場合ではなくなった。どうやってキヨミさんのことを沖野さんへ伝えたら良いのか、考える間もなくなってしまったのかもしれない。
もし、沖野さんがここへ来て、どうしてあの時嘘をついたんだと責められたら、一体、あたしはなんと言ってその質問の答えに導いたら良いのだろう。
なんの考えもなしについ出てしまった言葉だった。
そんなことで、果たして沖野さんは納得してくれるだろうか? いや、先程の電話での声を思い出すと、そんな簡単なことではないだろう。
「……沖野さん、姉ちゃんが死んだこと、気がついたのかな」
ずっと無言で不安そうな瞳を泳がせていた孝弥が、消えそうな声で呟く。
「あの人、どうなるんだろう」
あたしの頭の中にも、同じ言葉が浮かんだ。
それは、モヨも同じかもしれない。互いに目を見合った。
こちら側は、キヨミさんの事故や死をすでに受け止めている。その上で、やりきれない切なさや無念を引きずって悩んでいる。
だけど、沖野さんは、やっと今、キヨミさんの死と向き合うスタートラインに立ったところだ。
いや、それはまだ分からないけれど、もし、そうだったとしたら、今の彼は、どうしようもない、どこへも向かえない気持ちを抱えたまま、ここへ向かっているのかもしれない。
彼は、あたしを、孝弥やモヨを、責めたりするのだろうか。あたしたちに向かってどうしようもない悲しみを怒りとしてぶつけるのだろうか。
それで、気持ちが済むのなら、あたしはそれでも構わない。責められる覚悟を決めなくてはならない。むしろ、嘘をついたのはあたしだ。
責めて、罵倒して、泣き叫んで、それでキヨミさんの死を受け止めることができるのなら、あたしは、それを受ける覚悟を決める。
外は、まだ雨が降っている。
まだ昼間だと言うのに、夕方のような薄暗さを纏う窓枠の向こうが、どこか現実じゃないような気がした。今ここにいる自分が、ただの都会の景色の一部だったら良いのに、と願ってしまう。
孝弥もモヨも視界に映らないほどに、現実から目を背けて遠くを見つめる。
ブッと、震え出したスマホに瞬きをした。
濁って霞んでいた視界が、一気に暗く、濃くなっていく。
「……はい」
『雨宮さんだけでは、ないようですね?』
「……あ、はい」
沖野さんの声に、あたしは驚いて店内を見回した。
『ああ、すみません。フレーバフルの向かいのパーキングに車を停めています。窓側に雨宮さんの姿が見えたもので。雨が強いので、まだ車内におりました』
外の雨音が、沖野さんの声と一緒にかすかに聞こえる気がした。
『あの、もしかして、一緒にいらっしゃるのは孝弥さんではないですか?』
「……え」
思わず、孝弥に視線を送る。
電話の相手が沖野さんだと察しているようで、孝弥は店内や窓の外を気にしだした。
時折、沖野さんのため息のような息遣いが聞こえてきて、さっき話した時よりは落ち着いた口調に聞こえているけれど、まだ声色は震えているような気がした。
「……そう、です」
『……あ、雨が上がりそうだ』
ふと、沖野さんの声が柔らかくなる。
あたしは窓の外、空を見上げてみた。
明るくなった灰色の雲が白さを増して、遠くの切れ間から光の筋が現れた。
ぽつりぽつりと窓を濡らす雨粒が反射する。天気は気まぐれ。心の闇なんてお構いなしだ。
泣きたい気持ちがあるのに、人前でなんて泣けないから、モヨも孝弥も雨に泣いてもらったような気がする。沖野さんは、大丈夫だろうか。
この空のように、雨と晴れの混ざり合った戸惑いの気持ちのまま、なんと声をかけたら良いのか、迷ってしまう。
『少し、話ができますか? ここではなんなので、良かったら皆さんで僕の車へ乗ってください。場所を変えましょう。待っています』
沖野さんからの通話を終えて、二人を交互に見る。
「どうなったの?」
不安げに、モヨが聞く。
何も言わないけれど、孝弥もテーブルの上で握った手を振るわせる。
「場所を変えて、話がしたいって。孝弥は時間大丈夫なの?」
ずっと眉間に寄せていた皺を緩めて、腕時計に視線を落とすと、小さくため息を吐き出した。
「ごめん、俺は戻らないといけない。本当はついていきたいけど、これから大事な打ち合わせがあるから」
沖野さんを探るように窓の外へ視線を向けながら、孝弥は眉を下げて悔しそうに言った。
「じゃあ、あたしが全部責任もって話してくるから」
モヨが真っ直ぐに孝弥を見つめて言うと、ようやく孝弥の表情が少しだけ緩んだ気がした。
「ありがとう、モヨ。だけど、モヨが責任を負う必要はないからね。俺もいずれあの人とはちゃんと話をしたいと思っているから。今は、姉ちゃんの真実をしっかり話して、そして、聞いてきてほしい」
「うん、分かった」
「頼むな、じゃあ、また」
孝弥の表情はまだ困惑していて、上手く笑えているようには見えなかった。
「モヨは、大丈夫?」
「……うん、大丈夫ではないけど、大丈夫」
困ったように笑うモヨに、あたしも上手くは笑えない。残っていた紅茶を乾き切った喉に流し込んで、席を立った。
店の外に出ると、水たまりのできた歩道に差し込んできた太陽の光が反射して眩しい。
一気に気温上昇。蒸し暑さに店内の涼しさからは一変して体が汗ばんでくる。
「……うわ、あつーい」
たまらずに手うちわで仰ぎながら、モヨがため息のように言った。
向かいのパーキングとは言っていたけれど、道路を挟んでビルとビルの間にはいくつかパーキングを示すPの文字が見える。どこへ行けばいいのか迷い始めた時、すぐそばで一台の高級車が駐車スペースに入ってハザードを付けて停まった。
車から降りてきたのは、あの時に会った時と同じ。スーツ姿で都会の背景が良く似合う沖野さんだった。
あたしとモヨの姿には気が付いている様子で、道路沿いに設置された機械を操作した後にこちらへと向かってきた。
「……雨宮さん、お久しぶりです」
すこし戸惑いながらも、沖野さんは笑顔を向けてくれた。あの時の笑顔とは、また少し違って、とても悲しそうに見えた。
「優志さん、ご無沙汰しております」
あたしが軽く会釈をした程度だったのに対して、隣に立っていたモヨが深々とお辞儀をしてから、真っ直ぐに沖野さんに向かって言った。
すぐにあたしからモヨへと視線を送った沖野さんの目が、見開いていく。
「……キミ……は」
モヨが沖野さんのことを知っていたように、沖野さんもモヨのことを知っているように感じた。
「……はい、百代です。姉が、いつもお世話になっております」
笑みのないモヨの表情に、あたしは背筋がゾクリとする感覚を覚える。
モヨは自分の名前が嫌いだと言っていた。それなのに、モヨになる前のモヨを知る沖野さんに分かってもらうには、そう自己紹介するしかないのだろう。
今の言葉は、モヨの中では一番吐き出したくない言葉。心の中で、きっと葛藤しているんだと思う。
「……江莉……さんの妹?」
「……はい、そうです」
沖野さんは混乱しているのか、あたしとモヨを交互に見てから、地面へと視線を落として力無く笑っている。
「なんだか、ますますよく分からなくなっている……すみません、雨宮さん。僕はいったい、どこから何を聞くのが正解なのでしょうか? あなたは、すべてをご存知なのでしょうか?」
俯いたまま震える声で聞こえてくる、沖野さんの声。
ポツリ。先ほど差し始めた日差しはとっくにまたかげって、今度は細い線を落とし始めた。
頬に、髪に、ぶつかりくる針のような雨が心の奥にまで刺さる気がした。
「ここでは、濡れてしまいますね……うちのオフィスに案内します。乗ってください」
深いため息を吐き出した後に、沖野さんが顔を上げて車の方に手を向けた。
モヨと視線を合わせて、あたしたちは沖野さんの車へと乗り込んだ。
せっかく希望の光が差したかと思えばまた泣き始める空に、困惑してしまう。
ここまできてしまった以上は、真実を伝えるしかない。なにが本当で、なにが嘘か。
はっきりさせなければならないのは、本当のこと。もうこれ以上、沖野さんに嘘は付きたくない。
全てを受け止めて、前に進んで欲しい。
最初から読むには↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

