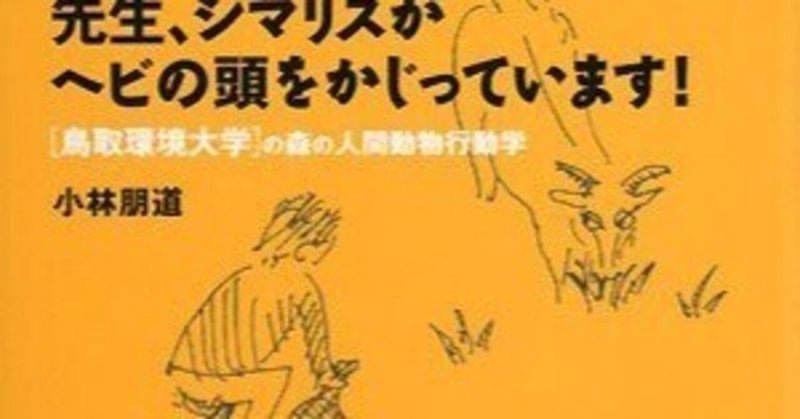
【読書おすすめ】先生、シマリスがヘビの頭をかじっています!(小林朋道)
鳥取環境大学の教授である著者が、動物行動学の研究者としての日々を易しく、しかし含蓄深く語ります。人類にとって普遍的な部分を、こんな平易な文章で語れるのスゲー!と夢中で読みました。生物多様性は、人間の生きる環境としてマストなのであります。こういう、好きなことに邁進して専門性発揮、かつ楽しげな人、大好きです~~
特に、日本固有種である「ナガレホトケドジョウ」の生態を突き止めようと、しつこくしつこく100回近く、ウェイダーを身につけ地味に地味に調査するくだりが、実におもしろかった。
このレジリエンスよな!効率主義でも楽観主義でもない。
(私は元オットのおかげで、このフィールドワークがどれぐらいの作業量で地道なものなのか想像できます)
また、「自然科学研究において高度な技術がもてはやされている中で、五感と経験をフルに発揮しなければこのような研究はできなかろう、という自負もある」ところも頷けます。こういうのは、人間の総合力がフルに発揮されるしかない分野だろう。
それから、次のような見解も面白い。
動物行動学では、我々の祖先の狩猟採集人の社会では、得るものが大きければ、 たとえ 確率がかなり低くても、 諦めずにその可能性にかけて やり続ける特性の個体の方がより多くの子孫を残しただろうと 示唆している 。
そして私たちは、そのような特性をもって生き残ってきたものの子孫だ。
私はこの 裏付けをとりたくてGeminiに訊いてみた。そしたら、ちゃんと次の分野で文献を上げながら教えてくれた。(疑り深く訊いたけど、難しくて半分も理解できなかった)
1,遺伝子研究
2,考古学的証拠
3,現代狩猟採集民の観察
これらの証拠は、狩猟採集民社会における個体のリスクテイク特性と、その子孫繁栄への影響に関する考え方を裏付けています。
リスクテイクは、獲物や食料を獲得する機会を増やす一方で、危険にさらされるリスクも伴います。しかし、狩猟採集民社会においては、リスクテイクをいとわない個体が、より多くの資源を獲得し、より多くの子供を残すことができた可能性が高いと考えられています。
こんな風に私達の特性として、大きなものに向かってあきらめずに可能性を信じる遺伝子がちゃんとあると思うと、勇気が湧いてきました。人生ずっと挑戦だぜ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
