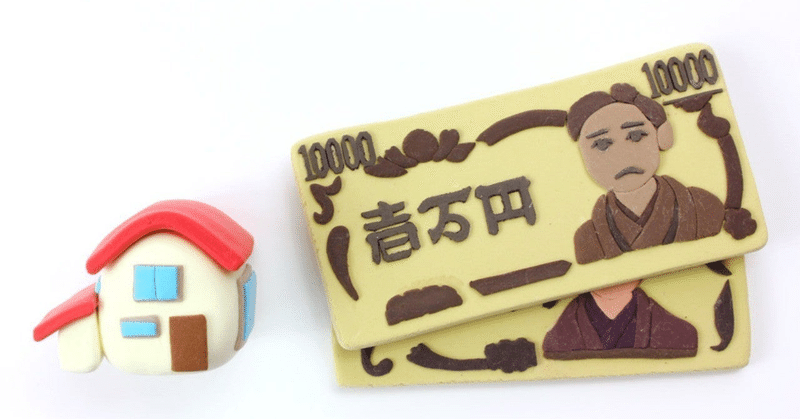
FP3級合格レベルの知識で、同性愛者と異性愛者のどっちが得をするのか調べてみた
どうも、残り僅かなキャンパスライフ謳歌中のレズビアンの大学生こと「りぃな」です。
就活も終わり、暇を持て余した〜♪
…………のではなく!
就活を経験して、今後の自分のライフプランなどを考えるようになって、改めて、
「同性愛者として同性パートナーと生きていくこと」
への経済的不安を覚えました。
そして、お金に関する勉強をしようと思い立ち、先日無事に、ファイナンシャルプランナー技能士(略してFP)3級を受験し、見事合格しました!
※この「経済的不安」というのは、同性愛者の中でも私がゲイ(男性同性愛者)ではなく、レズビアン (女性同性愛者)だから、男女の平均所得の差を思ってより不安を強く感じているのかもしれません。

勉強に使った本たち
そして、とても純粋に気になったので、
今回はFP3級の試験に合格するために学んで得た知識を元に、
・私が異性パートナーと婚姻した場合
・私が同性パートナーと婚姻(したかったけれど、現在の日本で法的には)出来なかった場合
の2つの人生を想定して、
どれだけ得または損をするのか
を調べてみます!
※FP3級2018年度の出題範囲に準拠しています。3級では扱わない内容および私が理解しきれなかった内容、また2019年度以降の法律の改定などには対応していません。

***
〜損するかもしれない例〜
①所得税の配偶者控除
納税者本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下(年収で言うと103万円以下)であるとき、原則38万円が控除される
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、要件を満たせば控除される可能性がある
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず配偶者にあたらないため、控除されない
②所得税の配偶者特別控除
配偶者控除の対象にならない場合で、納税者本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38〜76万円であり、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であるとき、最高38万円が控除される
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、要件を満たせば控除される可能性がある
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず配偶者にあたらないため、控除されない
③所得税の扶養控除
納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が38万円以下(年収で言うと103万円以下)であるとき、一般に38万円が控除される
[異性パートナーと婚姻している場合]
パートナーとの子どもは扶養親族として認められるため、扶養控除を適用出来る可能性がある
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
パートナーとの子どもは、血縁上/戸籍上の父母の扶養親族となるが、血縁上/戸籍上の父母でない者の扶養親族としては認められず、扶養控除を適用できない
例)女性同士のカップルの場合
子どもは、産みの母の扶養親族となり扶養控除を受けられる可能性があるが、もう一方の母(出産していない)は母として認められないために扶養親族とならず、扶養控除の対象とならない
④所得税の障害者控除
納税者本人または控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合、27万円(特別障害者の場合、40万円または75万円)が控除される
[異性パートナーと婚姻している場合]
納税者本人が障害者である場合は控除される
また、パートナーは配偶者にあたり、パートナーとの子どもは扶養親族にあたるため、障害者である場合は控除される
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
納税者本人が障害者である場合は控除される
ただし、パートナーは婚姻出来ず配偶者にあたらないため、障害者であっても控除されない
また、パートナーとの子どもが障害者であった場合、扶養親族と認められない場合は控除されない
⑤個人住民税(道府県民税、市町村民税)の所得控除
その年の1月1日現在、住所がある都道府県または市区町村で課税され、所得税と同様に配偶者控除などの所得控除がある(所得税の場合と控除額は異なる)
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、要件を満たせば控除される
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず配偶者にあたらないため、控除されない
⑥個人年金保険料控除
一定の要件を満たした個人年金保険に加入している場合、一般の生命保険料控除と別枠で、同額の控除が受けられる。年金受取人が、契約者または配偶者のどちらかである必要がある
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、要件を満たせば控除される
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず配偶者にあたらないため、控除されない
⑦公的医療保険・健康保険における家族出産育児一時金の支給
被保険者(会社員)の被扶養者(会社員の妻、一般的に年収130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満である人)が出産した場合、1児につき42万円が支給される。
[異性パートナーと婚姻している場合]
婚姻しており妻にあたるため、要件を満たせば支給される
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず妻にあたらないため、支給されない
※被保険者本人が出産する場合は、被扶養者に関係なく1児につき同額の42万円が支給される
⑧公的医療保険・健康保険における埋葬料・家族埋葬料の支給
被保険者(会社員)が死亡したとき、葬儀をした家族に対し5万円が支給される。また、被扶養者(家族)が死亡したとき、被保険者(会社員)に5万円が支給される
[異性パートナーと婚姻している場合]
被扶養者(家族)にあたり、支給される
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず被扶養者(家族)にあたらないと見なされ、支給されない
⑨公的医療保険・雇用保険おける介護休業給付の支給
家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たしたときは、休業前の賃金の40%相当額が支給される
[異性パートナーと婚姻している場合]
家族にあたるため、条件を満たせば支給される
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ないため、パートナー等が家族にあたらないと見なされ、支給されない
例)自分の父母を介護するために休業した場合は、家族の介護にあたるため、支給される
一方、パートナーまたはパートナーの父母などを介護するために休業した場合、婚姻関係がないことから家族と見なされず、支給されない
⑩国民年金の第3号被保険者
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険に加入している人)に扶養されている配偶者は、第3号被保険者となり、保険料の負担はなくなる
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたり、自分で保険に加入せず扶養されている場合、第3号被保険者になる
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず配偶者にあたらないため、第3号被保険者になることは出来ず、第1号被保険者または第2号被保険者となり、保険料を負担する必要がある
⑪公的年金・加給年金の給付
厚生年金の加入期間が20年以上あり、その人によって生計が維持されている65歳未満の配偶者、または、18歳到達年度の末日までの子がいる場合に支給される年金
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたり、条件を満たしていれば支給される
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず、配偶者にあたらないと見なされ、支給されない
⑫公的年金・遺族給付
被保険者(年金加入者)または被保険者(年金受給者)が死亡した場合、遺族に給付される
要件・金額は第1号被保険者(国民年金)と第2号被保険者(厚生年金)で異なる
給付を受給できる遺族の範囲は、国民年金の場合、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者、厚生年金の場合、妻・夫・子→父母→孫→祖父母の順
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたり、要件を満たしていれば受給できる
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず、配偶者にあたらないと見なされ、受給できない
⑬法定相続人
民法では、相続人の範囲を被相続人(死亡した人)の配偶者と一定の血族に限り、また配偶者は常に相続人となる
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、常に法定相続人になれる
また、遺留分権利者(遺留分を請求する権利がある人)になり、被相続人の財産の3分の1または2分の1を請求出来る
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻が出来ず、配偶者にあたらないため、法定相続人になれない
また、同様に遺留分権利者にもなれない
被相続人が遺言を残すことによって相続人になることが出来るが、遺留分権利者(被相続人の父母などの血族)から請求を受ける可能性がある
⑭相続税の配偶者の税額控除
配偶者が相続により取得した財産が1億6000万円以下または配偶者の法定相続分相当額以下の場合には、相続税がかからない
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、控除を受けられる
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻が出来ず、配偶者にあたらないため、控除は受けられない
⑮贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与があった場合、基礎控除とは別に、2000万円までは贈与税がかからない
[異性パートナーと婚姻している場合]
婚姻して20年以上経過していれば控除を受けられる
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻が出来ず、配偶者に当たらないため、控除は受けられない
また、今後、戸籍上同性同士でも婚姻が出来るようになったとしても、婚姻出来るようになる前までの期間を婚姻期間に含められるか分からない
例)30歳から事実上、婚姻関係にあった戸籍上同性同士のカップルが、50歳のときに戸籍上同性同士でも婚姻出来るようになり、50歳で婚姻をして、60歳で贈与を行なった場合
50〜60歳の10年間だけを婚姻期間とし、30〜50歳の20年間は婚姻期間として認められない可能性がある
⑯直系尊属から住宅取得投資金の贈与を受けた場合の非課税措置
20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から、一定の住宅を取得するための資金を取得した場合には、取得した金額のうち、一定額が非課税となる。
[異性パートナーと婚姻している場合]
パートナーとの子どもに対して贈与を行うと、父母という直系尊属にあたるため、非課税の対象となる
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
パートナーとの子どもに対して贈与を行なっても、血縁上/戸籍上の父母ではない場合、父母として認められず非課税とならない
例)女性同士のカップルの場合
産みの母にあたる人から贈与を受けた場合は非課税の対象となる可能性があるが、もう一方の母(出産していない)は母として認められず非課税の対象とならない(課税の対象になる)

***
〜得するかもしれない例〜
❶個人事業主が支払った保険料の扱い
個人事業主が支払った保険料について、被保険者が事業主本人やその親族の場合、支払った保険料を必要経費とすることはできない
※自分またはパートナーが個人事業主の場合
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、親族にあたり必要経費とすることはできない
ただし、事業主本人の生命保険料控除として処理することができる
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻出来ず親族にあたらないと見なされた場合、必要経費とすることができる可能性がある
※どちらが得するのか分からないが、費用の扱いが異なることはわかった!
❷不動産譲渡時の居住用財産の3000万円の特別控除
居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた場合、譲渡所得の金額から最高3000万円を控除することができる。ただし、配偶者・父母・子などへの譲渡ではないこと
[異性パートナーと婚姻している場合]
配偶者にあたるため、特別控除は不可
[同性パートナーと婚姻出来ない場合]
婚姻が出来ず配偶者にあたらない(同性パートナーとの関係性はただの友人)ため、特別控除が適用される可能性がある
***
以上が、今回私がFP3級の試験勉強の中で見つけた、「同性愛者であることで損するかも?(得するかも?)」というポイントでした!
(FP3級程度の知識なので、間違っている箇所もあるかもしれません。間違っている箇所など気づいた方はご連絡くださると嬉しいです>_<お願いします!)
見ていただいて分かる通り、
「同性愛者である」
から損をするのではなく、
「現在の日本で同性カップルは婚姻届が受理されず、法的に"ふうふ"として認められない」
から損をするということですね。
(だから、事実婚とかほかにも事情があって婚姻届を出さない/出しても受理されない人たちは、同じ状況ってことなんでしょうね)
軽い気持ちで調べ始めてみただけなのに、想像以上に「配偶者」が強すぎてビックリしました。
(マジ配偶者、最強じゃん………)

やっぱり、
同性婚
(性別に関わらない平等な婚姻の権利)
が、1日でも早く実現して欲しいな…………

日本でも、
同性婚及び性別に関わらない平等な婚姻の権利を求める運動
ってないのかな…………

ないのかな…………

と思ったそこのあなた!!!!!
こちらのサイトで署名に参加したり、
#結婚の自由をすべての人に を実現するための裁判や様々な運動について知ったりすることが出来るそうです!
↓↓↓

パートナーが同性か異性か関係なく、全ての国民が平等に「婚姻する権利」を持つことが望ましいな、と私は思います。
(権利を持つということが望ましいのであって、絶対全員が婚姻すべき!とは決して思っていないので、そこはご注意を)
#LGBT #レズビアン #同性愛者 #同性カップル #同性パートナー #同性婚
#FP #ファイナンシャルプランナー
誰もが平等に権利を持てる社会になったら嬉しいな♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
