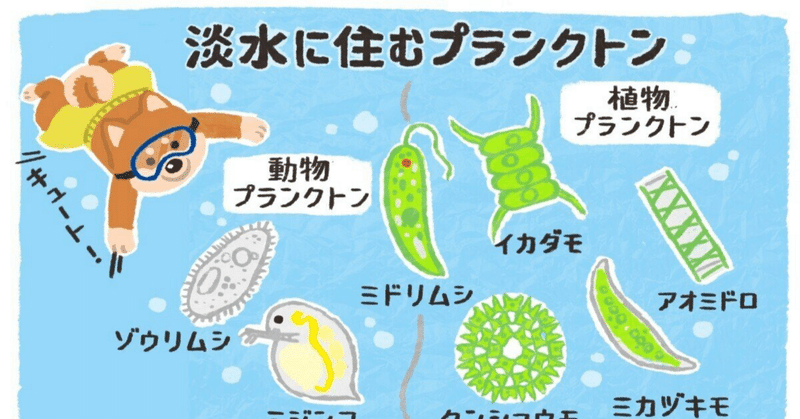
浄化槽の処理方法の種類(一覧)
ここでは、実際にどんな種類の浄化槽があるかをまとめていきます。
浄化槽の処理方法の種類は、建設省告示1292(今の国土交通省)で定められている「浄化槽の構造基準」に記載されており、以下のとおりです。
処理方法種類
処理方法の種類一覧(建設省告示1292記載)
1.分離接触ばっ気(告示区分第1)
2.嫌気ろ床接触ばっ気(告示区分第1)
3.脱窒ろ床接触ばっ気(告示区分第1)
4.腐敗槽(告示区分第4)(単独浄化槽)
5.地下浸透(告示区分第5)(単独浄化槽)
6.回転板接触(告示区分第6)
7.接触ばっ気(告示区分第6)
8.散水ろ床(告示区分第6)
9.長時間ばっ気(告示区分第6)
10.標準活性汚泥(告示区分第6)
11.接触ばっ気・ろ過(告示区分第7)
12.凝集分離(告示区分第7)
13.接触ばっ気・活性炭吸着(告示区分第8)
14.凝集分離・活性炭吸着(告示区分第8)
15.硝化液循環活性汚泥(告示区分第9,10,11)
16.3次処理脱窒・脱リン(告示区分第9,10,11)
また、建設省告示1292に明確な記載はありませんがこれとは別に
17.回分式
18.オキシデーションディッチ法
があります。
告示区分
告示区分は、それぞれ
第1は小型の合併浄化槽
第2-5は単独浄化槽(第2と第3は使われていないため削除された)
第6-12は、合併浄化槽
をまとめてあり6-12については、数字が大きくなるにつれて水質基準が厳しい(処理能力が高い)ものになっています。
処理方法種類 試験ポイント
このうち、浄化槽管理士試験では、単独浄化槽はほとんど出題されません。(新設が禁止されていることが関係していると思われる)
以下を、覚えると種類を理解しやすいです。
・ばっ気:ブロワで空気を送り込むこと
・接触:接触材が入っているもの
・接触材:ばっ気をする槽で微生物を住まわせる家
・嫌気:ばっ気せずに無酸素状態にしている槽(無酸素では、嫌気性微生物(空’気’を’嫌’う微生物)が処理をすることが由来と思われる)
・嫌気ろ床:嫌気する槽で微生物を住まわせる家
処理と合わせて固形物のろ過も行う
・脱窒:窒素を除去する(嫌気と好気を循環させる)
・活性汚泥:接触材やろ床のような生物膜(微生物の家)を使用せず、液体内の微生物で処理
・回分式:一つの槽で、嫌気、好気、沈殿等の処理を行う
・オキシデーションディッチ法:流れるプールのように循環させながら処理を行う(空気が出る場所は好気、出ていないところは嫌気)
例えばですが2.嫌気ろ床接触ばっ気は、嫌気のろ床で処理した後、接触ばっ気処理を行うものや8.散水ろ床は、ろ床(砂ろ過のような砂槽)に汚水を散水しながら処理をするのように、名称のとおり処理されます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
