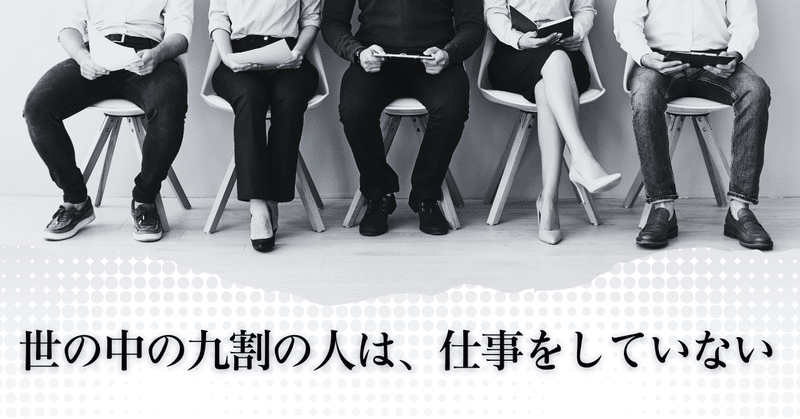
世の中の九割の人は、仕事をしていない
人間の労力や時間のほとんどは、一応「仕事」という名前がついているだけの、何のために/誰のためにあるのかよくわからない無意味な「作業」ないし「運動」で費やされている。
例えばエクセルを開いて、閉じて、開いて、閉じてという指先ラジオ体操で今日の貴重な一日を終えた人は日本だけでも百万人以上いるだろう。
もしかしたらこうした時間の無駄に耐えられず、「こんな仕事、意味あるんですか」という禁句を発して上司に食ってかかった人もいるかもしれない。
こうした状況において、大抵の場合、上司は「規則だ」とぶっきらぼうに返事するだけだろう。
というより上司だって、役員だって、取引先だって、意味不明な仕事を会社に強制してきた規制当局だって、誰も「その仕事が何のために必要なのか」も分かっていないのだから、そう返答するしかない。
ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)という言葉を知る人も増えているが、効率化が進んでいる時代で、なぜか無駄な仕事も増えてしまっている。
「仕事という名前がついているだけの何か」を減らし「真の意味での創造的な仕事」の割合を増やせば、驚くべきことに(しかし論理と割り算さえわかれば誰でも理解できるとおり)、「世の中に提供できる付加価値が増加しつつ仕事も楽しくなる」というパラダイス的/ご都合主義的すぎて疑いたくなるような状況が得られるわけだ。
だが現実の会社生活・社会生活においてこれに気が付かない人があまりにも多い。
だからこそ、もう終わってしまったことを責めるためだけの会議のような、無意味の極致に手を染めてしまう。
「人は無能になる職階にまで出世する」
しかし、なぜ会社には「無意味な何かを生み出すことを仕事だと思っていたり、恐ろしいことにこれこそが経営だと思っていたりする人もいる」のだろうか。
一つの理由は、次に示すような「人は無能になる職階にまで出世する」という数理的に証明できる法則があるためである。
条件1:組織はピラミッド状であり複数の階層(職階)が存在すると仮定する。
条件2:ある職階において最も成績が良かったものがより上位の職階に就く(成績が悪い場合にも降格・解雇はされない)と仮定する。
条件3:複数の職階において求められる能力はそれぞれ異なると仮定する。
条件4:個々人が持つ能力値はランダムに割り振られ、異なる能力間に相関関係はないと仮定する。
これらは特に現代の官僚制組織ではありそうな状況だろう。
上司が無能だと笑うのは簡単だが現実はそう単純でもない。おそらくすべての人が大なり小なりこうした無意味な仕事もどきを作りだしている。
多くの人が心当たりがあるかもしれないが、「特定の職階で優秀だったものが次の職階でも優秀である確率は低い」のである。
会社だけでなく、あらゆる組織でこの問題に向き合う必要があるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
