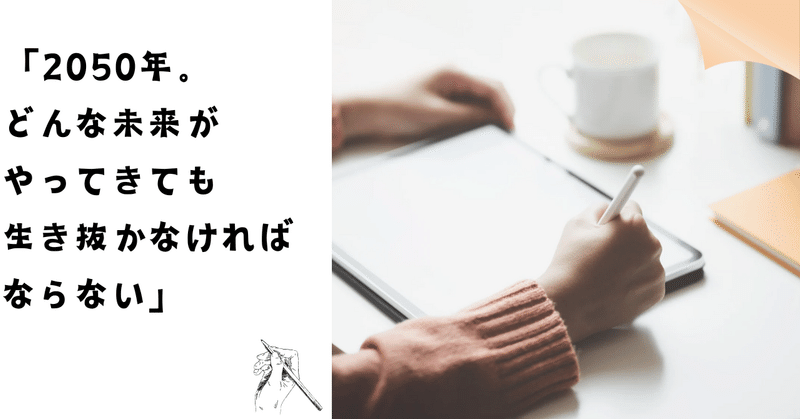
「2050年。どんな未来がやってきても生き抜かなければならない」
私は、中学校教諭として勤務校に籍を置きながら、現在校区3つの小学校5、6年生の児童たちに授業をしている。
教員人生26年目で初めての経験をさせて頂いている。
1ヶ月が過ぎ、中学入学前の児童たちと直に触れ合いながら、ふと感じることがあった。
この目の前の小学生たちが、「働き盛り」となり、家庭を持ち、子育てを始める30代半ば頃、世界は2050年を迎えている。
地球環境を救うためにカーボンニュートラルの実現を目指した2050年。
大国が経済成長を優先したことで、温暖化と環境破壊が進んでいるだろう。
その時、世界中の都市は熱波に襲われ、食糧難に悩まされているのだろうか。
いや、グリーントランスフォーメーションが功を奏し、快適な環境で暮らせているかもしれない。
世界ではテクノロジーが進化し、シンギュラリティを経験した2050年。
AIやロボットが日常に入り込み、人の労働がテクノロジーに移行しているだろう。
その時、ターミネーターのように、AIロボットと戦う日がやってくるのだろうか。
いや、ドラえもんのようなAIロボットを楽しく協働共生しているかもしれない。
日本が南海トラフや日本海溝などの巨大地震を経験してきた2050年。
沿岸部の津波被害や都市部の火災被害によって、経済が大打撃を受けているだろう。
そこに、人口減少による内需縮小が加わり、低所得国になっているのだろうか。
いや、豊かな自然とホスピタリティによって観光大国になっているかもしれない。
2050年という未来がどうなるかなんて誰にもわかりはしない。
ただ一つ言えることは、
これまで人類が経験したことのない振れ幅の大きな未来がやってくるということ。
振り子がどちらに振れるのかはわからない。
地球環境、シンギュラリティ、自然災害という避けられない課題に対し
破滅の道を進むことになるのか、共存共生の道を切り拓くのか。
いずれにしても、子どもたちは目の前の世界を生きなければならない。
いや、生き抜かねければならない。
そう考えた時、「今の大人たちが受けてきた教育を子どもたちも受けるべきなのだろうか」という漠然とした疑問が湧いてくる
教師よりも丁寧に何でも教えてくれるAIは、
どんなジャンルもあらゆる言語で答えてくれる。
今の教育で、一生懸命に国、数、英、理、社の知識を詰め込んだところで、
その知識は進化を続けるAIに敵わないどころか離される一方。
しかし大学受験に必要だからといって「とりあえず」国、数、英、理、社を勉強させられる。
果たしてそれでいいのだろうか。
もう一つは、「教員の私的な好みや趣味」を、子どもたちに押し付けていないだろうか。
長い間、生徒指導を担当してきた立場で、こんなことを綴るのもどうかと思うが、
髪を染めたり、ピアスをしたりすることが、なぜいけないことなのか。
「校則で決まっている」「学校にふさわしくない」「体を傷つける」など、我々教員は様々な理屈を並べ立ててきた。
しかし、それは「あるべき生徒像」という「教員の好みや趣味」を、子どもたちに押し付けているだけではないだろうか。
「我慢を教える」と言って正当化するのは、戦中の国民服やパーマ禁止を彷彿とさせる。悪しき統制主義ではないかと思う。
学校で徹底しなくてはならない社会のルールというのは、「他人に迷惑を掛けない」という公共の福祉の考え方の範囲内であるべきだ。
茶髪やピアスなどについては、本人の決定に委ねる以外にないのではないか。
それが、憲法13条が要請している「個人の尊重の精神」である。
私は、子どもたちの元気に遊ぶ姿と、未来を見据えながら、改めて思ったことがある。
「どんな世界でもサバイブできる子どもを育てたい。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
