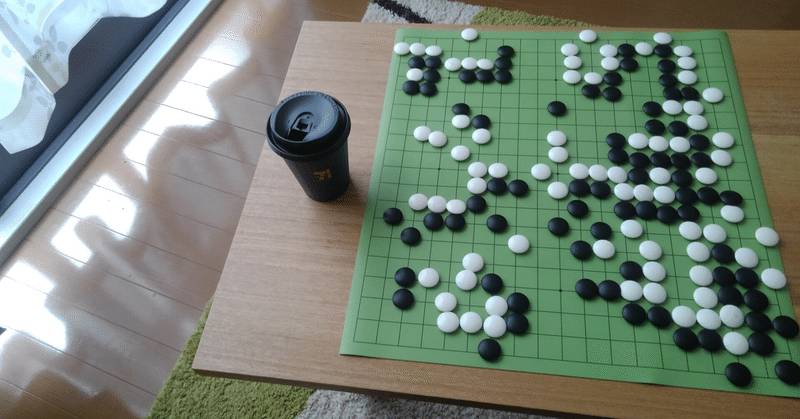
囲碁界の終わりの始まり、そしてその先へ
「正直こんな題名は書きたくなかった」というのが本音だ。
ただ、もう終わりは始まってしまった。この流れを食い止めるのは相当に険しい道だろう。だが、この終わりは止めなくてはいけない。
1.終わりの始まり
先日、こんなニュースが目に飛び込んできた。
囲碁界に対して、警鐘を鳴らしていた私としては、正直棋戦の縮小と聞いて「来るものが来たか」としか思えなかった。しかし、本因坊戦が縮小対象と聞いて目を疑った。
なぜ、よりにもよって本因坊なんだ。
本因坊というタイトルは、囲碁独特のものだ。本因坊戦は七番勝負を行うタイトル戦だ。囲碁界で七番勝負をやるタイトルは3つあって、「棋聖」、「名人」、そして「本因坊」である。ちなみに、お隣の将棋で、七番勝負をやるのは「名人」、「竜王」、「王将」、「王位」の4つである。
この通り、囲碁界の七番勝負タイトルは「棋聖」、「名人」、「本因坊」があるが、棋聖と名人は将棋にもあるのである。
そして、本因坊は囲碁にしかないのである。
こう考えると、冒頭での驚きも頷けるかと思う。
よりにもよって、囲碁にしかないタイトルをいきなり削りにかかったのだ。
これが意味するところは大きい。
つまり、囲碁にしかないいわば囲碁界の看板と言えるといえるタイトル戦を削ったのだ。つまるところ、「もはや囲碁は看板すら取り扱う価値なしのコンテンツですよ」という烙印を押されてしまったと言っても過言ではない。
無論、囲碁界関係者は存続したことに喜んでいるだろうし、囲碁ファンも同じ思いだろう。(事実、存続に感謝する旨のツイートをプロ棋士の先生方がしていた)
しかし、はたから見たら、どうだろうか。
囲碁界の看板コンテンツである本因坊戦が見る価値なしとして削られたのだ。
そんな看板ですら見る価値なしのコンテンツを抱える囲碁界に誰が興味を持つか。
「囲碁がそんな見る価値なしのコンテンツなわけないだろう」とお思いの囲碁界関係者もいるだろう。
しかし、囲碁のコンテンツとしての戦闘力はもはや残酷なまでに数値化されてしまっているのだ。
次項でそれを見ていこう。
2.囲碁界のコンテンツ戦闘力
さて、囲碁界のコンテンツ戦闘力だ。例えば、一番わかりやすいタイトル戦の視聴回数を見てみよう。
日本棋院のチャンネルで、一番再生回数が多いのは、第46期棋聖戦の二日目だ。
その回数が、16万回である。
お隣の将棋界と比較をしてみよう。YouTube配信されている将棋界のタイトル戦で一番再生回数が多いのは、間違いなく今年の王将戦だろう。
その数、なんと156万回である。
一応言っておくが、2日合わせてではない。2日のうちの1日で、156万回だ。
(ちなみに、2日合わせると307万回。先ほど挙げた囲碁の第46期棋聖戦第七局は2日合わせると24.5万回である。一応何倍かというと12.5倍である。)
何と9倍強だ。あと、4万回足したら、10倍である。
もはや圧倒的まである。
では、ここで質問だ。
あなたはとある企業の広告担当者だ。囲碁か将棋のタイトル戦に広告を打ちたいとしよう。そこでこの再生回数を見たとき、あなたはどちらに広告を打ちたいと考えるだろうか。
言わずもがなだろう。将棋だ。アウトリーチ力の桁が違う。
周回遅れの比ではない。控えめに言っても、もはや将棋には絶対に追いつけない。
これがコンテンツ戦闘力の差だ。
今までは、このような形でコンテンツのアウトリーチ力が明確に数値化されることはなかった。だが、今ゲーム配信の環境が整っている状況下では、それがしっかり数字に表れる。
さらに駄目押しといこう。
この将棋のコンテンツ戦闘力は大いなるポテンシャルを秘めている。
というのも、この視聴回数はe-sports界と比較しても遜色ないのだ。
例えば、VALORANTの日本代表を決める大会における最多視聴回数は155万回。これは、先ほど示した王将戦の再生回数と近似している。
このe-sports全盛期の時代に、それと肩を並べるほどの再生回数をとれるのが将棋なのだ。
やりようによっては、将棋界はまだまだスポンサーをつけることすらできそうである。
無論、このコンテンツ戦闘力は藤井六冠の勝ちっぷりに拠るものなので、一過性のものとは言えなくもない。
しかし、この藤井先生フィーバーを使うことで、将棋というコンテンツのすそ野を広げ、その結果将棋全体のコンテンツ戦闘力を高められ、それが後々になって実を結ぶだろうことは想像に難くない。
(ただ、今の活動で将棋の戦略的側面や戦術的側面などの将棋というゲームそのものにおける面白さという面を伝えきれているかというと若干の疑念がある。しかし、実は将棋におけるスーパープレイについてはきちんと伝えられているのである!例えば、藤井六冠の銀のタダ捨て解説動画はなんと148万回再生されている。これだけでも将棋界の未来は明るい気がする。ちなみに囲碁界にこのようなものはない)
ここまで、囲碁界お先真っ暗なお話ばかりしてきた。ただ、これで「囲碁界終了のお知らせ」では何も面白くない。蛍の光を流すにはまだ早い。
変わるためにはどうすべき考えていかないといけないのだ。それを次項で書くとしよう。
3.終わりの始まりの、その先へ
正直変わるべきポイントは山ほどある。ただ、未来ある解決策にしよう。
それこそ、極端なことを言うと、プロ棋士のリストラをすれば、ある種の解決は見込めるかもしれない。だが、それは未来ある解決策ではない。
囲碁というコンテンツの面白さとは何も向き合っていないその場しのぎの解決策だからだ。
未来ある解決策とは、プロ棋士がなすべきことをきちんとやりきることができる解決策だと思う。やることをやりきった後に、それでもにっちもさっちもいかないならば、仕方がない。
そして、私はプロ棋士がなすべきこととは、盤上の熱闘を通じてよい結果を残すことと、その競技の面白さを伝えることだと思っている。
そして、囲碁界はまだまだこの二つはやり切っていない。前者は世界戦での勝利だ。これは大いに課題があるが、正直世界で勝つための育成の部分は囲碁二桁級の私がどうこう言えるものではないだろう。このあたりの話は囲碁高段者の方かプロ棋士の方が書いてほしい。
だが、後者は囲碁ド素人の私でもいえる部分がまだまだある。
囲碁の面白さを全くと言っていいほど伝えきれていないポイントを挙げていこう。
①初心者、初見さんに合わせたゲームの解説がない
手始めにこれだ。まずこれを何とかしてほしい。囲碁のタイトル戦の解説を見ればわかる。シチョウがどうの、隅の生き死にがどうの、攻め合いがどうの……。
うん、わかりますよ。そこが争点なんでしょう?そこが囲碁棋士の読みの深さを示せる場所と思っているんでしょう?
全くわかってない。
何でそこが争点なの?その争点がどんな影響を及ぼすの?
そ こ が 陣 地 に ど う 影 響 す る の ?
その部分の平易な言葉での説明が一切ない。
私が説明するならこうだ。(解説のたびに毎回やる予定だ)
⑴囲碁は陣地とりゲームです。
↓
⑵現状、黒と白の陣地はこことここに○○ポイントあります。
↓
⑶そこで、今、黒と白はここを巡って争っています。黒(白)にとって、ここがとられてしまうとこんな影響が出ます。
↓
⑷では、今争っているここでの攻め合いやら死活やらを考えていきます
これらの説明がないのである。
高段者にとって、⑴~⑶は不要だろう。なぜなら見ればそんなことはわかるからだ。説明なんざ鬱陶しいだけだろう。
違う!断じて違う。
もっと!
言葉を!
尽くせ!
Just Do IT‼
なぜ見る人に初心者さんや初見さんがいることを想定しない?
明らかに、ゲームの根本、そして現状把握のための言語化が足りていない。
プロ棋士の先生方にとっては、この程度のことは一瞬で把握できる。しかし、囲碁を知らない人からしたら、盤面は黒と白のなんかよくわからない模様の何かだ。何ならこれがゲームかすらも怪しいところだ。正直、オセロと思ってくれたら割といい方だと思う。
言葉を尽くせないのだとしたら、それは訓練が足りていない。
なぜなら、プロは素人よりも盤面のことがよくわかるはずだ。わかっているはずなのに、言葉を尽くせないというのはそれは尽くせないのではなく、尽くす努力をしていないだけだ。怠慢というほかない。
②盛り上がりポイントが一切わからない
これも非常に大きな問題だと感じる。というのも、すごい手を打ったとしても、リアクションが薄いのだ。緩急がない。知らない人からしたら緩しかない。ゲームなのだから盛り上がりポイントは絶対どこかにあるはずだ。(もちろん静かに終わるゲームもあろうが、勝ちを決めるポイントはあるはずだ。そこでしっかり感情を込めるべきだ)
リーグ戦に限って言えば、解説場所と対局場が近いという日本棋院の構造上の問題点を考慮すべきなのだろうが、では盛り上がりポイントがわからないのはよいことかというと、そんなわけはないし、タイトル戦で盛り上げポイントが分からないままの理由にはなってない。
囲碁で「名局」は数あれど、「名実況」は聞いたことがない。
例えば、先ほど例に出したVALORANTで名実況がある。VALORANTの日本代表Zeta Divisionが格上のTeam Liquidに勝ったシーンの岸大河氏の名実況である。
(動画の3:19:15から名実況の部分である)
「これは奇跡ではありません!Championsへの軌跡です!」
洒落た言葉遊びだが、この大会におけるZeta Divisionの快進撃を表す言葉としてこれ以上のものはないだろう。
(この大会でZetaは負ければ終了の崖っぷちから復活を遂げ、ジャイアントキリングを成し、因縁の相手にきっちりリベンジを果たし、もう一発ジャイアントキリングを果たして、結果世界3位を獲得するというどこをとってもドラマしかないようなことをやっている)
ボードゲームも見てみよう。麻雀の名実況だ。Mリーグ2020‐2021シーズン終盤の南四局オーラスにセガサミーフェニックス近藤誠一選手が奇跡の倍満ツモで、大逆転トップを果たした時の日吉辰也氏の名実況である。
(リーチ前)
「リーチでしょ!誠一さんに任せたんだよ。あなたで負けたらしょうがないって言っているんだ。リーチでいいじゃないか」
(ツモシーン)
「いけるか!近藤!いった!!!嘘だろこの男!!裏1でいい。裏1で倍満、どうなんだ!?あった!信じらんないだろこんなの!!」
心が、魂が震える名実況というほかない。もちろん、オーラスに逆転の可能性を残す倍満の手組みをした近藤選手の技なくしてこの実況はない。しかし、その技を、そしてその興奮をわかりやすく伝えるこの実況なくして、この大逆転劇は語れないだろう。
ちなみに、Mリーグのスローガンは「この熱狂を外へ」である。まさにこの実況はこの熱狂を外へ伝えるものであったと私は確信している。
果たして、囲碁界はこういったことができているのだろうか。淡々とやって喜ぶのは一部の玄人だけだ。無論、アカデミックさが必要というのもわかる。しかし、棋戦は研究発表の場だけではない。興行なのだ。エンターテインメントなのだ。そのエンタメ性を伝える努力、すなわち熱狂を外へ伝える努力をしないといけない。
③トップ層の露出がない
そして、これだ。囲碁界はトップofトップの露出が少ない。確かに芝野虎丸先生のツイッター、高尾紳路先生のブログがあるが、やはりテキストベースが多い。動画での露出は少ない。なお、動画だと、林漢傑先生・鶴丸淳志先生の「つるりんチャンネル」、柳時熏先生の「囲碁棋士 柳 時熏のGo Channel」、飛田早紀先生の、「女流棋士・飛田早紀の囲碁チャンネル」、柳澤理志先生の、「プロ棋士 柳澤理志の囲碁教室」などがある。
https://www.youtube.com/@gochannel7707
https://www.youtube.com/@user-me5bx6wq8c/about
https://www.youtube.com/@user-fw9jm9ur3s/about
では、果たして、目に見えないものを応援しようと思うだろうか。その姿、立ち居振る舞いが見えてやっと実感が湧くのではないか。
いやいや、対局でその姿を見せているじゃないかと思うかもしれないが、違うのだ。研鑽に励むところでもよし、時にイライラして柄にもなく口が悪くなっているオフショットでもよし、とにかく檜舞台以外での姿が見たいのだ。
ここでも例を出そう。将棋の渡辺名人だ。ラフな服装で、現代将棋の研究について話す動画がある。
ゴリゴリの現代将棋の内容にもかかわらず、なんと再生回数が50万回を超えているのだ。(囲碁のタイトル戦の最多再生回数より多い!)
現役名人という将棋界のトップofトップである渡辺名人が体を張って、手ずから解説をしているのだ。凄まじいというほかない。
なお、続編の作戦術の動画も再生回数は40万回を超えている。
麻雀界では、これまたトップofトップの多井隆晴氏の活動が真っ先に挙げられるだろう。
多井氏はVtuberさんと積極的にコラボし、しまいにはVtuberさんとMリーガーがタッグを組んだチーム戦リーグ「神域リーグ」まで作ってしまうほどだ。
なお、このリーグのドラフト会議の同時接続数は6万人と脅威的なものだった。そして、この神域リーグの影響はMリーグにも波及し、Mリーグで多井氏と同じチームの松本吉弘氏いわく、神域リーグ前と後では、Mリーグの視聴数が1.5倍になったそうだ(以下の切り抜き動画参照)。百万単位の視聴者がいるMリーグの視聴数が1.5倍になったのだ。外への影響力は凄まじいものといえるだろう。
なお、多井氏はこういったコラボ活動以外にもMリーグでの自戦の解説をMリーグ直後の深夜に行うこともしている(基本トップを獲った時のみだが)。これは、別のMリーガ ―の方々もしており、自分のYouTubeチャンネルを持つMリーガーは、対局後すぐに配信をしながら自戦の振り返りをしている。
ちなみに、このようなことを仰る方がいるだろう。
「囲碁は世界が相手なんだ!国内だけの将棋や麻雀と違う!配信なんかしてファンサービスにかまける余裕はない!」
そのセリフ、プロesportsプレイヤーの前で言ってみてほしい。
ついでに彼らからビンタかグーパンでもされてきてほしい。少しはマシになるだろう。
認識が甘すぎる。
全く周りが見えてない。
近視眼的にも程がある。
プロesportsプレイヤーの人たちを見てほしい。
彼らは世界を相手にしながら、きちんと配信活動もしている。
例えば、先ほど話に出たVALORANTにおける日本のプロチームZeta Divisionに所属しているLazvell選手のtwitchチャンネルを見てほしい。
単に練習配信だけではなく、視聴者さんからの質問に答える配信や本業のゲームとは違うゲームをする配信すらある。
先ほども書いたように彼らZeta Divisionは国内戦を勝ち抜いて、世界で大立回りを演じ、結果世界3位という日本のVALORANT界で快挙を果たした。
配信活動もしつつ、なおかつ成果もあげているのだ。
そのような人がいるのに、囲碁は世界を相手にしているから配信活動をしている暇なんてない?
頼むから寝言は寝て言ってほしい。恥ずかしくないのか。
ちなみに、VALORANTはチームゲーで、個人の負担が少ないから配信ができるのだ、とかいうこの世の終わりのような寝言を言う人もいるかと思う。
(大体チームゲーといっても、個人技主体のFPSで個人の負担が少ないと考えられる神経がわからない)
なので、そういった下らない意見を封殺するため、個人競技で世界を相手に成果を残しつつ、配信も見事に両立させているプレイヤーを二人ばかり挙げておこう。
①ヒカル・ナカムラ氏
チェス界では知らぬものなしのグランドマスター。世界5位の実力を持ち、世界選手権の出場者決定戦に何度も出場している。まさにチェス人口8億人の最前線でしのぎを削っているプレイヤーであろう。ちなみに、配信は本業のチェス以外に、チェスを知らない有名人にチェスを教える配信というのをやっていた。企画的にも、動画の内容的にもとても面白いと思ったのでぜひ見てほしい。
(井山先生がヒカ碁好きな有名配信者さんに囲碁を一から教える配信とか個人的には見たいのだが、どうだろうか)
②梅原大吾氏
ご存じの方も多いだろう。「世界のウメハラ」だ。日本のみならず、世界をまたにかけた凄まじい大活躍をしていることは周知の事実だと思う。梅原氏の戦績だけで、一本記事が書けよう。配信では、本業のストリートファイターの配信のみならず、お散歩配信も好評を博している。
さて、ここまで他業種の活動を見てきた。とにかく、きちんと自分の体をさらして、活動をしている。姿が見えるからこそ、声を聞けるからこそ、日常で生活において、どのような形でその競技に取り組んでいるのかがわかるからこそ、応援しようと思えるのだ。
囲碁界は応援されたいと思えるようなことをやっているのであろうか。
野球のWBCかサッカーW杯での日本の活躍を見て囲碁ファンがこの人気が囲碁にむけばなぁという趣旨のつぶやきをしていた記憶がある。
違う。人気が向くんじゃない。
囲碁が応援されるようにならなければならないのだ。
そのためにも、トップ層はもっともっと露出してほしい。負けた自戦を悔し涙を流しながら振り返るシーンがあれば絶対に見てみたい。逆に決め手をドヤ顔でしゃべるところも見てみたい。推しのアイドルのライブをDVDで見ながらニヤニヤしているところなんてあれば最高だ。
まだまだ、やれることはあるはずである。
4.あとがき
さて、ここまで長々と書いてきたが、この本因坊戦の縮小をきっかけに囲碁界は本腰を入れて変わらなければいけないと思う。というより変わらなければ、未来はないと思う。蛍の光が終わってしまう。
そして、ここまで読まれた読者の方は思うだろう。
なぜここまで書くの?と
それはシンプルに元院の人たちの存在だ。
プロになるべく、人生をかけて、血反吐を吐くような思いをして、それでも夢破れた人たちがいるのだ。
自分はその元院の人たちを大学囲碁界で見てきた。あれだけ囲碁の実力がある人でも届かない世界があるというのに、その目指した先がこの体たらく?
そして、何も手を打たず、ただただ業界の終わりを指をくわえて眺めていく?囲碁なんて古いコンテンツだから死ぬのを待つしかない?
人生をかけて挑んだものは滅びゆく遺物だったと元院の人たちに思わせるつもりだろうか。
そんなことは一囲碁ファンとして、心の底から願い下げである。
だからこそ、囲碁界は変革してほしいと本気で願うばかりである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
