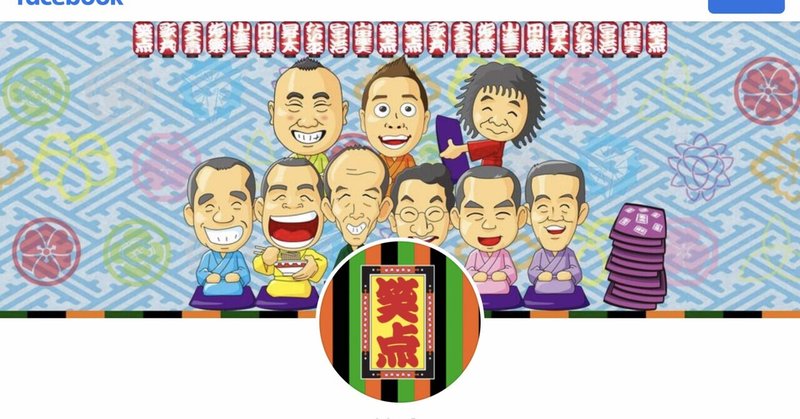
久しぶりに見た「笑点」は面白かった
日曜日の夕方といえば「笑点」である。今日は笑点について書く。
今日と言いながら、このところずっと書いていた。少し書いては、続きを書こうとして方針を変えたり、当初は久々に見た笑点の意外な感想をささっと軽く書こうと思っていたのに、書き出すと、自分の子供の頃からのお笑い体験が思い出され、一度はここ50年のテレビにのお笑い番組の歴史を遡りそうになり、笑点の感想を書こうとした当初の意図から大きく脱線するではないかとまた後戻りし、そんなこんなで、なかなか下書きのところを抜け出せず今に至ってしまった。私の悪い癖だ。思いついたことを全て書き留めとこうと思って、訳のわからない方向に行き、長くなる。推敲すればいいのだが、それはもうほとんど書き直すに等しい作業で、体力が足りない。とか言いながらまた長々書いて、読者を飽きさせ始めている、、、とほほである。
というわけで、笑点である。
【笑点はつまらないのか?】
多分、全国ネットでは唯一の落語家メインの番組で、この番組のレギュラーになることは、落語家にとって売れた証みたいなもんだ。しかし、大喜利レギュラーの座はたった6つ+司会分のみ。その奪い合いはイカゲームの如き熾烈なものに違いない。イカゲーム観てないけど、、、。
しかし、それだけ熾烈なレギュラー争いを経た精鋭が集っているはずなのに、少なくとも私が物心ついてからの笑点は「古臭い笑い」のレッテルを貼られ、若いもんには見向きもされない高齢者のための番組というイメージが定着してしまっている。
当初の番組企画者は立川談志。当時私はまだ生まれておらず、その頃の笑点は見たことがないが、当初は毒のある新しい落語家の番組を目指したようだ。しかし、他の出演者が談志のブラックユーモアについていけず全員降板。それで結局、談志も降板し、司会は当時人気の放送作家兼タレント前田武彦に交代。その後、コメディアンの三波伸介へ、その後はずっと落語家で、三遊亭圓楽、桂歌丸、春風亭昇太と引き継がれて今に至る。昇太以外はみな故人となってしまった。ちなみに私は三波伸介の頃からリアルタイムで見ていて、圓楽の途中からたまにしか見なくなった。
その間数十年。ドリフの席巻、タモリの登場、80年代初頭のビートたけし、ツービートら漫才ブームの洗礼を受け、とんねるずを経てダウンタウン、少し遅れて爆笑問題、ボキャブラ組ら90年代組。飛んで21世紀、第七世代から群雄割拠の現在までを体験している私たちにとっては、笑点はバラエティ番組のいわゆるお笑いとは別物だった。今もビートたけしを源流にした笑いの流れは続き、さらに、90年代後半からは大阪の勢力も東京に進出し、吉本興業覇権の時代に入る。
私は笑いの専門家ではないので自分なりの解釈でしかないが、大阪の吉本的な笑いがナンセンスな瞬間芸のようなものであるとしたら、東京03や古いところではシティボーイズなど東京のお笑いは演劇的なストーリー性があり、落語はどちらかというと東京の笑いと親和性が高いように思う。
大阪の笑いが全国区になり、東京でどんどん増殖していく中、落語はさらに居場所を失うかに見えた。しかし、笑点は長寿番組としてずっと続き、高視聴率を保っていた。ある意味謎である。歳をとるとこういうのが好きになるのか、それとも、まだ落語がお笑いの中心だった昭和の半ばごろを知っている高齢者がいまだ健在だからなのか、まあそんなところだろうと思っていた。つまり、上の世代がいなくなり、私たちが高齢者となった頃には、笑点もともに消えるだろうくらいに認識していたのだ。
しかし、久々に見た笑点は私のこれまでの認識を覆した。
笑点は現在50代の私の心をも掴んでしまった。もしかしたら私が高齢者となる時代にもまだまだ元気に生き延びているかもしれない。そう思えてきたのだ。
【久々に見た笑点に心を掴まれた】
ここ数年で、笑点のメンバーは半分以上が入れ替わり、イメージが刷新されたのもある。
三遊亭円楽(元楽太郎)の死とそれによる降板。その前には長く司会を務めてきた桂歌丸師匠も亡くなり、永世名誉司会という存在となった。歌丸さんが病気で司会を降りた時、新しい司会として選ばれたのが春風亭昇太というのもちょっとした驚きだった。林家三平(いっ平改め)がレギュラー降板という出来事もあった。自ら実力不足を認め、修行してきますとの言葉を残して降板したのだ。林家一門では、爆笑王三平の名跡を継いだいっ平にテレビでの活躍を期待しただろうし、番組制作側としても、あの海老名家の一員でありマザコンキャラ、妻は女優で、三平まで背負わされたいっ平のキャラはおいしかったと思われるが、新三平はそれを背負いきれなかったようだ。そんなこんなで、ここ数年はレギュラーメンバーの入れ替えが続いた。
とはいえ、林家木久扇師匠は85歳で、笑点レギュラー1969年から54年目、好楽師匠は途中中抜けはあるけれど、1979年から、小遊三師匠は1983年からと、レギュラー6人のうち半分が後期高齢者の古参メンバーである。なのに、久々に見た笑点は、私の目にずいぶん新鮮に映ったのである。
新メンバー加入よりも古参の3人の変化が大きいのかもしれない。
3人とも、特に木久扇、好楽の2人がいい意味で歳をとっていたのだ。85歳の木久扇師匠は足下もおぼつかないのか、座布団が溜まって安定が悪くなってくると、フラフラしてその上に座ることができず、後ろに椅子が用意されている。その姿だけで笑える。滑舌も明らかに悪くなり、それでも特に気にすることなく積極的に笑わせにかかる。かつては演じてきたおバカキャラが、やっと本人に追いついて違和感なく合体したそんな感じ。物真似せずともヨボヨボした彦六師匠の喋りそっくりだ。若い頃というのはどうしても本来の自分はバカではないという思いが垣間見えてしまい興醒めしていたところもある。しかし、今や演じなくてもバカっぽい。なのに、大喜利の回答は以前より断然面白くキレがある。これは長年の精進の末か。気取りのない自分らしい言葉選びができている。歳とって身体の力も抜けてしまったが、同時に頭の力も抜けて、身体のヨボヨボ具合に合った仙人のような自然な言葉が出てくるから自然に面白い。これが人間力って物なんだろう。
かつて立川吉笑が、笑点の特番に出て大喜利をやった時に受けなかったことを書いたコラムで、笑点的大喜利の面白さには人間力が重要で、「何を言うか」よりも「どう言うか」、「誰が言うか」がものを言うと書いていた。松本人志の「IPPONグランプリ」的な大喜利では自分のような存在感の薄いものでも面白い回答を出せば受けるが、笑点的な大喜利ではその落語家の存在の仕方と人間力でもって回答の言葉の面白さが増幅される。そんな場で、自分のようなまだまだ人間力のない落語家がイキっても、面白くならないのだと。
立川吉笑、さすが分かっている。私が久しぶりに笑点を見て感じた面白さとはまさにこれ。木久扇師匠や好楽師匠が歳をとって人間力を増し、その回答の面白さが増幅され始めた結果なのだ。
吉笑はそのコラムの中でこうも書いていた。
『木久扇師匠や小遊三師匠と同じ解答を自分が言っても全然ウケないだろう。なぜなら人間力に圧倒的な差があるから。(中略)そういう目線で笑点を見たら、あそこに並ばれている師匠方のすごさがよくわかる。神話に出てくる神々のごとき存在感。何気ない一言を強烈なボケに変えてしまう人間力。(中略)「笑い」として、ベタなものはレベルが低いと見下しがちだけど、それは大きな勘違いだ。そのことに気づいたとき、自分のお笑い観がガラリと変わった。』
「あそこに並ばれている師匠方は神話に出てくる神々のごとし存在感」というのは褒めすぎな気もするが、それぞれの師匠が神話の中の神々の如くに、それぞれ異なる魅力的なキャラクターを確立していることは確かで、若い頃はキャラを確立したいあまりに無理な回答を連発して滑っていたものが年を経て、自然にキャラと自分自身の笑いがシンクロするようになってきた結果が、現在の木久扇師匠や好楽師匠、小遊三師匠の自然なボケにつながっているように思う。V6で言えば、トニセンの面目躍如である(以下、司会とカミセンは師匠の敬称略)。
レギュラーメンバーの会話の中から生まれた「チームマカロン」という呼び名も素晴らしい。宮治と好楽師匠が自分たちの着物の色をマカロンっぽくない?と言うと、翌週(だっけか?)たい平がその色のマカロンを作ってきて、その呼び名が定着したとか。ベテランが偉そうにふんぞりかえることなく、若手の提案を受け入れる風通しの良さもこのところの笑点の良いところかもしれない。多分、これは司会が春風亭昇太になったことによる恩恵だろう。
司会が変わり、ここ数年でメンバーの半分が入れ替わった中で、どう上手く場を転がすか。これまでおなじみだった大喜利メンバー同士の関係性、例えば、円楽師匠(元楽太郎)と歌丸師匠の罵り合いとか、女優を妻に持つ三平へのイジリとか、そういうことができなくなった中で、新しいメンバーはどんどん新しい関係性を作り上げている。
木久扇師匠のおバカキャラには磨きがかかり、好楽師匠はいつのまにか鉄板の怠け者キャラに。私がかつて見ていた頃はもっと硬派な感じだったかと思うのだが、久しぶりに見たら、歳をとったせいもあるのか?いつもヘラヘラ笑ってる怠け者になっていた。小遊三師匠は昔からナルシストのキモい色男キャラだがこれは変わらず。贅沢を言えば、木久扇、好楽両師匠が歳を経て自己内化学反応を起こし、さらにいい味出してるだけに、小遊三師匠の色キモ男キャラにも年相応の変化が欲しかった。
昇太は50代の独り者だったが、今や結婚して、晩婚いじられキャラとなった。これは独身よりおいしい立ち位置。そんな中、海老名家をバックに持つ落語界のサラブレッドでマザコン、かつ女優を妻に持つ三平はおいしい突っ込まれキャラになれるはずだったのに、結局、それを活かせなかったのは残念。そして、その三平の抜けた穴に入ってきたのがマカロンの桂宮治。そして、円楽師匠の抜けた穴には一之輔が入り、旧知のこの2人はトムとジェリーのように仲良く喧嘩する設定を発見したようだ。
実は私は笑点抜擢のニュースを聞くまでは、桂宮治という落語家を知らなかった。若い頃は落語番組のスタッフをやっていた時期もあって、その後も比較的落語界の情報もチェックしてきたつもりだったが、ここ10年くらいはブランクになっていたのだ。その間に、春風亭一之輔が頭角を表し、桂二葉みたいな若い才能が育ち、講談の世界では神田松之丞改め伯山なんて100年に一人の逸材が登場。さらに、私が20代の時にADとして参加していた落語のホール中継録画の番組で、舞台袖で太鼓を叩いていた小さんの弟子で二つ目のさん好さんが、いつのまにか真打柳亭市馬師匠となり、なんとなんと落語協会の会長になっていた。時は流れ、落語界も変化していたのだ。
笑点も永遠のマンネリのようでいて、時代に合わせた変化をしていた。時代の空気がどんどん変わっていく中、笑点も変わり続けているからこそ、変わらないように見えるのかもしれない。しかし、それにしても、ここ数年の変化はこれまでになく大きいものだった気がする。
これまで、基本的にレギュラーメンバーの交代にあたって、実力不足という理由が挙がることはほぼなかったと思うが、林家三平降板の際、三平自身が自らの力不足と語っているように、その実力不足が取り沙汰された。これは笑点の歴史において初めてのことではないだろうか。実力至上主義がいいとは思わないが、何年も成長しない落語家の大喜利の回答にモヤモヤし続けるよりは、素直に面白い回答のできる落語家をキャスティングする方がスッキリする。今回は、そういうわかりやすさに踏み切った、結構エポックな出来事だったんじゃないかと思うのだ。
笑点からもわかるように、落語家というのはかなり高齢になっても、それを味として現役で活動できる(漫才もできそうだが)。そして、歳を取ればとるほど、人生経験も増し、人間の様々な生き様を知り、歴史を学び、社会情勢に耳を傾けることで、自らの人間力も増し、滋味深い言葉や振る舞いが芸に加わる。長く現役でいられるということはそういうことでもあり、瞬発力が求められる若い笑いとはまた違った笑いの世界が見えてくるのだ。
とはいえ、そんな笑点も若くて実力もある新メンバーが入ったことで、テンポの良い笑いも手に入れた。それには司会の昇太の力に負うところが大きい。若手のテンポの早い返しからベテランののんびりのほほんとした回答に上手く繋げられるのは昇太だからこそ。これはディレクターの編集に寄るところも大きいのかもしれないが、以前に比べ、1人の回答から次の回答に移るテンポが速くなっている。数えたことはないが、1問に対する回答の回数は増えているのではないだろうか。宮治の早いテンポの喋りと好楽師匠や木久扇師匠のゆっくりしたテンポが違和感なく繋がる。早口の宮治とややのんびりめの一之輔のやりとりが間に入ることで、遅すぎもせず早すぎもしない絶妙の気持ち良いテンポが生まれている気がする。昇太の采配とディレクターの編集の賜物だろう。
ここまでスタッフのことをほとんど書かなかったが、長寿番組をさらに続けるために、何も変わってないように見えて、常に時代に置いていかれない形を考えているに違いない。
「落語は人間の業の肯定である」と笑点を作った立川談志は言ったが、ずっと人間の業に向き合い、ヨボヨボになるまで人間とは何かを考え続けてきたベテラン落語家の言葉や振る舞いが面白くないはずがない。
具体的に言うと、久しぶりに見た笑点で私が最も心に残ったのは好楽師匠の変化である。この人って、こんなにエゴを感じさせない人だっけ?その語りからは自意識みたいなものがほとんど見えてこないのだ。自意識という意味では、木久扇師匠のさらに進んだ老人化というか、よぼよぼの口調が自意識を消して、心地よい笑いになっている。
落語の行き着く先ってこういう世界なのだろうか?
若いうちはもっとブラックで世の中を刺しながら、歳をとるに従ってその笑いも変わっていく。ほんわかだけが年寄りではないし、その人なりの歳の取り方があり、それに沿ってその人の笑いも変わっていく。そのように変わっていける人間だけが見るものを気持ちよく笑わせられる芸人になれるのかな。
私はこのところの笑点を見ていてそんなことを思った。
笑点の放送は今日の17時半から。25分からは「もうすぐ笑点」って予告番組をやっている。別に笑点の回し者ではないけれど、しばらく見てないという方はちょっとチャンネルを合わせてみてはどうだろう。
あー、やっと書き終わった。全然まとまりないうえに、全然筆が進まず、しばらくnoteの更新もできなかった。いっそ違うテーマを先に書こうかとも思ったが、なんとなくそれもできず、プレッシャーもあるのか、眠気ばかりが襲い、数行しか書けない日が続いた。でも、なんとか終わった。そして、また長くなってしまった。でも、推敲する体力はもったいないので、笑点の話はここで終わらせ、別のテーマに移ろうと思う。
トンネルを抜けた。そんな感じだ。
病の方も、このところあまり調子が良くなく、仕事につながるような作業も、サポートをお願いするためのこうしたコラムやエッセイも全く書けなかった。でも、noteでトンネルを抜けた今、病の方も良くなって行ってほしいし、そうすれば、さらに文章も書けるだろう。良い循環に持っていきたい。
このところの不調でお金を稼ぐ作業が何もできておらず、この間の収入は1万円のみ。7月末はピンチです。ここから20日間、サポートいただけるよう、体調に気を付けつつ、コラムや企画などを積極的に書いていきたいと思います。応援してください!
サポートはこちらから。手数料が少ないです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
