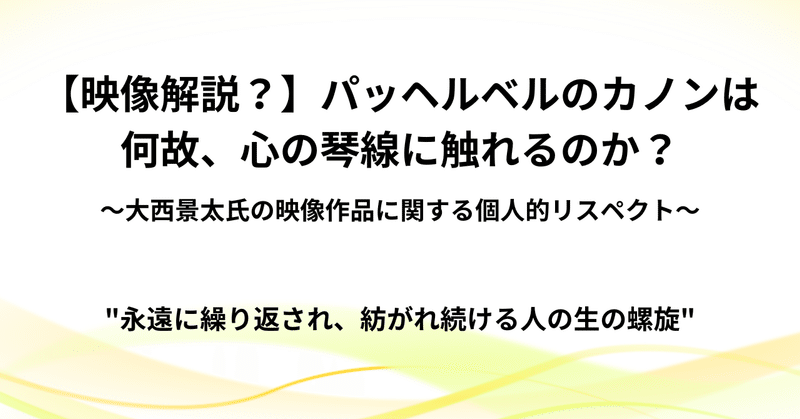
【映像解説?】パッヘルベルのカノンは何故、心の琴線に触れるのか?
はじめに
何故、パッヘルベルのカノンは人々の心の琴線に触れるのか?。それは、この曲が人の生の螺旋、DNA(意志)の螺旋を表現しているからだ!。というテーマで、ちょっぴりスピリチュアルな記事を書きたくて、そう考えるキッカケとなった出来事を思い出したり、あらためて関連資料を検索したりしていたところ、新たに衝撃を受けてしまったので、それらについても併せて、一通り書くことにしました。
以下、よろしければ、お付き合いください。
パッヘルベルのカノンとの出会い
世が令和になったその日、スピリチュアルな事にちょっぴり興味を持ち初めた私は、当時、ネットで、特に動画鑑賞により情報収集していました。すると、おすすめ動画として、いろいろな関連ジャンルの動画が出てくるようになり、興味が湧いたものは眺めていました。
そのなかで、パッヘルベルのカノンとも出会いました。たぶん、(当時、時々聴いていた)なんとかヘルツとか、なんとか波みたいな音・音楽からの繋がりだったのでしょう。
いくつかのカノンの演奏を聴いてるうちに、「確かに、なんか他の音楽とは違う気がする、魂に訴えかけてくるような雰囲気がある」と、ふわっとは感じていたのですが、なにかの拍子に、とある衝撃的な動画に出会い、それが確信に変わりました。
それが、NHK名曲アルバム+における大西景太氏の映像でした。
大西氏の動画にて、跳ねては滑り、前へ前へと進んでいく小さな立方体を見て、「あー、これは人間で、この音楽は人の一生についての時間の流れ、更には、人の世(DNAの意志)が世代を超えて繰り返し続くことを表現している音楽なんだな」と、かなり感動しながら何度も鑑賞しては、空想を膨らましていました。
その後、このことを誰かにアウトプットするような機会は特になかったのですが、この度、自分でnoteのページを立ち上げ、このこともネタにしようと思い立ったので、「映像を改めて観なおして、記事には関連するリンクも貼ろう」と考え、検索をしていたところ、なんと!、大西氏のnoteを発見し、このカノンの映像についての解説記事もあることが判り、恐れ多くも参考のために拝見することとしました。
記事を最初から読み進めていた私の最初の印象は、「ふーむ、音や音楽を映像で表現するというのは、こういうこと、、、なのか?」と、自らの芸術や創造に対する素養のなさの痛感でした。
※話の途中ですが以下に、大西氏のnote記事のリンクを貼っていますので、是非、訪れてみてください!
※また、この映像は現時点において、以下のNHKのWEBサイトで鑑賞することができます。よろしければ、味わってみてください(受信料は貴方の心がけ次第ということで、、、)。
しろうと解説
ここで、これまで心に書き溜めていたという、パッヘルベルのカノンに対する私の考えを吐き出しておきます。
まず、カノンという形態(?)が、"自と他"あるいは"世代"を表現しているように感じました。そして、「永遠に繰り返され、紡がれ続ける人の生の螺旋、ひいてはDNA(意志)の螺旋、、、。」と、文字にすると、とても厨二な感じがしてしまいますが、これらが、この曲が心に沁みこんでくるポイントの1つではないかと考えます。
次に、曲の展開が人の一生を表現している(のではないか)、という点です。これが、この曲が世代を超えて心に沁みこむ、最大の理由ではないかと考えます。そして、この曲の最大感動パートが世代によって少しずつ異なる(ような気がする)理由でもあると思えます。若い人ほど前半パートに魅力を感じ、人生の経験が深まった人たちほど後半パートに安らぎを感じているような気がします。
以下に、大西氏の映像に(氏のnote記事にも)登場する(ステージ)番号を用いて、私が持つイメージを綴ります。
・導入部(1)は、ゆったりと、しかし確実に成長をし始める、誕生、子守歌、ゆりかごのイメージ。
・音数がだんだん多くなり、音の高低も激しくなっていく、ちょっと危なっかしい成長期(2,3)から、紆余曲折してるようにうねる部分(4)は悩み迷うやんちゃ期(思春期?)でしょうか。
・そして、元気に楽しく仲間や恋人と踊っているかのような、青春真っただ中という感じの誰もが知るメインの(?)メロディ(5)。
・押しては引いて、逃げては追いかける駆け引き、あるいは先導しては後に続く、人生のパートナーとの苦楽の分ち合いを表現しているようなステージ(6,7)を経て、続くステージ(8)では、ふたりは無事に結ばれ、生活も安定したようです。
・続く、音が分かれるステージ(9)では子供を授かり、パートナーも含め家族の仲睦まじい生活が表現されているようですが、終盤には子供たちは巣立ち、パートナーとも別れの日が来て、また、ひとりになってしまう、といった印象です。
・最後のゆったりとしたステージ(10)は、最初(1)の"ゆったり"とは少し異なり、西洋であれば軒先のロッキングチェアに揺られて、日本であれば縁側にたたずみ、そして静かに終わりを迎え、最後には"1つになる"("また皆が集まる"、"次が始まる")というふうに感じました。ここは宗教観、生死観などによって印象は異なるかもしれませんね。
アート、クリエイトとスピリチュアル
さて、心の中の書き溜めを整理しながら、大西氏のnote記事を読み進めていた私は、近年にない衝撃を受けました。
それは、記事の最後の最後、"最初のスケッチ"と書かれた1枚の画像を見た瞬間の出来事です。背筋がゾッとして、思わず「うおっ、!」と声が出てしまいました。まさに"戦慄が走る"という感覚でした。
なんと、最初に大西さんのカノンを鑑賞してから、私がずっと心の中でモヤモヤと書き溜めていたことが、本当にその1枚にすべて表現されていました。少なくとも私にはそう思えて、かなりの衝撃を受けつつも、その指は、しっかりと"スキ"ボタンを押していました。。。
ここまで、書いて(読ませて)おいて言うのは何ですが、このスケッチを観て、感じていただければ、こんな稚拙な記事を読む必要はないと、我ながら心の底から思います。。。
このスケッチを観た私は、「いわゆるアーティストやクリエーターと言われる人たちは、音や映像(色や形のレベル?)、その他、五感で感じることを(言語化することなく)"直"に理解・表現できてしまうんだろうな」と、あらためて感嘆しました。
そして、なんとなく、「こういうことが"スピリチュアル"という言葉の本質なのかもしれないな」とも、漠然と感じ始めています。
私が霊感ゼロである理由も、"これ(無理やり言語化しようとすること)"なのかもしれませんね。まさに「考えるな!、感じろ!」といったところでしょうか。。。
おわりに
それでは、今回はこの辺にしておきます。
最後に、私がパッヘルベルのカノンを好きになり、スピリチュアルな何かを感じるきっかけとなった、上野隆史氏の指揮による日本ニューフィルハーモニック管弦楽団の演奏のリンクを貼っておきます。
よかったらお楽しみください。
それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございました。
お越しいただき、ありがとうございます!! この場所で、少しでもポジティブになれる、少しでも顔を挙げて前向きになれるような"何か"を感じてもらえたら嬉しいです🙏。もっと多くの人たちに、もっとポジティブな気持ちになってもらいたく、この場所を充実させていきます😇
