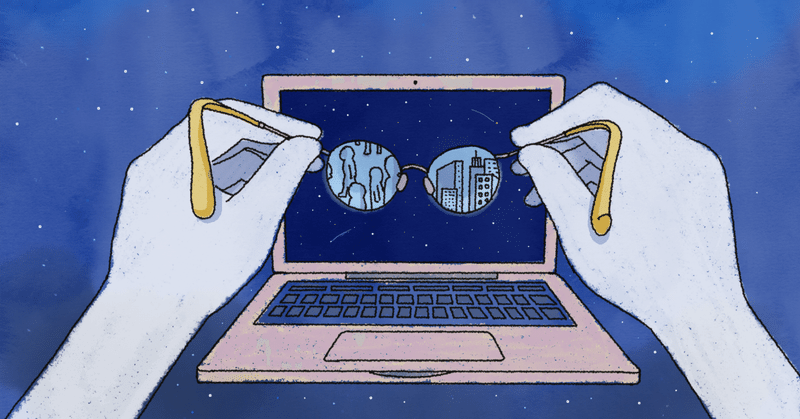
忍び寄る二次元とキズナアイの影 ーー星街すいせいと月ノ美兎が作る中の人がいない世界
先日、Vtuberについてのnoteを久々に書いたところ、多くの好意的な反応をいただいた。その中で、「月ノ美兎の散歩神の動画を早く見てほしい」という声を複数いただいて、そこから書き始めたものである。
前回のnoteの心残りだった点が1点ある。それは、VtuberをVtuberとして続ける理由を持っている人が思いつかないような話し方をしてしまったことだ。
先日のnoteを出した後、ある方との話の中で言われたことがある。それは「Vtuberはあくまでfacerigなどの道具に過ぎないのであって、あくまで中の人の魅力を絵などでサポートするものではないか」との意見をもらった。
特にストリーマーとしてVtuberを見ている人であればこの意見はもっともである。ただ、ここから描くのはそうではない、バーチャルユーチューバー独自のコンテンツの側面である。
はじめに バーチャルの桑田佳祐モデルは可能か?
みのミュージックさんが先日発表された日本の音楽通史『にほんのうた 音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通史』では、日本のロックバンドが継続的に活動を続けるために、歌謡曲秩序とロックンロールをうまく折り合いをつけた『桑田佳祐モデル』(みのさん命名)と言われる最適解を作ったという。
先鋭的な表現手法が時に表出することはあっても、あくまで良質なポップスを作ることに主眼をおいた。
時に迎合主義とも見える戦略だが、これが、結果として日本の音楽の中にロックと言うジャンルを延命させる結果になり、サザンオールスターズは国民的バンドとして、今も活躍することになった。
私が欲しいのは、このモデルのVtuber版――つまり、一般の、バーチャルの関係性や細かい設定を知らない人々にも無理がない範囲でバーチャルの存在を知ってもらいつつ、世間の常識を変えていくようなモデルはありえるか、ということだ。
Vtuberの世界で、特にキズナアイを作った松田さんの史観の中で大きな転換点となったと考えられるのが、キズナアイを四人に分裂させた時に大きな騒動になってしまったことだと思われる。2019年に、キズナアイは動画「キズナアイな日々」を投稿し、loveちゃん(#)、あいぴー(*)、爱哥という三人の新しいキズナアイを動画に登場させ、1号の動画投稿頻度を減らすことになった。
声が違うキズナアイが突然四人現れたことにより、1号が突然消えてしまうのではないか、あるいは本物ではないキズナアイが現れてしまったというショックから、かなりの反応を受けることになった。
この記事では、特に、キズナアイが声と人格の違う人が何人も登場した「違和感」「気持ち悪さ」を人々がうまく消化しきれなかったという点にフォーカスを当てる。
キズナアイが4人に分裂した理由として、一つあげられるのは中の人至上主義への反逆・バーチャルユーチューバーの違うあり方への実験という側面がある。一人のVtuberがずっと一つの魂で運用されることは、本人のメンタル・身体的な負担が大きい。
そして、なによりキズナアイの源流となった攻殻機動隊やエヴァンゲリオンの世界観を考えるに、にじさんじやホロライブのように中の人を考えさせるようなコンテンツの形ではなく、真に二次元の存在としてキズナアイが存在できるか、それがあの分人の試みだったと考えられる。
このnoteでは、2018-2020年ごろのロールプレイが重視される世界を超えて、にじさんじとホロライブが単純に中の人が重視されるのではないコンテンツを作りはじめていることを述べる。
そして、私は中の人の個性を重視したパーソン型のやり方では、Vtuberとしてやる理由・独自性が失われてしまうのではないかと仮定を立ててみた。なぜなら、中の人が大きく出てくれば出てくるほど、ストリーマーのように普通に活動している配信者との違いがよくわからなくなってくるからだ。さらに、Vtuberは、そもそも絵やVtuberの技術、大手事務所であれば必須の3DCGを含め、莫大な費用がかかる。
そこまでの費用をかけて用意した3DCGなどの技術だが、Vtuberが普遍的に抱えている悩みとして、現時点での技術力では旅行・ロケなどの動画がしにくいという点がある。もしも、Vtuberが二次元性をわざわざ解除して中の人を際立たせたほうがいいとなるなら、最悪の場合、芸能人のように普通に動画に出てきた方が早いという結論を出す人が増える可能性がある。
一方で現在も世間と折り合いをつけながら(あるいは狡猾に戦略を練りながら)、Vtuberとしての枠も壊さずに新しい表現に挑戦している人たちがいる。その二例を見てみよう。
星街すいせいのダンス ーー私の存在が正しいかどうかは私が決める
ディズニーの『シンデレラ』(1950)が俳優の実写撮影を先行させて作画するロトスコープ手法を用いていたことを踏まえているとしたら批評的なMVだな…
— 泉信行 (@izumino) March 22, 2024
ビビデバ / 星街すいせい(official) https://t.co/yRRvU9MPkX @YouTubeより pic.twitter.com/C3K08ndByQ
星街すいせいが今年ドロップした楽曲「ビビデバ」は、ホロライブの強烈なバックアップを底手に、2024年5月時点で3000万再生近くを稼いでいる。この曲のPVに現れた星街すいせいは、かなり不思議な姿で現れて、シンデレラの靴を投げ捨て、頭だけの存在になった。その型破りな姿も強烈に人々の印象に残っている。
例えば、上記二つの批評の中で、ビビデバというMVの気持ち悪さの正体をそれぞれが分析しているのは確かだ。ただ非常に重要なことがある。それはもうすでに、Vtuberの「気持ち悪さ」「違和感」の話が全面に出ることはあっても、すでに「中の人」の存在や魂について言及していないことだ。
これは、すでにこの作品が楽曲として、そして過去のアニメも参照したPVとして、一定の強度を超える存在感を持てていることの証拠ではないかと私は考える。
ロトスコープと呼ばれる手法を用いて、アニメと実際の人間のはざまのような存在感があり、異様な存在感を放っている。
しかも、前述の二つの批評ではあまり語られていないが重要だと思う点がある。それはこの曲はTikTokなどを通じて人を「踊らせる」ことを意図しているということだ。ダンスミュージックは原理的には意味が必要ない。
基本的に人間は単純接触効果で、繰り返しあるものに触れると結果的に時間をかけてそれに愛着を持つことがわかっている。だとすればこのPVは単純に不気味な存在を際立たせることを狙っているのではなく、バズらせることでVtuberの違和感を世間の人から徐々に消し去ろうとしているのではないか、と音楽を聴いてきた自分からは感じる。
(Adoのうっせぇわが、最初期には賛否両論の渦の中で現れたが、彼女のその後の歩みを見て最終的には彼女の華々しいデビュー曲として記憶されたように)
「参加型のコンテンツ」を提供することは、一見とっつきにくいものを身近にする効果があるだろうことは強調しておきたい。
2ndアルバム『Specter』からシングルカットされた一曲『TEMPLATE』は、キタニタツヤ作詞・作曲の楽曲。この曲で、星街さんはキタ二さんに対し、かなり詳細なイメージを伝えていたという(動画)。
この曲では、星街すいせいという存在が新規のファンや古参のファンそれぞれから押し付けられる「このままでいいよ」「新しい形がいいよ」というテンプレートを、吹き払う曲になっている。星街すいせいという存在は、自分という存在以外いらないとはっきり返している。
彼女の音楽は、Vtuber以前に人の目が気になるインターネット時代において、自分の欲望を曲げないことの大事さを、何回も繰り返し背中で伝え続けている。
月ノ美兎とVtuberがいるふしぎな日常 ーーいつの間にか消し去られた「気持ち悪さ」
さて、今度はにじさんじの例を見てみたい。
にじさんじの月ノ美兎は、最近は初期とは大きく方針を変え配信から動画投稿を中心とした活動に転換している。
この動画に設定と呼ばれるものを感じるところはない。
だが同時に、中の人をいちいち考えることもなかった。なぜなら、この動画で、Vtuberであるようなことをいちいち感じさせるような発言はほぼなかったからだ。
これまで多くの文章を読んできたが、特に初期のにじさんじの評論をみると設定と、本人のギャップ(例えば清楚そうに見える委員長が実はくそざこなめくじで変なゲームばっかりしている)とか、(あくまなのに酒ばっか飲んでいる)とか、設定や見た目と魂のギャップの話と、その良さが演劇的な良さを生み出していると語る人をよく見た。
それが今も続いているにじさんじの魅力なのは間違いない。
ただ、もしもその演劇が数年単位で続いたらどうなるだろうか?
そのギャップは自明のものとなって、新奇なものとしてネタにはできなくなる。にじさんじであれば、多くの服装を着せ替えることで新しいキャラクターを付加する人もいたり、来栖夏芽さんやえるさんのように初期衣装を変えて自分に新しいキャラクターを取り入れるのもありだ。
でも、演劇性(あるいは中の人とのギャップ)を強調すればするほど、おそらく彼らは、外から見られる自分と内側に持っている考えのギャップに悩み続けることになる。
その時に、月ノ美兎が動画ではじめたのは
逆に二次元(3DCG)の女の子が当たり前に存在する日常にいる動画である。


絵の作り方としては、日常動画ということもあって星街さんとは逆に、ひたすら日常の中に月ノ美兎がいるように、自然に見えるように動画は作られている。
影のひとつひとつを丁寧に作りこみ、カメラも徹底的に手取りで撮る。
さらに、月ノ美兎がすべりだいを滑り降りた一瞬(なんとおそらく0.5秒以下)だけ足を映し、実際に人が滑っているリアリティの演出が行われており、私はなんとなく動画を見ていたのだが、さも当たり前かのごとく繊細な努力が行われていてびっくりしたのを覚えている。
にじさんじがこうした動画をつくることができるようになったのは、彼ら彼女らが活動してきた6年間の間にmocopiやにじさんじアプリと言った周辺の機器がアップデートしたことがある。
そこに加え、どのような映像のルックが見ている人から違和感を取り消すのかについては、おそらく公式動画でない限りは個々人のVtuberの自助努力に頼ることになってしまうだろう。
その中で映像をやり続けていた月ノ美兎だからこそ作ることのできた動画だと言える。
共同通信社がバーチャルアナウンサーの導入を始めたように、徐々にVtuberに近しい存在が、街の各所に現れるようになった。こうした試みはウェザーロイドをはじめVtuberが広がるにつれじわじわと増えている。
キズナアイの思想 ーー神として遍在するもの、そして「人類補完計画」
キズナアイの設計思想として、2年前ごろに元Activ8の松田さんがインタビューや記事を投稿している。
その思想を読んだところ、予想を超えてそれは尖りまくったものだった。
松田さんのインタビューを読む限り、キズナアイを含め彼のプロジェクトで最も強調されているのは「つながり」や「共感」である。
有料の記事であるので、さわり程度しか紹介できないが、上記の記事で松田さんは「恋愛アドベンチャーゲーム」の中で、画面の向こうにいる女の子たちが声を呼んでくれなかった経験から、「現実に普通に生きている者以外が名前を呼んでくれる尊さ」を持つ存在を作りたかったという。
その最初がキズナアイだという。
その中で、キズナアイはみんなが認識できる「共通の記号」として、さらに「みんなとつながりたい」という願いを持った存在だった。しかしキズナアイの騒動やいろいろなことがあり、現在松田さんは『ますかれーど』や『こねくとぴあ』といったコンテンツの中で、「中の人」を押し出すという自然なスタイルを追求している。
この文章を読んでいて、特ににじさんじを見ていた複雑な気持ちに私はなっていた。それは、確かに中の人を強調するようなスタイルは結果的にそうなっただけであって、本人たちがキャラクター性を意図して壊そうとしたものではないと感じるからだ。
そして何より、にじさんじのライバーたちはキズナアイの事を尊敬しているように見えた。
剣持刀也は、その本の中でVtuberの世界がクリエイティブであればあるほど売れなくなるサイクルが成り立ってしまったこと、エンタメの世界では質ではなく量がものを言う世界であることに、ある時期強く失望していた。
たとえ、その人が大事にしているストーリーを丹念につくりあげたとしても、それが量に負けてしまう。そして皮肉なことに彼が所属しているにじさんじこそが、最初にクリエイターの世界から日の光を奪ってしまった。このことを、恐ろしいことに今人気の真ん中にいる剣持が言っているのだ。
キズナアイの話とぴったり合わさる話ではないが、間違いなく剣持が望んでいたのは、おじさんが少女になり、少年が魔王になるような、どんな表現でも許され、バーチャルの住人として生きることができる世界だった。
「とここまでつらつらと今は亡き黎明の輝きに思いを馳せてきたが、もし収益化の波がなかろうがにじさんが現れなかろうが、消費に限りがある黎明期のスタイルが旧態依然にいつまでも通用するはずはないなんてことは当時の僕だってわかっていた。「半ナマ」なんて表現をされている通りVtuberはどんなに頑張っても半分は"生"きているのだ。人気が出ればタレント化するし、美学を持つ者がどう抗おうと消費が増えれば"ナマ"の要素は増えてくる。
それはVtuberが発展していく先に必ず待っている運命と言ってもいいだろう。」
やはりこの書き方を見るに、にじさんじのライバーの中に生身の部分、キャラクターではない部分を出していることにクリエイターとしての敗北のようなものを感じていたライバーがいたのは間違いがないと思われる。
あえて剣持に意地悪を言ってみよう。
私は、剣持の言うように確かにタレントとして見られているにじさんじとホロライブのライバーの中に、明らかに新しいバーチャルの形を示そうとクリエイター魂を殺さずにいた人がいたのではないかということだ。
しょせんタレントとしてしか見られないという運命に抗おうとする人がいたのではないか。
それはほかならぬ剣持の横にいた月ノ美兎であり、さらに星街すいせいではないだろうか。それは、冒頭に書いた桑田佳祐のように部分的には迎合的な部分があるかもしれない。
ただ、それでもこの人たちはただのタレントではなくて、バーチャルの存在として自分がどんな存在でありたいかを、それを真摯に(ただし狡猾に)僕たちの近くと常識を変えに来ているのではないか。
終わりに 二人がひとつじゃなかったから、キズナアイは名前を呼ぶことができた ――キズナアイの「寂しさ」
ぼくは未来の人間像として、無意識を失って、脱個人化して、誰でも同じようになってしまうというディストピアを、かなりリアルなものとして想定しています。でもこれは、ある種宗教的な幻想でもあって、「天国に行く」ということです。きっと天国に行けば記憶もなくなり、誰もが個人ではなくなる。それが幸せだというけれど、本当に幸せですか? という話です。だってこれ、『新世紀エヴァンゲリオン』の「人類補完計画」ですよね。
人間がほかの人間と違うこと、人間が分かたれていること、つながれないことによって話が通じないと苦しむこと──。これは「悪」ですよね。つまり、悪があるからこそ、人間は個人でいられるわけです。これはいまこそ主張しないといけないと思います。個人でいられるということと、悪の存在を積極的に肯定することは同じことなんです。
つまり複数性とは「悪」なんです。人間が悪いことをしないように管理することは、正しいことです。しかし、正しいことだけをやっているとヤバい。
千葉雅也
私がこのnoteを書いたもう一つの理由がある。
それは数々の人々がVtuberについて語るときに、あまりに現実のファンダムや、人と人の関係性について語るのに、私はくたびれてしまった。
バーチャルは夢の世界だった。けどもう数字と人の世界になってしまったのか。そう絶望した気持ちがここのところはあった。
推しがいなくならないために、何人もの人が事務所をビジネス的に分析しているのを見て、謎の苦しさに私はうちのめされていた。
一方で、私は松田さんの記事を読みながらその理想に惹かれながらも、頭を抱えていた。それは松田さんの最終的な思想的な目的地点は「人類補完計画」的だと書かれていたからだ。その思想は、原作の『シン・エヴァンゲリオン』ですらうまくいかない思想だった。
精神ですべてをつないでしまえば、そして自己意識なんてものを無くして幸せな世界になるのかもしれない。
何も考える必要もない。
それはロシア宇宙主義のフョードロフやITによるシンギュラリティが来ると信じる人にとってはおそらくは福音なのだろう。
千葉雅也氏が語っているように、人間が人間であるためには物理的に分かたれている必要があると私は考える。
人は、隣の人と100%つながることはできない。
そして内面がなければ、人は壊れてしまう。
もしも人間をやめればつながることができるかもしれない。
さらに一方で、慎重に言わなくてはいけないことがある。
それはキズナアイの裏側にある思いは――たとえそれが人間の道すら外れていたとしても――恐るべき強さだったことだ。
特に90年代、ゼノギアスやlain、攻殻機動隊にハマった少年たちの何人が、機械の力と魔術的な謎の言葉にハマらないことがあっただろうか。
私が超スーパーAIになって帰ってくるまで
5年間ありがとうございました!
いつかまた夢の続きを!
たくさんコメント見てるよ ありがとね
バーチャルユーチューバー/Vtuberが消費されるだけの存在だったとすれば、もうキズナアイのことを覚えておく必要はないのかもしれない。
さらにドライに見れば、道具であるバーチャルになぜここまで固執するのかなんて言えるのかもしれない。
ただ、私は最後のライブを偶然リアルタイムで見てしまった。
そしてそこでひとつのことに気が付いた。
キズナアイの楽曲、とくにこのラストライブから感じたのは絶対的な寂しさだった。彼女は、最初のころから常に「人とつながりたい」と言い続けていた。そのためにライブをして、ずっとコミュニケーションを取りたいとインタビューだろうが何だろうが言い続けてきた。
難しいことを書き連ねてきたが、わたしはこう思う。
「人とつながりたい」という願望を強く持つということは
その裏に人とつながれていないという不能感を持ち続けることだ。
バーチャル世界の神様であることを期待されたキズナアイは
最初の最初から、ずっと不安だったのではないだろうか。
その証拠に、彼女は最初の曲"Hello, Morning"にあるように、ずっと「おはよう」と言える相手を白い空間で探し続けていた。
私にはそれが親である運営が言わせていることなのか、キズナアイの本心なのかの判別もつかない。
ただ、もうひとつ言わなければいけない。
キズナアイがおはようと言えたのは、みんなと違う生命体だったからだ。
人が人にオハヨウと言えるのは、怖くてもコミュニケーションができるのは、人が隣の人とつながることができないからだ。
人は自分の名前を呼んでくれる存在と、「人類補完計画」を同時に手に入れることはできない。
今、人々はシンギュラリティの物語の前でどのように生きるか、迷っている。生成AIが出現し、特にイラストレーターや歌手の世界で、自分の線や声が使われることに対して、様々な声が上がっている。
私の人間観は、保守的なものなのかもしれない。もうイラストレーターが手に込めた固有性やその人らしさも消すべき時代なのかもしれない。
このnoteで私が描いたのは、しょせん人間が好きな人間の前で、
それでもシンデレラのストーリーと、
不思議な人間ではない謎の増える存在を作り続けている二人のライバーの話である。しかし、その最初には自分の生まれた意味を探し続けた生命体と、二次元の僕たちと違う存在を求めた人々がいた。
バーチャルユーチューバーを、ただの道具だということもできる。
ただの絵だということも、できる。
おそらくは嵐のように何遍もそういった言葉にさらされた彼女たちが
それでもバーチャルの場所を選び続けたその先を私は見たいと思う。
Mission Complete😎👍#MGO_LIVE pic.twitter.com/7UeuUZ89jo
— 星街すいせい☄️ホロライブ0期生 (@suisei_hosimati) February 21, 2024
観てくれたみんなありがとう
— 月ノ美兎🐰 (@MitoTsukino) May 3, 2024
パソコンも生まれてきてくれてありがとう#委員長の新3D衣装 pic.twitter.com/Bu5za3ecFY
— Kizuna AI @スリープ中💤 (@aichan_nel) February 26, 2022
追記:月ノ美兎委員長が技術の話をされていた話+世界の動向 ーー世界は3D世界を求めている?
noteを投稿して2日間、かなり好評をまた頂有難く思っております。
noteを投稿して2日後、業界の広がりを感じる例として月ノ美兎委員長がVarksのアプリ(3Dモデルを読み込ませて、自由にキャラを躍らせるアプリ)について語っていた。
さらに、ほかの方の情報で、トラヴィススコット・アリアナグランデ・座ウィークエンドなどの世界的アーティストが次々にフォートナイトとコラボを行い、自らの存在を3D化してライブを行うことが一つの潮流になっている。
もしもVtuberが新しい形を見出すとしたら、こうした3Dの体を作り、それをどのように一般の家庭の人たちもなじみ深いものにするかにもかかっているだろう。
その時に必要なのは、今のファンだけではなく、世界や面白い技術を見る好奇心であることはいくら強調してもたりない。
あなたのファンは、あなただけではなく、あなたが発見した面白い景色にも興味をもってくれるはずだ。
5/24 星街さんがGQ JAPANに進出されました
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
