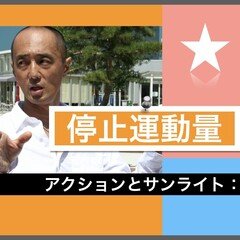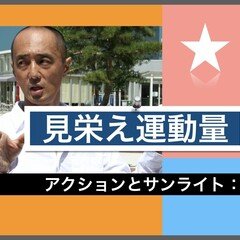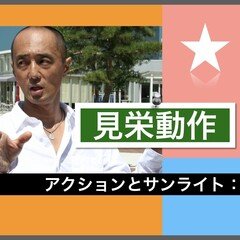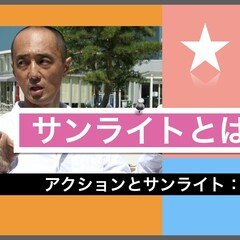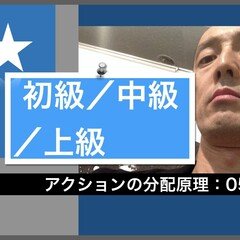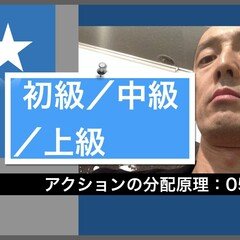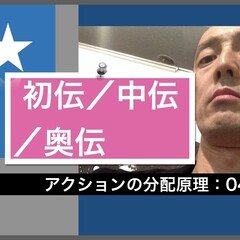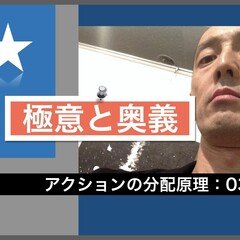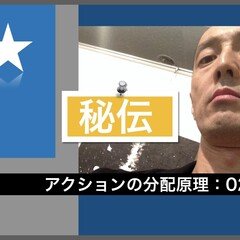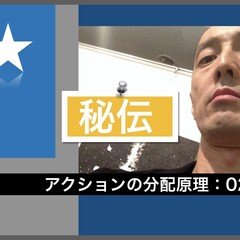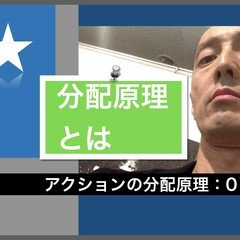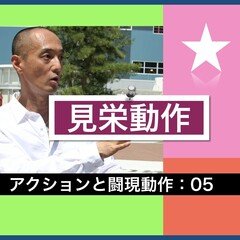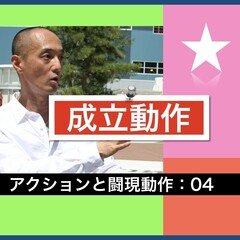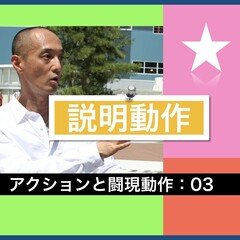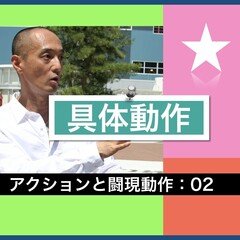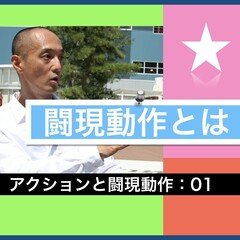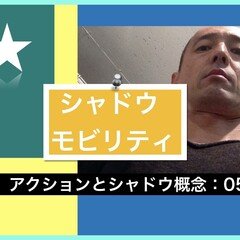最近の記事

アクションとサンライト05:停止運動量
<停止運動量> ●=瞬間停止形態運動量 ●見栄え運動量=見栄え維持運動量との違いは、動作の流れにメリハリをつけるために、瞬間的に行うというところ。つまり毎回全ての技に対して行うわけではない。 ●残心運動量と被る場合もあるが、ここではそれ以外のケースとして設定する。 ●残心運動量の視線ベクトルが倒した相手に向いているのに対し、停止運動量は、必ずしもそうとは限らない。=客席・カメラ方向の場合もある。(=相手がリアクションで視線範囲からフレームアウトした状態) ●見世物化するためには、きれいな形を表出する必要がある。 ●そしてそれだけでなく、その形を瞬間停止させることで技の印象を強めることが要求される。これが瞬間停止形態運動量、略して停止運動量である。 ●メリハリをつけることも目的の一つなので、リズムにも影響を与える。 ●いずれにしても、運動的な静と動の相反共存なので、ここにアクション習得のテーマが潜んでいるのである。つまり極意レベルということ。 そんな話をしています。

アクションとサンライト04:残心運動量
<残心運動量> ●残心運動量 ●残心ポイントとは、格闘過程の各終末に発生する、または挿入することができる説明動作の挿入ポイントである。 ●入れるか、入れないかの大枠は、振付けによってある程度決められるが、エースが自分で入れるべき決定権を持っていると考えてよい。 ●もちろんこれは自立したエースの場合のことで、全ての人が目指すべき目標の一つでもある。 ●残心運動量とは、残心を決めるときに決めの技に対して、他の技よりも力感を込めるなど、アクセントを付ける必要がある。そのため運動量が多くなるというのが一つ。 ●もう一つは、特に多勢相手の連続的な振付けに挿入する際は、それまでの流れを生かしつつ、いったん止めるため、エース自身が急停止・瞬間静止・急発進という過程を経ることになる。そのために、これまた運動量が上がるということ。 そんな話をしています。
マガジン
記事

アクションの分配原理01:分配原理とは
<分配原理とは> ●技術を分配するためには、ある種の法則性に従う必要がある。それが分配原理である。 ●そのために必要なのは、まず技術の明確化とその分類。次に分配原理となる。 ●秘伝/極意/奥義というのは、分配原理の一つである。 ●他にも初伝/中伝/奥伝や、初級/中級/上級などがある。これらがどう異なるのか、それを明らかにすることで、分配原理自体が整理され明確になるのだ。そうなることで初めて利用することができるようになる。 ●これらをアクションの技術性に限定して線引きし、定義したものがアクションの分配原理である。 ●分配原理の重要性は、習得における優先順位を決めることが、上達の正確性と最短性に関わってくるからだ。 ●今回扱う、秘伝/極意/奥義や、初伝/中伝/奥伝、初級/中級/上級は全てが密に関わってくるということが明らかになるだろう。 そんな話をしています。
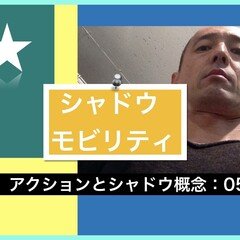
アクションとシャドウ概念05:シャドウモビリティ
<シャドウ・モビリティ> ●通常用いられるモビリティ=アクション・モビリティは、単なる機動性を指す概念に過ぎない。それは高い運動能力や操作力に裏打ちされた機動性であり、具体性はない。 ●それに対しシャドウ・モリビリティとは、立回り表現におけるモビリティを高めるために、密かにやっていること。 ●=例えば、自者運動量保存原則はその基本中の基本。 ・運動量操作には、保存・発生・利用の三つがある(さらに細分化されるが)。 ・運動量操作法は、全てシャドウ・モビリティである。その際、相手と合わせる能力はシャドウ・アジャスタビリティ。 ・ただし自者運動量発生原則だけでは単なるモビリティに過ぎない。 ●まとめ ・シャドウ・モビリティ=立回り表現におけるモビリティを高めるための操作を含む機動性。 ・三つの運動量操作(保存・発生・利用)を駆使する。 ●シャドウ・アビリティ ・高いモビリティとアジャスタビリティを使って、相手と合わせる能力。 ・運動構造の一致は、その基本となる。 ・双方のシャドウ・アビリティが高くないと、高度な立回り表現としての高速化はあり得ない。 そんな話をしています。