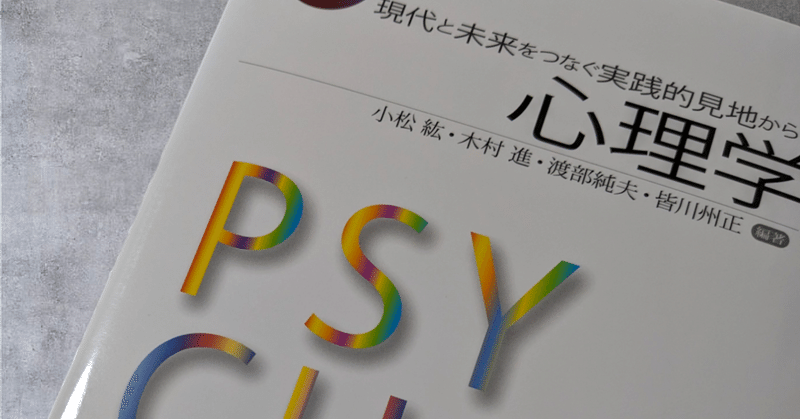
まなびのきろく#4 「福祉心理学」学習メモ~社会人の通信大学1年生~
福祉心理学科 スタディ・ガイドから
・well-beingという考え方=昨今言われている「生活の質(QOL)」を支える概念。
・福祉心理学は、現在この「生活の質」を充実させ援助することができる学問として期待されている。
・心理学でいうところの「自我」についての理解が必要になる。
・デカルトは2つのものを切断するという考えによって(物と心のように)客観的見方の手法を提示することに成功した。→この考え方は自然科学を発展させる大きな原動力になった。
・「福祉心理学」は1人1人に幸せを提供するための実践的学問。そのためにも「人間尊重の精神」と統合を通しての「創造」への考え方を抜きにしては考えられない。
?「統合」とは何?
・レポートを作成するにあたり、「社会福祉」と「福祉心理」の関係をどのように扱ってよいのか困っている方が多い。
・「社会福祉」の領域を考える→福祉の対象となる人・家族・地域などに直接かかわり、成果をあげる「臨床的福祉」の側面がある。
・「福祉心理」は主として「臨床的福祉」に関する専門性を用い、高いレベルの心理学的な知識と技術を必要とするものであると考えられるので、「臨床的福祉」の視点をしっかり持って、分析・考察を行うことが大切。
?「臨床的」とは何?
レポートを作成するにあたり、将来の「福祉心理学」の姿を考えるという視点も入れて欲しい。
レポート課題集C 心理専門編より
・福祉心理学とは・・・この世に生を受けた瞬間から死を迎えるまで、ライフサイクルを通して抱えなければならない問題や課題は山のようにある。このような時代を生き抜く人々の、一人一人が求める「幸せの追求」をサポートし「生活の質」の向上のために貢献する必要不可欠な学問。
・「他者への関心と理解」「社会への関心と理解」「自他尊重的コミュニケーション力」「他者配慮表現力」「社会貢献力」を身に付けてほしい。
・自分の身近な福祉の問題を取り上げ、「福祉心理学」の理論や技法から、どのような援助が可能なのかまとめなさい。
・「福祉心理学」では、まず心理学の視点から人間理解を深めていくことを行う。そのうえで、何らかの援助を必要としている人に対して、どのような援助方法があるのか、ひとりひとりのニーズにどのように応えていけばよいのかについて、理念と実践から考えていく。
・「心理学」を「福祉」にどう活用するかという観点から考える。
・テキスト「現代と未来をつなぐ実践的見地からの心理学」の第一部「心理学の歴史から未来を考える」~第三部「心の成り立ちと個性の形成を考える」までをよく読み、人間の心理的活動がどうなっているかを理解するための努力をする。
・参考図書にあたり、人間理解のための方法や視点の共通点と違いについてまとめ、考えを膨らませる。自分自身が今まで行ってきた理解の仕方についてもふりかえりを行う。
人間のすべての行動面に「心理学」は関わりをもちますから、日々の生活の中で気になる人間の行動をとりあげ「心理学」とつないで考えてみるとよい。
◎人生のライフステージの課題とは
◎福祉心理学の視点で理解しているか
◎テキスト以外の文献で発展的学習をしているか
◎自分の考えをまとめる力があるか
◎専門的内容をどれくらい理解しているか
到達目標(レポート課題集より)
1.人の心の基本的な仕組みと機能を理解し、環境との相互作用の中で生じる心理的反応を理解し、説明できる
2.人の成長・発達段階の書く気に特有な心理的課題を理解し、説明できる
3.日常生活と心の健康との関係について理解し、説明できる
4.心理学の理論を基礎としたアセスメントの方法と支援について理解し説明できる
5.公認心理師に関する内容について理解し説明できる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
