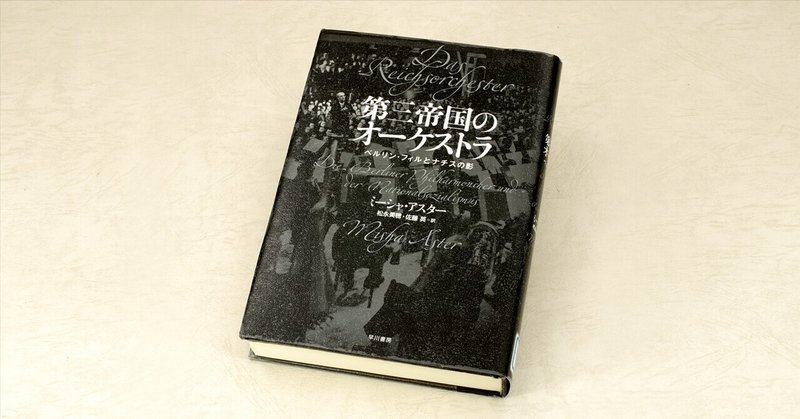
「第三帝国のオーケストラ ベルリン・フィルとナチスの影」
ミーシャ・アスター著 松永美穂・佐藤英訳 2009年12月 早川書房
ベルリン・フィルはナチスが政権を握った1933年、政権のプロパガンダに利用するため、ゲッベルスの宣伝省の管轄下に置かれ、「帝国オーケストラ」として特別の地位を与えられた。ナチスの公的な機関として様々な役割を担わされると同時に、戦時下で破格の扱いを受けながら終戦まで活動を続けたベルリン・フィルの様子を綴ったノンフィクション。
本書は2015年頃かそれ以前に1回読んでいるのですが、感想を記録していなかったため細部をかなり忘れていることや、改めて確認しておきたいところがあったため再読しました。
楽団は1882年にベンヤミン・ビルゼの主催するオーケストラから脱退した団員54名がベルリン・フィルハーモニー管弦楽団として独立。1903年には団員の出資による有限会社として法人化、1930年代まで独立した自主運営のオーケストラとして活動してきた。
ところが、1930年代になると、経営は次第に苦しくなる。その理由としては第一次大戦後のハイパーインフレなどによる不況、ベルリン市の財政難による支援の減少、同じく国家による支援も不定期で安定しないこと、資産家の個人による寄付にも限界があった、といったところ。そこに1929年の世界恐慌により、財政は一層難しくなる。
1933年1月30日にヒトラーが首相に任命され、状況は一変する。2月7日には1933年度の「国の予算第1種」ということで特別の助成を得られるオーケストラの一つにベルリン・フィルが含まれる、と内務省の見解を示す(他のオーケストラはシュレージエン・フィルハーモニーとナチス帝国交響楽団)。1933年3月~4月フルトヴェングラーがゲッベルスに援助を求める。内務省と宣伝省の間で調整が行われ、ベルリン・フィルは宣伝省の管轄下に置かれ、ヒトラーの承認によって1933年11月1日に正式に「帝国オーケストラ」となった、とのこと。
ついでに記しておくとナチス帝国交響楽団というのは正式には「国家社会主義帝国交響楽団“Nationalsozialistische (RS) Reichs-Symphonie-Orchester”というらしい。ドイツ語で検索してもあまり有意な情報は得られないのですが、1933年のニュルンベルクでの党大会で演奏し、その際ゲッベルスは日記に「ここには・・・第一級のオーケストラが来なくてはいけない」と記したとのこと。
ナチスが文化・芸術、スポーツなどの分野において国民を啓蒙しつつ、国威発揚の手段として利用しようとする姿勢は政権獲得当初より積極的であり、政権獲得後1年を経ずしてベルリン・フィルが「帝国オーケストラ」としての地位を獲得した理由は明確だと思います。ゲッベルスをはじめ、ヒトラーやゲーリングといった面々がクラシック音楽に関心を示していたこと、この点については特にベルリン・フィルが既に世界的なオーケストラとして充分に知名度があったこと、更にフルトヴェングラーという20世紀前半における最大級の巨匠指揮者がその第1指揮者を務めていたことが、殊更大きかった。フルトヴェングラーについてゲッベルスは日記で何度もその演奏の感想を記述しているなど、彼自身が心酔していることが窺われますが、フルトヴェングラーの活動はベルリン・フィルの活動と不可分であり、ゲッベルスが殊更ベルリン・フィルを「帝国オーケストラ」として格別の計らいをしていたこともむべなるかな、と思います。
1934年、フルトヴェングラーはヒンデミットの交響曲「画家マティス」の初演を巡る政権とのトラブルでベルリン・フィルの第1指揮者、ベルリン国立歌劇場の監督、帝国枢密顧問官、帝国音楽院副総裁といった公職を全て辞任したが、1935年には客演指揮者としてベルリン・フィルに復帰。
ヒンデミットは音楽的に殊更前衛というわけでもなく、更にユダヤ人でもなかったのですが、ユダヤ人の音楽家との交流や、オペラでのヌードシーンがあるなどの理由で“退廃的”とのレッテルを貼られ、「画家マティス」のオペラ版の演奏を政権が禁じたことにフルトヴェングラーが反発したことにより上記の騒動が起きた。
この「ヒンデミット事件」をはじめ、フルトヴェングラーはナチスと距離を置く姿勢を貫いていた一方で、1945年2月に亡命するまではドイツに留まり演奏を続けた。
戦後に非ナチ化裁判でしばらく活動を禁止されていた理由には、ナチスと完全に決別した姿勢をとらなかったことが問題視されたわけですが、フルトヴェングラーにとっては音楽と政治は別との考えが根底にあったことは間違いないと思われます。
“音楽と政治”の問題はロシアのウクライナ侵攻のときでも問題となっていますが、これもその政治情勢の劣悪さが道義的問題にまで及んでくると、それをまったく別物と割り切ることは難しいと考えます。
フルトヴェングラーが“純粋な音楽の奉仕者”であったのか、それを建前としつつ己のやりたいことを続ける動機に利用したのではないか、といった問題はなかなか決着をつけるのが難しい問題だと思います。
実際のところ、真実はその中間の何れかにあるのだろうと推察されます。
フルトヴェングラーのことはともかくとして、本書のテーマであるところのベルリン・フィルとナチスの関わりこそ、まさに“音楽と政治”の問題の中核をなす問題といえます。
国威発揚のプロパガンダの手段として一流の芸術家やアスリートなどが称揚されることはなにもナチスに限った話ではなく、普通の民主主義国であっても行われていることですが、こうした傾向は非民主的な独裁国家や共産主義国で特に著しいのはさまざまな事例からも明らかといえるでしょう。
組織としてのベルリン・フィルは「帝国オーケストラ」となる前は自主運営の有限会社であったため、団員の選考も当然のことながら音楽的素養のみで選ばれていましたが、これがナチスの公的機関となると(というより、あらゆる組織全体について)ユダヤ人団員の存在そのものが問題視されるようになってきます。
1930年代の団員数は95-106名の間で推移し、そのうちユダヤ人団員は4名(概ね4%、その中にはシモン・ゴールドベルクもいた)であったとのこと。
フルトヴェングラーは楽団の演奏水準を維持するため、ユダヤ人団員の存在を容認するようゲッベルスに何度も念押ししているようですが、ゲッベルスはこの巨匠指揮者との関係維持のため、ある程度黙認の姿勢を示しつつ、最終的にはユダヤ人団員の数はゼロになる。
演奏団体としての優秀な団員の必要性よりも、ユダヤ人がドイツ国内に存在することそのものが生命の危険を孕むようになってくると、必然的に団員として留まることは不可能となっていったようです。
ユダヤ人団員の消滅の一方で、ナチス党員の団員の数は明確に確認できる者15名、可能性のかなり高い者3名で最大20名ほどは居たようです。
興味深いのはオーストリア併合後に同じく「帝国オーケストラ」となったウィーン・フィルでは最大42%がナチス党員であったとのこと。ウィーン・フィルのナチスとの関わりについてはウィーン・フィルのホームページにもその歴史の説明ページに項目があって説明されていますが、
https://www.wienerphilharmoniker.at/ja/orchestra/history/nationalsozialismus
それによると1938年以前にも党員数は20%、1942年には123名の団員のうち60名がナチス党員であったとのこと。
これはベルリン・フィルの党員比率と比較しても驚くべき差で、併合後のオーストリア国内におけるナチスの賛同者がどれほど多かったかを示す証左といえるのかもしれません。
「帝国オーケストラ」となってから興味深いのはその演奏レパートリーの変化。ドイツ音楽の偉大さを世界に誇示するという大目的にために、必然的にドイツの作曲家の比率が高くなっていくわけですが、その中核をなしたのがベートーヴェン、ブラームス、ブルックナー、ワーグナー、それにリヒャルト・シュトラウス、それに1938年以降はモーツァルトが加わる(併合前は“外国人”だった)といったところ。
オネゲル、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーといった敵性あるいはナチスの価値観に相容れないヒンデミットのような“退廃的”作曲家は忌避され、メンデルスゾーン、マーラー、シェーンベルクといったユダヤ人作曲家の曲は演奏されなくなる。
とはいうものの、総体的にはナチ化以前のプログラムと比較すると、ベルリン・フィルとしてのレパートリー自体にはあまり大きな変化は見られないとのこと。
これは上記のドイツ的作曲家の曲はナチス台頭以前から、世界的に名声を得ていて海外公演も定期的に行っていたベルリン・フィルとしての看板曲目であったこと、それがメインであったという点において、大きな変化という程でなかったということらしい。
この点はフルトヴェングラーの音楽的好み・得意曲目であったことも少なからず影響している、ということでもある。
フルトヴェングラーの戦前から戦後の活動期全般のレパートリーを見ても、この点はナチスとの関わりとは無関係にフルトヴェングラーにとっての十八番といえるところで、ナチスのプロパガンダで一層レパートリーが先鋭化したとしても、確かに総体的に見ると、大きく変わらない理由も納得のいくところだと思います。
本書の中で語られる「帝国オーケストラ」となってから興味深い事例としてはゲッベルスとゲーリングの権力抗争の道具として翻弄されてきたさまざまな出来事があります。
「帝国オーケストラ」の中でもいわば特Aクラスに相当するベルリン・フィルはベルリン大管区指導者であり、かつ宣伝相であるゲッベルスのいわば“虎の子”であり、プロイセン州首相・国家代理としてのゲーリングにとって“虎の子”に相当するのはベルリン国立歌劇場管弦楽団だった。
両者は待遇面で片方が並ぼうとすると、片方が待遇を引き上げる、といったことがしばしば行われるようになる。
また「帝国オーケストラ」としての最高位となる特別階級についてはベルリン・フィルの他にウィーン・フィル、ベルリン国立歌劇場管弦楽団に加え、ヒトラーの要望によりバイエルン国立歌劇場管弦楽団が加えられた、とのこと。
ベルリン・フィルとしてはウィーン・フィルはともかくとしても、ピットに入って観客に姿を現さないオペラの伴奏団体とステージに上がって純粋な器楽曲を演奏する専業オーケストラが同一視されてしまうことの不満があったようです。
演奏家としてのプライドに加えナチス高官の私的な権力争いの道具(=玩具)として翻弄される様子は喜劇的ですらあり、また独裁国家ならではの公私混同がまかり通る様子は醜悪というほかない。
戦争が激化し演奏自体が困難を極めるようになっても、ベルリン・フィルはその演奏水準の高さから特別待遇を継続され、成人男子のすべてに兵役義務が課されるようになっても、ゲッベルスの直々の指示により、兵役は免除され続けた。
当時のドイツでは男子は地区ごとに軍の名簿に登録され、旅行などでの移動に際しても居場所を明らかにする義務があり、徴兵の呼び出しがあった際にも兵役免除についての証明を確実に行う必要があったとのことですが、ゲッベルスの指示とはいえ、これを徹底することは行政システム上なかなか難しいところがあったようです。
実際にヴィオラ奏者の一人は東部戦線に送られ行方不明(死亡認定)となったとのこと。
こうした例外はあるものの、他のオーケストラが戦争末期に活動停止に追い込まれても、更には本拠のフィルハーモニーホールが爆撃で破壊されてもベルリン・フィルは活動をし続けた。
最後の演奏会は1945年4月16日で、ヒトラー自殺の2週間前であり、ソ連軍がベルリンを包囲していた時期。このような情勢下で演奏会を開いてどれほど観客が来たのかは記述がありませんが、驚異的なことというほかありません。
ゲッベルスは国家崩壊が目前に迫り、自身の生存も絶望的な状況の中でベルリン・フィルに構っている余裕は殆どなくなったようですが、代わりにベルリン・フィルの存続に力を貸したのはアルベルト・シュペーアで、ベルリン攻防戦で全ての男子が国民突撃隊として招集された際にもベルリン・フィルの団員に対して兵役免除を徹底させたとのこと。
シュペーアは終戦間際にヒトラーが連合国の占領下におかれるインフラを破壊するように出した指示に反対するなど、終戦後を見越したと思える活動を行っており(こうした姿勢が大きな理由となってニュルンベルク裁判で死刑を免れた)、ベルリン・フィルの団員を保護することはナチスの大義などとは最早無縁なところでドイツの至宝というべきベルリン・フィルを守ろうとしたと思えます。
本書では終戦後のベルリン・フィルについても簡潔に述べられています。
フルトヴェングラーがスイスに亡命し、看板指揮者の居ない中にあって、団員の殆どが演奏可能であり、組織としての健在ぶりと自主運営への再転換を果たす必要に迫られた。
非ナチスというより反ナチスであり、戦時中は白バラ運動や7月20日のヒトラー暗殺未遂事件の関係者とも接触のあったレオ・ボルヒャルトはロシア生まれのドイツ人指揮者ということでロシア占領下のベルリンでの活動には大変都合が良かった。
1945年5月26日に行われた戦後初のベルリン・フィルのコンサートではボルヒャルトが指揮して「真夏の夜の夢」序曲、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番、チャイコフスキーの交響曲第4番の演奏が行われたとのこと。
戦争終結後わずか2週間という速さでの演奏会であり、ナチス時代では不可能な演目であり、新しい時代に対するシンボリックな出来事だといえるでしょう。
ベルリンが連合国4か国の分割占領となったことによりベルリン・フィルは米軍の管轄下となる。東側ではなく、西側の管轄下に入ったことがベルリン・フィルにとってどれほど幸運に働いたかは言うまでもないところでしょう。
ボルヒャルトは8月23日に検問所を通過する際の運転手の誤解によりアメリカ兵に射殺されてしまうのですが、その後チェリビダッケが常任指揮者となり、フルトヴェングラーの復帰を経て、ヘルベルト・フォン・カラヤンが1955年に常任指揮者となるのは我々が良く知るところ。
戦前に“2回もナチスに入党した”カラヤンが民主的な手続きを経て常任指揮者に選出されたことを著者は揶揄していますが、それはまた別のお話ということで。
本書を通じてナチスとベルリン・フィルの関係を概観してみると、本書の冒頭でドイツの社会学者ヴォルフ・レベニースの「(ほとんど)ありきたりなドイツの物語」と題して書かれたまえがきにもあるとおり、ナチスによる文化芸術への干渉やユダヤ人の排除といった行動原理はなにもベルリン・フィルにだけ特別に起こったことではなくて、国家を代表するような芸術家やスポーツ選手、著名人に対して漏れなく起こっていたことであり、またそれ以上にドイツ国民全般に対して行われた規制や干渉そのものと基本的に大きく変わらないということがはっきりする。
これはナチスの影響がどれほど広大な分野に包括的に及んでいたか、という点を改めて認識することになるのと同時に、組織化され歪んだ論理をあたかも正義であるかのように打ち出す独裁体制がどれほど危険なものであるか、という認識を改めて思い起こすのです。
ベルリン・フィルが今日においても世界最高峰のオーケストラである所以は戦後に民主的な自主運営という設立当初の組織に戻ることが出来、優秀な人材を世界から集めることに成功したからなのだ、ということの大切さを改めて思うのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
