
作業記録で生まれた変化 その3/Tak.さんとの新企画について/1日1ページを読むだけで教養は身につくのか
Weekly R-style Magazine ~読む・書く・考えるの探求~2020/04/06 第495号
はじめに
はじめましての方、はじめまして。毎度おなじみの方、ありがとうございます。
noteで二つ新しい試みを始めました。
それぞれの企画については、本編で書きましたのでそちらをご覧ください。
前者はガチの企画、後者は毎日更新のリハビリとして開始した試みです(途中でやめるかもしれません)。
最近noteに投稿することが増えていますが、もちろん本拠地はR-styleなのでボチボチ書いていけたらなと思っております。
〜〜〜noteのサポート機能〜〜〜
先日、noteで「サポート」してもらえました。
「サポート」というのは、めちゃくちゃ簡単に言えばクリエーターに対する寄付のようなもので、noteの各記事の下の方に「サポートする」というボタンから実施できます。
金額は、100円・500円・1000円の選択肢が用意されており、それとは別に任意で金額を設定することもできます。あと、140字までのメッセージも入力できるので、お気に入りのクリエーターに応援メッセージを合わせて送信することもできます。
記事の購入などと違って、こちらは純粋に応援マインドでお金をいただけるわけですから、たいへん恐縮であると共に嬉しさもいっぱいなのですが、「〜〜さんからメッセージが届きました」という通知があって、「よし、返信しよう」と思っても、noteにはその機能が(現状)ついていません。
「サポート」してもらえたときに、自動的に表示される返礼メッセージの設定は可能なのですが、いただいたメッセージに対して個別にメッセージをレスできないのです。
「いいね」ボタンを押したり、記事を購入したりというのは数が多くなりがちなので、自動返礼の機能はありがたいのですが、サポートってそう数が多く発生するものではない(はず)なので、個別に返信させてもらえるとたいへん助かるな〜と思いました。
*まあ、こういう話はnoteのプラットフォームに直接意見を投げ込むべきですね。
とりあえず、noteを使っているクリエーターの方は、設定できる返礼メッセージをきちんと設定しておいた方がよいと思います。
*「アカウント設定」→「リアクション」の項目から設定できます。
〜〜〜これからのWRM〜〜〜
新年度が始まって、いろいろ変化を考えています。noteで新しい企画を始めたこともそうですし、シゴタノ!の記事も四月から少し方向性を変えていく予定です。
それもこれも、「本」作りを目指した、アウトプット・ワークフローの確立のためです。
少し前の号(492号)で、「この仕事を続けていく、という決意」を宣言しましたが、その決意は、定期的に「本」を作っていくことで実現されるでしょう。
これまではつれづれなるままにブログやシゴタノ!を更新していましたが、経営者視点見れば、それは労働資源を非目的に浪費しているにすぎません。それはもちろん楽しいことですし、それこそが「ブロガー」のあり方の一つかもしれませんが、これまでは「楽しい」に比重を置きすぎていたきらいがあります。それを変えていこうと考えているのです。
当然このメルマガも変化の対象となります。
このメルマガでは、一時期からかっちりした連載の形をやめ、ハッシュタグで記事の関連性を示すだけにして、できるだけ自由に記事を書くようにしました。そのおかげで、記事を書くのはたいへん楽になりました。というか、その時節はそれくらい負荷を下げないと(体調的に)まともに更新できなかった、というのが本当のところでしょう。
一方で、その時節からここまで書いてきたことで、何かしら「本」としてまとめられるような何かがあるかというと、いささか疑問です。ある程度のボリュームは揃いますが、自由に書きすぎていて、「これ!」というテーマを設定しづらい状況なのです。
ここに現状の課題があります。
経営者視点で言えば、できるだけ「本」を作れるように日々のアウトプットを行なっていきたいところです。その視点で言えば、何かしらのテーマを設定し、そのテーマに応じて10とか20の記事を書いていき、それをまとめて「本」にする、というワークフローを確立させるのが一番でしょう。
一方で、そうして目的追求思考になりすぎるとつまらなくなってしまう可能性もいなめません。あくまで私の経験にすぎませんが、結果を逆算して、ロードマップを描くようになると、途端に面白さが減退してしまいます(あるいはそういう可能性が爆増します)。それは避けたいところです。
加えて言えば、今週号の本編で書いているようなことは、あまり「本」になりそうもありません。しかし、情報的価値がまったくないかというとそういうわけでもないでしょう。その意味で、このメルマガを「本になりそうなこともないこと」を書く場所として──企業における研究所的な位置付けとして──使っていく考え方もできそうです。
現状まだこの問題については考え続けているところなので、明確な答えは持ち合わせていませんが、このメルマガも新年度から少しずつ形が変わっていくかもしれません。その点について、ご意見・ご感想あればぜひお願いします。
〜〜〜今週見つけた本〜〜〜
今週見つけた本を三冊紹介します。
社会学者である見田宗介さんの対談集です。個人的には、河合隼雄さん・吉本隆明さん・三浦展さんとの対談が興味津々です。それはそれとして、超高層のバベルなるものが実在するとしたら、一階に住んでいる人と最上階に住んでいる人は話す言葉がきっと違うでしょうね。
講談社選書メチエからさらに一冊。当人の著作はいっさい読んだことはないのですが、西田幾多郎さんの哲学には興味を持っています。本書は彼の哲学の後期に現れた「絶対無の場所」までに至る思考を追いかけるのがテーマなようです。
"『シンセミア』『ピストルズ』からつづく神町トリロジー完結篇"らしいのですが、前二作を読んだことがないので基本的にはさっぱりです。ただ、非常に面白いタイトルだなと思い目をつけました。ちなみに、organismは「有機体、(微)生物、有機的組織体」といった意味です。
〜〜〜Q〜〜〜
さて、今週のQ(キュー)です。正解のない単なる問いかけなので、頭のストレッチがわりにでも考えてみてください。
Q. このメルマガ、短い記事がたくさんあるのと、長い記事がどーんとあるの、どちらが好みですか。
では、メルマガ本編をスタートしましょう。
今週も「考える」コンテンツをお楽しみくださいませ。
――――――――――――――――
2020/04/06 第495号の目次
――――――――――――――――
○「作業記録で生まれた変化 その3」
○「Tak.さんとの新企画について」 #知的生産の技術
○「1日1ページを読むだけで教養は身につくのか」 #教養について
※質問、ツッコミ、要望、etc.お待ちしております。
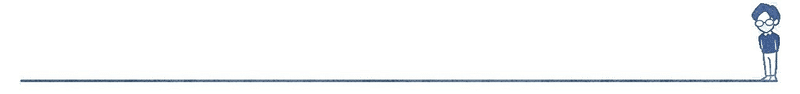
○「作業記録で生まれた変化 その3」
前回は、作業記録によってたくさんの「メモ」(文章メモ)が書かれるようになったことを紹介しました。
とにもかくにも、毎日メモは増えていきます。もっと言えば、楽に楽しく文章メモが書けています。そうなると、この文章メモを軸にしてワークフローを組み立てられないかと考えたくなるのは自然なことでしょう。
ちょうどそのとき、たまたまある場所で哲学者西田幾多郎さんの本の書き方を知ることができました。西田幾多郎さんは、机の上に広げた原稿用紙に、毎日その場で考えたことを書き足して、ある枚数になったところで終わりにして、一冊の本としていたというのです。超かっこいいですよね。
その話を聞いて、私の脳内に湧いてきたイメージは、一本のラインです。
作業記録に次々とその日に考えたことを文章で書いていき(つまり一本のラインを作り)、それを後から原稿の形に加工して利用する。そういうワークフローが完成したら、負荷を抑えながらも質を維持したアウトプット活動が行えるかもしれません。
■視点の変更
ここには大きな視点の転換があります。
これまでのメモの扱いは、切断的断片の操作に重点を置おいていました。ちょっとした思いつきを見出しメモの形で切り取っておき、何かしら原稿を書くタイミングがやってきたら、それらの見出しメモの中から使えそうなものを選別して文章化する(≒書き下ろす)という流れです。
一方これから目指そうとしているものは、連続的断片の操作です。
作業記録という一日の記録の「流れ」の中に、そのとき思いついたさまざまなものを文章として書き下ろしておき、それを後から文章のパーツとして利用すること。言い換えれば、文章を書く段階になってから「さあ書くぞ」と腕まくりするのではなく、すでに書いてある文章群から「おっ、これ原稿になりますね」と取り出すこと──そういう仕組みです。
つまり独立した断片の操作から、ある流れを編集することに重点を置くこと。これが大きな視点の転換の意味するところです。
■大きな差異
もしかしたら、上記の二つはほとんど同じに思えるかもしれません。しかし、実際は大きな違いがあります。
これまでは、何か思いついたことがあっても「今は別の文章を書くときだから」と、思いつきの一部分だけ(つまり見出しだけ)を記録して、その後は元の文章に意識を戻していました。いわば、意識の「脱線」の枝を切り取って保存し、「本線」(≒そのとき書くべきこと)に戻るように無理やり持っていったわけです。
一方、新しいやり方は、そのとき思いついたことをそのまま文章化していきます。つまり、意識の流れを無理やり変更する必要がないのです。だからこそ、文章メモはたくさん増えていくのでしょう。で、それらのメモが一定数たまったら、文章メモを「編集」して、原稿にしてしまうわけです。原稿を書くことから、原稿を作ることへのシフト。そうした変化がここにはあります。
■さいごに
仮に、見出しメモを書き留めておき、それを後から利用する方法を「ストック式」と呼ぶならば、そのつど着想を文章の形で書き留めていく方式は「フロー式」と呼べるでしょう。
もちろん、フロー式であっても、文章を投稿する際には手直しが必要となります。しかしそれは、writingというよりはeditingであり、その負荷は一気に書き下ろすよりも数段楽なはずです。
先に文章を書く。その文章を(見出しではなく)素材にして、完成稿を組み上げる。
そうして考えてみると、私のR-styleの毎日更新は、一日一回だけ行われる「文章メモ」の書き下ろし作業だったと言えるかもしれません。今後はそれをより小さい形で、たくさん行おうと考えているところです。
そして、その先に「本」の生成がつながっていくならば、一つの理想的な形となるでしょう。
(つづく)
ここから先は
¥ 180
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
