
独学という名の後継者 / 継続的に考えるために
Weekly R-style Magazine ~読む・書く・考えるの探求~ 2022/03/07 第595号
○「はじめに」
今週は本編は通常号のボリュームですが、この「はじめに」は簡略版でいきます。少しずつ、段階的に通常モードに戻していきましょう。
〜〜〜ポッドキャスト〜〜〜
ポッドキャスト配信されております。
◇第九十九回:Tak.さんとツールが「わかる」とは何か by うちあわせCast
◇BC032 『隷属なき道』 - ブックカタリスト
うちあわせCastでは、ツールを「わかる」ために必要なことと、それをアシストするノウハウ本の在り方についてお話ししました。
ブックカタリストは『隷属なき道』をごりゅごさんが紹介してくださりました。私も読んでみようと思います。
では、本編をスタートしましょう。今回は原稿を二つお届けします。
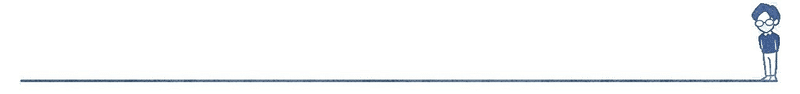
○「独学という名の後継者」
今回は、「ライフハックのその後」について検討しよう。実際的な話と理念的な話がある。まずは、実際的な話から。
■ライフハック後の話題
これまで確認してきた、「知的生産の技術」→「仕事術」→「ライフハック」という個人ノウハウの情報流通は、その後どうなっていっただろうか。
まず「ライフハック」は、ほぼ停滞している。ノウハウの有効性は別として、「話題」としての力はかなり衰えていると言えるだろう。その点は、「ライフハック」(あるいは〜〜ハック)と付くコンテンツが激減していることからも理解できる。マーケティング→プロモーション界隈が手を引いているということは、話題の力がないと見限られている──そこの市場が「薄い」と認識されている──ことを意味するからだ。
では、個人ノウハウの情報流通は途絶えてしまったのだろうか。もちろん、そんなことはない。2020年近辺でその話題の場を担っているのは、「独学」というキーワードである。
その中心にあって、華々しく輝いているのは、言うまでもなく読書猿の『独学大全』だ。2020年に出版された分厚い本書は、ノウハウ本の潮流を変えたシンボリックな存在と言ってよい。
もちろん、あらゆる偉人が単独で偉業を成し遂げることはなく、周囲の人たちやそれ以前の人たちの成果を助けにするように、本書もまた単独でその輝かしい業績を手にしたわけではない。それは、本書が過去のノウハウを集約している、という意味だけでなく、本書以前にも「独学」に関する書籍のくさびが打たれていたという意味もある。
たとえば、荒木優太の『これからのエリック・ホッファーのために 在野研究者の生と心得』(2016)や『在野研究ビギナーズ――勝手にはじめる研究生活』(2019)によって、「在野研究」という分野が日の目を浴びた。
そこで言及されているのが、単なる「研究」ではなく、「在野研究」であることは注目に値するだろう。一つには、それが──往々にして──個人の営みであること、もう一つには「権力・権威」の機構とは距離を持っていることが特徴である。
個人の営みに注目する点は、知的生産の技術からの流れではあるが、権力機構との距離感は「反権力」的(ないし非権力的)な佇まいがあり、米国の「ライフハック」のマインドセットとの呼応が感じられる。
『知的生産の技術』において梅棹忠夫も「学校制度」の問題点を指摘はしていたが、しかしそれは学校離れを示唆するものではなく、学校に足りない部分をなんとかして補おうという意味でのノウハウの提示でもあった。学校は前提であったわけだ。それはもちろん、梅棹忠夫が学校に所属するだけでなく、国立民族博物館という研究機関の長でもあったからだろう。
1970年頃の時代においては、そのような権力・権威機構と結びついた「インテリ」への憧れが機能していたのだろう。「末は博士か大臣か」である。
一方で、2020年頃になるとポスドク問題ももはや珍しいものではなくなり、また知識人の権威も──主にインターネットの普及と共に──落ちてしまったがゆえに、そうした憧れは機能しなくなりつつある。というよりも、それが理想として機能するには、あまりに距離が感じられるようになったと言ってもいい。一握りの人だけが手にできる「特権」と似たようなものに感じられる、というわけだ。
そうした視点から見ると、在野研究はきわめて魅力的だ。誰の許可もいらないし、何の規制も制約もない。会議にもでなくていいし、書類を大量に書かなくてもいい。所属する組織を配慮した発言をする必要もない。きわめて自由である。
誰でもがすぐに手を伸ばせるし、誰に気兼ねする必要もない。きわめて「個人的」に行える。実体は別にして、「在野研究」という言葉の響きには、そうした魅力が感じられる。
もともとこうした分野に興味があり、しかし学術機関に所属していない人が、「在野研究」というキーワードを話題にするのは非常に理解できる流れである。
■知的生活
もちろん「在野研究」だけではない。たとえば、日本における「ライフハック」の立て役者とも言える堀正岳は、『知的生活の設計―――「10年後の自分」を支える83の戦略』(2018)において、「知的生活」というキーワードの復興を担っている。「知的生産」と「知的生活」は、その内実に違いはあれど、重なるところもあるし、共に「技術」や「方法」を必要としている点は同様だ。
「インテリ」へのピュアな憧れが減退したとは言え、それでも「知的な人」「知的な生活」に憧れる人が絶えることはない。また、昨今の「騒がしい」情報環境において、それとは違ったものを反動的に求める人たちも一定数いるだろう。
そうした人たちにとって、ある種懐かしさある「知的生活」というキーワードは新鮮に響いたはずである。
*2022年にはハマトンの『知的生活』が新版で出版されている。
■『勉強の哲学』
以上に加えて、もっと直接的に影響を持つのが千葉雅也による『勉強の哲学』(2017)だ。本書もまた多くの人に読まれたヒット作である。
単に勉強の方法を提供するのではなく、「そもそも勉強とは何か?」と読者に問いかける本書はまさに哲学の本であるが、しかし──タイトル通り──「勉強」の本でもある。
勉強。
この言葉は、昨今のコンテンツ業界では「受験勉強」や「試験勉強」とほぼ同義に使われていた。テストがあり、それをクリアするための「効率的」な学び方。それは、在野研究や知的生活とは基本的には異なる営みである、と認識される。言い換えれば、私たちは「勉強」という言葉を、あまり好ましく受け取っていない。特にやりたいわけではないけども、自分の目的を達成するためには避けては通れないもの。そんな印象だ。
その勉強観を強く揺さぶったのが本書である。
勉強というのは、ある規範の中でそれに沿う適切な答えを出すものではなく、ラディカルに自分を変容させる行いである。本書はそうした勉強観を提示した。言い換えれば、外側から押し付けられる規範性に従うのではなく、むしろそこから逸脱するための「方法」として勉強を再定義したわけだ。
一見すると、これは「自己啓発」の文脈に近い。押し付けられたものからの脱出=自由の獲得、というのは連想しやすい構図である。しかし、本書はそこに「他者」や「歴史」や「偶然」というある種の重しをつける。自由ではあるが、しかし何もかもが「意のまま」というわけではない。そこには環境へのまなざしがある。この点が、『勉強の哲学』が一見自己啓発風でありながら、それらとは質的に(あるいはカバーしうる領域的に)違っているところである。
若干、話が逸れた。
本題に戻ると上記のような書籍の数々によって、「個人が何かを学ぶこと」への関心が醸成されてきたと言える。その後、本命とばかりに飛び出してきたのが『独学大全』だったわけだ。
■『独学大全』
『独学大全』は、名前の通り独学の手法を集めた書籍だが、もう少し言えば「独学のための手法」を集めた書籍と言える。どういうことか。
単に、ノートの書き方や暗記法が列挙されているだけでなく、「そもそもどうやってその勉強を続けていくのか」というノウハウ──広義のセルフマネジメント──も一緒に提示されているのだ。これはなかなか面白い構成である。
自己啓発の文脈において、「このように生きるべし」という指針と、それを支えるいくつかのノウハウが提示されること自体は珍しくない。たとえば『7つの習慣』はまさにそうした内容を持っている。いかに生きるべきかの指針が7つの習慣として示され、その上で「ミッション・ステートメント」のような、一段階具体的になったノウハウが述べられる。
とは言え、その「ミッション・ステートメント」というノウハウをどのように実践していけばいいのかまでは示されない。あたかも、それをやろうと決意したら、すぐさまにでも実行できると言わんばかりの態度である。まさにそれが「自己啓発」の特徴であろう。つまり、「自己/意識」に自分という存在を支配下に置くことがほとんど前提になっているのだ。だから、「ミッション・ステートメント」を続けようと意図しても、それがなかなかうまくいかないことは、はなから問題にされない。それができるのは「最低条件」のようなものだからだ。
しかし、現実的な人間はなかなかそうはいかない。自分であっても自分の思い通りにいかない(=他者性がある)し、それまでの習慣(=歴史)や、偶発的な出来事(=偶然)もある。つまり人は環境に取り囲まれ、その中で生きている。
従来の自己啓発書は、そうしたものを存在しないものとして、あるいは存在したとしても「自己」に対してはほとんど無力な存在として扱ってきた。しかし「自己」ないし「理性」はそこまで強力なものでもないし、強力であるべきでもない、というのが近年の共通理解になりつつある(『啓蒙思想2.0』などを参照)。
よって、学校などの外部環境/外部足場をうまく使えない人間は、まずその環境を整えることからはじめるしかない。その視点こそが『独学大全』の独自性である。
■独学の位置づけの変化
その『独学大全』が大ヒットした(あるいは今もしている)のは今さら力説するまでもないだろう。Amazonランキングでも上位だし、たくさんの書店でその姿を見ることができる。「古典」になれるかは時のみぞ知る事柄だが、それでも2020年代で注目される一冊になったことは間違いないだろう。
また、本書以降さまざまな「独学」本が書店に並ぶようになった。あるいは、独学を特集する雑誌や、その他のコンテンツ、コミュニティー、グループなども生まれている。現象として見れば、これは一種のブームと呼ぶことができるだろう。
むろん、『独学大全』以前にも独学を扱った書籍などは存在したが、ここまで大きな規模ではなかったし、全体的には受験を意識した「勉強」をテーマにしたものが多かったように思う。現在は、もっと「研究」的な内容が増えてきている。
一方で留意しておきたいのは、『独学大全』は別に受験勉強を排除してはいないし、既存の学校制度に比べて独学の方が素晴らしいとも説いていない。既存の学校制度がうまく使えない環境にあるとき、ないしは自分が抱える問題がそうした制度ではうまく対応できないとき独学が必要になる、というポジションである。
本書において、このポジションがよく読み落とされることがあるのだが、非常に大切なポイントであろう。なんだかんだいって、学校は強力なのだ。教えを直接請える教師がいて、同じ学びを共にする学友がいる。それらは結局のところ環境/外部足場であり、うまく使えば自分を後押しできる。
しかしながら、『独学大全』以降に出てきた独学系コンテンツの中には、「独学は悪いものではない」を通り越して「独学こそが素晴らしいのだ」と暗に学校教育を否定しているものも少なくない。差異化のためのレトリックとは言え、さすがにそれは大げさ過ぎるだろう。あるいは、それを真剣に信じているならば生存者バイアスか、歪んだ認識を持っているに違いない。
たとえば、私は基本的に独学者であるが、その知識は非常に偏っている上に、信頼性もあやふやなものが多い。プログラミング知識もそうだし、人文系の話題もそうだ。独学者は、基本的に読んだ本から知識を得るわけで、ということはどんな本を出会うかでその知識の質が決定されてしまう。しかし、そもそも本の質を吟味をするための知識を持たないわけだから、基本的には出たところ勝負というか、運任せ(=偶然)である。
こういうのは雑学的に知識を楽しむ場合はなんら問題ないが、何かを体系的に論じようとしたときに非常に困ることになる。穴が多すぎる上に、どんな穴が空いているのか自分で把握できないからだ。
もし可能であれば、西洋哲学について体系的に学んでみたいという思いが私にはある。そのためには教師の存在は必要不可欠とまでは言わないが、有益であることは間違いない。
そうしたことを思えば、「独学こそが素晴らしい」とは口が裂けても言えない。独学は楽で自由であるが、その代償は間違いなく──しかも見えない部分で──支払っているのである。
とは言え、こうした言説は差異化のためにどんどん奇抜に、あるいは先鋭化していくものである。よって、独学至上主義が謳われる事態も避けがたくはあるのだろう。それが私たちの常識を遥か超えたところまで到達してしまったとき、独学のブームもまた一つ終わりを告げるのかもしれない。
■さいごに
今回は「ライフハック」ブームの後に続くものとして、実際的(実体的)な話を確認した。姿や形は変われど、こうした分野への関心は継続的に続いていくのだろう。少なくとも、まったく途絶えてしまうよりははるかによい状況と言える。
その上で、次回は理念的な話を検討してみようと思う。いかなる形がよいのか。それを考えてみる。
ここから先は
¥ 180
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
