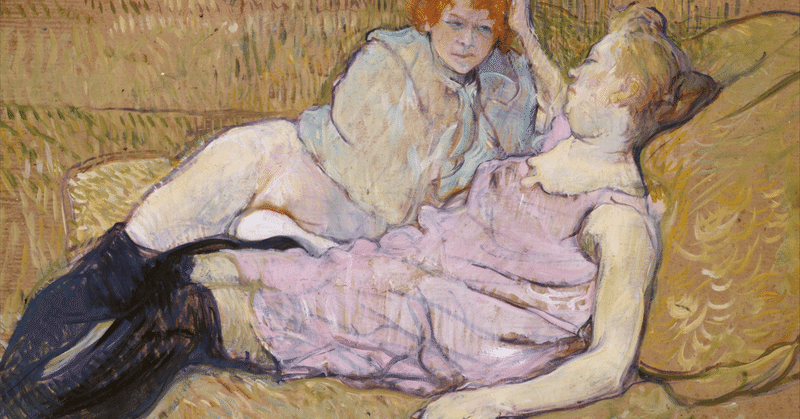
生きている他者に対して、哀悼可能性を見出すことは可能か:2023/05/06読書会用資料
要旨
本章全体の議論の予告(1~4段落)
本章では、「何によって、私たちは他者の生命を保護しようとするのか」という問いの前提を問う。言い換えれば、「いつ、どんな時に、生命の保護は要求されるのか」、そもそも「何が生命としてみなされるか」という議論の特徴を明らかにする。
他者の生命の保護について論じる際、その問いは特定の一人の他者の保護に関する問いと、特定の人間集団の保護に関する問いに分かれる。本章ではこのうちの前者の問いを扱う(後者の問いについては第3章で論う)。
他者の生命の保護に関する問題は、不可避に社会的・政治的になる。その問いは、「単に個人についての問いであるわけではなく、組織的配置や環境システム、政府の形式についての問いでもある」。では、「いかなる構造や組織が、ある人口ないし全ての人口の生を保護するために構築されるのか」。
***
生を区別する父権主義的構造(5〜8段落)
こうした問いは、父権主義に関連する問いに引き継がれる。
誰が保護=保全する集団に属するのか。その問いを問う人々の生は、その問いが問われる対象の生と分割可能なのだろうか。
こうした分割は、例えば「可傷的な集団」が同定されるときに生じる。フェミニストたちにとって、「可傷的な集団」についての言説は非常に重要だった。「可傷的である」と言えば、それが保護されるべきだと言えたからである。
しかしそうした言説を許可するとき、2つの問題が生じる。
まず、この定式化は、集団には可傷的な集団とそうでない集団があることを前提にしている。
そして、この定式化が行われるとき、権力の父権主義的構造が再生産される。
***
哀悼可能性としての生の価値評価(9〜14段落)
本書における問いは、ある生を、あるいは一連の生を保存するために何を行うか、あるいは行うことを拒否するかというもののみならず、生の保存のためのインフラストラクチャ的条件が再生産され、強化されるような仕方でどのようにして世界が構築されるか、というものである。
生の価値を評価する差異的=差別的方法は、諸々の生は多かれ少なかれ哀悼可能であると考えられる、という暗黙の評価図式によって特徴付けられる。その価値が、ある枠組みの中では前景化されるが、別の枠組みの中では失われてしまうということが往々にして起こっている。
ここで私たちがやりたいことは、哀悼の根本的な可能性に関する政治的想像力を定式化することである。
私たちは、哀悼の可能性の不平等な分配について語る必要がある。私は、その喪失が近しいものである時、哀悼することが異なった形式を——非人称的な形式すら——とることを主張したい。
生が哀悼可能であるとは、それが喪失されるより以前においてさえ、その喪失の機会においてその生が哀悼されるに値すると主張することである。
もし他者の喪失が喪失として登記され、死の予感が恐れられ、その不安定さが、破壊や傷害から庇護されるべきものとみなされるなら、生を価値づけ、保護する私たちの能力は、現在進行中のその哀悼可能性に関する感覚に依拠することになる。(生の平等な価値づけとは、即ち哀悼可能性が平等に存在することである)
私が分節化しつつある倫理は、特定の政治的想像力に、手続きの推量的方法、条件法の実験的方法を必要とするような平等主義的想像力に結びついている。
つまり、失われれば哀悼されるであろう生のみが哀悼可能な生と見なされるべきであり、それは暴力や破壊から積極的かつ構造的に保護される生なのである。
***
私と他者の代替可能性から考える「生の平等な哀悼可能性」(15〜17段落)
私たちは一般に、生が保存されるべき道徳的ジレンマに直面するとき、諸々の仮説を定式化し、それを様々な想像上のシナリオによって吟味する。もし私がカント主義者なら、次のように問うかもしれない。
もし私がある仕方で行為するなら、全員が同じ仕方で行為するよう、あるいは少なくとも同じ道徳的原理に従って行為するよう望むことができるだろうか。
問いをより一般化すれば、私が一連の暴力的行為を提起するとき、私が行為を提案するのと同じ仕方で他者が行為するような世界に生きたいか、というものだ。
私たちは再び、私が恐らく他者に対して欲しえないことを私に対して欲するのは不合理である、と結論づけることができる。あるいはもし、私が行為するような仕方で他者が行為すべきだとすれば、世界そのものが居住=生存不可能になるだろう、と結論することもできるだろうし、そのとき私たちは、生存可能性の閾値を示していることになるだろう。
(このように考える場合)ある人の行動は、他者の行動の形で自分自身に帰ってくるのである。そうした行動は複製され、あるいは攻撃性の場合には、他者から生じるものとして形象化され、自分自身に向けられるだろう。
もし私が行っていると想像される行為が、原理上、私が被ってもいる行為であるとすれば、そのとき、個人的行為についての考察を、社会的生を構成する相互関係から切り離すことはできない。
この仮定は、生の平等な哀悼可能性について私が行いたい議論にとって、重要なものであることが明らかになるだろう。
解題
【理路の整理】哀悼可能性について
哀悼の可能性とは何か。ここでは、生が喪失されるより以前においてさえ、その喪失の機会においてその生が哀悼されるに値すると主張することである。
「失って初めて気づく」価値が生の価値ではないところがポイントである。なぜバトラーは、平叙法ではなく条件法によって哀悼可能性を語らねばならないのか。
この問いについて考えるために、11段落冒頭のパッセージを引用する。
この仕事の規範的目標は、哀悼可能性の根本的平等をめぐる政治的想像力の定式化に貢献することである。
それは単に、私たち全員が死者を哀悼する権利を持つ、あるいは死者は哀悼される権利を持つ、というものではない——それは疑いなく正しいが、私が意図する十全な意味を捉えていない。誰かが哀悼されることと、同じ人物が生物として哀悼可能性の性格を持っていることとの間には差異がある。後者は条件法を、つまり、哀悼可能な人々は、その人々が失われるなら、哀悼されるだろう、という条件法を伴っている。哀悼不可能な人々は、その喪失がいかなる痕跡も残さないであろう、あるいは恐らくほとんど痕跡を残さないであろう人々なのだ。
実際に哀悼されるかどうかで生の価値を考えると、その時点で多数の生を価値検討の俎上から取りこぼしてしまう。だから私たちは、生が実際に喪失されているかどうかにかかわりなく、「喪失されたとしたら哀悼可能だろうか」と問わねばならない。
したがって、生の平等な価値/全ての生の平等な保存は、全ての生に対する平等な哀悼可能性として理解される必要がある。
……ここで唐突に、なぜバトラーは今この議論をしているのか、改めて確認しておきたい。
第1章でバトラーは、生の相互依存的本質を取り上げ、全ての生は平等に保存されるべきであると論じた。そして第2章冒頭で、「本章では、「何によって、私たちは他者の生命を保護しようとするのか」という問いの前提を問う」と宣言している。
乱暴にまとめれば、バトラーは第1章で論じた「全ての生の平等な保存」がいかにして実現可能かという問題に向き合い、第2章でまずその問いの前提を検討しようとしている。ここでいう問いの前提とは、すなわち「生が保存されるべきである」とはどういうことか、ということである。前述の通り、生の保存価値は「生が、その喪失以前においても哀悼可能である」ということを意味していた。
この前提を踏まえ、バトラーは2つのアプローチで「何によって、私たちは他者の生命を保護しようとするのか」という問いに迫っている。「他者の生命の保護について論じる際、その問いは特定の一人の他者の保護に関する問いと、特定の人間集団の保護に関する問いに分かれる」と書かれてある通り、特定の個人をテーマにするアプローチと、特定の人間集団をテーマにするアプローチである。本章の前半で後者について軽く触れられているが、大部分は前者のアプローチでの考察に充てられている。
先の哀悼可能性の議論を踏まえると、特定の一人の他者の保護をテーマにする問いは、以下のように言語化されるだろう。
「いかにして私たちは、他者の生命が喪失される以前において、その他者に対して哀悼可能性を見出すか」。
【問い】本章の議論の基礎をなす精神分析的主張についての問いかけ
いかにして私たちは、他者の生命が喪失される以前において、その他者に対して哀悼可能性を見出すか。バトラーはこの問いを、精神分析(メラニー=クライン)をベースにした道徳的問題(カント)として捉えている。
「私の格率が普遍的法則となるべきことを私もまた欲しえるように行動し、それ以外の行動を決して取るべきでない」、「君の格率がいついかなる場合でも同時に法則として普遍性を持ち得るような格率に従って行為せよ」(邦訳84頁)という定言命法が実効性を持つのは、「人は自分の行為を誰か他人の行為として想像するのであり、反転された、あるいは相互化された潜在的破壊行為として想像する」(同85頁)という心性を有しているからである___とバトラーは語る。
自分から他者への攻撃性が、他者から自分への攻撃性へと不可分に接続されるなら、「私が生きるためには、他者の生は喪失されるべきでない」という考えに必然的に到達する……とバトラーは結論づけようとしている(と私は理解している)。
このバトラーの理路に対して、2つの疑問が浮かぶ。
一つ目は、「自分の行為を他人の行為として想像する」のは普遍的な心性だろうか、という点である。これは単に私が精神分析の知識を欠いているために感じた疑念かもしれないが、だとしても検証は必要だろう。
二つ目は、「自分の行為を他人の行為として想像する」として、そもそも人は常に自分の生を保存しようとするだろうか、という点である。自分が死んでもいいならば、他者もまた死んで良い、という考えはあり得ないだろうか。
この点も結局精神分析的な問いになるので、私は今一度メラニー・クラインの著作を精読した方が良いだろう。クリステヴァの『メラニー・クライン――苦痛と創造性の母親殺し』あたりから読んでみるのがいいかもしれない。
もし既に皆さんがこの点について詳しければ、ご知見を共有いただきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
