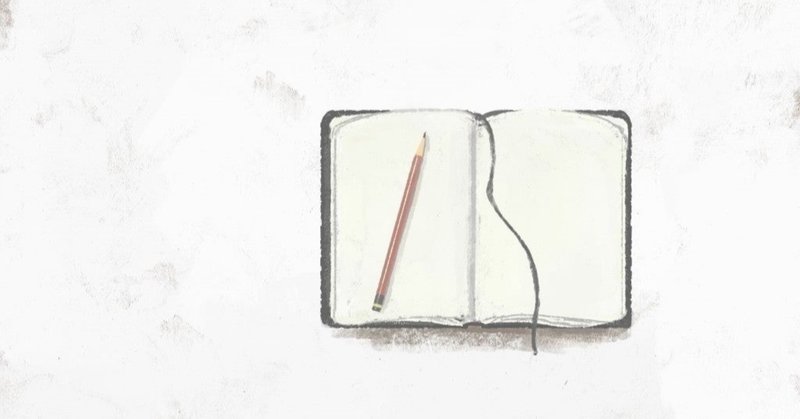
幼児期は、あれもそれも模倣〜シュタイナー幼稚園の連絡帳のこと〜
息子たちを通わせているシュタイナー教育の幼稚園で先生とやりとりしている、連絡帳があります。それを日々暮らしに活かしていく中で得た実感が「模倣の法則」です。
大人は子に模倣される存在。
伝えたいことがあるのなら、口であれこれ言うのではなく、
模倣されていいように
自己教育を続けよう。
子は、あれこれ言われれば、内容を理解するのではなく、
「あれこれ言う」を模倣する。
その「あり方」を模倣するだけのこと。
先生は、「大人は教えたり楽しませたりする存在ではない」とさえ仰るくらい。
あらゆる模倣そのものが、子どもにとって遊びであり学びだから、幼児期はそれで充分なのだと。
真面目な人は、ここで精一杯頑張ってしまいがちではないでしょうか。私もそのひとりでした。
入園当時は、同じ幼稚園のお母さんたちが皆、素晴らしく立派な方々に感じていました。自分もあんなふうになりたいと理想を高く掲げながら、できないできないと自分や環境を責め、結果子どもにもイライラあたったりして…あれ?本末転倒!!私、一体何をしてるんだろう??
そんな出口の見えないトンネルにいた時、ひとつだけ自分の行動で良かったなあと思うことがあります。それは、恥を捨てて、怒鳴ったことも反省したことも。その時の自分をありのまま先生に伝えること。
こちらから何も言わなかったとしても、実は子どもの姿を通して、色々なことに先に気づかれていることが多かったと思います。
「幼稚園の先生」といえども、シュタイナー教育の観点から乳幼児〜成人までの成長発達を網羅されている上でのお返事は、本当に奥深くて感動さえ憶えます。
幼児たちが高校生になる頃の子どもたちの姿を、すでに見据えていらっしゃるんですよね…驚愕です。
何でも、は言い過ぎかもしれませんが、たぶん色々お見通しなので、さらけだした方が先生も「なるほど、そういうことがあったんですね、謎が解けました」とスッキリしてくださったりと、話が早かったです。
先生への信頼
先生が母たちから絶大な信頼を得ているのは、私のような超長文になりがちな人も含めて、2歳児〜6歳児までの保護者、約30人と、自由記述式の連絡帳のやりとりを、常にしてくださっていることが大きいです。
メールでなく「手書き」のノートで、という先生のこだわりは、今のハイスピードなやりとりに慣れている親の私たち自身が、ハッとさせられる気づきを得る対象にもなっています。
例えば、どんなにたくさん(4ページとか!)書いても、大抵は翌日にお返事が書かれたノートが返却されるのですが、それが親たちは楽しみで仕方ないわけです。
その証拠に、子どもを送った後にお返事ノートを引き取り、待ちきれなくて幼稚園を出た瞬間ノートを開いて歩きながら読んでいる母仲間を、よく見かけます(笑)。歩きスマホならぬ、歩きノート?(私もやっちゃいがち…)
すぐに返事が来ることに慣れているからこその行動。
しかもたま〜に、「(昨日ノートを出した方の)お返事は明日になります」と張り紙が貼られている時があるのですが、この時の残念な気持ちったらありません(笑)。でも、スマホで「いつ来るかな」といつでも返事を待ち受けられるメールと違って、ノートは現物が戻ってこないのだから、仕方ないし、楽しみな気持ちをいったん手放すしかありません。
ある人は悶々とする時間が延びて、ため息が多くなるかもしれないし、また別の人は、パッと切り替えてその日を味わう中で、新しい気づきを得て「あ、昨日悩んでたことって実はこういうことかな?!」とワクワクするかもしれません。
そのどちらでも、いいのです。同じ「待つ」でも、メールとは感覚が全然違うものだなと思います。
シュタイナー教育は大人の自己教育が重視される
様々な失敗を経て腑に落ちたのは、大切なのは完璧を目指すことではなく、どんな状況であれ、意識して自己教育に努めているかどうか。その姿勢があるかどうかなんだなあということです。
これがわかってきた頃から、私は自分を責めなくなってきました。
同時に、美しくて立派で崇高にすら見えていた(笑)母仲間たちが、良い意味で身近に感じられるようになっていきました。そうなると会話もしやすくなり、実はみんな大変で、悩みながら子育てしてるんだとわかってきました。
中でも、特に私の安心感を広げてくれた人がいます。
私は長男を今のシュタイナー園に転園させた頃、「前の園では母親たちの中で自分が浮いていたと思う」と、ドキドキしながら話しました。するとその返事がカラッとしたもので、
「ここにわざわざ通ってるってことは、あなただけじゃなくて皆んな変だからさ!気にしないで大丈夫!アッハハハハ!!」
と笑い飛ばしてくれたのです。あ、そうか?!そうなんだ(笑)と。
他にも「この園を選んでる時点で、もともと子育てに対して熱心だったり、頑張り屋さんが多いはず。みんな頑張りすぎに注意だよ〜!」と、行事前のいそがしい時に声をかけてくれた人もいました。
皆さん、自分たちのことをよくわかってらっしゃる。
シュタイナー幼稚園も様々なところがあるようですが、わが家が属している園は、深く考えるのが好きな真面目でマニアックな親たちが、それを求めてわざわざ引っ越してきたり、遠くからでも通ったり。
子どもとの関わりを通して自分も学び、成長していくことを望んでいる。そんな人たちが多めに集まっているコミュニティなのかなと思います。
もちろん子育てへの取り組み感には温度差はあって、私のような貪欲な人もいれば、連絡帳しばらく出してないや〜って人もいますよ。(うん、いてくれなきゃコワイでしょ笑)
何にせよ、各家庭、さらには保護者ひとりひとりの個性の豊かさと、多様性を認め合う関係性はすごく好きで。
大人たちが尊敬しあい、支え合う、そんな姿を子どもたちが見て育つというのは、純粋に嬉しいなと思っています。
それもすべて、模倣の対象になるからです。
長くなったので、今日のところはここまで。
:::::
2020年10月11日(日)、長男の心身の発達を促す目的で、エールプログラム3ヶ月チャレンジを始めました。息子たちの変化、産後クライシスからの夫婦のパートナーシップの変化、ご指導くださっているキタハラタツヤさんとのやりとりを、リアルタイムで有料マガジン【エール for くるくるそわそわなムートくん】にて公開しています。
最初の1週間は、購読しなくても読めるようになっています。それ以降も、一部ご覧になれます。
身体ののびしろを見つけて、家族で楽しく遊びながら、一生モノの身体の土台をプレゼントしてあげたい。家族のかたちを考え直したい。
ぜひ、寄ってみてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
