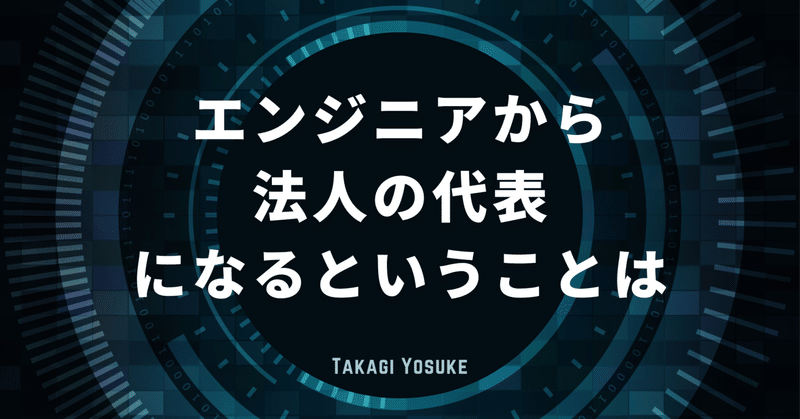
エンジニアから起業家になるということは
自己紹介
こんにちは、株式会社LangCoreの共同代表取締役・COOを務めている高木です。元々は上場企業やスタートアップでエンジニアとしてのキャリアを積んでおり、インフルエンサー系の事業会社を創業した後に2022年にM&Aでイグジット、その後フリーランスエンジニアをやったり、ダラダラした後にLangCoreの設立に至りました。
LangCoreでは生成AIを組み込んだプロダクトの受託開発や、生成AIを活用した新規事業創出・業務改善のコンサル、技術顧問業を営んでおり、業績としては初年度は1億円前後の売上着地予定で順調に成長できています。
今回は、私が起業して事業が立ち上がるまでの気づきを書きたいと思います。
書いたきっかけ
最近プライベートやX(Twitter)で「エンジニアとしてキャリアを歩んでいるが将来起業したい」「今までエンジニアをやっていて最近起業した」という方とお話しする機会がたまたま多く、エンジニアにとって起業という選択肢が数年前より多く選択されている感覚があります。
そもそもの起業家の数が増えたことや、AIやブロックチェーンなどディープなテクノロジーが徐々に(ある程度技術的な知見があれば)実装しやすくなってきたようになってきたなど様々な要因がありそうです。
本記事を書こうと思ったきっかけとしては、そういった方が増えてるのであれば、元エンジニアである私自身が過去経験した失敗や知見を僭越ながら共有したいと思ったためです。
エンジニアにとっての起業というキャリア
多くのエンジニアにとって、自分の考えたアイデアや事業を形にし、それが多くの人に喜んでもらえるという経験はエンジニア冥利に尽きるのではないでしょうか。また、私個人の話では働き方においても正社員と比べてかなり自由になりましたし、毎月の給与を得られるだけでなく会社という資産(プロダクト資産、最強の仲間、取引実績 etc.)がどんどん積み上がっていく感覚は何にも変えがたく、大人ならではの青春を謳歌している感覚で楽しいです(言わずもがな楽しいばかりではないですが)。「意外と簡単に起業自体はできるんだな」ということと「リスクも意外とないな(最悪フリーランスエンジニアになるか)」というのが初めて起業してみた時の所感で、エンジニアというキャリアを積んでいたことでローリスクハイリターンなチャレンジができると考えました。
エンジニアから法人の代表になるということは
法人の代表になるということは、経営に責任を持つということです。
経営者になった後に驚いたことは、売上を立てなければ会社は潰れるという事実です。当たり前すぎるのですが、会社員としてエンジニアをやっていた中で業務中あまり考える機会がなかった真実でもあり、銀行残高がどんどん減っていくタイミングに「あ、大体の起業家ってこんな感じで潰れていくんだ」と絶望した時期があったことは忘れられません。
何よりもせっかく起業するのであれば、今までの思考や得意領域に囚われず、お金をいただく仕組みについて考えていけると良いと考えています。
ここからは、事業立ち上げの過程で私がハマってしまった落とし穴について3点紹介します。
事業を技術起点で考えてはいけない
起業しようとなった直後まず考えるのは「何で稼ぐか?」という問いです。当たり前なのですが、会社が売り上げを出すためには顧客からお金を払ってもらわなければいけません。
つまり顧客がお金を払ってでも解決したい課題ありきで事業が成り立つのですが、エンジニア出身起業家の特徴として、技術起点で事業を考えがちです。
2022年、2023年は"生成AI ブロックチェーン NFT"などがバスワードとして飛び交っていました。エンジニアとしては先端技術にはどうしても興味をそそられてしまいます。私もハッカソンにたくさん出場して新規プロダクトを考え、それっぽい賞を受賞したりなんかして、"絶対にこの事業でいける"と思い込んでしまった時期がありました。
ハッカソンという限られた時間の中で、顧客がお金を払ってでも解決したい課題、十分な市場規模、それを真っ先に考え実行できる技術力、全てが綺麗にハマるケースは稀で、期間中にそれを狙うのは容易ではありません。何よりも、ハッカソンというゲームと事業立ち上げというゲームは全く別の競技であり、勝つための思考法が異なります。
「自分の実現したい世界があって、それがこの技術じゃないと成し得ない。そうじゃないなら会社は潰れても良い」というアーティストタイプの起業家以外は、常に顧客の課題ドリブンで事業を組み立てていくのがベターなのではないでしょうか。プロダクトは作れば売れると考えてはいけない
エンジニアが起業した直後は自分の事業アイデアを自分で実装するケースが多いでしょう。作ってるときは絶対に売れると妄想ばかりが膨らんでしまいがちです。ぶっちゃけ新規事業は10個作って1つ当たれば良いくらいの確率です。
新規事業を上手く当てるにはプロダクトが素晴らしいだけでなく、課題の深さ・広さ・頻度が十分であり、十分なマーケティング費用を確保して情報を届くべき人に届ける、顧客の予算を確保する、ことなど複合的な条件が噛み合って初めて成り立たせることができます。
逆に、この世の中にはなんとプロダクトを作らずに売上を立てる起業家もいます。まずは課題を見極め、コンセプトを固めLPだけ作って広告を数万円分だけ回したり、思い当たる知人に「こんなプロダクトがあったらどれくらいの作業時間が浮く?」とインタビューを重ねたりしています。プロダクトを1ヶ月かけて実装するよりも小さいコストで仮説検証を行なっているわけですから、非常に素晴らしい手法と言えるでしょう。
私はLangCore社でも新規事業を立ち上げていく役割を担っていますが、今までとは逆転の発想で初期はモノを作らないを念頭に置いて仮設検証しています。技術ばかりにこだわってはいけない
エンジニアが起業直後に直面する悲しい現実として、クライアントは自分たちが考えている素晴らしい実装の1/10も理解してくれてはいないでしょう。さらに言えば、どんなに質の高いコードを書いても、どんなに素晴らしいユーザー体験を作っても、どんなに素晴らしいアーキテクチャを組んでも、あなたの会社に顧客がついていなければその価値を体験させることができません。
まずは1円でも売り上げを作るために必要なのは他でもなく泥臭い営業です。エンジニアから起業家になろうとする貴方に最初に求められるのは、今までとは打って変わって営業力になります。
「生成AI・ブロックチェーンやりたい」みたいな技術起点で事業作るならクライアントワークやった方がよっぽど勝率が良く、「プロダクトで稼ぎたい」がモチベーションなら技術のことは一旦忘れて課題起点で事業作らないと絶対詰む
— Takagi Yosuke (@ramenjp_) November 23, 2023
終わりに
とはいえ、事業を立ち上げるからといって最初から何もかも切り詰めて考えなければいけないわけではありません。やってみなければわからないことがほとんどだと感じています。私は正社員として会社に勤めながら、とりあえず週末起業したことがきっかけて今のキャリアがあり、過去に5,6個ほど事業を考え、検証しては潰した経験もあります。
これから経営者になる上で最も大事なマインドセットとして、自分の役割範囲を限定せずなんでもまずはやってみる精神を持つことと、結果が出るまでやり続けることだと考えています。
Twitterでも似たようなことを発信してます。ぜひフォローしていただけると喜びます🫡
エンジニアやデザイナーが起業する失敗パターンの多くに良いプロダクトを作れば勝手にバイラルで広がるという幻想を信じすぎているケースが多すぎる。
— Takagi Yosuke (@ramenjp_) December 16, 2023
自分もエンジニアなのでそれで過去に大失敗したことがあり、故に気持ちは痛いほどわかるけど、結局業績の伸ばすために必要なのはゾスの精神なのよね
株式会社LangCoreは生成AIを使って新しい活用事例、法人向けソリューションをどんどん作っているエンジニアドリブンな組織です!
自分も同じ立場だったからこそ、自分で事業を0から作ってみたい、将来起業してみたいエンジニアが活躍できる場を用意しています。興味がある方はぜひご連絡ください🔥
そんなLangCore社に開発を依頼してみたい、どんな会社なのか話を聞いてみたいという企業様もぜひご連絡ください😄
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
