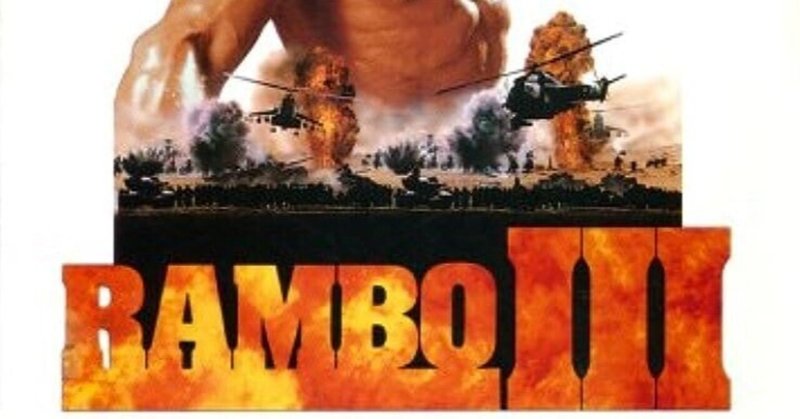
真読書感想文『ランボー怒りのアフガン』
「ランボー怒りのアフガン」の小説版を読んだ感想を書いていく。
原作と映画の大きな違いは、大佐を助けたあとだ。
映画だとソ連兵を宙吊り爆殺するなどかなり元気があったが、原作だと大佐を担架にのせてずっと歩き続けている。
ランボー本人は36時間寝ておらず体も傷だらけで死んでもおかしくないという状態なのに、「大佐を生きて返すんだ。」という信念だけで歩き続ける男。大佐の水分補給の時だけ休憩するという徹底した大佐への愛がかっこいい。
もう一つの大きな違いは登場人物だ。祖国を裏切ったソ連兵と現地にいる英語が通じる女性が出るが、少年兵は出てこない。
アフガン人が捕まえたソ連兵を殺そうとした瞬間、ランボーが「こいつを使わせてくれ。」とナイフを取り上げる。
皆の前で恥をかいたアフガン人はランボーにブチ切れるが、その事に気付いたランボーは「そんな気はなかったんだ。」と自らナイフで手をスライス。
この男気発揮シーンはかなり良い。
そしてそのソ連兵を大佐救出のために連れて行くが、いつランボーたちがいることを叫ぶか分からない。そこでランボーは彼を殺そうとするが、「俺にはできない!」と運命に任せることにする。
結局そのソ連兵は本当に心を入れ替えてアフガン人に協力しようとしていたのだが、戦闘のさなか命を落としてしまう。
怒ったランボーは「なんてことだ!」と叫びながら自動小銃を打ち続ける。このシーンは映画には無いが、スタローンが「ウワーー」と叫びながら乱射しているシーンは想像しやすい。
英語が通じる女性は看護師(?)なのでランボーが助け出した大佐を看ることになる。
しかし、そこにソ連軍のヘリが近づく音が!
他のアフガン人たちは皆逃げ出すが、この女性は「患者を捨てておけない。」とランボーと残ることになる。
結局ランボーとムサ(映画にも出てきた案内役)と共に3人で大佐を運びパキスタンまで歩き続けることになり、腕の骨が折れても黙って馬を曳き続ける。
この男気に痺れます。
また、映画だと羊を使った競技でアフガン人と親交を深めていたが、原作はもっとエゲつない競技をする。
子牛の首無し死体を使うのだ。競技自体も過激を極めている。最後はランボーが子牛の内蔵まみれになるのだが、映像化するにはグロすぎるので映画では羊にしたのだろう。(実際に存在するブズカシという競技なのだが、生きた羊を使っていた時期もあったらしい。)
そのブズカシにて、無敵のチャンピオンであり族長でもある男を倒すのだが、その後の「アフガン人の最高の敬意の表し方」である握手からのキスシーンが堪らなく良い。
さらに、敵の描写としてソ連の大佐や少佐の心の葛藤があるのも良い。映画ではプロパガンダのために単純に悪として描かれていたが、小説版では「こんな戦争から抜け出したいんだ!」や「さっさとあのアメリカ人(ランボー)殺して祖国に帰りたい。」などの弱気発言がある。
中間管理職の辛さが見受けられるのが良い。
最後になるが、全体的にランボーが「これは俺の戦争じゃないんだ!」と悩み続けているのが良かった。
スタローンは「帰還兵の苦悩」というテーマをすっかり一作目に置いてきてしまったが、原作者のデヴィットマーレルは覚えていてくれたのが嬉しい。
読んでいる最中ずっと「テンテンテンテーンテーン」というテーマ曲と共に暴れるスタローンが頭に浮かんできて集中できなかったが、とにかく面白かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
