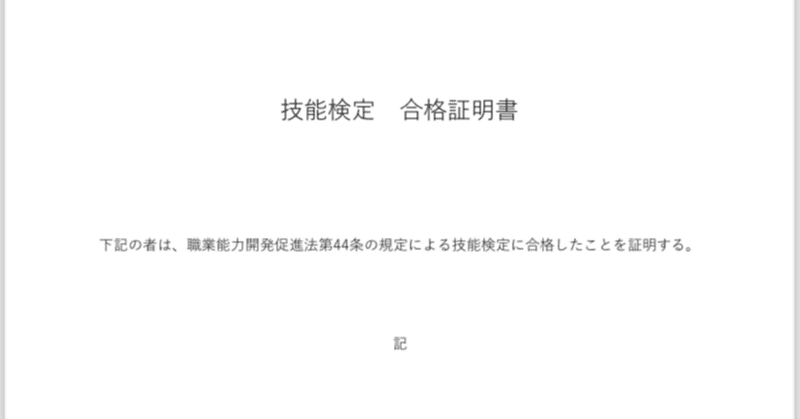
FP3級合格までの道のりと「こうすればよかった」後悔(2024/4月:CBT試験)
FP3級合格しました!
前からお金は当たり前に好きだったんですが、FP検定の勉強を受けたらなお、お金の勉強が好きになりました。
今回は、FP3級受験の独学勉強方法、CBT試験の簡単なレポ、「これやっとけばよかった!」と個人的に後悔したことなどをまとめてみます。
🌟FP検定勉強しようか迷ってる!
もしくは
🌟勉強中だけど試験が不安!
な方などの、何か参考になれば幸いです!
はじめに
個人的な話:受けたきっかけ
・留年して時間ができた&学費の工面が必要になり、お金関係(扶養の壁問題や貯蓄等)での悩みが尽きなかった
・経営塾を受けていくうちに、お金の勉強に対するアレルギーが少し薄れた
・人生を耕すためにはお金の知識を身につけることが必須だと思った
等です。
ちなみにアカウント名の通り、(そもそも3級自体にそこまでの効力はなさそうですが)FP資格が業務に直接繋がる職業ではないので、ほとんど趣味の取得といえます。
「受かりやすい」って本当?
多分私が最初にFP検定というものを知ったのは、Instagramの「取りやすい資格5選!」みたいな投稿からです。
数字で見ると、2種類ある試験実施団体のうち「FP協会」の方では、大体80〜85%が平均合格率らしく、これだけ見たら「なんだ余裕じゃん」と思うかもしれません。
私もそう思いました。
割と軽い気持ちでテキストのページをめくってみました。
🤔ふむふむ、6つの係数減価償却ソルベンシーマージン比率保健の受取人によって所得税贈与税相続税に分かれ特例があり勤続年数20年だとこうで標準報酬月額の1/3…2/3…5/6……?????
情報量が…情報量が多い!!
合格率、絶対嘘!!!
こんなの受かるわけがない!!!!
……おそらく、この「初期段階で諦める人が多い=受からなそうな人はそもそも無理に受けない」ことが、合格率の高さにつながっているんだと思います。
「勉強したら受かる。勉強した人が受ける」という、難しいようでいて単純な話ですね。
金融関係・不動産関係にお勤めの方や、税理士/弁護士/社会保険労務士の方、個人事業主として収支を管理している方、社会人経験を多く積まれた方だったらわかる単語も多いのかと思いますが、なーんにも触れてこなかった20代前半人間には初めて出会う言葉と数字ばかり。
でもまぁそんな0からのスタートですが、学科の勉強時間60時間+実技の勉強時間5時間、サボりつつも3ヶ月程の勉強で資格取得に至りました(早い人は一週間とからしいので、結構のんびりペースかも?)。
一番最初、分厚いテキストを前にした時の、「意味わからない!とっつきにくい!」という壁さえ乗り越えたら、
試験自体は2択or3択の選択式なので、記述式とかよりはずっと楽です。
6割取れれば合格なので、ちょっとくらい間違えても結構平気。
常識的に考えればわかる、みたいな問題も割とあったりします。
「受かりやすさ」を受ける動機にできるほど簡単な勉強ではない、と個人的には感じましたが、「FP試験を通してお金の勉強をしっかりしたい!」と思っている人は、受かりやすいと思います。
私の勉強法
「みんなが欲しかった! FPの教科書 3級」を紙本で購入→テキストを一読(最初はノート取ってたけど途中からは読むだけ)
2.並行して、図書館でお金関係(税金、保健、NISA、節約や貯蓄エッセイ等)の本を読み漁る
3.「FP3級合格のトリセツ 速習問題集」を電子で購入→付属の問題集アプリをダウンロードし、移動時間やドライヤー中などにポチポチ。
4.携帯の無料アプリ「FP3級試験対策」「FP3級学科試験対策問題集」も入れ、同じくポチポチ。
5.分厚い紙のテキストは持ち歩けないけど、携帯でもテキストを見れたらな…と思い、「史上最強のFPテキスト」を電子で購入
6.試験が近づくものの、なんとなく手詰まりを感じていたところ、「ほんださん / 東大式FPチャンネル」に出会う→移動時間などに「FP3級をたった9時間で最速合格できるFP爆速講義」を聞く
7.間違えた部分をほんださんの動画で確認しながら、問題集の正答率をひたすら上げていく。本についてきた試験過去問を解く
8.試験日直前に「FP3級過去問道場」さんの存在に気づく
…と、ここまでが学科試験勉強の流れでした。
ちなみに後述しますが、実技試験は別日に申し込んでいたため、学科終わり〜実技試験までの数日間を使い、
ほんださんの実技関連の動画を聞く
実技過去問を解く
の流れで勉強しました。
ちなみに、(これ言っていいかわからないんですがテスト、全然見たことないよ〜って問題出てきて泣きそうになったし見直しの自己採点時では一か八かの解答が多くヒヤヒヤだったものの)、学科は8割・実技は9割取れたので、勉強は裏切らない…!になりました。やった〜
こうすれば良かった!!
今回の私の、手探りで勉強してみた経験も、別に無駄ではなかったんですが、正直人には全然オススメしません。
もしまた3級の勉強をやり直せと言われたら、
ほんださんの動画を一通り見て、ざっくりとした概要を掴む
過去問道場をやりまくる
必要と感じたら、テキストを買う
くらいで、十分かなぁと思います。
書籍たちを見比べるのももちろん勉強になったのですが、なにぶん安い買い物ではないので、できるだけ費用を抑えたい!という方は無料のアプリや動画で出来るところまで勉強し尽くしてから、課金媒体を検討する…でも、遅くないかもしれません。
しかし、勉強への課金行動には、『分厚いテキストを買ったからには……もう後戻りできない!』のマインドを得れるという副産物がついていきます。
私は自分に甘いため、もし本を買わず、まずは携帯で出来ることから…と始めていたら多分、よそ見をし続け勉強を忘れ、「でも何もお金払ってないし損してないからいっか♪」と諦めていた自信がありました(最低の自信)。
また、文字情報での記憶が得意な人、聴覚情報の方が記憶に残りやすい人、様々だと思います。
本を読むのは好きだけど映像を見るのがそこまで得意ではない私が、結果的に「ほんださんの動画最高!」と思えた理由は、本で一通りの単語を一応インプット→動画、という順番だったからかもしれません。
当たり前ですが、誰のどんな言葉より「自分にあった順序の勉強法」を信じるのが一番の近道だろうなぁと思います。
書籍は紙? 電子?
紙本1冊、電子2冊を購入した体感ですが、「どっちも一長一短」だと感じました。正直これも各位の好みだと思いますが、一応比較してみます。
紙のメリット
・「勉強してる!」感が出てテンションが上がる
・電子よりよそ見しにくい
・人に譲渡しやすい(※年度により法改定などが頻繁なため、推奨されてはいない)
紙のデメリット
・重く分厚く、持ち運ぶには億劫なため、ふと読み返したくなったときに不便
・場所を取る&年度ごとに更新され新刊が出る(=シーズン逃したら売れない)ため、ゆくゆくは資源ごみになる可能性がある
電子のメリット
・持ち運べる。場所や時間を気にせず、通勤中やベッドの中でも読める=「あ、あれなんだっけ」と読み返したい時にすぐ辿り着ける
・サイトによっては割引やポイントのサービスがある
・場所を取らないため、半永久的に保有できる
電子のデメリット
・強い意志を持ってないと、すぐ他のアプリに目移りする
・(人によるけど)デジタル画面で細かい字を読むと疲れて目が滑る
・充電が切れたら、サイトが閉鎖したら、ネット環境がなかったら、等のリスクがある
_私は自分に発破をかけるため、あからさまに「勉強してる感」のある分厚い紙本を買いました。
そしたら読み物としての面白さも感じたため、今後の人生で気軽に読み返せる用に電子でも買いました。
ちなみに見比べたかったので、3冊とも全部違う出版社の本ですが、これも好みだと思います。
正直、書籍単体で試験に挑む!というより、動画・アプリ・書籍の連携でお互いに補強しあうのが一番だと思うので、迷ったら値段や、ペラペラめくった感じの心地よさとかで決めて良いかと。
試験当日
CBTに切り替わった初年であり、実際の例がまだ少ないと思うので、簡単ですがこちらも流れを書いておきます。
受験者専用サイトに登録し、最寄りもしくは寄る予定がある場所の近くなどのテストセンターを予約する(人気の場所は希望の日程が空いていない場合も多い)
受験開始時間の15〜30分ほど前を目安にテストセンターの受付をし、書類のチェックをしたり説明を聞いたり荷物を預けたりする。メモ用紙とペンをもらう
指定された席でパソコンと向かい合い、受験する。最初に、操作慣れ用の簡単な導入がある
終わったら印刷ボタンを押して、受付で点数結果を受け取る
紙の試験よりスムーズで、日程の縛りもそこまでない(テストセンターごとに開いてる時間や休館日が違うのは多分注意かも?)ため、個人的には今年に受験を決めてラッキーだな〜と感じました。
試験時間自体は90分と60分ですが、終わり次第退室ができるため、早さに自信があれば予定と予定の隙間に試験を捩じ込むことも不可能ではないと思います。言ってしまえばクリックするだけの簡単な動作なため、私は大体30〜60分くらいで終わりました。
3日前までは日時と会場の変更が可能なため、まずは申し込んでおくと自分に圧をかけられて良いと思います。
学科と実技は別日? 同日?
紙試験時は、年に数回という特性上、午前学科・午後実技と1日完結がデフォルトだったらしいものの、CBTでは結構自由です。
空いてる日程の都合上で別日にしたんですが、これが結果的に良かったかも? と思っています。
あくまで私個人の意見ですが、「勉強時間が別で取れる」「学科の4日後以降に実技、みたいにしておくと、もしも学科が合格基準に達してなかった場合、実技の日時変更が可能=勉強のし直しや、学科の再チャレンジ時にまたまとめて受けることができる」等をメリットに感じました。
とはいえ、終わり次第退室ができるのを生かして、サクッと同日に受けるのも手ですよね(多分私も日程が空いてたらそうしていました)。
ちなみに、テストなんて機会はそうそうないと思い色々なところに行ってみたくなったため、学科と実技を違うセンターで受けたのですが、楽しかったです。もし割とテストセンターが多い地域に住んでいらしたらご参考までに……
なんて、つらつら思いつくままに記憶を辿った長文でしたが、なにかお力になれそうな部分はあったでしょうか?
この世にはたくさんのFP試験記や対策記事があるため、重複する部分も多いかと思いますが、自分用の覚書としても書いてみました。
もしなにか不透明な点や気になる事などありましたら、私の答えられる範囲でお答えできればなと思うので、お気軽にコメントくださいませ。
それでは、
応援してます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
