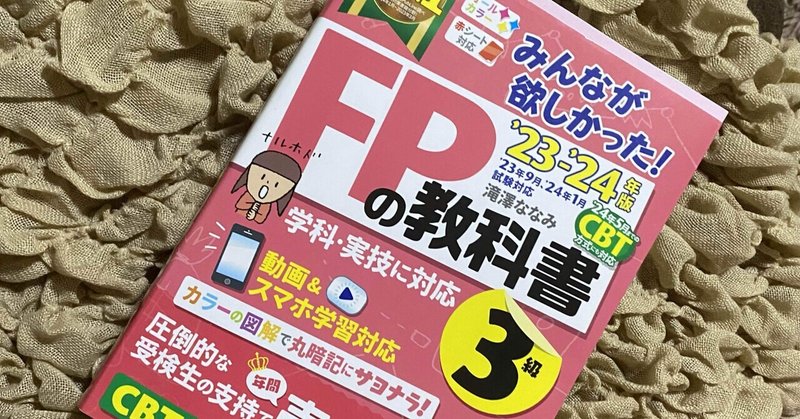
彼女もち、「結婚前提(配偶者優遇)制度」の多さにびっくりする
こんにちは!
わたしはお金の勉強が大好き系女です。
◼️はじめに
「結婚前提制度」ってフシギ
ついこの前まで、FP3級受験に向けて勉強をしていたんですよ(合格通知が来たら、勉強内容まとめもまた出します!)。
しかし、その際、ひとつの疑問がわきました。
それは、
「結婚前提の制度、多すぎんか?!」
ということです。
配偶者控除にはじまり、相続、税金、保険、不動産……FP(ファイナンシャルプランナー)試験における、枝分かれした6つの分野のほぼ全てで「結婚してるほうがお得よ!」という制度が出てきました。
は〜なるほど、日本は昔から割とそういう、"お家制度"的なのを大事にしてるもんね〜、20年以上連れ添った夫婦の税制優遇とかもあるんだね〜〜……
………えっ、
「結婚してるかしてないか」で、本来払うべきだったお金が変わる
って仕組み、よく考えたら結構面白くないですか? っていうか、疑問に思ったことないですか?
私は思いました。
勉強しながら、不思議だなぁ……と思っていました。
「女性は家庭を支えるべき」みたいな"伝統的家族感"が制度を作った理由なのでしょうか。それとも単純に「愛し合ってるなら助け合っていいよ!」みたいな?
でもでも、たとえば極端な例ですが、婚姻届を出す前日でどちらかが亡くなった場合、2日後だったら配偶者として(おそらく)もらえてたはずの遺産が全部他の親族のものになったりするの、少し不思議ですよね。
たとえば身近な例ですが、愛なんていくらでもあるし支え合って生活してるし20年以上余裕で同棲してるのに、「法律婚の制度が整ってないから」ってだけで、"結婚できていたら得られたはずの恩恵"が同性カップルだと全部受けられないの、意味わからないですよね。

このnoteを書いてるワケ
そう、私と私の恋人は同性同士で、「(まだ)結婚できない」ほうの人なため、そういう「結婚前提制度」がテキストに出てくるたびに、「なるほど国ちゃんって結婚してる人にはこんな優遇を用意してくれるのね…この制度は1億6千万でこっちの制度は2500万ね…」等メモしつつ、泣泣泣謎泣笑泣なぜ? みたいな複雑感情になっていました。
FP検定を受検する人の中で、ここに疑問を抱かずに勉強できていた人がもしいらっしゃるのならそれは、実は結構すごいことで、実は特別なことで、そしてとても良きことだ…! 私も早くそちら側に行きたい!!
ということで、一種の腹いせと、冷静な事実確認として、教科書や問題集(すごく分厚い。種類はまた後日紹介します…!)をペラペラめくり、ひたすら制度を羅列していきますね。一応分野ごとに分けてあります。
※何社か買ったり調べたりして、正誤確認は一応しているのですが書き間違いや改定前後等あるかもしれないので、あくまで素人調べであることをご了承くださいませ…!
ぜひ皆さんもびっくりしてください!
◼️いくつあるだろう、「結婚前提制度」🎶
社会保険・公的年金_「扶養」の範囲外
税法上の扶養は戸籍上の配偶者のみに認められており、社会保険(健康保険)では法律婚でない内縁関係の配偶者も被扶養者となれますが、同性の配偶者が被扶養者となることはできません
▼「配偶者」「被扶養者」「家族(遺族)」が受けられる恩恵
第3号被保険者=「第2号被保険者に扶養されている配偶者」は、保険料の負担がない
出産一時金、家族出産一時金_被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が出産した場合、1児につき50万円支給
埋葬料、家族埋葬料_葬儀をした家族に対し5万、被扶養者(家族)が死亡したときは被扶養者(会社員)に5万円支給
加給年金_厚生年金の加入期間が20年以上の人に、配偶者(65歳未満)または子(18歳到達日年度末日〜等条件あり)がある場合に、65歳以降の老齢厚生年金から加給して支給。その後配偶者が65歳に達すると配偶者の老齢基礎年金に加算
離婚時の年金分割制度_夫婦間の合意または裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分割
遺族給付_被保険者または被保険者であった人が死亡した場合、遺族の生活保障。寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算なども(それぞれ条件が違う)
生命保険・損害保険_「家族(遺族)」の範囲外
▼「配偶者」「被扶養者」「家族(遺族)」が受けられる恩恵 ※同性パートナーを配偶者として認めている保険会社もある
総合福祉団体定期保険_従業員等の遺族保障を目的とした定期保険。保険の受取人は被保険者(役員・従業員)の遺族または法人
個人年金保険料控除_を、受けられる保険契約の要件の一つが「年金受取人が契約者または配偶者のどちらかであること」
家族傷害保険、ファミリー交通事故傷害保険_1つの契約で家族全員が補償される
個人賠償責任保険_1つの契約で家族全員が補償対象となる
税_「控除」の対象外
▼「配偶者」「被扶養者」「家族(遺族)」が受けられる恩恵
所得控除_税金を計算する時に、所得から控除することができる(課税されない)もの。人的控除(納税者自身や家族の事情を考慮した控除)と、物的控除(社会政策上の理由による控除)
配偶者控除・配偶者特別控除_要件①民法に規定する配偶者であること等を満たすと、最高38万〜48万の控除(配偶者以外の親族には「扶養控除」がある)
障害者控除_納税者本人が障害者である場合のほか、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合に適用
寡婦控除_合計所得500万円以下&①夫と死別後再婚してない者 ②夫と離婚後再婚しておらず、扶養親族を有するもの のどちらかに該当する寡婦へ適用
社会保険料控除、医療費控除、セルフメディケーション控除_納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料を払った場合に適用
相続・贈与_「法定相続人」になれない=「他人」として税額2割加算
▼「配偶者」「被扶養者」「家族(遺族)」が受けられる恩恵
法定相続人_被相続人の配偶者と一定の血族に限る。配偶者は常に相続人。血族相続人には優先順位
法定相続分_民法で定められた各相続人の相続分。配偶者のみの場合は配偶者がすべて相続。他にいる場合も常に相続人
配偶者居住権_被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、原則としてその建物の全部について無償で使用・収益する権利
遺留分_遺贈の偏りにより残された家族が家を失い、生活できなくなるという事態を防ぐために、一定の相続人が最小限の遺産を受け取ることができる制度
生命保険の非課税限度額「500万円×法定相続人の数」
遺産にかかる基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の数」
相続税額の2割加算_配偶者および1親等の血族以外の人が、相続または遺贈によって財産を取得した場合には、算出税額の2割が加算
配偶者の税額軽減_配偶者が取得した財産が1億6000万or配偶者の法定相続分の、いずれか多い金額までは相続税がかからない
贈与税の配偶者控除_婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(またはそれを取得するための金銭)の贈与があった場合、基礎控除とは別に2000万円までは贈与税がかからない
……………などなどなど!
◼️どうでしょう
書いてるだけでも疲れたので、きっと読んでるだけでも疲れちゃった…のでは…?!
そしてこれはまだ「3級」の範囲なので、多分もっとあるし、そしてきっと語弊もある……。
正味、どっちも稼いでたら扶養はそんな意味ないだろうし、出産関係は金銭給付以上の壁があるし、年の差カップルじゃないと年金系はそんな……等、突っ込もうと思えば突っ込みどころも多いんですがひとまず、パラパラめくって「配偶者」「被扶養者」「家族(遺族)」前提の文を抜き出しただけでも、上記の通りでした。
あるかもしれない悲しい未来
ではでは、長くなってしまうので一部抜粋ですが、もしこの、制度たちの恩恵を受けられない(つまり、2024年の現状だ)と、どんな状況が想像できるのでしょうか。
⬜︎ 例えば、「法定家族」なら家族保険の契約1回分で済むところを、余計に払わなきゃだったり?
⬜︎ 例えば、もしどちらかが働けない状況になった時、「扶養」に入れず、保険や税の優遇を受けられなかったり?
⬜︎ 例えば、パートナーを亡くしたら、(名義人がパートナーだった場合)家を追い出されて、遺贈があっても税額が加算されて、遺族年金も何もなくて、……そうやって、一番悲しい時に何度も「あんたは他人です」と突きつけられたり?
ウワ!
嫌すぎる!
嫌だ〜〜〜!! 怖い〜〜〜!!
もちろん、お金関係の優遇があるから結婚したいだけ……な、わけはありません。
けど、そっか、私たちは国や法や制度から「いないもの」とされているんだなぁと、改めて思うと、やっぱり何度でもびっくりです。
びっくりですね。
いやぁ……びっくりだ……
びっくりびっくり
………
以上、びっくりしたことの共有でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
