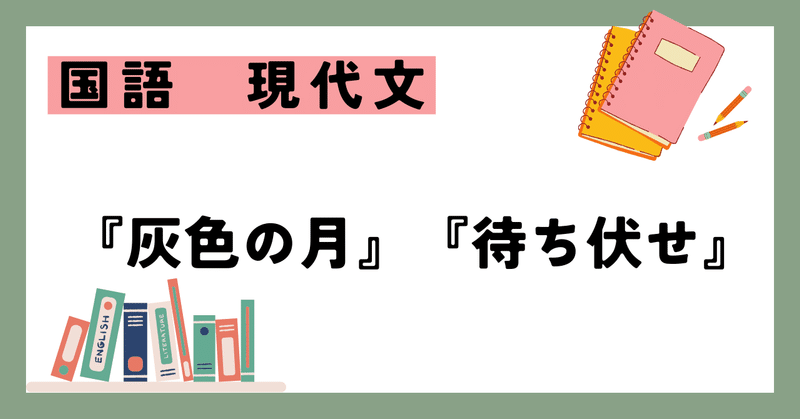
高等学校国語科用『国語総合-現代文編‐』を今の私が読むと④
教化書を読み進めること数日。半分ぐらい読むことができました。教科書にはいろいろな種類の文が載っているし、全て短いので、読みやすいなと感じています。★の単語は”語彙を広げる上で注目すべき語句や慣用句”として挙げられていたもの。
〇【小説】灰色の月ー志賀直哉
この小説の最後は「昭和二十年十月十六日のことである。」で締めくくられていた。日本で戦争が終わったのが昭和20年8月。終戦直後のできごとのようだった。
電車はいつの時代も疲れ切っている人であふれているなと思う。
小説には終戦直後という時代背景があるけれど、この電車に乗っている場面だけをとると現代も昭和も似たようなものではないだろうか。モンペを着た女性はスーツを着た女性で、少年工はバイト終わりの学生だろうか。小説を読んでいてすごく既視感を覚えた。
タイトル『灰色の月』に引っ張られてだろうが、このお話は私の頭の中で灰色で再生された。昭和であること、登場人物がみんな疲れている感じで、なんとなく活気がなかったので、脳が灰色で処理したような気がする。
(カラーテレビの本放送開始は昭和35年頃だそう。)
★仮想:実際にはない物事を、仮にあるものとして考えてみること。
★もの憂い:なんとなく心が晴れ晴れしない。だるくおっくうである。苦しい。つらい。
★暗澹:薄暗くはっきりしないさま。暗く陰気なさま。将来の見通しが立たず、全く希望がもてないさま。
〇【小説】待ち伏せーティム・オブライエン
学生時代、私が初めて触れた種類の戦争小説だったと思う。殺す側の体験記。戦争によるPTSDの話は聞いたことがあったけれど、この話を読んで認識を改めた記憶がある。
戦争系の体験記はどんなけ読んでも想像しきれていないのが分かる。
その上でだけれども、この体験記では待ち伏せをして手榴弾を投げて人を殺す。特に技術等いらなそうな所が嫌だ。もし、私が主人公の立場であったら同じようにし、同じように自分が死ぬまで殺した人のことを思い出すだろうなと思えてしまうところが嫌だ。
戦争という体験、戦争で人を殺すという体験、この先、することはないと信じたい。
この話を読んでもう一つ記憶よみがえってきた戦争のお話があるので、紹介したい。こちらも教科書に載っていたお話で『一つの花』という題名だ。
社会の教化書では歴史を、国語の教科書では悲惨さを伝えようとしていたのかなと今になって思った。
★躊躇:あれこれ迷って決心できないこと。ためらうこと。
★瀬戸際:勝負・成否などの分かれ目。
【読んでよかった!】思って頂けたらサポートよろしくお願いします。
