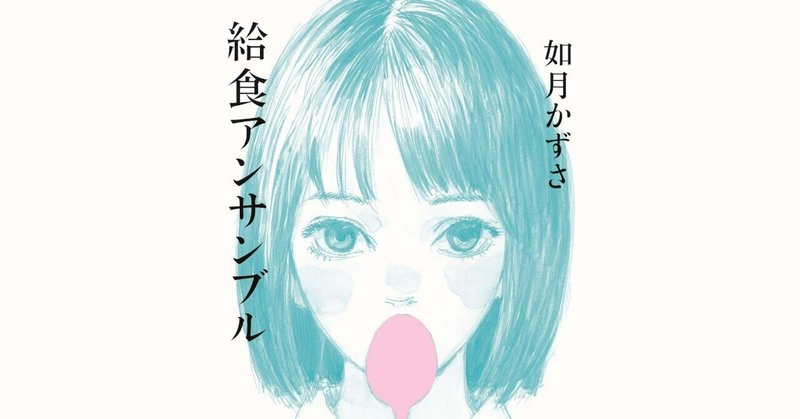
『給食アンサンブル』の授業を見学して
昨年の秋に、『給食アンサンブル』を使った小学校の授業を見学させていただく機会がありました。
子どもたちと本の距離を縮める、とても素晴らしい授業だったので、記事にまとめてご紹介したいと思いながら、どんどん時間が経ってしまったのですが、授業を中心になって進められていた先生が、6月にこの取り組みについて講演をなさるということなので、いまさらながらその講演の宣伝をかねて記事を書くことにいたしました。
『給食アンサンブル』で授業をしてくださったのは、神奈川の川崎市立東小倉小学校さんです。
出版社の方から最初にそのことを教えてもらったときには、授業で読書会でもするのかな、くらいに考えていました。ところがくわしい話をうかがうと、国語の時間を8コマも使って、『給食アンサンブル』を教材に本格的な授業をされるとのことで、まずそこでびっくりしてしまいました。
夏休みのまえに、6年生の子どもたち全員に学校から『給食アンサンブル』が配られ、子どもたちは夏のあいだにそれを読んで授業に臨んだのだそうです。
もともとは、授業を受ける子どもたちに、作者からメッセージをもらえるとうれしい、というお話だったのですが、せっかくの機会なので、リモートでその授業を見学させていただくことにしました。
私が見学したのは、子どもたちがグループごとに『給食アンサンブル』の好きなエピソードの感想や考察を発表する授業でした。
自作の映像を用いたプレゼン能力の高さや、作者でも思いつかなかったような独創的な考察にも驚いたのですが、それよりも子どもたちが丁寧に作品を読みこんでくれたこと、そして『給食アンサンブル』の物語やキャラクターを好きになってくれたことが、作品について熱く語る姿から伝わってきてめちゃくちゃ感激しました。
その授業の翌週に行われた、学校の近所にある北野書店さんの書店員さんを招いての読書交流会もリモートで見学させてもらったのですが、こちらも大変な活況で、先生にノートパソコンを運んでもらって、各グループにお邪魔するたびに、次々に質問や感想が飛んできました。
「3回読んだ」「これまで読んだ本のなかでいちばん好き」「いつもはあまり本を読まないけど『給食アンサンブル』はおもしろかった」など、子どもたちからうれしい言葉をたくさんもらい、児童書作家として至福の時間を過ごさせていただきました。
その後、子どもたちは北野書店さんと連携して『給食アンサンブル』のフェアを開催してくださることになり、卒業前の忙しい時期にもかかわらず、写真のような非常に力のはいった展示をつくってくれました。

授業はリモートでの参加でしたが、このフェアには実際に足を運び、6年生のみなさんにもお会いして、感謝を伝えることができました。
そんなわけで、『給食アンサンブル』の授業見学では、ほんとうにうれしい経験をさせていただきました。あの授業をきっかけに、もっと本を読んでみようかな、という気持ちになった子どもたちも、少なくなかったのではないかと思います。
ただ、授業の様子をこの目で見たときには、うれしさと同時に、信じられない、という気持ちもありました。子どもたちがこんなにも『給食アンサンブル』を好きになってくれて、作品についていきいきと語ってくれていることが、とても信じられなかったのです。
だって、この作品で授業をするから、事前に家で読んでくるように、とかいわれたら、たいてい「うわ、めんどくさ…」となるじゃないですか。
私自身、高校時代には定期的に学校から小説が配られて、テストに出題するので読んでおくように、といわれたのですが、「どうして読みたくもない小説を強制的に読まされなくちゃいけないんだ」という思いで、読みはじめるまえから課題の小説にネガティブな印象を抱いていました。
なので正直なところ、実際に授業を見学するまでは、無理に読まされたことで、子どもたちが『給食アンサンブル』を嫌いになっていなければいいな、と心配していました。
にもかかわらず、子どもたちが『給食アンサンブル』を好きになってくれたのは、『給食アンサンブル』がとびきりおもしろい傑作だから! …と、断言できるほど私は自信家ではありません。
『給食アンサンブル』のいくつかの要素が、国語の教材として子どもたちに読んでもらうのに適していたことはたしかでしょう。各話30ページ程度で文章も比較的読みやすいとか、1話ごとに主人公が変わるので、ひとりくらいは共感できるキャラがいることが多いとか、身近な給食をテーマにした身近な学校生活の物語であるとか。
ですが、もしも教材に選ばれたのが、例えば村上雅郁さんの『きみの話を聞かせてくれよ』や森絵都さんの『クラスメイツ』でも、子どもたちは『給食アンサンブル』の場合とおなじように熱心に授業に取り組んでいたと思います。
また、私がリモート見学をさせてもらうことが決まったのは、プレゼンの授業の前日なので、作者が見にくるからということで、子どもたちが特別に張りきって準備をしてくれたわけではないでしょう。作者の関与がいっさいなくても、授業が成功していたことは間違いありません。
子どもたちが『給食アンサンブル』の物語を好きになってくれたのは、なにより東小倉小学校の先生方の授業の進めかたや授業内容が優れていたからです。
私が見学したのは終盤のプレゼンの授業だけで、細かな授業内容はうかがっていないのですが、宿題として感想文の提出を求めたりせず、授業も子どもの主体的な活動を中心に進めるなど、さまざまな工夫をされたのではないでしょうか。
昨年授業を見学したときから、こんなふうに児童書を使った国語の授業が全国で行われたら、児童書を好きになってくれる子や読書に親しんでくれる子がすごく増えるんじゃないだろうか、と思っていました。指導書のない教材で授業をするのはハードルが高いけど、なんらかの形でノウハウが広まって、ほかの学校でも同様の実践がしやすくなるといいな、と思い続けていたのです。
その『給食アンサンブル』の授業を企画してくださり、見学のときなどもお世話になった森壽彦先生が、6月に開催される川崎市の学校図書展示会のなかで、この授業実践について講演をされます。詳細についてはこちらのページをご覧ください(講演会は事前予約制です)。
授業の内容についてどのくらいくわしく話されるのかはわかりませんが、児童書を使った国語の授業を成功させるためのヒントが得られるかもしれません。
児童書と国語の授業の幸福なアンサンブルが全国に広まるために、ぜひ多くの先生方や、子どもの教育に携わる皆様に、森先生のご講演を聴いていただけることを願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
