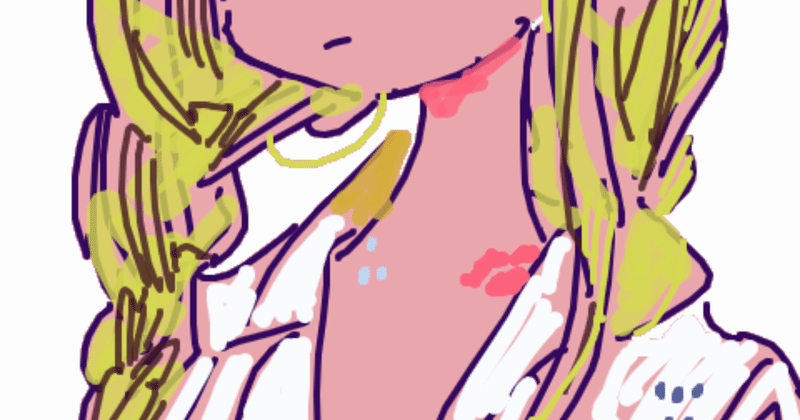
ズッ友
いつからかもう忘れてしまったが、こうやって仕事の合間にひとり屋上に行って、空をぼんやりと眺めることが習慣づいている。
なぜ僕が屋上の鍵を持っているのかというと僕がこの高校の教員だからで、なぜ特に用もないのにここに来るのかといえば、他人に会いたくなくなって何もかも投げ捨てたくなる瞬間がたまにあるからだ。
教育に対して情熱を持っているわけでもなく、このままずっと定年まで惰性で働いて、老後に身体を壊しながら遊ぶ人生のどこが楽しいのだろうと、ふと頭を過ぎってしまうのだ。
欄干にもたれかかって、ぼんやりと考えた。もし今すぐにこの欄干を飛び越えてしまったら、どうなるのだろうか。
もちろん答えはひとつ。ここは4階建ての校舎の屋上だ。地面には脳漿の飛び散った僕の死体が転がるのだろう。明日の地方新聞に載るかもしれない。
かつて僕は、この高校の生徒だった。
成績はそこそこ良かったが、パッと目立つわけでもなく、学園祭でLUNA SEAのコピーを演奏してモテていたイケている男子に嫉妬して、顔面を真っ黒にしてピアスをジャラジャラと付けたコギャルをバカにして、なんとなく大学に入ってなんとなく教職課程を取ってなんとなく教員になって、40歳手前になってここに戻ってきた。
人間の寿命が80年とすれば、もう半分に達することになる。思わず口に出した。
「意味ない人生だな……」
意を決して、欄干を無心に飛び越えた。この辺りは住宅地だ。一軒家の屋根がたくさん見える。その屋根にゆっくりと近づいている。ゆっくりと、ゆっくりと、僕の身体が宙を舞う。

飛び降りたら一瞬で意識がなくなって即死だろうと思っていたが、意外にも落ちる時間が長くて戸惑う。今になって、地面に突き刺さることに恐怖を覚えた。
「死にたく……」
そう言いかけると、誰かの手が僕の肩を叩いた。
振り返ると、そこにはひとりの女性がいた。髪は金髪ロング、耳と鼻にピアス、そして顔は真っ黒に焼いているが瞼の上だけは真っ白。
「やっと他の人に会えたぁ。超長かったってゆうかぁ。てか、ウチが死んだのが悪いんだけどぉ。でも、おぢさんじゃん。ウチ、タッキーみたいなのが良かったってゆうかぁ」
だるそうな口調で間延びして話す。こういう女性……というか同級生の女子を、はるか昔に見たことがある。僕がバカにしていた、コギャルというやつだ。
「ま、いいかぁ。退屈で死にそーだったしぃ。てか、もうウチ死んでんだけどね、あはははは」
「あの、君は誰?」
「あー、めんごめんご。久しぶりに人と会えたから嬉しくってさぁ。まぁもっとジャニ系っぽいイケてる同級生のほうが良かったけどさぁ。でもおぢさんもイケるよ、ウチ。ウチは大黒さくら。ここの生徒」
「ここの……生徒?」
「つっても20何年前の話だけどさぁ。まぁ、イジメつーかハブつーか、そーゆーのが無理で飛び降りってゆうかぁ?」
「……じゃあ、君は死んでるのか?」
「んー、つーか、あの世とこの世の境目っつーか。いいかげん20年もやらされるとMK5って感じ」
「死んでるの?死んでないの?」
「細かいことはいいじゃーん。せっかくこっちに来たんだから、おぢさんも楽しもーよ。オケる?」
「…………カラオケ?」
「そ。あ、もしかして、おぢさん、行ったことない?遅れてるぅ。今どきの若者といえばカラオケじゃん」
「いや、行ったことはあるけども……。僕たち、死んでるんだよね?それに僕は20年後の人だし」
「おぢさん、しつこいなぁ。モテないでしょ?」
さくらと名乗る少女は、真っ黒な顔をしわくちゃにしてゲラゲラ笑った。

不思議だ。
本当ならば僕の身体は地面に叩きつけられているはずなのに、血も出ていなければなんの痛みもない。かといって、幽霊のように浮遊しているような気分でもなく、あくまでも生きていた頃のように手足が動く。
ただ、景色がまるっきり違った。いや、建物そのものはみんな変わらずに並んでいる。古ぼけた校舎、近隣の住宅、商店街のアーケード、駅前のバスロータリー。だけど、さくらと僕を除いて、人の姿がひとりも見当たらない。車も止まったままだ。
「……なんで、誰もいないんだ?」
思わず口に出すと、さくらがぶっきらぼうに答えた。
「わかんない。生と死の境界的な?」
「誰もいない世界に放り出されるのか」
「そ。ここに20年もいるとさぁ。もはやチョベリバ通り越してどーでもよくなってくるけどぉ」
「…………」
何も言えずに、ただしばらく歩いた。
満員電車。信号待ちの群れ。交通渋滞。普段はいつも煩わしいと思っていたものが一気になくなると、こんなにも音のない世界になるのか。
さくらがカラオケに行きたがるのは、大きな音を出せるからじゃないだろうか。いや、単純にもともと好きなだけだろうか。
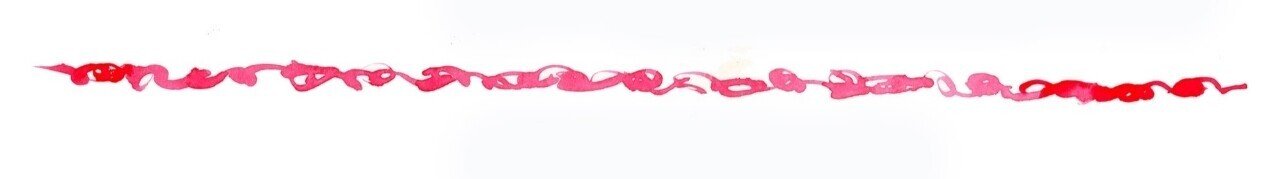
「じゃ、なに入れる?おぢさん最近の曲あんま知らなそー。DA PUMPとか知ってる?」
「……USA?」
「なにそれ。やっぱおぢさん知らないんだね。遅れてるぅ」
「いや……」
20年前のコギャルが知っているわけないよな。
「厨房からビール取ってくるね」
「いや、ちょっと待って。君は未成年でしょ?」
「20年以上ここにいるけど?」
「でも、君は自殺した高校生で……」
「おぢさんマジ細かすぎっ」
なみなみと注がれたジョッキに頭を押し付けられて、強引にビールを飲まされた。僕はアルコールに弱く、缶チューハイ半分くらいでもグデングデンになってしまう。
いきなりビールを入れたら最後、頭の中がぼんやりとして、なんだかどうでもよくなってしまった。
どうせ僕は死んでいるんだ。しかもさくら以外は誰もいないんだ。
僕みたいな中年が現役JKとふたりきりでカラオケなんて幸せ以外のなんでもない。お金を払う必要もないのだから、厨房からありとあらゆる酒をかっぱらってこよう。
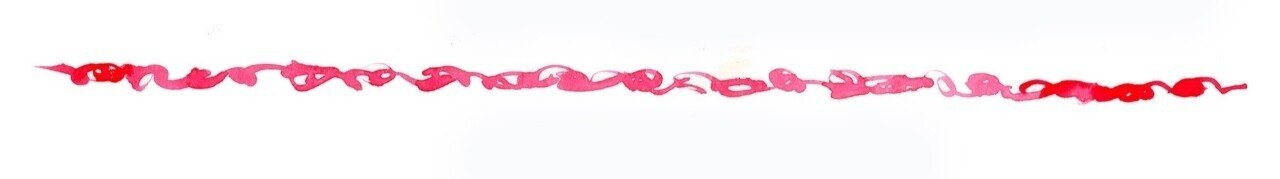
「マジウケるぅ。おぢさん、河村隆一のモノマネ上手すぎってゆうかぁ」
テーブルにはたくさんの空きグラスが散乱している。もうこれで何杯めなのだろうか。途中で焼酎を煽ってからはいっそうフラフラする。リクエストされるままにひとたび熱唱したあと、どすんとソファーに倒れこんだ。
「ちょっとごめん。さすがに限界かも。休ませてくれ。好きに曲入れて歌ってくれ。アムロちゃんでもglobeでもSPEEDでも……」
歌本を枕にして寝そべった。カラオケ店の歌本なんてかなり久しぶりに見た。デンモクの使い方がわからないと言うさくらが、スタッフルームからかっぱらってきたのだ。いちおう今でも存在はするんだな。
「ウチも、ちょっと休憩ってゆうかぁ」
そう言ってさくらは、横たわった僕の背中を抱え込んだ。慌てて僕は退けぞった。いくら泥酔しているとはいえ、まだ理性はある。
「やめなさい。君は高校生だし、僕は大人だし、そういうことはダメ」
「ふぅん。やっぱ先公だね。超マジメって感じ」
「……当たり前だろう」
「まっ、おぢさんくらいの歳の人とやっちゃったせいで、退学してから死んだんだけどね、ウチ。だから学校の子たちはたぶん、ウチが死んだこと知らない。オトナがインペイしたから」
さくらが声のトーンを落とした。
しばらくふたりとも無言のまま、座り直して向き合った。ドリンクバーで冷水を2つ汲んできて、さくらに片方を渡した。 さくらはとても美味しそうに飲み干して、星を描いたマニキュアの塗られた自分の指をじっと眺めた。
「ねえ、おぢさんは、なんで死んだの?」
指あそびをしながら、さくらはこちらを見ずに僕に訊いた。
「うーん。なんとなく、かな?」
「ふぅん。わかんないけど、わかるようなって感じ」
「君みたいに事情があるってわけでもないんだ。学校で特に問題も起こしてないし、厄介な生徒にも当たってないし、給料も良くはないけど悪くもない」
「死んでみてどう?良かった?」
「…………。まだ、よくわからない」
「だよねー。ウチはちょっと、……いや、チョベリ後悔してるかな」
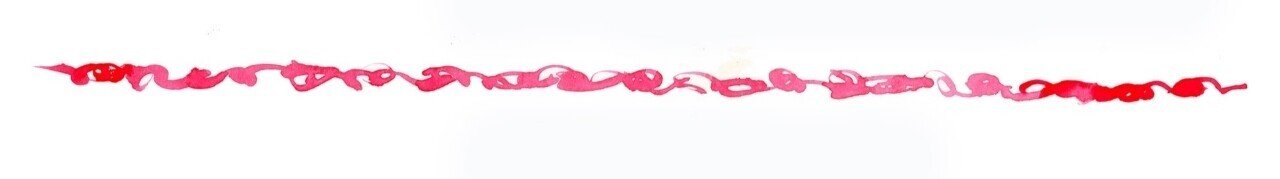
いつの間にか、眠ってしまっていたらしい。
頭がズキズキと痛む。吐き気がする。ソファーで寝たせいで腰も重い。このままここで再び眠ってしまおうか。どうせ誰もいない街だし、閉店を過ぎてここに居ようが迷惑もかからない。
さくらは隣ですやすやと寝息を立てている。メイクの半分以上が取れていた。その顔は幼かった。
さくらを恋愛対象としては見られない。未婚の僕には子供はいないが、いたらこんな感情になるのだろうか。
だけど、生きていたら僕と同じ年頃のはず。40歳のさくらに会えていれば……。いや、そんなことを願ってはいけない。
「ずっと、一緒だよ……」
さっきから、さくらは同じ寝言を繰り返している。涙を流している。そのたびにメイクはどんどん取れていき、素顔に近づいていく。
「ああ、一緒だな」
金色の髪を撫でてそう呟いて、情けなく声を上げて僕は泣いた。スイッチを点けたまま無造作に置いていたマイクがその声を拾って、部屋じゅうに鳴り響いた。
もう永遠に、死ぬことすらできない。
サウナはたのしい。
