
天の川の向こう側
「マイトも、花火大会は行かねえの?」
椅子を舟漕ぎしながら、ダイが僕に話しかけた。僕の名前は大谷舞翔(おおたに まいと)。ダイのフルネームは大和田大輝(おおわだ だいき)。出席番号が隣どうしで席順が前後だったことから仲良くなった。
「うん。昔は夜店とか面白かったけど、もう今見たらしょぼいし。花火だけなら家のベランダからも見れるしな」
「だよなあ。わざわざ神社まで行くほどじゃねえよなあ」
地元の神社では毎年、七夕の日に花火大会が催される。この日だけは境内が全解放され、焼きそばや綿飴やヨーヨーなどの露店が建ち並び、家族連れがたくさん押し掛ける。
といってもさほど大きな神社ではないので、中学生の足だとせいぜい15分もあれば一周できてしまう。
親に連れられて行った小さい頃は楽しかったが、学年が上がるにつれてつまらなく感じるようになってしまい、とうとう去年は、家から花火を少し見るだけで終わった。今年もたぶん、そうなるのだろう。
夏休みの思い出なら、市民プールに何回かでも行けば作れるだろう。スポーツは苦手だが、小学生の頃にスイミングスクールに通っていたおかげで、水泳だけはそこそこ得意なのだ。
今日は、七夕よりもよっぽど楽しみにしていたことがある。7月1日。プール開きの日だ。
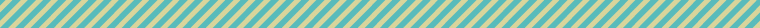
いい歳をしてドラえもんのプールバッグはさすがに恥ずかしいのだが、これしか持っていないのだから仕方がない。いつから使っているのだろう。もうボロボロで、色落ちによって、もはやドラえもんの身体が青というよりも緑に近くなっている。
テレビでチラッと視た天気予報では、今日の最高気温は30度だと言っていた。家から市民プールまで、せいぜい徒歩10分ほどだが、着いた頃には汗だくになっていた。
中学生以下の入場料は、2時間まで150円。賑やかな親子連れの波を避けて、少しでもまともに泳げそうな場所を確保する。といっても、せいぜい15メートルくらいだ。クロールをするには距離が足りないので、ゆっくりと両手を掻いて平泳ぎのストロークを始める。冷たい水飛沫が全身を刺激して気持ち良い。
無邪気な子供に何度か妨害されながらも、僕は30分ばかり泳いだ。そろそろ疲れてきたので休憩しようと、隅にあるベンチに座る。容赦なく照りつけてくる太陽で、数分もしないうちに身体は再び火照った。脱衣室の前にある自販機でアイスでも買って食べたい気分だが、その楽しみは帰りまで取っておきたい。
しかし……。この炎天下になんの水分補給もしないというのも厳しい。日射病になってしまう。ベンチから立ち上がり、自販機の近くにある冷水機へと向かう。すると、先に女の人がジャブジャブと美味そうに水を飲んでいた。
後ろに髪を結っていて、身長は僕より少し低いくらい。同い年くらいかな、とぼんやりと思っていると、彼女がこちらを振り向いて、聞き覚えのある声で言った。
「あ、マイじゃん」
少し吊り目で凛々しいその顔を数十秒間ながめてやっと、彼女が誰なのかを思い出せた。
「……ミライ……ちゃん」
後半の「ちゃん」は小声になった。萱島未來(かやしま みらい)。小学生の頃によく遊んでいた女子だが、中学校に上がってからはクラスが一緒になることもなく、会うのはかなり久しぶりだ。
以前は彼女の方が背が高かったはずなのに、いつの間にか追い越してしまっていた。そして……。慌てて目を反らしたものの、水着の胸のあたりが大きく膨らんでいるのが気になってしまった。
「久しぶりだね。アイス食べない?」
昔と変わらない人懐っこい笑顔で、僕の手を左手でつかんで、右手で自販機を指さした。小さい頃は毎日のように繋いでいたはずの手なのに、なぜかドキドキした。
「い、いや、いいよ」
と、慌てて振りほどいて、「もうちょっと泳いでくるから」と言って一目散に走り去った。
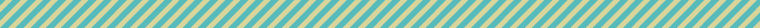
次の日もプールに入り、人波をすり抜けて泳いだ。初日の昨日よりもいくらか空いていて、なかなか快適だった。今日は少しクロールも取り入れた。
冷水機に向かう途中、なんとなく辺りを見回した。どうやら今日は彼女は来ていないようで、安心したやら残念なのやら、よくわからない気持ちだ。
今日の気温は35度に達するとのことなので、少し早いがアイスの時間にしよう。そう思ってロッカーに戻り、財布から140円を取り出して自販機へ。しかし、コインを入れても商品のランプが点滅しない。どうしたものか。
「はい、10円」
背後から声がした。振り向くと、昨日と同じ笑顔が見えた。
「ミライ……」
ちゃん付けで呼ぶのはなんだか恥ずかしい。かといって苗字で呼び捨てるのも抵抗がある。結果、下の名前で呼び捨てという、いちばんぶっきらぼうな形になった。つい胸に目が行きそうになるのを必死で堪え、彼女の指先に握られた10円玉を見つめた。平成31年……レアなやつだ。
「そこのアイス、150円だよ」
「あっ……」
そうだ。何しろ1年ぶりなものだから忘れていた。この市民プールの自販機のアイスは、外よりも10円、高いのだった。
「あ、あの、10円もらっていいの?」
僕が確認すると、彼女はこう答えた。
「じゃ、帰りに駄菓子屋でうまい棒買って」
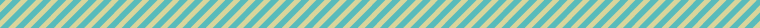
帰り道の途中の住宅地の中に、ひっそりと駄菓子屋がある。僕が物心ついた頃にはもうすでにかなり古びていた建物で、店の奥に座っているお婆さんは、たぶん80歳を超えていると思う。
うまい棒を1本だけというのもなんだか気が引けたのか、彼女は缶の三ツ矢サイダーも買った。僕はさっきアイスを食べたばかりだし、スーパーで買った方が安いと思いつつも、同じく三ツ矢サイダーを買った。
駄菓子屋そのものも珍しいが、今どき備え付けのベンチがあるというのも珍しい。しかも木製。よく考えたらこんなの、漫画でしか見たことがない。小さい頃はあまり気にしていなかったが、新しいマンションやコンビニがどんどん建っていくこの街で、こんなレトロな商店が生き残っているのは凄いことなのだろう。
「ここに来るの、何年ぶりかな?」
うまい棒めんたい味を豪快に齧った後、遠くを見て彼女が言った。
「さあ……。僕はたぶん、来たことないな」
「いや、マイも来てたよ。小さい頃、一緒にここに来て、サイダー飲んだ」
「そうかな?」
記憶を辿ってみたけれど、どうにも思い出せなかった。それにしても、昔は気にしていなかったが、マイという呼び方はちょっとやめてほしい。僕は男子なのだから。人差し指を立てて、彼女は説明を続ける。
「七夕の日だった。花火大会の日。花火見に行く前に、ここで待ち合わせした」
「うーん……。憶えてないな」
彼女は三ツ矢サイダーを一気に飲み干して、しゅんとした声で呟いた。
「そうだよね。昔のことだもん」
「なんかごめん……」
そう返して、缶のラベルに書かれている文字を見た。SINCE 1884。三ツ矢サイダーって、そんなに昔からあるんだ。
「ね、花火、見に行こうよ。来週、七夕でしょ?」
「うーん……」
「どうせ、一緒に行く女子とかいないんでしょ?」
「いないけどさ……。逆に、ミラ……、戸城さんは、彼氏いないの?」
「好きな人はいたよ」
「えっ?いつのこと?誰?」
「無理。プライベートな質問には、答えられませーん」
「ちぇっ、なんだよ」
「で、どうなの?行くの?行かないの?」
「まだ、わかんないよ」
「明日も、プール来る?」
「たぶん」
「今日と同じ時間?」
「たぶん」
「じゃ、行くか行かないか、明日までに決めといて。自販機の前で待ち合わせね!」
「え?ちょっと‥‥‥」
言いかけたと同時に、彼女は走り出した。数秒後、何かを思い出したかのように、甲高い声を上げた。
「あ、あとね」
こちらを振り返らずに、少し早口で続けた。
「わたし、もうすぐ引っ越すんだ」

「なあ、俺、やっぱ花火行くことにしたぜ」
鼻息を荒くして、ダイが僕の机を両手で叩いた。
「え?前は行かないって言ってたじゃん?」
「ああ、確かに、野郎どもで行ってもつまんねえけどさ。ほら、樟葉美月(くずは みづき)いるじゃん?」
「うん」
樟葉美月はうちのクラスの女子で、顔立ちが整っていて性格も落ち着いていて、男子の間で秘かに人気がある。
「でな……、あの……、そのぉ……」
ざっくばらんなダイがこんなにもじもじしているのは初めて見た。
「ぜ、全しゅうちゅう……」
と、最近はやっている漫画のキャラクターの真似をしながら2回ほど深呼吸したあと、赤らんだ顔でこう告げた。
「実は、大和田大輝は、樟葉美月さんと、お付き合いすることになりました!」
一気にまくしたてた後、ダイは教室の反対側の席で本を読んでいる樟葉のほうを見た。しばらくしてダイの合図に気づいた樟葉は、にこやかな顔で手を振った。
「今度、一緒に花火見に行くんだぜ」
どうだ、と言わんばかりに、ダイは胸を張る。
「そうか。おめでとう」
と、一応は祝ったが、内心ではちょっと……、いや、正直にいえば、かなり嫉妬していた。
-「どうせ、一緒に行く女子とかいないんでしょ?」-
昨日の彼女の言葉が、頭をよぎった。
もうすぐ引っ越すと言っていたが、どこに引っ越すのだろう。
小さい頃はたまに遊びに行っていたので、彼女の家がどこにあるかは知っている。僕の住むマンションから歩いて10分もかからないほど近くだが、なにせ細い路地の突き当たりなので、家に行く用事がない限り、通りすがることはない。
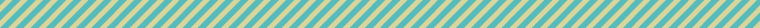
今日も学校から帰って着替えたあと、ドラえもんのプールバッグをぶら下げて外に出た。今日はいつもと違う方向に歩き、彼女の家がある路地へと出て、そのまままっすぐに進んだ。
すぐに、なつかしい一軒家へと辿り着いた。玄関に掲げられた“KAYASHIMA‘’のプレートの文字は少し薄くなっていた。左側に見える窓の向こうが、確かミライちゃんの部屋だった。けっこう広かった記憶がある。
「マイ、何してんの?」
後ろから声がした。……彼女だ。
「あ、いや、その……」
実際、僕はいったい何をしているのだろうか。自分でもよくわからない。もうすぐ空き家になる他人の家を覗いて何がしたいのやら。
「ま、いいわ。せっかくだから、上がってきなよ」
「え?」
間抜けな声を出す僕の手を取って、彼女は扉の錠を開けた。この前よりもドキドキする。小さい頃に何度も入った部屋のはずなのに。
といっても、カーテンは取り払われ、段ボール箱の山しかなく、壁にたくさん飾ってあったポケモンのバッジや、ベッドの脇に並べられていたディズニーキャラクターのぬいぐるみはみんな消えていた。
「引っ越すって言ったでしょ?家のなか整理してたら、なつかしいものいっぱい出てきたよ」
ほとんどの段ボール箱はガムテープで閉じられていたが、まだ開いたままのものもいくつかあるらしい。彼女が箱をひっくり返すと、中に入っていたたくさんのおもちゃが床に散らばった。
かつてベッドに置いてあったスティッチのぬいぐるみ、プリキュアのネックレス、連結器が壊れたプラレールのトーマス……。
「これとか、むかし花火の夜店で買ったやつ」
と、彼女はクレヨンしんちゃんのお面をかぶって見せた。今あらためて見たら、ちょっと顔のデッサンが狂っている。たぶん正規の商品ではないパチモノだ。
「あと、これ‥‥‥」
散らばったおもちゃの山の中から、次に彼女が取り出したものは、小さな指輪だった。もちろん本物ではなく、プラスチックで作られたチャチな偽物だ。小さすぎて、今の彼女の指にはもうはまらない。
「実は、マイも持ってるはずだよ、この指輪‥‥‥」
「えっ?」
「3年生の頃、夜店で2人とも同じこの指輪買って、結婚する約束した」
「そう‥‥‥なの?」
思い返せば、そんなような気がしないでもないが、もう3年生の頃なんて、ほとんど忘れてしまった。
「やっぱ、忘れてるよね。そりゃあ、そうだよね。もう中学生だし」
彼女は力無く笑った。どう反応すればいいのか少し悩んだが、自分でもなぜかわからないけど、これが今のところの正解な気がして、こう言った。
「今度の花火大会、やっぱ一緒に行こう」
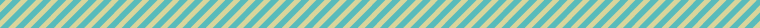
7月7日の午後5時まえ。今日はプールには行かず、駄菓子屋のベンチに座っていた。相変わらず暑い日が続いている。
「早いね」
麦藁帽子に薄いピンク色のワンピースの彼女が、僕の目の前に現れた。この一週間、毎日のようにプールで会っていたのだが、今日はいつものシャツと短パンのラフな格好ではなく、オシャレだ。いつもは後ろで縛っている髪も、今日はお団子になっている。
何度か部屋の中を探してみたが、指輪は見つからなかった。小さい頃に遊んでいたおもちゃは全部、捨ててしまったり、親が近所の子供にあげたりしたので、手元に残っていないようだ。
「指輪、なかったよ」
「やっぱり。捨てちゃってるよね」
「うん。なんかごめん」
「いや、いいよ。どうせ、小さい頃の話だし」
僕は、駄菓子屋のお婆さんから、2本の三ツ矢サイダーを買って、そのうちの1本を無言で彼女に渡した。
「え?奢ってくれるの?なんで?」
「小さい頃によく遊んでたミライちゃんが引っ越すらしいって母さんに言ったら、じゃあ餞別のお土産をあげなさいよ、って」
「それがこれ?100円だし、飲んだら終わりじゃない。しょぼすぎ」
「しょうがないだろ。まだ中学生だから、高いものは買えないし」
三ツ矢サイダーの缶はすぐに空っぽになって、ベンチの横のリサイクル用ゴミ箱に放り込まれた。あっけなすぎる餞別だ。
僕はとうとう、この1週間、どこかのタイミングで言おうとしていたものの飲み込んでいたひとことを言った。
「いつ、引っ越すの?」
彼女が、とうとうそれを訊かれたか、と言いたげな表情をした……ように見えたけど、実際にそうだったのかどうはわからない。
「…………」
しばらく沈黙していた。
……ドンッ!ドドンッ!
沈黙を切り裂くように、大きな花火の音が聞こえた。花火大会の開催は午後7時からだが、練習用の花火をいくつか打ち上げているのだろう。
ドドドンッ!ドンッ!
途切れ途切れに鳴る花火にかぶって、確かに彼女の声が聞こえた。
「明日の朝」
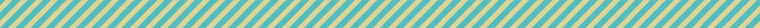
夜店では焼きそばやフランクフルト、夏の定番のかき氷も買った。食べ物ばかりだが、もう金魚すくいやヨーヨーに興味をそそられる歳でもない。それよりも、早く花火が見やすい場所を探そう、と言いかけたところで、彼女が向かい側の屋台を指さした。
「ねえねえ、アレ、やってみようよ」
その屋台には、西部ガンマンショー、と書いてあった。つまりは射的だ。
「うーん……」
3回100円。奥の棚にはたくさんのおもちゃや駄菓子が並べられていた。ほとんどが子供向けの小さなものだが、ニンテンドースイッチやiPadなどの高価なものも混ざっている。
「……うん、やろうよ」
屋台のおじさんに100円玉を差し出して、いざピストルを構えた。目当てはニンテンドースイッチだ。実は前々から欲しいと思っていたのだ。
しかし、一発目も二発目も、弾は狙った方向とは全く逆へと飛んでしまい、すぐにラストチャンスとなってしまった。
そういえば僕は水泳以外のスポーツはダメなのだった。いやしかし、水泳も含めてスポーツが全くできないのび太の特技は射的だ。ならば僕にも……。
……パァンッ!
弾がはじける音が聞こえた。なんと、さっき僕が撃った最後の一発が当たったのだ。ニンテンドースイッチに……ではなく、隣の景品に。
「はい、お兄ちゃん、これあげるよ。おめでとう」
屋台のおじさんが僕に渡した景品は、水泳用のゴーグルだった。がっかりする僕のほうを見ずに、彼女は嬉しそうに言った。
「結構いいんじゃない?」
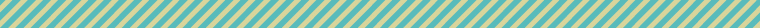
今度は彼女が挑戦したが、三発とも全く当たらなかった。正直、僕より下手かもしれない。
「おっかしいなー」
不満そうにぼやきながら、再び僕が持っているゴーグルを見た。
「ねえ、それ、着けてみて」
「え?なんでここで?嫌だよ。恥ずかしいよ」
「いいじゃんっ!」
彼女は僕からゴーグルを横取りして、勝手に封を開けて、僕の頭に強引に取り付けようとした。
「ちょ、やめ……苦し……ていうか、これ……」
すっぽりはまってくれない。
「このゴーグル、僕には小さ過ぎて、サイズ合わない」
せっかく当てたのに、これでは使えない。どうしたものかとボーッとしていると、彼女は再びゴーグルを奪って、今度は自分の頭にゴーグルをはめた。彼女の小さい顔には、ちょうど良くすっぽりはまった。
「わたしにはぴったり」
嬉しそうに言って、彼女はしばらくゴーグルを着けたまま歩いた。ふと思いついて、僕は言った。
「それ、あげるよ」
「え、いいの?」
「うん。だって、どうせ僕にはサイズ合わないし。三ツ矢サイダーだけってのもアレだし」
「……ありがとう」
「うん」
ドンッ!
ドドドンッ!
ドドドドドドドドドドドドンッ!
空に、天の川を描いたかのような綺麗な模様の花火が飛んだ。

花火大会が始まった。
あたりには、大人のカップルがたくさんいる。ダイたちもたぶん近くにいるのだろう。狭い神社だから、そのうちすれ違うかもしれない。
彼女と僕は、周りからはどう見えているのだろう。単に仲の良い異性の友達どうしなのか、それとも……。いや、でも、告白したわけでもないし、何より、恋とかいうものがなんなのか、まだよくわからない。
「……あの」
「なに?」
本当は、ここで手を繋ぐとか、ロマンチックなことがしたかったけど、いざとなるとドキドキしてできなかった。
「いや、……花火、きれいだね」
「あれ、天の川だよね」
彼女はしばらく沈黙して、こう続けた。
「織姫と彦星って、年に一度しか会えないんだね」
「うん」
「……明日、遠くに引っ越すわたしは、もしかしたら一生マイに……えっ?」
彼女の手をぎゅっと握った。彼女が何を言おうとしているのかはわかっていたから、その先を聞きたくなかった。
もう小さい頃のミライちゃんはいない。小さい頃の僕もいない。結婚指輪のおもちゃもなくした。でも、たぶん、僕は、彼女が……。
ドンッ!
ドドドドンッ!
ドドドドドドドドドドドドンッ!
花火は何度も鳴り続けた。ずっと、永遠に鳴り続けていてほしいなと、僕は思った。
サウナはたのしい。
