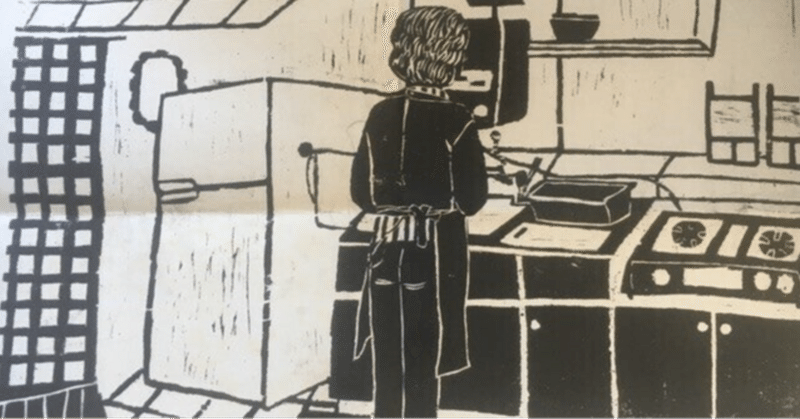
私の「料理にまつわる脳内地獄」の話
私は料理本やレシピが嫌いだ。反して、母は山のように料理本を、レシピの切り抜きを所有している。
1. 料理本が嫌いな理由:子供の頃のトラウマ
子供の頃、食事の時間が自分にとっては地獄だった。食事の時間が近ついてくると母は料理本を、レシピをひっくり返し始める。そして、本を見ながら料理を始める、想像に難くないが手順は悪いし時間はかかる。これが台所で繰り広げられる。
一方で、父が茶の間でイライラし始める。「まだできてないのか、なんでもいいからご飯と味噌汁と漬物をもってこい」と言う。父は「難しい料理を作らなくていいから、手早く作ってみんなで食事をしたい」と言うのだが、そんなのは夢の夢だった。追いかけてでてくる主菜、時間差で少しずつ副菜が出てくる。私はそれを申し訳なさそうに父に持っていく、その間に父の食事は終わっている。父は「こんなに品数はいらない」と吐き捨てるようにいって食卓から離れる。
父の気持ちもわかる、が、母親を責めるのも気の毒だ。多少でもなにかになればと母親を手伝うものの子供なのでたいして役に立たず怒られるばかりでさらに絶望感が襲ってくる。
母は、みんなが食べ終わった頃に食卓について食事をする。そこから後片付けは夜遅くまでかかる。これが毎日続いていた。
2. 料理本が嫌いな理由:おふくろの味なんてものはない
母の作る料理は、毎回違うレシピで作られる。これは今でもあまり変わらない。購入した料理本は数千冊はくだらないと思う。同じ「いりどり」でも、毎回違うレシピで本を見ながら作る。
自分から見ると、こうやってるから味が定まらないし、一度出てきた味は二度と同じものは出てこないといった感じ。
自分も、難しい料理はいいから簡単な料理でいつもの料理が食べたいと思うしそれは今でも変わらない。
レシピ本を見て作る料理は、時間に余裕があって料理を楽しみましょうといいうときならいい。が、日々それをやってたらたまらないと思っている。
3. 料理本が嫌いな理由:じつは料理ってすごく複雑
食事の時間が地獄、、から抜け出したくて、高校で調理師の資格をとり、短大で栄養士の資格をとった。お菓子作りは子供の頃からやっていたが、高校で習った栄養学や調理学、食品学はめちゃくちゃおもしろかった。調理実習で作ったものはどれも美味しくて、少し呼吸が楽になった気がした。
して、それなりに作れる自分が料理のレシピを見ると、、レシピに書いてない外側のプロセスが絶望的に難しいということに気がついてしまう。
そもそも、その材料をどうやって買い揃えるの?余った食材をどう管理するの? 必要は調理器具や技術は何?みたいなことは知っているという前提で書かれている(仕方がないんだけど)
自分は社会では業務設計を生業にしているのだが、料理のプロセスを設計と考えると気が狂いそう、、と思う。たまに見かけるレシピをみると絶望する。
自分が興味があるのは「野菜料理」なのだが、それらのレシピには、タンパク質の食材を合わせたものが大半を占める。食べたいのは野菜なのに、なんで豚肉やエビとか組み合わせないといけないの?!と思ってしまう自分がいる。
食材は、その扱う種類が増えれば増えるほど工程は倍々に膨れ上がる。+1ではない。料理ができる人にとってはできて当たり前のことだが、そのプロセスを読み解くと「いやいや、これ、初心者には無理でしょ」と思ってしまう。
時間と心に余裕があって「料理を楽しみましょう」と言う時にはいいけど、日常にそれをやられた自分にはトラウマになっている。
4. 料理本が嫌いな理由:正解を外側に求めてないか?
基本的に、レシピがある場合一度は「その通り」にやってみないとわからないところがある。自分の場合、簡単そうでできそうと思ったレシピにはトライするし、やったら最低でも10回くらいは繰り返し作ってみなくても作れるようにするし、自分なりにアレンジしていく。
が、母は繰り返さない。そして、作ってみて何か味が定まらなくて「これじゃないかもしれない」みたいになる。もはや味がどうなのか?ではなくて、そういう「心持ち」が嫌いと思ってしまう自分がいる。
5. 山口さんに言われた一言から
この話を、先日山口祐加さんの著作『自分のために料理を作る』の読書会でご本人がいらして、対話する時間に参加させてもらった時にしました。
そうしたら、山口さんが
「それでも(母が)諦めてないってところがすごいですね」
と一言おっしゃった。
いや、たしかにそうだわ。
母もこの本は読んでいたので、これは母と話してみようと思った。
6. 母との対話
数日後の夕食の時間に、山口さんが母のことをこう言っていたという話をした。ところ、母から出た言葉は私にとっては衝撃だった。
「料理家によって調理法がぜんぜん違うので、それを実際にやって違いを知るのがおもしろいのだ」と言ったのだ。
なるほど、だからえんえん続けられるんだと驚いた。
一方で、わたしはそのことで父親がいつも怒っていたという話をしたら、母は、(父親がそう考えていたとは)「ぜんぜん知らなかった」と言うのだ。
言われてみれば台所と茶の間は物理的に離れている、父親の様子は見てないから知らなかったと。その間に立っている私には「父親は怒っている、母親はなんとかがんばって料理をしている」という構図になっていたのだが、これは私の脳内だけで起こっていたらしい、板挟みってやつ。
私は今でも母親が料理本を見て作る料理が嫌いで、それは父親のイライラする姿がフラッシュバックするからだ。そして、それだけ文句をいいつつも、それが一切解消されることなく父は死んでいった。こう言う問題は、一生かかっても解消されないのか?という絶望の中で自分は生きてきている。
母に言わせれば「私に言えばよかったのに」と今さら言うのだが、父はいつも怒っていたので、たぶん言ってもケンカにしかならなかったように思うし、父もそう思うから言わなかったんだと思う。
7. 食の不自由さ
私にとって食は地獄でもあり天国でもある。自分は好きな時に食べたいものを食べたい、自分でコントロールできるようにしたいと切に願っている。
願えば願うほど、社会の中の「食の不自由」を見つけてしまう。
自分がそうなのだが「自分の不自由さ」が言えるようになった時には、問題は解決していると言える。私からすると食の場面には言語化されてない不自由さがたくさん潜んでいて、こっちを見ている。
日常の食事の問題は、レシピや技術未満の問題がたくさんある。山口さんのこの本にはそんな問いかけを正面から投げかけています。
私の「人は本当に食べたいものを食べているのだろうか?」という問いはまだまだ続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
