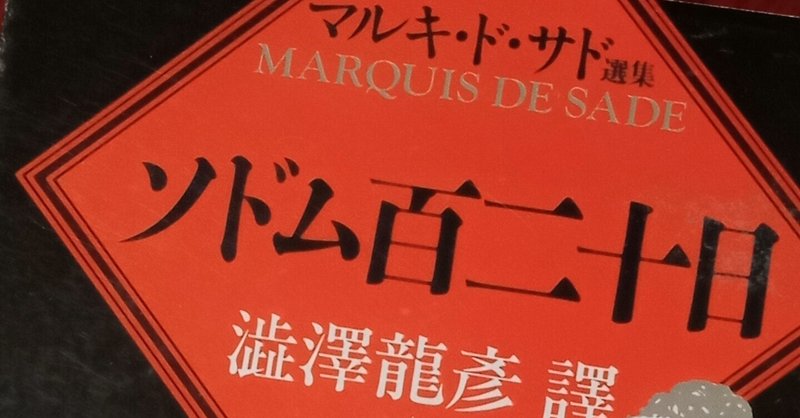
倒錯する欲望。鬼畜文学の金字塔、マルキ・ド・サド著『ソドム百二十日』
禁断の一冊を紹介したい。
マルキ・ド・サドの「ソドム百二十日」である。
この小説はフランス革命がおこる直前の一七八五年ごろから作者がバスティーユの獄中で書き始めた。
本名ドナティアン・アルフォンス・フランソワ・ド・サドはパリに生まれた貴族であったが、淫行と放蕩を好み、催眠剤を飲ませた上の婦女暴行や乱交パーティーの開催などで度々投獄されており、人生の三分の一におよぶ日々を獄中で送った。彼の私生活もさることながら、書かれた作品すべてに暴力的かつ不道徳極まる世界観が一貫しており、淫猥で性倒錯的で反キリスト教主義の登場人物が、純真で信仰深く美しい人物をなぶりものにするという作風である。獄中での執筆においては没収されることを恐れて細い紙片を貼り合わせ、そこにびっしりと小さい文字で裏表に書き連ねた。この「ソドム百二十日」については全長が十メートルを超える巻物になっていたと言われている。
ながらくの間、禁書扱いとなっており、罪を問われることを恐れた親近者に破棄された作品があるものの、現存するものについては数奇な運命を経て保管され、二十世紀初頭に一部のシュールレアリズム作家らによって紹介・翻訳され、現在にいたる。「ソドム百二十日」の草稿については競売でフランス政府が買い上げ、現在は国立図書館に保管されている。
十九世紀ドイツの精神医学者クラフト=エビングは同性愛や病理学的に逸脱した性の研究で知られており、彼によって、相手を辱め苦痛を与えることで性的興奮を得る性質を持つ者をサドの名にちなんで「サディスト」と名付けた。
「ソドム百二十日」は主に四人の登場人物がいる。革命に揺れるフランスのどさくさに紛れて莫大な富を得て放蕩の限りを尽くすブランジ侯爵とその弟司教、デュルセ、キュルヴァル法院長である。彼らは同じ道楽を持つ筋金入りの変態や極悪人、あらゆる悪徳に通じた手練れの熟女らを集め、彼らの餌食となるべく国中から集められた未成年を含む無垢な男女もかき集め、スイスの山奥の城へ籠って百二十日におよぶ饗宴を催そうと目論む。
ブランジ侯爵は自分の性癖についてこう言う。
「悪徳こそ、人間にあの精神的肉体的な振動を感じさせるべき唯一のもの、いちばん甘美な逸楽の源泉であると、わしは納得しているよ」
かれは道徳に反した行いを恥じない。罪を自覚し、それが快楽に直結することを誰よりも確信している。性欲求と道徳の境界があいまいな常識に背を向け、世間の尺度を何一つ持たない彼はある意味、絶対王政が揺らぐ時代において個人主義を掲げた先進例と言えなくもない。実際、サドの作品において、反道徳的ではあるものの哲学的ともいえる思弁が何ページにもわたって展開される場面が多くみられる。
この「ソドム百二十日」の最大の特徴は、反道徳勢の人物らの性器の特徴と醜悪な性癖、極悪な性格の描写が延々と続く点である。
「半世紀を生きた身とはいえ、いまだに一日に七回、ないし八回を平然とやってのけることができた」
「おどろくべき力に恵まれた侯爵にとっては、片手で娘を凌辱することも易々たる業で、何度もこのことを実地に証明して見せていた」
「この雑巾みたいな尻たぶらの真んなかに、いつも開きっぱなしの大きな孔があいているのだが、その巨大な直径といい、臭いといい、色といい、尻の孔というよりはむしろ便器の穴といった方が近かった。なおその上に、ソドムの豚をおびき寄せる餌として、彼はこの部分をいつも極端に不潔な状態にしておく習慣をつけていたので、孔のまわりにはつねに厚さ二寸ばかりの糞が土手のようにこびりついていた」
まるで鬼畜百科事典とも呼ぶべき代物である。
次の展開が饗宴に連れていく哀れな犠牲者の選定である。まるで競技予選のような様相を帯び、邪悪な人物たちの手から手へとなぶりもののされる犠牲者たち。彼らの目にかなうものは残されるが、対象外となった者らは決して生きて帰ることはできなかった。
さらに饗宴の会場の描写もある。
「王座の両側には、それぞれ天井に接するほど高い柱が一本ずつ離れて立っていた。この二本の柱は、何らかの過失を犯して、懲らしめてやらねばならない人間を縛りつけるためのものだった。懲戒のために必要なあらゆる小道具が、この柱には取りつけてあった」
「三色の綾織布のトルコふう寝台が、同じ調子の室内装飾とともに、この部屋部屋をひとしく飾っていて、各閨房には、およそ望みうるかぎりのもっとも官能的淫蕩的なものがすべて、凝り過ぎと思われるまでに取り揃えてあった」
「土牢は三重の鉄扉で閉ざされ、その内部には、見ただけでも怖気をふるいたくなるような、残忍無比な技巧と洗練の限りをつくした野蛮とが案出しうる、あらゆる種類の不気味なものが揃っていた」
しまいには、この饗宴の規則まで策定してしまうほどの徹底ぶりである。
「神の名を発するときにはかならず、悪罵あるいは呪詛の言葉を同時に発し、できるだけ頻々とこれを繰り返すべし」
「なぶり者はすべて、男であれ女であれ、身勝手に身体を清潔にすべからず。とくに排便後は、月番の友だちのはっきりした許可なくしては、けっして拭浄すべからず」
こうした経典が延々と続く。これらのおぞましい戒律は「罪の聖書」と形容しても差し支えない内容で、ついに百二十日におよぶ狂乱の宴が幕を開けるのである。
ところが、どうしたわけかここで小説が終わってしまうのである。サドはこの小説の構想を、現存する形の六倍にするつもりだったとしている。紙が足りなかったのか、獄中の制約があったのかは謎であるが、この作品が完成していたら目もくらむ前人未到の怪作となっていたに違いない。
私はこの作品を名作文学と考えている。これは、ただのポルノではない。ただのエログロナンセンスでもない。既存の価値観と文化を全否定した哲学であり、良心を捨てた先にある人間が持ちうる地獄とその可能性を私たちに提示しているのである。人間はここまでの悪を想像できるのだという証であろう。いわゆる「いい本」だけが名作ではない。想像力はあらゆる方面に触手を伸ばすべきだろう。悪を知らなければ私たちは善の価値も知らぬまま日々を送るに違いない。もし現代でこの本が禁書になったとすれば、それは人々の想像力を奪う行為に他ならない。
生きるうえでは悪の免疫も必要なのだ。これは人生のワクチンである。これを読んで怖気を催したら副反応と思って諦めて欲しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
