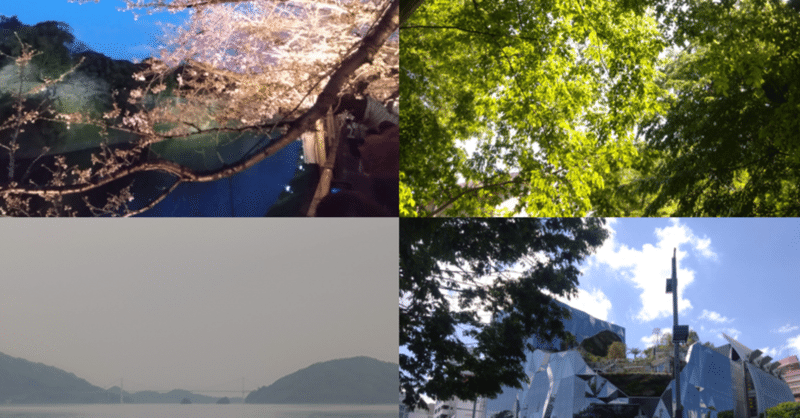
2024年4月後半
4月は色々ありつつも、振り返るとメリハリなく色合いがハッキリせずに過ぎてしまったような気がしている。それはそれで幸せなのかもしれないが、張り合いがないと感じる私。
でも思い返せば、桜色、新緑色、青空、曇り空、まさに色々だった。
(5/3一旦アップし、5/7,8加筆修正し、5/8 15:20公開しました)
20240416 Tue.
日曜に広島で法事、それに続く親戚達との瀬戸内海クルーズを経て
月曜夜は近江八幡宿泊。
今日は近江八幡をたっぷり一日観光して、夕方移動&帰宅。
8:00過ぎ ホテルを出てバスでヴォリーズ学園へ
ヴォリーズ学園概観や近所の保育園近辺を散策
裏道を通り、掘りの端っこを発見
9:30頃 水郷めぐりの事務所着
10:00~11:40 水郷めぐり
11:50 たねやの施設 ラ コリーナにて休憩とカフェ
12:30頃 バスで中心地 八幡掘へ戻る
12:50-16:30 ヴォリーズ関連の近江兄弟社、教会など
資料館(市立資料館・郷土資料館・歴史民俗資料館・旧西川家住宅)
16:30-17:00 コロニアル風戸建て住宅など見学しホテルへ、荷物受取り
17:30 琵琶湖線 近江八幡駅から米原へ
18:00 新幹線 米原から品川へ
手漕ぎの舟で水郷めぐり。近江八幡の水郷は文化庁による 重要文化的景観 に選定されている。日本遺産の「 琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産 」の構成文化財だそうだ。
そういうわけで、元々舟で堀を回りたいとおもっていたが、行ってみて現地の観光地図を見ると、水郷めぐりは1つではなく4つくらいあることを前の晩に知った! どれに行けば一番いいだろう?
迷って決めた場所は結果的に満足いく選択だった。ラッキー。

ヴォリーズ学園に近いところが出発点、手漕ぎの風情、時間たっぷりで景色が変わる、漕ぎ手のおじいさん(70歳位)の話が興味深い。話も面白いが、本業はやはり舟漕ぎだろう。狭い用水のようなところを90度に曲がったり、風に吹かれて流れされているときにも、うまーく舟を進めていた。その証拠に5分くらい前に出た同業の舟に最後は追いついていた。

葦(あし・よし)が生えていて、こういう風景は日本に沢山あったんだろうなと思える景色。桜の盛りは過ぎていたが、遅咲きの桜はまだ残っていた。



背の高い葦の間を音もなく船は進む。これは……追っ手から逃げる姫様のような気分になった。一方でこうして移動していると悪人に襲われる可能性もあるなぁと怖くもなった。

でも、湿地帯だから、ぬかるんでいるのかな
途中、サギにも出会った。私達が真横を通ったとき、魚を狙っているのか飛び立たずに居た。

亀も印象深かった。浮いている木の幹に止まり甲羅干しをしているらしい。

時代物の撮影でも使われるそうだ。


葦が生える水辺は、毎年焼いて下草を燃やさないと、雑草が生い茂り景観を保てなくなる。しかし最近は煙が流れて民家からクレームが来るため毎年は出来ないらしい。人手不足も関係していそう。
日本古楽器 篳篥は、漆を塗った竹製の縦笛が管の本体、この管に葦を潰して作ったリード=蘆舌を挿し込んで演奏するそうで、そのリードが作れなくなってしまう。毎年本当は燃やして生態を保ちたいと考えているが悩ましいと船漕ぎのおじいさんが話してくれた。

ちなみに、ヨシとアシは同じものなんだって。舟で他のお客さんと、どっちなんだろう、わかりませんね~と話していた。
水郷めぐりのルート。たっぷり80分コース。

下記サイトによれば、水郷めぐりは4つどころではない、6つもあるそうだ。私達が乗ったのは、近江八幡和船観光協同組合。30人くらい漕ぎ手がいたそうだが、コロナで減少傾向にあるらしい。漕ぎ手は土地の人もいるが、京都や他の地域から、大企業退職者や医者などユニークな方もいらっしゃるそう。
水郷の次はラ・コリーナという観光施設へ。全く行くつもりがなかったのだが、水郷めぐりのおじいさんが、あれは建物を見るだけでも行った方がいい、ここから近いし、と盛んに進めるから行ってみた。
ラ・コリーナは近江八幡自慢の会社、たねやの施設。
和菓子のたねや、きっとデパ地下などで見たことがあるはず。バームクーヘンのクラブ・ハリエClub Harieもこの会社。
その本社がある近江八幡に、広い敷地と凝った建築を活用したラ・コリーナほんとに面白い建物。

山に埋もれて見えるように、自然と交わるように、設計されているらしい
昨年、青森県三内丸山遺跡でみた竪穴式住居も屋根が地面とつながっていた。それと似ている

もっとゆっくり時間があれば、バームクーヘン工場の見学もできるらしい。
バスで八丁堀へ戻ってから、とことこ歩いて概ねヴォリーズの建物は見てまわった。市立小学校さえも美しいヴォリーズ風概観の建物。ヴォリーズは近江兄弟社(メンタームの会社)を立ち上げ、そのグループ会社は現在、学校、病院、介護施設などを運営している。


ヴォリーズ建築は、もともとある街並みに溶け込んでいる。お堀の周囲もブラブラすると板塀の家屋や大きな商家などが渋い街並みを作っている。スキッとした美しさ。





ずっと保存されていた場所もあるし、一旦、現代風にしたところを戻した場所もあるそうだ
近江八幡全体で街づくりに取り組んでいる
最後に、資料館や有力商人の住居を見学。そこで豊臣秀次に関する史実、日牟礼八幡宮および城下町の成り立ちなどについて初めて知った。豊臣秀次は秀吉の弟で、何度も秀吉に試されたり無理難題を押し付けられたらしい。それでも秀吉天下取りのために動いたのに、結局最後切腹を命じられたも同然の状況でこの世を去った。それまでにこの地を与えられてから町人町や職人町をつくり町の基礎を作った。若くして為したその功績は地元でずっと長く語り継がれているようだった。

天皇が行幸されたとき神社のご神体がご挨拶に向かい、また神社へ戻るという流れをなぞらうお祭りがあるそうで、今日は神社へご神体が戻るところだった
1日近江八幡の人達が打ち出している観光資源を通じて感じたことを書いてみると、土地の神々と民の営みに、秀吉の弟 豊臣秀次と、建築家ヴォリーズが大きな影響を与え、その資産を大切に護り育てながら自ら生きている堅実な人々の街。それが近江八幡。
私なりに納得したところは、縄文時代から人々が住み着いたこの地は、湿地帯として萱などの農産物を生かした生業を営みつつ、戦乱のなか豊臣秀次により城下町を構え、その町としての第二次産業としての武器製造や商売の機能を発展させた。その構想はずっと引き継がれ、町の骨組みとなっていて、若くして散った豊臣秀次を大切に思う町の人々がその構想を大事に守りながら街をつくってきた。明治時代にヴォリーズがやってきて、秀次の文化を担う若者たちと一緒に、西洋建築やその思想をこの地に根付かせ、近江兄弟社・たねや(和菓子)など地元を代表する企業を発展させ、町の人々の営みを融合させて現在の街並みを作っている。伝統や丁寧な仕事・三方良しの商売を営み、赤ちゃんからご老人に至るまで健康的な生活をし、教育を行き渡らせている。
ここで生活することは幸せなのだろうなと思える場所だった。
(見えていない場所、郊外には工場など今のビジネスがあるだろう。幸せそうでいて、ここはここの苦しさがあるのかもしれない)
□
品川駅に20時前。母も私も自宅へ着いたのが22時前。たっぷり遊んだなぁ。

滋賀県米原にもスタバがあるかと思ったら、そこにはなくて残念だった。新幹線駅だけ、というあっさりした駅の作りだった。近江八幡にもスタバはあるが観光エリアとは離れた場所に立地していてそこまで行けず。かといって駅近にある彦根で途中下車する余裕もなく。
そういうわけで、広島県、オマケで寄った岡山県でスタンプ貰ったことが、滋賀県でゲットできなかった埋め合わせになった。滋賀県には琵琶湖を目指してまた来るだろう。そんなに大事なんかいと自分ツッコむw
□
滋賀県といえば、とび太くん!
色々なバージョンがあって楽しい♪

③女の子版とび子? ④水郷めぐりのとび太 ⑤と思ったら道の反対側にもいた!
20240417 Wed.
鎌倉でオーバーツーリズム対策として国の実証実験を5月連休に行う予定との報道。江ノ電が非常に混雑して、観光に来て満員電車だということとともに、地元在住者が乗れない事態が起きている。そのためGW中2日間、鎌倉駅から長谷駅までの徒歩移動を推奨するもの。本番どうなるだろう。
他にも市が取り組む社会実験もあるらしい。
公に数値も確認できるような取組みを始めることは、これまでにない鎌倉の動きだ。
■
上野文化会館小ホールで『東京・春・音楽祭』の一貫で、イスラエル出身でアメリカ在住、イノン・バルナタンのピアノコンサート。

とても熱烈に拍手をする人が多かった。
確かにとても上手。
だが、私はあまり好きになれなかった。
自分の好みが、新しいものにたいして保守的に、心狭くなっているのかもしれないと思いつつ、好きになれなかった。これだけの技術があり、繊細な表現からダイナミックなところまで、幅広く、何でもできる感じなのに、なぜ私は好きになれないのだろう?
繊細な表現は好き、色合いを感じるような演奏。
ダイナミックなところは、すごいなぁと思うけれど、力が前面に出過ぎでちょっとなと思う。
両方をできることはとてもすごいことだと思う。
しかし、
最後に好きになれない。
なんだか「おれ、すごいぞー、すごいだろー」みたいな感じが出ているからかな。真っ赤に血圧あがってる感じに弾いている様子からかな。(それは生理的な反応にすぎないのに)
ジブンの好みには何か偏りがあるな、ということを実感。
同時に、好みは好み。それでいいじゃない、とも思う。
ジブンの偏りがあってもいいし、その偏りを外してもいいと思っていれば、それでいいような気がする。
演奏を気に入った方のブログ。
20240418 Thu.
朝と夜に読書会。ベイトソン/レヴィ・ストロース
その他はダラダラしてしまった。
以下、そのいいわけ。
春先は毎年調子が悪い。
仕事をしているときは、3月末から5月まで特に忙しい時期だった。体調があまりよくないのに忙しいと、ダブルで響く。この時期に副鼻腔炎にかかったり、理由のわからない肝炎にかかったりしたことがある。そこまでいかなくても、秋冬と比べたら、やる気も集中力も段違いに低い。
春先に身体を動かしたり、山菜など苦味を食べたり、代謝をよくしようと試みて少しは良くなっているかもしれないが、基本的には同じだ。
でもこの数年、会社勤めをしていないとストレスや忙しさがないので、以前よりかは調子がよいように感じていた。今年は、だらだらした頭痛が昨年末から続いていることもあり、花粉症的な鼻づまりと相まって、頭のなかがモヤッとしっぱなしだ。
結果、なにかをしようという気が起こらないとか、
なにかをするまで時間がかかって、それまで結果的にぼーっとしているとか、やったのに、肝心なことを忘れていたりする。
ポンコツだな。
でも気が起こらないということは、本当はしなくてもいいことかもしれない。本当にすべきときに、やる気になるものかもしれない。
だから、ダラダラ時期には無害なことをしようと思う。
ちょこっと、小さい場所を片付けたり
良く寝たり、
身体をほぐしたり。
まぁそう思っていても、ぼーっとしてる。
そのこと自体は、良くも悪くもないことだ。ただの状態。
20240419 Fri.
朝読書会。ラスキー
出たくないなぁと思いつつ、自分が当番だから出る。
結局、すべてが雑談の時間になった。雑談といっても論文を読まないだけで、その領域の話をしているのだけれど。
「『人の器』を測るとはどういうことか」
という書籍が出版された。
まずタイトルにざわつく人がいる。
それを受け入れたうえで、どう活用しようかと考える人がいる。
会社とか組織で取り入れたら、どうなるんだろう?と思う人がいる。
でもこの本は、一番メリットがあるのは自分を見つめ直し、自分を育てようとする気持ちを持ち続けようという気になること。
育てる方法は、道徳的に人格をよくする/出来ること、スキルを増やしたり高める、それ以外に弁証法的認知能力を高めることも重要だと教えてもらっている。
■
この動画で語られていることに、すごく同意。
数値化、言語化、それできないところにある身体値。身体値を信頼して、数値や言語と併用していることが賢いと感じている。
20240420 Sat.
頭が痛い
夕方遅くなって実家へ。
電車の連結がスムーズで、ひどく遅くならず19時くらいにたどり着けてよかった。
今日は一緒に夕飯を食べて、早めにお風呂に入って寝るだけ。
20240421 Sun.
庭仕事に励んだ。またもは旺盛に繁殖している。

ひとつの株からいくつ花をつけるかわからないが、ひとつの花から4つの種ができるそうだ
ハナニラは、実は周囲の環境を読んで複数の繁殖方法からひとつを選んでいるのではないだろうか? 詳しく調べたり確認したい場合、これは種苗業者にツテをつくればいいのだろうか? ハナニラに対抗する植物、ハナニラに害を与えるが土壌や他の植物にとって安全な薬物、ハナニラを好んで食する動物、そんなものがいないだろうか?
20240422 Mon.
実家にて朝を迎える。天気は雨。
家のなかの片付け、新聞紙を縛ったり、冬物の寝具を片付けたりちょこちょこ手をつけたが、基本的にのんびり過ごす。
14時過ぎに母と歌舞伎へ出発。母にとっては、これが本日一番力をかけるべきイベントだ。出かける支度をして、腹ごしらえ・お手洗い対応など入念にし、時間の余裕をもって出発。
片岡仁左衛門と坂東玉三郎の共演で芝居と踊り。二人を一緒に観られるのは、もう最後かもしれない。そんな可能性も大いにあり得る。
彼らが若いときは本当に良かっただろうな。その頃、私は働くことに精一杯で観にいく余裕が無かったような気がする。あるいは若くて、歌舞伎なんて自分にはわからないと思っていて、仁左衛門と玉三郎におば様たちがキャーキャー言うのをみて、冷ややかに距離をとっていたのかもしれない。
一昨年も16,000円というチケット代は高いと思っていたが、いまは一等席18,000円、二等席14,000円、三階で6,000円と4,000円。桟敷席は20,000円。
https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/869

2人の所作は4K画像で残してもらいたいくらい、それをアップや角度を変えて見てみたいくらいに素晴らしかった。
タンゴとかアイスダンスと同じくらい…という表現がなんですが、『神田川』は日本のそれ。二人が生きてるときに目にすることができてよかった。
仁左衛門さんのふくらはぎや太もも、メリハリがあってセクシー
玉三郎さんは身体の軸と支える筋肉が鍛錬されつづけているのだろうな~という美しいポージング!
歌舞伎は個人の人柄や力量が、歌舞伎界の技と伝統に支えられた舞台の上で花開くのだなぁ、と当たり前のことなのでしょうが感動した歌舞伎初心者です。
夜の部は、ポスターにある芝居『於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)』踊り『神田川』のほかに、踊り『四季』もあり若手の踊りを楽しむ趣向だった。幼稚園か小学生くらいの子供でも、それぞれ個性があり身体の動かし方や頭の位置などで表現するものが違う。
■
課題文。あまり時間をかけられないので、過去のものを修正して提出することにした。とはいえ、かなり手を加えたつもり。
20240423 Tue.
最近、Tverを活用しすぎている。
あまりドラマを観なかったのに、この2-3月は『光る君へ』『不適切にもほどがある』を観ることが習慣づいてしまい、4月以降も『光る君へ』を継続し、『舟を編む』とか『366』を観ている。それから『あの本、読みました?』を見始めた。
目が疲れるといいつつ、目に負担をかけている。
考えたり何かするより、受動的に時間を過ごすことに傾いている。
本当に自分がやりたいことは何か?
本当に自分が活かされることは何か?
■
YeLL5人目さん
前回のつづきから。
前回私の発見は、この方はタイプとして、自分の内面を言葉にしにくい方で、それを言葉にして返すと、そうだ、そう思っていた、とおっしゃってくださる方。決して言語化が”出来ない”のではなく、内面にあり大事なものであり、それが当たり前にあるために言葉にならない感じ。
今日も、そのことをお話くださった。前回のセッション中より一段進んで「自分にはこういう気持ちがあった」とお話くださった。それは良かった。ありがたい言葉だ。
ああ、方向は間違っていないみたい。
しかしそうだとして、この先どう進んでいくことになるだろう?
だれもそこは決めていないしわからないことだけれど。
そこにどうアプローチするかによって、プロセスも結果も変わってくる。
ハッキリしているのは、拙速なアプローチ、単なる問題解決は違うのだ、ということだけ。
20240424 Wed.
ダメだった。やり直した課題文。
指摘されたことは改善したが、その結果、新たな問題が出たというか。
自分でもうっすら気づいていたことを、字数制限があるから、えいやッと出してしまった。
そこが次なる問題になり不合格。
これは三度目の正直というか、ブラッシュアップして出したい。
今回指摘されたことは、これまでもい似たことを指摘されている。私の書き方が、くどくなくあっさりしているというか、読者にはもっと明確にくっきり伝えるべきだという指摘だ。
だから納得。
■
坂本図書へ。
存在を知らなかった。
友人に教えられ、その人達と話を合わせられるように私も訪問。
3時間3300円+ワンドリンク。
本の冊数はそれほど大きいわけでない。
事務室に書架が並べられオシャレに展示されている。ゆるやかにカテゴリーされている。古い本・希少本もあるし、その分野の定本とされるものもある。
坂本さんが何に興味を持っているか、何に影響を受けたか、がちょっとだけ垣間見られる。
音楽に関しては、子供のころ読んだであろう本『世界音楽物語』(偕成社)が面白かった。とある作曲家中心に図版が切り取られている。
『野生の思考』は、何か所か鉛筆で丸をつけられたワードがあった。
静かな空間に、同じ時間枠に来た人7-8人。
お互い何を見ているのかな? 書架全体は何があるのかな? と気になりつつも読みだした本に夢中になってしまう。
気になった本
・野生の思考
・声と音楽 ブラジルの本
・ホツマ 言霊
・ロマンロランの数冊
・世界の木
・漱石全集
・大洪水 クレジオ
・月に歌うクジラ
・世界音楽物語 偕成社
・深沢七郎
・音楽機械論
・22の羅針盤
・非戦
・愛国者の憂鬱
行ってよかった。
しかし、坂本さんはすごいねー。
亡くなった後もちゃんと稼いでいる。
■
新しい眼鏡を受け取った。街の眼科とは測定法が違い、私の目はかなり外斜視が強いとのこと。斜視が固定的なものでなく、常時右や左に効き目を動かしながら見ているらしい。それでも皆に見えているのと同じように、球体は球体、サイコロはサイコロに見えている。斜めに入ってきていても、まっすぐ見えていると同じように、脳内で視覚信号を読み替えていることになる。
新しい眼鏡では、そのインプットの部分をレンズで変える。すると脳のなかで新しいインプットに合わせた視覚信号組み替えとなるよう、調整作業が為されていることを実感。
とりあえず初日の感想
・足元手前が盛り上がって見えるから、いつも坂道を歩いている視覚感覚、ほんとは平らなのに、フワフワ感覚
・スマホも平らでなく、真ん中が盛り上がった感覚
・赤地に黒文字、確かに妙な立体感。SNS投稿された数人が赤地黒文字のTシャツを着ている集合写真、妙に3D写真に感じられる
・食料品店の棚、5.6段、巾80-100cm 左右に互い違いにズレ動く感覚、進行方向へ、逆向きに歩くと逆向きに。ガチャめあっち向いてホイだからかな?
・クリアにあちこち見えるので、読まなくて良いものも読む(笑) 看板とか
・スマホの文字が大きくなったように感じる(太くはっきりしているからか)
・人の表情が見える。表情に惹かれる
・スマホ、解除画面パスワードをいれる●表示が●に見えない、■や★や▲?色々な形があったのかい? 不思議なことに眼鏡をかけて一旦見えてしまうと、裸眼になったときに、もはや●表示は●に見えず、■や★や▲に見える
20240425 Thu.
婦人科で定期チェック。
12月の検査結果を教えてもらう。相変わらず、コレステロールが高め。
一般の病院なら薬を進められるだろうが、ここは様子をみましょうといってくれる。母親も同じくその傾向があるので、病的ではないと思われる。
■
新しい眼鏡で本を読んでいて随分疲れる。
せっかく作ったのだから、使って目から脳内まで視神経を再訓練しなくてはならないと思うけれど、やたら疲れて眠くなるし、目の疲れや頭痛が起きているような気がして、モチベーションが下がり気味だ。
本を読むときに、視界のなかで焦点が合っている部分とぼやける部分があり、不均一になるのがストレス。裸眼で読んでいるときは、アナログ的に調整していたものが、メガネをかけるとメガネ調整範囲とそうでないところ、という段階にデジタルに変化するからかなぁ。
眼鏡をはずすと、家の中にいるのに焦点の合い方がずれるような気がするのもストレス。
■
レヴィ・ストロースの読書会、3回目。
『100分de名著 野生の思考』をベースに行っている。今日は第2回前半。
・「具体の科学」 自分のやることをあらゆる角度から徹底的に検証・・・彼らが思考から事実に至るとき、その仕事は完全無欠である」 彼らとは農民や田舎者。 p.32
これは頭だけ、部分だけを考える現代人とは違っている点。完全無欠でないことを”想定外”と言っている時もあるかもしれない。
・レヴィ・ストロース自身とても鋭敏な感覚を持った人で、感覚というものには論理性があり、そこには知性が内在していることを深く認識していました。 p.34
・複雑きわまりない多用な植物や動物でできた生態系のすべてが人間に語り掛けをおこない(「メッセージを送ってくる」)、先住民たちは自然界から送られてくるメッセージを、コードを使って解読し、それらを分類して、知財の体系をつくっています。 pp.34-35
・「ハワイの現地人の天然資源利用はほぼ完璧で、商業時代の現代のそれにはるかに勝っていた。現在は目前の経済的利益を与えてくれるあるいくらかのものは徹底的に利用するが、それ以外のものはすべて無視し、破壊してしまうこともしばしばである」(プクイ:ハワイの伝統知識を豊富に持つ女性の本より) p.35
感覚に論理性があり、そこに知性が内在している、という記述には勇気づけられる。そこにある何かを定式化できないと、あるいは、言語で定義できないと、無いものとされることが悔しかったから。
・本質的な飛躍は、後期旧石器時代に行っていて、現代人と同じ脳の構造への進化がすでに完成している。そして新石器時代を迎えている。このとき現在の世界の土台はつくられた、ともいえる。 p.37
・(弥生時代に)農業や国家によって、本物の「野生の思考」は歪められたり、変形されましたが、新石器時的特徴を色濃く残していました。pp.37-38
日本でいえば縄文時代にほぼ脳の構造は出来上がっていて、その頃の思考は今の思考に劣ることはないし、もしかしたら具体と思考をうまく組み合わせて、とてもレベルの高い知性を発揮していたかもしれない。
少なくとも、現代の私達が考えることが、縄文人より必ず優れているとは言えない、ということだ。彼らから学ぶものがある、ということになる。
・自然音から言語音を抽出するとき、感覚の「縮減」が行われていました。縮減とは、情報のある部分を消して言って、大切な部分だけ取り出して、縮小した模型をつくることです。p.39
・子供達が好きなミニカーや軍艦模型、あるいは人形などを通じて、物事を小さくすることで知的理解の中に取り込むことの快感の本質は、このように元来知的なものです。p.40
縮減という話、ミニチュアをみたり、屋上から下の世界をみるようなジオラマはとても面白く感じる。私は確かにそこに何か快感を覚える。
反対に詳細な事実をそぎ落としたものを見ている、ということも理解できる。抽象化した思考だけで進めると、現実的な問題に足を取られることがある。私は、あるいは現代の人達は、抽象化した思考に偏っている傾向にある。
■
肉をレタスで巻いて美味しく食べた。
そういえば買い物にいったとき、中身がずっしりした良さそうなレタスが1個あったけれど、包装が開いてしまっていた。他のレタスは軽々しているので迷ったけれどこのレタスがいい、とカゴに入れた。そしたら親切にレジの人が、このレタスは包装が破れているから別なレタスに換えます、と言ってくれた。でも他のレタスは中身がスカスカなんだよな~、だから、このままがいいです、と言ってビニール袋に入れてもらった。
あまり食べていないのに体重が・・・引き続きヤバイ状態。
20240426 Fri.
朝読書会。ラスキー論文
今日は論文読みは0%で、横道にそれて100%雑談をした。
人の意識発達段階を大人についても行っていくと、より複雑な思考ができるかどうか、が主だった指標になる。そう一言でいえるほど単純ではないのだが、まぁそういうことだ。
その指標で測ると、人の意識発達段階が高い人ほど大きな組織をマネージできて、課長、部長、取締役……とより高いレベルが必要になる。そしてグローバルCEOは最も高度な意識発達段階が必要になる。
場合によっては、CEOが一番高いわけではなく、取締役会や指名委員会のようなボードメンバーに意識発達段階が最も高い人を配置してCEOと対話することで意思決定を最良のものにする工夫をしている。
しかし世界中の名だたるヘッドハンティングの会社で人材を探してもそれほどの人物は数少ないそうだ。つまりはグローバルCEOを担えるだけの意識発達段階に至っている人はいない。
そうなると、現実的には複数人がチームになって役割を果たす、という解決策が出てくる。
一方で、私が思うに、本当にグローバルである必要があるかどうか再検討して、仕訳けたらどうだろうと思う。なんでもかんでもグローバル企業である必要があるだろうか?
今、メキシコで作られたアスパラガスを食べなければならないだろうか? 否。
少なくとも生鮮食品に関しては、グローバルよりもローカルではないか。
食べ物のうち、産地が限られ世界中が求めているとか、製造方法や加工・運搬方法が安定していて、グローバルに流通させるほうによりメリットがある、世界規模で産地を集約することにメリットがあるならば、グローバル流通をすればよいが、それは加工品に限られるのではないか?
冷凍技術や冷蔵技術が高くなり、3日あればかなり多くの場所へ届けることができる。それはそれでいいことだが、そのコストをかける甲斐があるものに絞れないのだろうか。
食品以外には?
自然由来の木材などの材料?
水? 多くは地元でよくて、外来のものは自国が上限制限してもいいのでは?
■
眼鏡をつくったために脳内が疲れるということと、この数ヶ月続く頭痛のために、動きだせない時間がある。特に午前中。今日もそうだ。
出掛ける時刻頃になると、頭痛が和らいだような気がしてくる。
しかし出掛けたらまた頭痛がして、こんどは気持ち悪くなってきた。
その後、それは引いた。
なんなんだろう。
昨日、血液権者の結果で相変わらず高めのコレステロール値が出ているので、一度その検査をしてもよいのかもしれない。MRI(脳神経)と頸動脈エコーなどの動脈硬化検査。
■
気が乗らないけれど、やはり行かねばならないだろう。
東京地方裁判所にて所属するNPO団体の内部処分にまつわる裁判を傍聴。
同じ頃、安倍晋三氏の国葬に関して裁判があり、その傍聴者や関係者が多く来所していて、入場に列ができていた。ギリギリになったなぁと思いつつ、辛うじて時間内に到着。
このNPO法人メンバーは全般的にきちんとした方が多いので、服装・時間・物言いなど気を使う必要がある。普段の私ではユルユルだから。
到着したことにほっとし、見知ったお顔に挨拶していたら思いがけない人から名前を呼ばれた。「えーっ?」
思わず大きな声を上げてしまった、二人して。
もう1,2年合っていない人、連絡も取っていなかった(取れずにいた)人。
わぁ、今日ここに来ることに気が乗らなかったけれど、こんなことがあるとは来てよかったわー。
元気に会えてよかった。
裁判そのものは、毎回遅々として進むのですが今日はあまり進展がなく。そのぶん弁護士さんを交えたアフター解説の方が盛り上がった。話題になっている事案についての書面等を見せていただいて、憤るを越えて、唖然として無反応になってしまった。
なんだこれ?
あまりに低レベルなんだけど、NPO会員にはオフィシャルに出来ないと関係者の間でクローズに進めているから当事者同士で解決できなくなっている。
■
これを書いていると思う。
やはり頭痛を理由にせずに、自分なりに前向きに進まなくては。
自分なりに前向きってどういうことか?
・身の回りをスッキリさせたい。
・モノがないところで1日の仕事を始めたい。
・不要なものは捨てたいが、不要と判断できない(していない)。
・その判断をしたい 見切りというか判断軸を作って実行する
・捨てたら勿体ないとか、捨てなければ良かったと思うことが
・課題文、もっとしっかりちゃんとしたものを書けるようになりたい(なんだ?この表現?)
構成があって、読みやすくて、中身があるもの。
言いたいことが伝わるもの。
・行動したい。
・考えているだけでなく、何か行動して次につながる
・次の世界を見たい、つくりたい。
・日々感じる、もやっとした中途半端な者たちの価値は認めつつ、すっきりする部分を増やしたい。
■
<視覚体験>
・単なる四角いポスターなのに、それが、食品棚を見た時のように左右に揺れて見える。大げさにいうと海中の昆布のようだ。眼前30-40cmのところにある
・モノが以前よりも立体的に見える。するとタケノコとかセロリ、パッケージなどが以前よりも小さく見える。メガネを外すと以前と同じサイズ。
■
夜セミナー聴講。
面白かった。
成人発達理論について、今までより俯瞰的な捉え方ができるようになっている自分もいて嬉しい。2017年頃から触れだした領域だから。
私にとっては、オンラインでオランダとつないだセミナーから始まった。自由に外出することに気兼ねしているときに、オンラインでのセミナーは有難かった。
仕事するうえで、わりと冷遇されている感じを受けているけれど、何か自分なりに前へ進みたいと思っているときに、ステップを示しているように思えた領域がここだった。会社組織のなかで、優遇されたり高いポジションに就いている人の中にも成長していない人と、大人だと感じる人がいた。 何をどうしたら成長につながるのか。何がどうだったから子供のままなのか。
成長には時間がかかることや、必要に迫られて成長が起きる(起こすではない)こともわかってきた。
いまは、いままであまり重視していなかった能力領域があることを知り、その本を原著でDeepLに頼りながら読み進めている。この本もいずれ翻訳本を出すらしいと今日のセミナーで耳に入った。頑張って出版前に読み終えたい。
今回面白かったのは、加藤洋平さんが成人発達理論やインテグラル理論に出会った頃のことで、新しい話を聞いたことだ。加藤さんが新しい魅力的なテーマに惹かれて、色々勘案したうえで飛びこんでいく様が生き生き語られて、何となく魂の行程を一部見せていただいたようで、とても気持ちが満ちるような気がした。
20240427 Sat.
夢
朝方、ずーっと年始から(いや昨年から)、身の回りをスッキリさせたいのに、相変わらずゴチャゴチャしたところでパソコン使ったりしているなぁと思う。
朝一番にこう思うのは悲しい。そこまで行き詰っている。
単なる片付けなのに。
■
過去のコレステロール数値を並べてみた。
50代に入ってから、総コレステロールとLDLが恒常的に正常値を少し上回っている。40代は高いとき、問題ないときが混在。30代は1度だけ上回っているがそれ以外正常。20代は150-170台と低い。
60歳という区切りの年だ。一応動脈硬化の状況を調べて見た方がよさそう。
そして、歩くほかにも何か運動するか、食事を替えるか、やれることをやったほうが良さそう。
もしかすると、体重をあと5kgくらい減らすとコレステロール値が減るかもしれない。実験してみたいが、簡単ではないなぁ。トライしてみようかな。
■
今日は気温が20度を切っていて歩くには良い温度。
明日は午前中から20度を越え、午後は28度が見込まれている。終日歩くには暑さが辛そう。
何か対策を。
水を飲むことと、タオル・帽子、サングラス。
途中でコンビニでパピコを食べるかもしれない。体温を下げないと。
楽しみとしては、スタバで「もっとメロンフラペチーノ」をテイクアウトしよう。
その時のために、友人おススメのタピオカ用ストローをゲットしよう。
柑橘類を持って行けるといいなぁ。
■
Concerns
・課題文で書く題材・・・
昨日も考えているのだが・・・書きたいものがないのか?ん?
・歩くこと
・何にとりくんで生きていくか
・プログレッション作成
■
成人発達理論、インテグラル理論を知って、
何が自分にとって変わったか?
・大きな地図のなかで捉えることにより、自分の成長を諦めなくなった。
・自分の成長について、どこか一面にこだわり焦ることがなくなり、より広い面で捉えることが出来るようになった。
・成長のためにやっていることは?
1)自然を体験して、世界システムを自然になぞらえて考える <認知>
2)Cognitiveな認知能力を高める意図を持っている <認知>
まずどういうことがCognitiveな認知なのか認識している段階
3)自然のなかにある自分を認知するために、自然に身をおく、庭で雑草を抜く、旅先で自然と人間の営みを観て認知し言語化する スナップショットでの理解と、季節をめぐる1年単位の理解 <体感>
4)役立ちそうな読書会に参加して認知を広げようとしている <認知>
・成長にこだわらなくなった
・意識段階によって起こりそうなこと、意識段階の違いによって発生しそうな対立を理解することで、現状起きている問題への理解が深まった (解決ではない) <認知><現実対応能力>
・資本主義にどっぷり浸かっている自分を認識し、影響からすっかり逃れることはないが、どの部分はその影響から外れた動きをしたいか考えることが出来るようになった。そのことに自信を持つようになった。 <認知><現実対応能力>
■
ガイアの夜明けで、新しい原宿「ハラカド」特集を観た。
原宿の神宮前交差点には、ラフォーレ原宿があり、明治通りを挟んだ隣には東急のビルがある。その対角線上に新たな東急のビルが出来て、4月17日からオープンした。
火曜日にその前を通ったが中にはまだ入っていない。
あまり期待していないから。

でもTV番組をみて好感を持ってしまった。実際行ってみたらどうのだろう?
流行を消費するのではなく、町に根差したものを作りたいという長野出身の東急の池田さんという人がプロジェクトリーダーだという。長野びいきなのだ、私は。
そのために
・銭湯を地下に作った、壁の絵は、銭湯絵師の人が描いたもの
・銭湯のあとで、神宮で地元に根付いている紫禁飯店の料理を出すという
・誰でも入れる雑誌図書館を、光が入る階段スペースに置いた。
そのことに期待を感じている。
他はかなり流行を消費するお店なのだろうけれど。今度友人と一緒に行ってみたいと思う。(すっかりTV戦略にやられている)
それと大事なのは、今後どうなるのか、この意図が維持されるか、半年・一年で変わってしまうか、その辺も見ていきたい。
今日は早く寝よう。
多分いま、外の刺激が多くて、内側の実践が少ない。
自分が外で実践することをおっくうに感じている。でもそれはやったほうがいい。
実行することと、受け取ることの差がもともと大きいのだが、これは小さくしていく必要がある。
他者の力を使うということが、あまり出来ていない。
(他者の力をもらっていること)
読書会で本のチョイスや話す場をもらっていること
ラスキー論文理解で学びの材料や補助線をもらっていること
(出来ていないこと)
何か自分へのフィードバック
面白い
https://www.youtube.com/watch?v=JeYBK1KK4G8
20240428 Sun.
玉川上水を歩く一日
コースは、東京の西の奥地のほう、羽村(青梅より少し手前)から四ツ谷大木戸を越して半蔵門まで。43km+3kmで46km。地球が出来てから46億年とかけた46kmウォーク。
時間的には、7:00スタート、19:30ごろゴール。途中合計して1時間半くらい休憩。
玉川上水という江戸時代の土木遺構であり、かつ武蔵野とつながる自然生態が活きたエリアとして貴重。
ブラタモリ的ポイント
・全長46km、高低差93m。地形を利用して江戸まで水を流し込む仕組み
・武蔵野台地の林と繋がりを保ち、生態系とても多種豊富。
・玉川上水から久我山辺りまでは川面が見える。そこから暗渠に。
・暗渠になった後、明大前には水道管が明治大学脇で地上に設置されているところが見える
・高井戸、明大前、代田橋、笹塚(一部開渠)
・初台~新宿の文化学園前までは暗渠の上に緑道
問題
どれも簡単に正誤はつけられない。とはいえ、どうしたものだろうか。
・小平で玉川上水や近隣の林を含めて、巾36mの道路建設予定がある。小平328号線の道路計画。隣接自治体は道路建設に着手している。
これを通すと、玉川上水が分断され水がよどむ、国指定の遺構が一部とはいえ壊される。現在玉川上水を横切る道路は最大で15m、道路は橋の形をとり、下を川が通っている状態。
・小金井で、樹齢数十年と思われる古木が切られて、小金井桜という若木が植えられた。それはそれでよいかもしれないが、古い樹木が為していた生態系は変わっていく。
・渋谷区において、玉川上水を暗渠にした緑地帯(笹塚・幡谷・西原・初台・新宿)について、伐採計画が提示されていてその反対表明が掲示されていた。
一番大切にすべきは玉川上水という治水が江戸の水系を作ったことで、それは過去の遺構というだけでなく、現在もその水系は地下で生きているということではないか。これを壊すことは、土地の安全性を脅かすことになる。
そのうえで、さらに道路建設が必要なのかどうか、今一度検討していいのではないか。今回聞いたのは、50年も前の計画を実行するというのだ。そのときと状況が変わっているから、今一度ゼロベースで考えるべきては。隣接する自治体では認可され道路建設が進んでいるとはいえ、そこに合わせなくてはならないというのは、成り行き任せだということだ。何の判断もしていないことになる。
以下、当日の様子。7:00スタートから19:30ゴールまで。
玉川上水をつくった兄弟像、庄右衛門と清右衛門
玉川上水は長さ43km、勾配93m、工期8ヵ月、羽村から四ツ谷大木戸まで
ほぼ平らなのに確実に江戸へ向かって水が流れる。計画して実行したとはその計算も、地形の読みも、土木工事技術もすごい。

スタート地点120名 想像していたより大勢いてワクワクしてきた

ここが玉川上水の起点
この右側に流れている多摩川から取水(分水)しています

新緑が美しいよ〜

概ね木陰を歩いていきます

途中には流れを分水したり高さ調整をしていたのか、遺構あり。

遊歩道を通じて、一日にこれだけ沢山のタンポポの綿毛をみたことはないくらい、沢山の丸い綿毛を見た。疑いなく人生で一番沢山見た日!

小平の公園では、今回の趣旨や玉川上水の貴重な特徴について、また現在進行形の関連事案について情報シェアがありました。

全長43km続く玉川上水の自然を描いた子供達の絵。

小金井
昔の太い木が切られて、高い位置に小金井桜を植えて数年

お昼すぎから日差しが強くなり木陰が減ったとこで、コンビニから調達

木陰のありがたさよ……
日向でも木があって水があるのは随分安らぐ

笹塚あたりから暗渠になり、一旦顔を出して、再び本格的に暗渠になる。
これはどこだったか…笹塚あたり、玉川上水と水道管がクロスしている。

明大前では、玉川上水を引きこんだ水道管が見えている。

線路の上を水道管が横切り、奥の線路は現役の京王線、真ん中草が生えているのは幻の山手線線路。

渋谷区の素敵なトイレ。

玉川上水43kmのゴールは四谷大木戸。そこからプラス3kmで半蔵門。つまりは内堀に突き当たる場所。皇居へ水を引いていたんだものね。
半蔵門にゴールしたときは、すでに真っ暗。19:30。途中1時間半くらい休憩などありましたが、正味11時間、72,575万歩。

長距離を歩くって、なんか面白いことが起きる!
最後の10km近くを着かず離れず歩いた人達7-8人が一緒にゴールし、お互い「お疲れさま~、頑張りましたね、私達」を声を掛け合った。疲れを紛らわすお喋り、進む道の確認、お手洗い、コンビニなど、気遣いながら歩いた即席チーム。
80歳の女性は、よどみなく歩く。だから私達も根を上げていられない。
最初から最後まで歩く人もいるし、家の前で待っていて皆が来たから歩き出したという人もいる。この自由さがいいなぁ。
20240429 Mon.
疲れた身体をメンテナンスする日
課題提出日。
頑張って書いたし、構成を考えたが、ふだん考えているとはいえあまり言語化したことがなかったので、こなれなかった感じがする。
でも課題を最初に書いたときから変化はある。
・書きたいことを書くだけではなく、書かない部分を作ることも必要。書きたいかどうかより、構成を重視する必要がある。
・読み手にとって、すっと頭に入りやすい流れになっているかを意識する。自分の頭にとって心地よいかどうかではない。
・とはいえ、書きたいことを書かないと、何を伝えたいのかがわからない。伝えたいことを、自分にとって伝えたいトーンで書くと、だいたいにおいて薄味すぎるらしい。はっきりくっきり書く必要がある。
・伝えたいことは、その言葉を強くするだけでなく、構成をしっかりすることで伝える力が高まる。
最初なんとか書いて提出したものの、あえなく不合格になっていて、その講評に釈然としなかった日々から、少し前進した。よしよし。
■
5月に100km Walkに出る人達と、昨年10月に行った人達とで同一のLINEを使っている。そこに、昨日28日の46km Walkについて投稿した。
最近は5月に向けた話題、そのためのトレーニングがメインテーマなので、私が書くと若干先輩風を吹かせているような感じになってしまう。
私の書き方がイケナイのかな・・・
そんなもやもやがありつつ、暑い一日に歩いた経験は、彼らの5月準備に役立つだろうという思いや、長距離歩いた経験は、やはりこの人達と共有したいという気持ちがある。だからなるべくサクッと書いてみた。
半分5人くらいが好意的反応を示してくれたので、まぁいいかな。
ここからは彼らの応援モード前回で参加しよう!
20240430 Tue.
1993年のこの日、wwwが規格公開されて一般に使われるようになったと。
ほぉ、そこから30年か。
いまインターネットにつながっていることは当たり前。
インターネットがあるから出来ること、起こってしまうこと、沢山ある。
インターネットがあるから廃れたことも、沢山ある。
戦争も今の形ではなかった
遠隔地の人と知り合いになることもなかった
見聞きすることは増えた
実際に体験することは、ネットがあるから増えた面も、ネットで済ませている面もあるなぁ。
実際に体験することの価値は、30年前より感じているかもしれない。
それはネットも、自分の年齢も影響している。
■
夕方は実家へ
ふだんは私鉄とJRを乗り継ぐが、GW中の今日は人の動きが増えていそうなので、JR一本で帰ることにした。200円くらい高いのだ。
夕方2時間ほど草取りしたことはよいとして、実は私は、とてももやもやしている。
日々を楽しんでいるようで不完全燃焼っぽい。
いや、自分で燃えないように制限しているというか、制限を外しても燃えない人間なのに、燃える人間になりたいというか・・・。
とある知り合いが周囲に声をかけてシークレット研究会を立ち上げた。初回ゲスト始め、テーマや中身は私の興味関心ととても重なっている。だけど参加資格があると思われていない。実際に参加資格を満たしていない。満たしたいのに、全くそうでない。
この会には、実績ある活動をしている人が招待されていて、私と過去接点があった方も参加している。でもその方々とも私は最近関係が薄い。
それとは別に年末、声をかけてくれた人に会いにいこうとしているが、連絡してもリプライがない。会う必要がないと仕訳けられたのだろうか。これは推測・憶測だ。
そういうことが気になるなら、何か自分で行動していってはどうなんだ?!
何も果たさずに死んでいく人間だ、今のままでは。
という気持ちになる。情けないというか・・・。
このバターン、いつもある私のネガティブパターン。
だからといって反対に、人に認められればいいのか、というとそういうわけでもないわけで・・・。
ふんっ!
1cmでも進め!
メリハリがないようで、この半月も、あれこれあったのかな。
1cmでも進む気持ちは、赤ちゃんがハイハイするように、なぜかわからないけれどやりたくてやっていること。
何かにならないことを焦っているのか、何かを成さない自分を責めているのか、何かを成せと叱咤激励しているのか、だんだんわからなくなる。
最後までお読みくださりありがとうございます。5/3-8まで中途半端な状況で読んでくださった方々、申し訳ありませんでした&それにもかかわらずありがとうございます。
日々、緑は濃くなり、花は咲き、鳥はさえずり、人間社会は刻刻と進んでいきます。しばし、気持ちの良い季節を味わえますように。
課題文、合格しました。5/2, 三本目。
ここまですでに14本くらい書いていますから打率は低くて、合格といってもそれなりです。約2000字、良かったらご一読いただけると幸いです。
男性性と女性性、両方感じられる人が魅力的だなぁと常々思っていて、その感覚からこちらを書いてみました。宜しければお時間あるときに読んでいただけると励みになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
