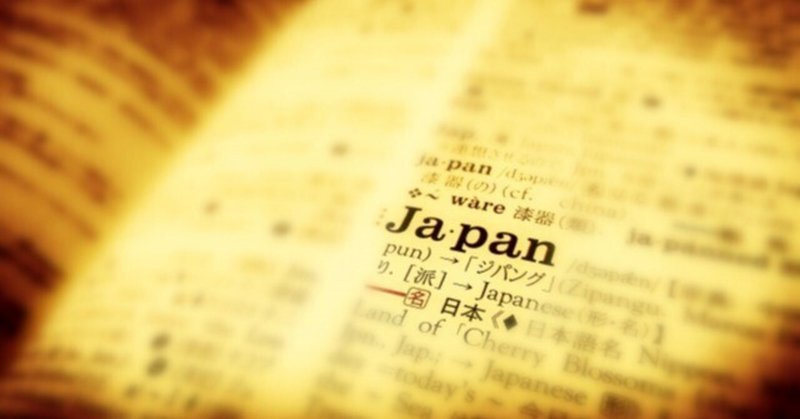
日本のEC市場はどう見られている?フランスから・世界からの視点
いくら海外住みだとはいえ、日本人の私が「海外から日本はこう見られているよ」と言っても、きっと大した影響力はないでしょう。(私がもっと有名な専門家かコラムニストにでもなっていれば、多少の影響力はあるのかしら…?)
しかし、海外の現地の人々からの言葉だったらどうでしょう?
今日は、DTCグローバルコマースのリードカンパニー、ESW(本社:アイルランド)のフランス支社副社長を務めるJérôme Duclos氏のコラムをご紹介します。
彼らが日本をセールスのターゲットとした時、日本はどう見られているのでしょうか。
DTC(D2C)とは
本題に入る前に、EC用語が1つ出てきましたので、ここで簡単に説明しますね。
DTCとは、Direct to Consumerの略で、D2Cと表記することもあります。
ブランド(生産者)が卸売業者や代理業者などを介さず、購入者(顧客)にダイレクトにコミュニケートやマーケティングをして商品を販売する方法(ビジネスモデル)です。
生産者が購入者に直接コネクトするため、購入者に添った商品の企画や開発ができます。また、事前に商品が売れる=支持されるかどうかをリサーチや検証もできるのがDTCのメリットです。
“購入者と共に商品を開発し販売する”…なんていうのも、理想的なマーケティングのひとつかと思います。
さて、それでは早速コラムを読んでいきましょう。
E コマースで最もホットなグローバル・スポット
フランスは、国境を越えたオンライン購入において世界第5位の市場に過ぎない。しかし、フランスのブランドや小売業者は、まだその可能性を最大限に引き出せていない。
メキシコ、インド、日本、韓国の4つの新興国際市場は、成長を目指すフランスのブランドや流通業者にとって、今日優先的に考慮すべき市場である。
ESWが18カ国の消費者18,000人を対象に実施した最新の「Global Voices research」の調査によると、国境を越えたオンライン購入において、フランスは中国(31%)、米国(29%)、英国(15%)、ドイツ(9%)に次いで4位から5位に順位を落としている(世界の14%から8%へ)。
また、2023年のフランス・ブランドに対する国際的な需要は、スイス(28%)、中国(22%、前年は35%)、スペイン(17%)、イタリア(12%)、インド(9%)の国境を越えたバイヤーによって牽引されたことが示されている。フランスで最も多く購入する国のトップ5では、米国(英国ブランドの17%に対し4.5%)、アラブ首長国連邦(英国ブランドの35%に対し、昨年2位の17%から2023年には10%へ減少)、韓国(9%から6%へ減少)、インド(英国ブランドの26%に対し、12%から9%へ減少)など、主要な世界市場の不在や低迷が目立つ。南アフリカでの需要も非常に低く(英国ブランドの26%に対し約5%)、オーストラリアと南米ではほとんど存在しない。
しかし、国内需要が変動・減少し、2024年には世界的な成長が鈍化し続けると予測されている今こそ、フランスのブランドや小売業者は、他の地域やさらに海外に目を向けるべき時である。国際貿易局によると、APAC(アジア太平洋地域)とLATAM(中南米)は、2023年から2027年にかけて、世界の電子商取引の平均成長率(11.16%)を上回ると予想されている。これらの地域を詳しく見てみると、Eコマース・チャネルを持つブランドにとって、成長機会として特に目立つ国がある。
ESWの最新レポート「Growing International Ecommerce Markets(成長する国際Eコマース市場)」は、Eコマースにとって現在最もダイナミックな世界市場、特にメキシコ、インド、日本、韓国を調査し、中国や米国など、フランス製品にとってより「予測可能な」国際市場との比較を行っている。これらの国々は、2023年時点ではフランスの主要な買い手市場には含まれていない、あるいはほとんど含まれていないが、長期的に市場を支配し、浸透させることは可能である。
市場の違いを十分に理解した上で、新しい市場を選ぶ
ここでは、いくつかの傾向や数字を明らかにする。例えばメキシコでは、買い物客はブランドを非常に重視するが、オンライン購入では価格と割引を好む。価格と商品の入手可能性が越境購買の主な要因である。2022年には、メキシコのオンライン買物客の80%が越境購買を行っている。FacebookとWhatsAppは人口の93%にリーチし、68%は2024年に同程度かそれ以上のオンライン消費を計画している。
日本は世界第4位のEコマース市場である。そこでの消費者は、店頭で買うよりも安いオンライン価格を求め、世界平均よりも短い配達時間を期待している。日本のEコマース市場は9年間で倍増し、消費者の61%は2024年もオンライン支出を維持すると予想している。
インドは世界最大のEコマース市場のひとつでもあり、1億2,500万人のオンライン買い物客がおり、現在から2026年の間に18.29%の成長が予測されている。買い物客の4分の1以上が年間72回以上のオンライン購入を行っている(アジア太平洋地域では中国に次ぐ)。
そして韓国では、オンライン・ショッピングが既存の最大の販売チャネルとなっている。消費者が近隣諸国や欧米諸国からより良い価格で購入すればするほど、国境を越えて購入する可能性が高くなる。購入の60%はオンラインであり、店舗での購入は40%に過ぎない。 2022年、越境ECは47億ドルに達し、買い物客の66%が2024年には同額かそれ以上のオンライン消費を計画している。
こうした市場で消費者をうまく取り込むには、ブランドは多様で、時には矛盾する消費者文化や期待の間をナビゲートしなければならない。例えば、日本では、顧客サービスは「OMOTENASHI」に基づいている。言い換えれば、細部にまで気を配り、ニーズを予測し、見返りを期待しないおもてなしをすることであり、礼儀正しさと迅速さに現れている。一方アメリカでは、カスタマーサービスはより直接的で非公式な傾向がある。アメリカのカスタマーサービスは一般的に効率と問題解決を重視し、顧客とサービス提供者の間のオープンなコミュニケーションを奨励する。アメリカの顧客が満足するのは、問題が迅速に解決され、「顧客は常に正しい」という対応を受けた場合である。
したがって、真に成功するためには、ブランドは何よりもまず、カスタマー・エクスペリエンスをローカライズし、ショッピングをより満足度の高い、安全でシンプルかつ迅速なものにするための専門知識を持つパートナーと、エンドツーエンドで協力しなければならない。これには、たとえばカスタマーサービスに現地の従業員を採用することも含まれる。ブランドはまた、現地の営業時間内にカスタマーサービスを利用できるようにする必要がある。ブランドの担当者が離れたタイムゾーンで働いているために、世界中のバイヤーが対応を待たされるようなことがあってはならない。
成長とは、それを見つけるところにある。幸いなことに、ブランドは豊富な外部データを自由に利用できるようになったため、既存の機会に取り組むことが容易になった。パートナーは、配送、返品、カスタマーサービス、需要創出はもちろん、注文、コンプライアンス、データ・セキュリティ、詐欺防止、税金、チェックアウトに関わるすべてのプロセスを管理する。
Source:Les hotspots les plus chauds du e-commerce mondial(JDN (Journal du Net))
おわりに
いかがでしたか?
フランスにとって日本は、優先的に販売のターゲットとするべき国のひとつに挙げられていましたね。そのためには、日本のOMOTENASHI文化を心得るべしと。
SUSHIやKARAOKE、MANGAのように、OMOTENASHIもまた、だいぶ世界に浸透した日本語となってきたようです。
恐るべし!滝川クリステルの影響力!(違うか笑。)
フランスが抱える問題や背景は日本ととてもよく似ていると、私はこの記事を読んで思いました。
日本にもフランスにも、今や世界中でよく知られ、好まれている食文化やブランドがたくさんあります。
しかし国内市場は飽和状態か、あるいはいまいちパッとしない。生き残るためには、ターゲットを世界に広げなければならないというところまで来ているのも、両国そっくりです。
これは私自身の大いなる偏見ですが、フランスはその国民性から、そもそもあまり他国に興味はなく、そして日本はというと、海外を相手にするのは臆病な節があります。つまるところ、フランスも日本も他国に目を向けないため、他国の知識に乏しいというイメージがあります。
このDuclos氏のコラムは、自国で売ることばかりを考えるのではなく世界に目を向けよう、他国のそれぞれの特徴を知り、あなたの製品がどの国や地域をターゲットにすれば売れるか、よく見極めようという、まるで「初めての越境EC」how to本のような内容です。数字がたくさん出てくるけれど、それほど難しいことは語っていません。
また、フランスに限らず、我々にも大いに参考になるデータだと思います。
これから新たにブランドを立ち上げよう、販売業を始めようとしている人にもぜひ読んでいただきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
