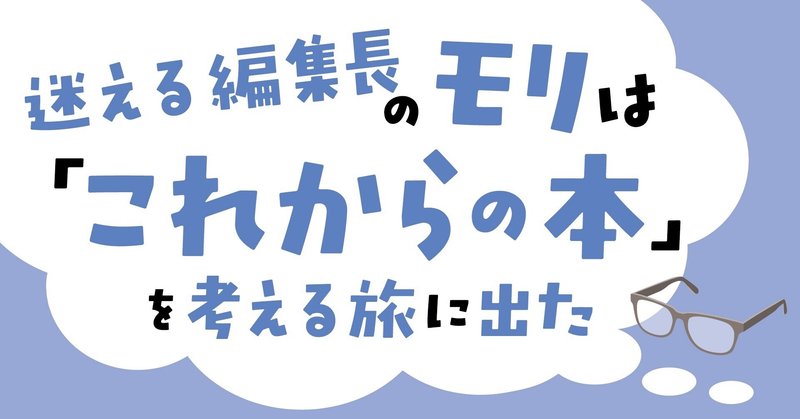
建築物より長く生き残る「本」で、「空間」を伝えるということ
★長い前置きは「第一回」記事と同じ文面です。
過去記事をお読みくださったかたは「※※」までスクロールしてください。
突然ですが、本がなかなか売れません。
正確に言うと、売れている本はたくさんあります。電子書籍の広がりによって右肩下がりだった出版市場も2019年から少し上向きになっています。
しかし、10年・20年前から比較すると市場は小さくなっていますし、本を売ってくれる本屋さんの数も、この20年で半数近くに減少しています。
なにより僕自身が一人の文芸編集者として、本を売るのが年々難しくなっているなあと痛感しています。
もちろん、いたずらに暗い話をしたいわけではありません。
作家さんと出版社でいろんな取り組みを行ってベストセラーになった本もいっぱいあります。作家さん自身が熱心に販促してくださり、本屋さんも店頭で大きな展開をしてくださり、出版社もさまざまなことに全力で取り組んでいます。
けれども、全ての本で望むような結果が出せるわけではありません。
僕が主に編集している文芸小説のジャンルではとりわけです。
商業出版である以上ビジネスで、本を作ることはビジネスと割り切ってしまえばいろんなことが楽になる部分もあります。しかしそんな簡単に割り切りたくない気持ちがどこかにあります。
その想いは自分が作る本だけでなく「本」という存在に対して抱いていることで、だからこそいろんなことを考えてしまい、苦しくなります。
おまえは何を甘いことを言ってるんだと叱られそうですが、僕はこの世のすべての本が売れて欲しいのです。
自社とか他社とかではなく、本というものがたくさん売れて、作家さんや本屋さんはじめ、本に関わる全ての人が幸せになって欲しい。そう願ってしまうのです。
それは、ばかげた願いなのでしょうか。
※
新型コロナが猛威を振るい、社会は一変しました。それは出版界も同様です。
出版社や物流のありかた。作家さんとの関係性や本の届け方。コロナ前から変わってきていたいろんなものが加速度を上げて変わろうとしています。それは悪いわけではなくて、これまで僕たちが目を背けてきたものに向き合う機会でもあると思っています。
これからの本作りやこれからの本の届け方を考えるうえで、本という存在そのものについて、ゼロベースで見つめ直さなければいけない時が来ているのではないかと感じています。
これからの未来にもっともっと本を広げていくために、本をリブートさせたい。
そのために、「本」というものをもう一度知らなければいけない。
今まで出版業界の編集者という狭い視野で本を作っていたけれど、もしかしたら本には僕が思いもしなかった可能性が隠されているかもしれないし、そもそも見えていなかったものあるかもしれない。
というか、本当に僕は本という存在を理解していたのだろうか?
もう一度まっさらな気持ちで本というものを捉えてみることで、これからの時代の「本」を再定義したい。
そのうえで、本をとりまく人たちみんなが幸せになれる世界につなげたい。
そう思って、このコーナー「迷える編集長のモリはこれからの本を考える旅に出た」を始めることにしました。
ここでは、出版業界にとどまらず、僕が話を聞きたいと思った人に話を伺い、「本」というものについて考えていこうと思います。
いわば僕の禅問答の旅であり、武者修行の旅です。
なかば私物化企画でありますが、編集長特権として多めに見ていただければ幸いです。
※※
前置きが長くなりましたが、第二回のゲストとして、草思社編集部の吉田和弘さんにお越しいただきました。
きっかけは、吉田さんがマンスリーレンタルした中銀カプセルタワービルに招いてもらったこと。
かの黒川紀章が設計し世界で初めて実用化されたカプセル型のマンションで、そのデザイン性の高さから日本を代表する建築の一つ。ビルの老朽化もあり取り壊しをめぐり議論がされるなか最後のマンスリーレンタル抽選に当たったそうで、招待してくれたのでした。

(カプセルタワービル外観。それぞれのBOXが居住区です)
実は吉田さんとは大学時代の同級生。かつて文学部として同じ釜の飯を食った仲ですが、何を思ったか卒業してから建築学部に入り直し、大学院まで出たあとに何を思ったか出版社に就職して、現在は同じく編集者をやっています。
ちなみにこの中銀カプセルタワービルにまつわる本『中銀カプセルスタイル』を編集したりもしています。

まるで宇宙船のようなカプセルタワーの部屋を眺めながら、ふと思いました。
建築の道を志し、その業界で働くこともできたはずなのに、どうして回り道をして「本」にまつわる仕事に関わろうと思ったのか――。
もしかしたら、そこに僕の見えていない本の姿があるのではないだろうか。
そんな疑問が頭に浮かび、お話を伺ってみることにしたのでした。
(聞き手:ポプラ社一般書通信 編集長 森潤也)
※せっかくなのでカプセルタワーの部屋で取材をしています。貴重な写真とともにどうぞ。
吉田和弘さんプロフィール
草思社編集部所属。文学部を卒業後建築学科に編入し、建築系出版社を経て現職。建築を中心に、広くノンフィクション書籍を担当する。
▼noteの「草思社@中銀カプセル出張所」にて、中銀カプセルタワービルの暮らしの模様を公開中。
文字よりも形のほうが理解できるかもしれないと思った
森 そういえばちゃんと話を聞いたことなかったけど、なんで文学部から建築学部に入り直そうと思ったの?
吉田 文学部三年生くらいのときにオムニバスで建築の授業を受けたんだよ。世界各地の建築のスライドを見ながら「建築とはコンセプトを形にして表すんだ」という話を聞いて、文字よりも形のほうが理解できるかもしれないとビビっときたのがきっかけだね。
森 たしか、いっしょに卒業はしたよね。
吉田 そう。文学部を卒業したんだけど、二年次編入という形で建築学部に入り直した。そこからは図面を引いたり模型を作ったり設計もしたり、ちゃんと建築の勉強をしたよ。その上でもう少し勉強したくて、大学院で建築史の研究室に行くことにしたわけです。
森 建築史の研究室では、どんなことをするの?
吉田 自分がいた研究室では西洋と日本の近代建築史を中心に学びつつ、海外の建築理論書を翻訳するゼミや、図面をアーカイブする作業なんかもしてたね。
歴史に関わるから、古文を使って大工の古文書を読んだり、西洋の技術書を翻訳した漢文を読んだりすることもあって、国語の勉強しといてよかったと思ったよね(笑)
森 古文や漢文の知識がそんなところで役に立つとは! というか、建築にまつわる古文漢文レベルの文献って、日本に残ってるんだね。
吉田 いろんな用途があって大工の文献が残っていたりするんだけど、ある時代から技術を普及させるためにけっこう複製があるんだよ。部数が作られてるから、現代にも残っているんだよね。
森 何年くらいの文献なの?
吉田 まとまったものができたのが、ざっくり1600年くらいかな。
森 具体的にはどんな内容の文献なの?
吉田 当時の大工棟梁たちが書き残した建築物を設計するための技術書で、「四天王寺流」「建仁寺派」などの流派の名前がついた建築方法が書き記されていて面白いよ。かつては一家相伝の建築方法を自分の家に伝えるという目的で文献が残されていたのが、だんだん普及版みたいな感じになっていく流れも見えてきたりね。そんな文献をわからないなりに解読して読んでたかなあ。

「紙で残す」ということを物量でわからされた
森 研究室で「図面のアーカイブをしていた」という話があったけど、それはどういうことなの?
吉田 日本の建築って人気があって、浮世絵みたいに海外の美術館とかが図面を買い攫ったりしてるんだよね。それを防ぐために国立近現代建築資料館というものが新しくできて、そこと大学の協力という形で有名な建築家の図面をプロファイリングして残そうというプロジェクトをやっていたんだよ。日本の近現代の建築家は黒川紀章さんみたいに海外にも名前が知れ渡っているがゆえに、図面が日本から消えている現状もあって、それをなんとかするためにスキャン化してデータとリアルな図面の両方を残そうと。図面自体のコンディション管理は資料館がやるんだけど、大学でリストを照合して納品するみたいな作業をしてたね。
森 へえ~。アーカイブしていく図面で一番古いものは何年くらいのものなの?
吉田 そのときやってたのは近現代だから1900年代だね。図面という概念自体が、文明開化で西洋建築を取り入れるために招いたお雇い外国人の建築家から来ているので、それより古い図面はちょっと概念が異なる所もある。
そうしたアーカイブ作業をしている時に、「紙で残す」ということを物量でわからされたというか、メディアとしての紙の強さを物量として味あわされたというか。紙で残すというのは本だけじゃなく図面においても重要だということはその時強く感じたことだね。

建築物よりも本のほうが長く生き残る
森 そういったことを大学院まで学んで就職するとなったときに、建築関係の業界に行くこともありえたと思うんだけど、出版社に入社するわけだよね。文学部に戻ってきちゃった感じがするけど、なんで出版業界に行こうと思ったの?
吉田 学んでいた研究室がわりと出版に近くて、先生が文献を読んだり書いたりする編集者みたいな人だったんだよね。その先生が編集という世界を見せてくれた気がするかな。
その先生の元で学んだことで文学部の時以上に「本」が分かったところもあって、古文書みたいな本が物として残ってることがすごいと思ったし、メディアとしての本のすごさを感じた。建築業界も就活で受けていたし受かったところもあったんだけど、そうした想いもあって、出版社を選んだというわけです。
森 なるほど、そういう経緯だったのか。
そうして建築系の出版社に入って建築関係の雑誌編集に携わってから草思社に転職したと。編集している本は『中銀カプセルスタイル』や京都大学の吉田寮を取り扱った『京大吉田寮』など、一貫して建築にまつわる本づくりをしていることが多いよね。
吉田 そうだね。建築空間が好きだし、三次元の建築空間を解体してどうやって二次元の媒体で伝えるか、ということを考えるのが好きなんだろうね。
森 三次元を二次元に落とし込むという発想は、小説編集をしていると考えたこともなかったなあ。
吉田 現代建築は長くても100年持たないと言われているから、実は本のほうが長く生き残る。物づくりとしては建築のほうがスケールは圧倒的に大きいしハイテクなんだけど、それに比べるとスケールが小さい本のほうが長く生きるというのは、こうした本を作っていて面白いなあとすごく思うね。
森 紙の本ってすごく長く残るというのは、意外と知られてないところでもあるよね
吉田 そうなんだよね。だから実は「本」にすることのほうが、建築の存在を長く後世に伝えるために重要なのではないかということでこうした本を作っている所はあるね。
森 そういったアーカイブ性や情報を伝えるという意図ならば、たとえば動画なんかのほうが情報密度が高いし、「空間」というものを伝えやすいと思うんだけど、「本」として残す意義ってなんだろうね。別に電子で残してもいいし、紙の本で残す理由ってなんなのかなと。
吉田 たとえば建築の場合は写真と紙の本の親和性が高くて、写真としてとらえられた建築の空間は、空間そのものじゃないけど「ある種の何か」を如実に伝えている気がするんだよね。たとえば、ガラスのヌメッとした質感とか、光の絶妙なまわり方とかかな。あと、図面には縮尺というのがあって、設計者はその特定のスケールに慣れているから、デジタルで自由に拡大縮小できるとかえって把握しにくくなることもあるよ。デジタル写真のほうが情報伝達では強いと思うけど、空間の伝え方という意味では紙焼きはある側面ではよくとらえて残せるんじゃないかなと思う
あと、面白い建築ほどコンセプトがよく考えられているから言語化しやすいところがあって、建築の概念みたいなものを言葉にするというところで文字を使うメディアである「本」という媒体はいいのかなと。もちろんそれはウェブで伝えられる部分もあるので、悩ましいい所ではあるけれども。

アーカイブ性のある本は商業出版であるべきなのか
森 話を聞いていると「アーカイブ」としての「本」の意味をすごく感じていて、そうしたアーカイブ性のあるものって、本の存在意義の一つとしてよく理解ができるんですよ。ただ、一方で我々は商業だから、そこに「儲ける」という概念が発生するわけじゃないですか。その場合に考えなければいけない要素が発生してくる。アーカイブしたいだけであれば、極端に言えば同人誌でもその目的を果たすことはできるし、そのほうがピュアなアーカイブができるかもしれない。商業になると赤字にはできないとかいろんな要素が入るので、そこのピュアさが濁ってこざるを得ないところがある。両方の良さもわかるがゆえに、それってどうしたらいいんだろう、とずっと考えているんですよ。
吉田 そこは難しい問題なんだよなー(笑)
森 商業でやる以上、関わってくれた人に還元するという意味でも世に知らしめる意味でも売れてほしいんだけど、商業主義を考えすぎるとピュアネスが濁ったり中途半端なものになってしまう懸念を常に持っていてね。
吉田 俺が作った『京大吉田寮』と『中銀カプセルスタイル』の本で共通しているのは、ある種の運動にしようという意図もあって、クラウドファンディングをやったり書店さんで展示会をやったり、と本づくりと周知を同時に展開させる作り方をしていた。
それは商業でなくてもできるんだけど、企業というフィルターを通すことで大規模にできたところはあるかなあ。あと、多くの人に届けるためには印刷や校正校閲など本自体のクオリティを高める必要があって、同人でできるクオリティの限界もどこかにあるのも事実ではあるね。
森 そうだね。商業だからこそやれることや広げられる部分は、たしかにあるね。
吉田 あと、単なるアーカイブでなく「コンセプトがたっている」というのは商業のポイントかもなと思う。中銀カプセルタワーをテーマにした本で、「建築」という切り口の本はけっこうあるんだけど、「中に住んでる人が面白い」という視点が今回作った本なんだよね。このカプセルの部屋にどんな人が住んでいて、どういった空間にして使っているのかという部分にフォーカスして写真と言葉を組み合わせてまとめているけど、自分でも面白く出来たんじゃないかなと思っている。そして市場の淘汰圧があるからこそ、それに耐えうるコンセプトを作って押し出していく必要があると思う。そういう意味でも編集者というフィルターが介在するのは商業出版の意義だと思いたいね。
森 その「コンセプト」は「企画」とも置き換えられると思うんだけど、大切にしている部分はある?
吉田 草思社の企画会議は営業部と編集部が参加するんだけど、基本的に民主的に決まるから社長の企画が落ちることもある。その時の判断基準の一つとして「すでにある本の二番煎じみたいな本は作るな」と言われているね。二匹目のどじょうを狙うより、今までになかった本を狙って出していこうと。「こういう切り口があったんだ」とか「こういうテーマがあったのか」といった新しさを企画として重視されていて、それは自分自身でも大事にしている部分ではあるね。
森 マーケティング的に考えると、売れる市場があるところを狙うというのは売りやすさや営業的に固い部分もあるわけだよね。一方で新しい切り口はリスクも大きくなる。確実に売れることよりも出版社として新しい価値観を社会に提供することを大切にしているわけだね。
吉田 そうだね。やはり出版社として本を出す意義はそこだと言われているね。
森 その意義は編集者である以上、大切にし続けたいね。本とはなにかずっと迷い悩んでいるんだけど、また一つヒントが貰えた気がします。
お互い頑張っていきましょう。今日はありがとう!

(風情のある、夜のカプセルタワービル)
▼noteに加えてtwitterでも情報発信中。カプセル暮らしの模様をお楽しみください。
▼本のアプリ「taknal」編集部に取材した過去記事はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
