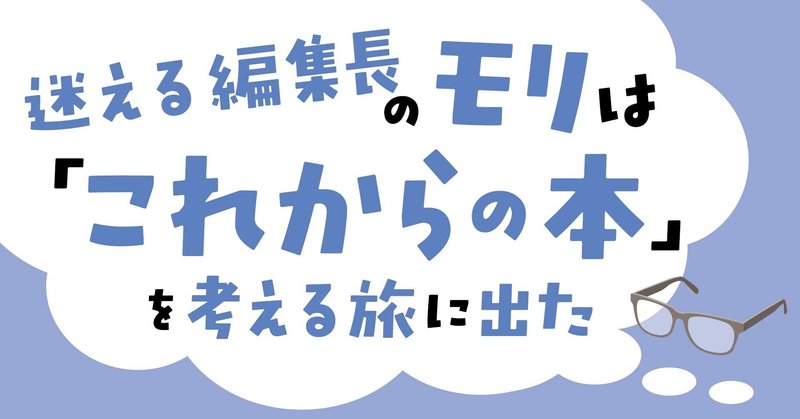
芸術って分からなくてもいい――Bunkamura広報・古門さん、亀澤さんインタビュー
★長い前置きは過去記事と同じ文面です。
過去記事をお読みくださったかたは「※※」までスクロールしてください。
突然ですが、本がなかなか売れません。
正確に言うと、売れている本はたくさんあります。電子書籍の広がりによって右肩下がりだった出版市場も2019年から少し上向きになっています。
しかし、10年・20年前から比較すると市場は小さくなっていますし、本を売ってくれる本屋さんの数も、この20年で半数近くに減少しています。
なにより僕自身が一人の文芸編集者として、本を売るのが年々難しくなっているなあと痛感しています。
もちろん、いたずらに暗い話をしたいわけではありません。
作家さんと出版社でいろんな取り組みを行ってベストセラーになった本もいっぱいあります。作家さん自身が熱心に販促してくださり、本屋さんも店頭で大きな展開をしてくださり、出版社もさまざまなことに全力で取り組んでいます。
けれども、全ての本で望むような結果が出せるわけではありません。
僕が主に編集している文芸小説のジャンルではとりわけです。
商業出版である以上ビジネスで、本を作ることはビジネスと割り切ってしまえばいろんなことが楽になる部分もあります。しかしそんな簡単に割り切りたくない気持ちがどこかにあります。
その想いは自分が作る本だけでなく「本」という存在に対して抱いていることで、だからこそいろんなことを考えてしまい、苦しくなります。
おまえは何を甘いことを言ってるんだと叱られそうですが、僕はこの世のすべての本が売れて欲しいのです。
自社とか他社とかではなく、本というものがたくさん売れて、作家さんや本屋さんはじめ、本に関わる全ての人が幸せになって欲しい。そう願ってしまうのです。
それは、ばかげた願いなのでしょうか。
※
新型コロナが猛威を振るい、社会は一変しました。それは出版界も同様です。
出版社や物流のありかた。作家さんとの関係性や本の届け方。コロナ前から変わってきていたいろんなものが加速度を上げて変わろうとしています。それは悪いわけではなくて、これまで僕たちが目を背けてきたものに向き合う機会でもあると思っています。
これからの本作りやこれからの本の届け方を考えるうえで、本という存在そのものについて、ゼロベースで見つめ直さなければいけない時が来ているのではないかと感じています。
これからの未来にもっともっと本を広げていくために、本をリブートさせたい。
そのために、「本」というものをもう一度知らなければいけない。
今まで出版業界の編集者という狭い視野で本を作っていたけれど、もしかしたら本には僕が思いもしなかった可能性が隠されているかもしれないし、そもそも見えていなかったものあるかもしれない。
というか、本当に僕は本という存在を理解していたのだろうか?
もう一度まっさらな気持ちで本というものを捉えてみることで、これからの時代の「本」を再定義したい。
そのうえで、本をとりまく人たちみんなが幸せになれる世界につなげたい。
そう思って、このコーナー「迷える編集長のモリはこれからの本を考える旅に出た」を始めることにしました。
ここでは、出版業界にとどまらず、僕が話を聞きたいと思った人に話を伺い、「本」というものについて考えていこうと思います。
いわば僕の禅問答の旅であり、武者修行の旅です。
なかば私物化企画でありますが、編集長特権として多めに見ていただければ幸いです。
※※
前置きが長くなりましたが、第四回のゲストとして、Bunkamura広報の古門さんと亀澤さんにお越しいただきました。
東京近郊にお住まいの方はおなじみかもしれませんが、Bunkamuraさんは渋谷にある複合文化施設です。クラシックコンサートやバレエなどが楽しめる「オーチャードホール」、演劇を楽しめる「シアターコクーン」、名作映画を上映するミニシアターの「ル・シネマ」、アートを楽しめる美術館の「ザ・ミュージアム」……。渋谷という一つの街で、多様な芸術を選び味わうことができます。
そんなBunkamuraさんですが、文化施設の運営のほかに、「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」という文学賞を主催されています。選考委員はただひとり。毎年交代するひとりが 決める文学賞という、少しユニークな賞です。
文学賞の運営を行われているということは、多様な芸術を扱うBunkamuraさんが、「文学」を「芸術」の一つとして捉えているということでもあります。
「文学」という言葉は広く、エンタメ的な文学作品もありますし、芸術的な文学作品もありますが、中でも芸術によればよるほど、その魅力を言語化しにくくなるように思います。そう、「芸術」とは、言葉にしにくいものなのです。
説明が難しい「芸術」の魅力とは、どういうところにあるのでしょうか。というか、人にとって「芸術」は必要なのでしょうか。なぜ必要なのでしょうか。
もしその理由が分かれば、「芸術」の一つでもある「文学」が人にとって必要な理由にも繋がるのではないでしょうか。
そんなことをお二人にお伺いしてみることにしました。
(聞き手:ポプラ社一般書通信 編集長 森潤也)
古門さん・亀澤さんプロフィール
株式会社東急文化村 広報室で勤務。Bunkamuraドゥマゴ文学賞の運営も行い、受賞作の発表の他、文学をより親しんでいただくことを目的に、WEB連載やイベント「ドゥマゴサロン 文学カフェ」の開催、小冊子「ドゥマゴパリ リテレール」の発行、また「PASSAGE by ALL REVIEWS」内での棚主として書店なども展開しています。
Bunkamura全体の発信をとりまとめる仕事
森:お二人はどういう経緯でBunkamura(以下敬称略)に入社されたんですか?
亀澤:大学が芸術学部で、芸術を学ぶ中で社会に文化芸術を届ける仕事をしたいと考えるようになり、いろんなジャンルの芸術が扱えるBunkamuraに魅力を感じて、新卒で入社しました。
森:古門さんはいかがですか?
古門:私はバイトから入ったんです。もともとBunkamuraは好きな施設でしたが、たまたまバイトの募集を見つけて、応募したらご縁があって今に至ります。
森:古門さんも芸術がお好きだったんですか?
古門:何かやっていたわけではないですが、芸術全般を観るのは好きでしたね。
森:お二人は「広報」として働かれていますが、具体的にどのようなお仕事なんですか?
亀澤:公演・企画のPRなどは各担当者がやりますが、全施設の動きを見ながらBunkamuraの楽しみ方を提案するのが広報の仕事ですね。
古門:Bunkamura全体の発信を広報がとりまとめているので、HPなど広報媒体を管理してシーズンイベントの見せ方を調整したりしています。
森:あとでお伺いするBunkamuraドゥマゴ文学賞の事務局の仕事も広報の仕事ですか?
亀澤:そうですね。広報の仕事の中に文学賞の運営も含まれています。
渋谷全体の開発構想の中の「本格志向の文化」を担う場所
森:まず、Bunkamuraという施設についてお伺いしたいです。
亀澤:大きく言うと、1989年にできた日本初の大型複合文化施設ですね。
★Bunkamuraとは
Bunkamuraは1989年に誕生した日本初の大型の複合文化施設です。コンサートホール(音楽)、劇場(演劇)、美術館(美術)、映画館(映像)の各施設をはじめ、カフェやアート関連ショップなどからなるクリエイティブな空間は、オープン以来、新しい文化の発信基地として常に注目を集めています。さまざまな文化・芸術に触れることができるだけでなく、ゆっくりとした時間を過せる、渋谷の人気スポットとして、年間300万人もの方が訪れています。

<オーチャードホール>
古門:ざっと成り立ちをお話しすると、1970年代に当時の東急グループの総帥・五島昇さんが、これからの時代は物ではなく心の部分を大事にすべきだから、21世紀に向けて本格的な音楽や演劇が楽しめる劇場やホールをつくろうと考えられたそうです。また、東急グループとして3C戦略(カルチャー、クレジットカード、ケーブルテレビ)を今後のグループの柱にしようという構想も当時あり、それらを踏まえて東急百貨店が中心となってまとめたのが渋谷の再開発計画である「渋谷計画1985」というものです。その計画の中で「カルチャー」の役割を担う立ち位置として、Bunkamuraの建設がスタートしました。だから渋谷全体の開発構想の中の「本格志向の文化」を担う場所として生まれたんですね。
森:そういえば渋谷の文化といえば、むかし東急文化会館ってありましたよね?
古門:あれも東急の施設ですね。1956年に建てられて2003年に閉館しましたが、その跡地に建ったのが渋谷ヒカリエです。プラネタリウムや映画館もあった複合文化施設で、ある意味でBunkamuraの前身とも言えるかもしれません。
森:なるほど、そうだったんですね。まさに渋谷の街と文化の発展は東急さんなくしては語れないですね……。
Bunkamuraには映画館や美術館などいろんな文化施設がありますが、それらはどのように決まったんですか?
古門:それもいろいろな経緯があったようですが、文化の基本とはアルタミラの壁画に書いてある「描く、歌う、踊る」の三つに集約されるのではないかということで、『美術、音楽、舞踏(演劇)』という要素が出てきました。Bunkamuraはこれらを踏まえた施設ではないといけないということで主要な柱が決まり、東急沿線で生活する人々の多様性を考えるとクラシック音楽専門のホールを作るのではなく、ジャズやポップスなどバラエティを生かしたホールがいいのではないか……などということを話し合って決まっていったそうです。

<ザ・ミュージアム。「神聖ローマ帝国皇帝 ルドルフ2世の驚異の世界展」会場風景(2018年)>
「ドゥマゴ」という場と「ドゥマゴ賞」という文学賞の両方のカルチャーを日本につないでいきたい
森:いよいよ本題に入りますが、Bunkamuraは様々な文化施設を運営しつつ、「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」という文学賞を主催されています。文学賞は出版社が主催しているものが多いですが、Bunkamuraという一般企業がなぜ文学賞を主催していらっしゃるんですか?
★「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」とは
パリのドゥマゴ賞のユニークな精神を受け継ぎ、Bunkamura創立1周年の1990年9月3日に創設した「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」。受賞作は、毎年かわる「ひとりの選考委員」によって選ばれます。
古門:「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」は、パリの「ドゥマゴ」という老舗カフェから生まれた「ドゥマゴ賞」を踏襲した文学賞ですが、Bunkamuraの地下にあるカフェは、その「ドゥマゴ」の世界唯一の業務提携店なんです。パリのカフェ文化を築いてきた「ドゥマゴ」という場と「ドゥマゴ賞」という文学賞の両方のカルチャーを日本につないでいきたいという意図で始めたところがあります。

<ドゥマゴ パリの外観>
森:なんと、そうだったんですね! 本家の「ドゥマゴ賞」ってどういう賞なんですか?
古門:もともと「ドゥマゴ」はヘミングウェイやサルトルらが愛した有名なカフェなんですが、1933年に「ドゥマゴ」で集まっていたバタイユやレリスなどの文学者やジャーナリスト13人が、ゴンクール賞の受賞日に権威主義に反対して立ち上げたのが「ドゥマゴ賞」です。
★「ドゥマゴ賞」とは
「ドゥマゴ賞」は、1933年、アンドレ・マルローの『人間の条件』にゴンクール賞が授与された日に、パリの老舗カフェ「ドゥマゴ」の常連客だった作家、画家、ジャーナリスト13人によって、自分たちの手で独創的な若い作家に文学賞を贈ろうと創設されました。いかなる派閥からも独立していた彼らは、各々100フランずつを出しあって賞金を1300フランとし、アヴァンギャルドな精神にみちた将来性豊かな受賞者を選びました。第1 回の受賞者は、処女作『はまむぎ』を出版したばかりの当時30歳の新進作家レーモン・クノー。彼はのちにフランス文壇の最も先鋭的な作家のひとりとして活躍しています。第2回以降の賞金はその精神に共鳴したカフェ「ドゥマゴ」の店主が引き受け、毎年1月の第4週、店内で最終選考及び受賞者の発表が行なわれています。現在の賞金は7750ユーロ。
創設時の主な選考委員は、ジョルジュ・バタイユ、マルティーヌ、ミシェル・レリス、ロジェ・ヴィトラックなど。
森:そんな始まり方をしたんですか!?
古門:始まりは本当にそうなんです。だからもともと「ドゥマゴ賞」というのは、権威におもねらない作品を選び出していく賞なんです。
森:面白いですねー。では日本の「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」のあり方としても、権威性より市井に通じるものを選ぶ賞なんですか?
古門:そうですね、現代に通じる先進性のある作品を選出したいと考えています。
森:たとえば「Bunkamura文学賞」のような企業独自の文学賞を立ち上げる可能性もおありだったのかな、と思っていたんですが、あのカフェの場も含めての「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」なんですね。すごく腑に落ちました。
古門:パリの「ドゥマゴ」で新しい文化が生み出されたように、「ドゥマゴパリ」で出会う人々から生まれる文化がBunkamuraにも根づいて欲しいという想いもありますね。
森:選考委員がおひとりで、かつ毎年変わるのもユニークですが、どのように選考委員の方を選ばれているんですか?
亀澤:特定のジャンルに絞られず「日本語で書かれた文学作品」というのが唯一の条件なので、文学作品を多様な視点で見られる方かどうかという点は注視しています。
森:一般的な文学賞だと候補作が提示されて、選考会が開催されますが、そうしたものはないんですか?
古門:我々から候補作をお出しすることは基本的にはなく、選考会というか意思確認会みたいなものは行なっています。選考委員の意思や志向を伺いながら、最終的に受賞作を選んでいただきます。
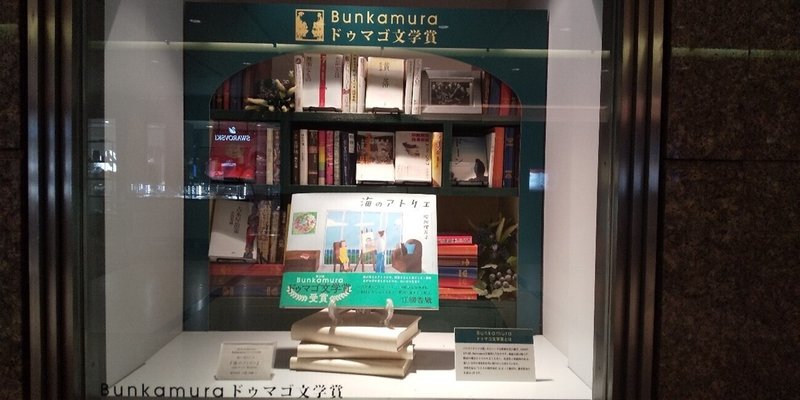
<第31回(2021年度)の受賞作>
すべての芸術の軸に「文学」があると思うようになった
森:Bunkamuraのいろんな事業はチケット代などの収益が発生しますよね。でも文学賞事業に関しては収益が発生しません。そのうえで、企業としてはどのように運営の意義をお考えなんですか?
古門:ブランディングの意味がありますし、Bunkamuraの「芸術」の複合の一つとして、「文学」が重要だと考えている部分もあります。また、Bunkamura自体に「発表・創造・出会い」という3つのコンセプトがありますが、「文学」においてそのコンセプトを体現するのがこの文学賞だと考えています。
森:ちなみに個人のご意見で結構なんですが、「文学」って必要だと思いますか?
亀澤:文学賞に関わってから、すべての芸術の軸に「文学」があると思うようになりました。演劇も戯曲がなければ始まらないですし、音楽だって元になっている題材が文学作品ということもあります。複合することが芸術を深くしていくことで、その中で「文学」のウエイトは大きいのかなと思います。
古門:「文学」があったほうが人生が豊かになると思いますね。文化芸術全般に言えることですけど、コロナで不要不急なものはやめなさいと言われて、たしかに急ぐものではないかもしれないけど、不要なものではないんじゃないかなと感じました。体の栄養のために食べ物を食べたりビタミンを取ったりするのと同じように、心の栄養のためには文化芸術があったほうがより豊かな生活を暮らせるようになるし、いろんな学びもあると思います。
芸術って分かる必要がないものもある
森:「文学」と一口で言っても、カバーする範囲はとても広くて、芸術に寄っている「文学」とエンタメに寄っている「文学」がありますよね。エンタメ的なものは「面白い」とか「感動する」とか魅力が言語化しやすいですが、芸術的な文学の魅力って言語化しづらいところがあります。文学に限らず、芸術性に比例して魅力が言語化がしづらくなる気がしていて、広く芸術に関わられているお二人に、「芸術」が持つ魅力をお聞きしたいです。
亀澤:エンタメだと答えが見えていたり提示されていることが多いですが、芸術はそれ自体についての説明は提示されていても、受け取り方が強制されているわけではないので、じっくり咀嚼して考えることができる余韻があるのが良さなのかなあと思います。
古門:芸術を受け取ると「なんなんだろうこれは」と心が揺さぶられることが多くて、それによって自分自身に気づきが生まれるところがありますね。
森:お二人がおっしゃる通り、芸術って一度咀嚼することで気づきがあるものですよね。逆に言うと絶対的な答えがないから、分かりにくいものであります。編集者をやっていると、分かりやすさや答えをすぐに求める世の傾向を感じていて、一瞬でどういう本か分からないとなかなか読者に手に取ってもらえない。芸術の場でも分かりにくいものが届きにくい傾向があったりしますか?
亀澤:そうですね。たとえば音楽の公演だと、具体的な曲目が出ていなかったり解像度が低い状態だと反応が薄いですが、曲名やいいコピーが出てきてイメージしやすくなると、興味を持つ人が増えるように思います。
古門:いまタイパ(タイムパフォーマンス)って言いますよね。コスパやタイパ的なものを求めるから、みんなが良いと言っている分かりやすいものがすごく売れるじゃないですか。その一方で、うちの子供を見ていると、分からないことがカッコ悪いと考えているのが見え隠れする時があるんですよ。でも、「分からないことこそ知りたい」とか、「分からないものを見ている自分がカッコいい」みたいな感覚は大事なんじゃないかなと思うんです。
森:僕も大学生の時に、まったく分かっていないけど大江健三郎を読んでいる自分がカッコいいと思ってましたね(笑)
古門:あと、間違えちゃいけないという強迫観念もありますよね。私はこう思ったけど、みんなと違うから言うのをやめておこうという感覚。
亀澤:それはありますね。
森:すごくよく分かります。
古門:本当は分からないことを言い合ってこそ生まれる何かがあるはずなんですけどね。
森:そう思うと、芸術が提示してくれる「分からないもの」って大切ですね。僕もいろんな展覧会に行くと、正直だいたいのアート作品がよく分からないんですが、こんな時代だからこそ、「分からなかった!」と言える機会があることは大事なのかもしれません。
古門:芸術って分かる必要がないものもあるじゃないですか。それはそれで一つの大切な経験だと思えると、みんなが楽になれる気がします。
森:「芸術って分からなくていい」って、すごく良い言葉ですね。たぶん「文学」も同様で、エンタメ的に面白い本もあるべきだし、分からないものを提示する本もあるべきだなあとあらためて思いました。
「芸術」はなぜ必要か
森:今回、「芸術」という視点からいろいろお話を伺いましたが、「芸術」はなぜ必要だと思われますか?
亀澤:私にとっては自分を客観視したり考えたり想いを整理するのに必要だなと思います。そういう機会がないと、自分の好きな世界だけ作って生きていってしまうタイプなので、知らない世界を知るきっかけになるのが芸術かなと思います。
森:古門さんはいかがですか?
古門:芸術がないと、寂しいじゃないですか。それを通じてほかの人の考えを知ることで、もっと人に優しくなれるんじゃないかと思います。ほかの人を知らないから排除したくなるので、芸術文化を通じて他者への感情や想像力が養われるから必要なんだろうと思います。
森:本当にそう思います。本日はありがとうございました。
・・・・・・・・
★Bunkamura×冬森灯 WEB小説『うつくしき一皿』連載中!
キッチンカーとサーカステントの移動式ビストロつくし。ギャルソンと本格的な腕前のシェフが客を迎える、少し不思議で、あたたかい空間です。それぞれの人生を送る客たちは、気持ちのやり場を失い、迷い憂う時、ビストロつくしにたどり着き、ここでなにかに出逢い、変化していきます。
ビストロつくしで味わう、世界で一番おいしい料理とは…?
芸術と食の詰まった心温まる物語。WEB上で読むことができますので、ぜひお楽しみください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
