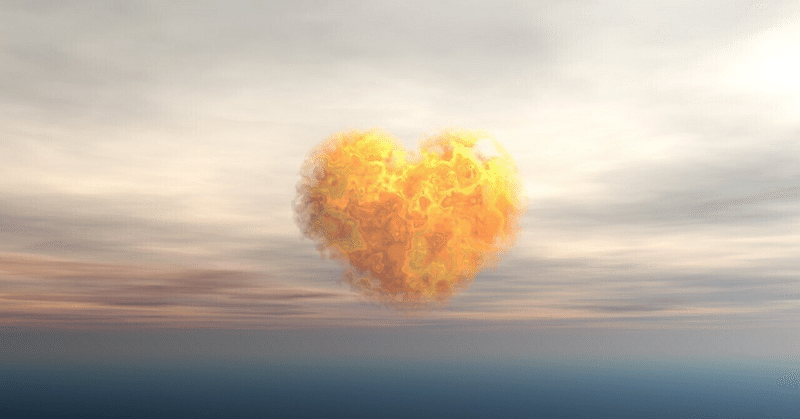
わなわな感から学ぶ。
先日久々に、他人に対し強い怒りを感じた出来事があった。
東洋医学では「五情」と言って、感情と臓器との関連性も診たりするのだけれど、特定の感情を悪いとか良いとか分類することはなくて、それぞれのバランスや与えあう影響を診たりする。どの感情がどの臓器、とシンプルに分類するのは簡単だが、ではどうバランスをとるのか、となってくると、ああ、どう生きたら良いのだろう、難しいものだな、と唸ってしまう。
最近、痛みと心の関係について少し勉強をしていたのだが、怒りという感情は痛みに対して大きな影響を持っているようだ。少しわかった気になっていたら、その事件は勃発した。
詳細は書かないけれど、家族以外には大して気持ちが動かないと思っていたわたしが久々に激怒を感じた。
感じた、と敢えて表現したのは、激怒した、というよりも、どれだけ瞬時に怒りを抑え込み表面に出さないでやり過ごすことにエネルギーを使っているかを、怒りの大きさが大きすぎたことで実感した。
あ、これね、この押さえ込む力、やり過ごそうとするコレが、余計にストレスを作り、痛み、病気につながるのね、と考えながらも、長年そうして生きてきた自分はここでじゃあ発散!と相手に健全なカタチで怒りを表現する術を知らないんだ。更に言うと、怒りを表現した後の自分を許せるかという自信も、怒りを受け取った相手がそれを単に一時的な一感情として受け止めて人間関係に影響のないものとして流してくれるという、相手への安心感や信頼感なんてものもないんだ。
だから、怒りを出すことを自分に許すことなんてできるはずもない。
だけどそのままでいるのは苦しすぎて、夜も更け始めていたがわたしは家を出て、しばらく頭を冷やすことにした。わたしが姿を消したことで、なんらかの嫌な思いはさせたかもしれない。もしかしたら逃げたことは卑怯だったのかもしれない。でも、今のわたしのキャパでは、そうするしかなかった。
運転をしながら身体の部分部分で、熱のあり方が違うのを感じていた。冷えたところと熱しているところが分離してる感じ。これも怒りが起こす熱なんだ、と半ば冷静に身体への影響を観察する。
車の中は寒かった。
暗くて、やりどころのない怒りを貧乏ゆすりに変えながら、ボリボリと細長いおかきを8つも食べてしまった。
こういうことがよくある。そのトピックを深めたいと勉強し始めると、現実的にそのトピックに関連することを体験するのだ。「では練習問題、どうぞ始めてくださ〜い」という感じで。意識が出来事を引き寄せるのかもしれない。
エニウェイ。
今回学んだことは、怒りという感情の前段階に「わたしだったらこうするのにどうして…?」という理解されたいという欲望だとか、「なんでこんなことするの?」という理解できない行動だとか、そういうものがわたしの中にあるんだなーってこと。それはわたしのこだわりであったり、こうするもんだ、という頑なな基準だったり。そういうものが多ければ多いほど、怒りを感じやすいのかもしれない。
結局は相手がどうこう、じゃなくて自分の癖やこだわりを見つめるってことなんだよなー。わかっちゃいるけど、むかつく!許せじ!としばらく引きずっていたが、もういい加減、思い出す時間ももったいないから次、行こう。
文章にしたら、客観的になる。文章化は大切なプロセスである。実感。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
