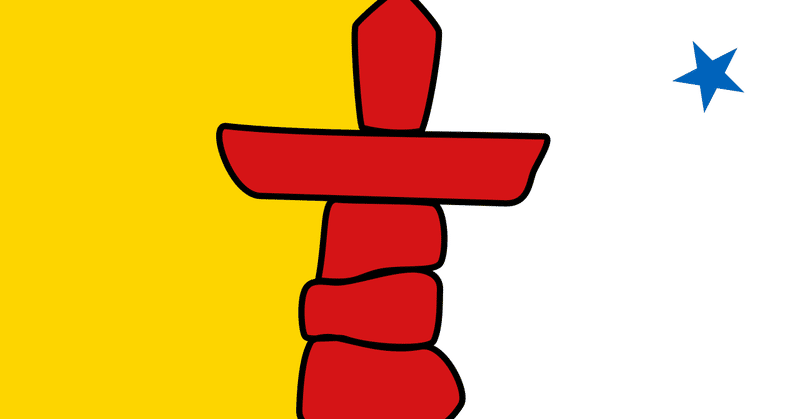
#21.イヌクティトゥット語(エスキモー語)
言語の話題に移りたいのだけれど、この題名には色々な問題を含んでいると思う。
まず今回のブログは特に断らない限り、ヌナブト準州で使われるイヌクティトゥットと呼ばれるイヌイットの言葉の方言をベースにしている。しかし、同時に知名度が日本では低すぎるため、黒田先生の『世界の言語入門』の目次でもあった「エスキモー」という単語も並列させた。
ただ、すべてのイヌイットと呼ばれる人たちがイヌクティトゥット語を話しているわけではないという点には注意が必要だ。同著にも言及があったように、エスキモー語─もっと目新しい単語を使うと「イヌイット語」とでも呼べばいいのだろうか─は複数の方言の総体みたいなもので、あくまでイヌクティトゥット語はそのうちの一つにしかすぎないらしい。
なので、あなたがアラスカなどでエスキモー語やイヌイット語という単語を耳にしたら、どこの方言のことなのか、興味深く思われる方は確認した方がいいかもしれない。
イヌクティトゥット語の位置
エスキモー・アレウト語族という名前を聞いたことがあるだろうか。ウォロフ語もそうだが、日本では滅多に耳にすることがない語族の一種だろう。
この語族の話者はロシアの極東にあるチュクチ自治管区からベーリング海を渡ってアラスカに広がる。そしてさらに海を越えて、グリーンランドまで達している。
冒頭でエスキモー語というのは「複数の方言の集合体」と話をした。まず一番最上位にエスキモー・アレウト語族というのが来る。その次の下位の概念はエスノローグによると、次のように分類される(1):
エスキモー諸語
→アレウト諸語
→エスキモー諸語→イヌイット・イヌピアック(カナダなど)→(!)
→ユピック(ロシア)→
上記のような分類とされている。
ここで上記の(!)からどのように続くかというと、次のような言語に別れていく。
①グリーンランド語(デンマーク領)
②イヌインナクトゥン語
③イヌクティトゥット語
④イヌピアトゥン語(北アラスカ)
⑤イヌピアトゥン語(北西アラスカ)
(1)参照:https://www.ethnologue.com/subgroups/eskimo-aleut
ここまできてやっと、タイトルのイヌクティトゥット語が見えてくる。
余談ではあるが、グリーンランド語も単一の言語ではなく、複数の方言/言語の集まりであるらしい。
変形合体 抱合語ロボ
ところで、ロボットものの映画やアニメだと複数のロボットが変形合体して、一つの大きなロボットになることがある。エスキモー諸語の知られた特徴として、単語の構成要素が独立しておらず、まるで一つの文のように合体する、「抱合語」という性格が強いことで知られている。エスキモー語ことイヌクティトゥット語は、そういった意味で、抱合語のオプティムプライムなのである。(注)
(注)・・・映画『トランスフォーマー』に登場するロボットたちの代表者。司令官。
例えば構成がシンプルな英語と比較してみよう。
I am going to school.
上記のすべての単語は独立しており、それらを英語の文法規則にそって、単語を規則的に並べただけといっても過言ではないだろう。同じ文章をイヌクティトゥット語と比べてみれば、その特徴が明瞭にわかる。
Illinniavimmuuqtunga
さて、どこが単語の切れ目であるかわかるだろうか。多分、難問になると思う。私も最初勉強しなければわからなかった。
実は以前に、グリーンランド語の辞書をコペンハーゲンで購入して、デンマーク語の文章と比べていけば、もしかしたらグリーンランド語がスラスラ読めるようになるのではないか、と思っていたことがあった。だが、それは無謀な試みであることを後々思い知らされた。
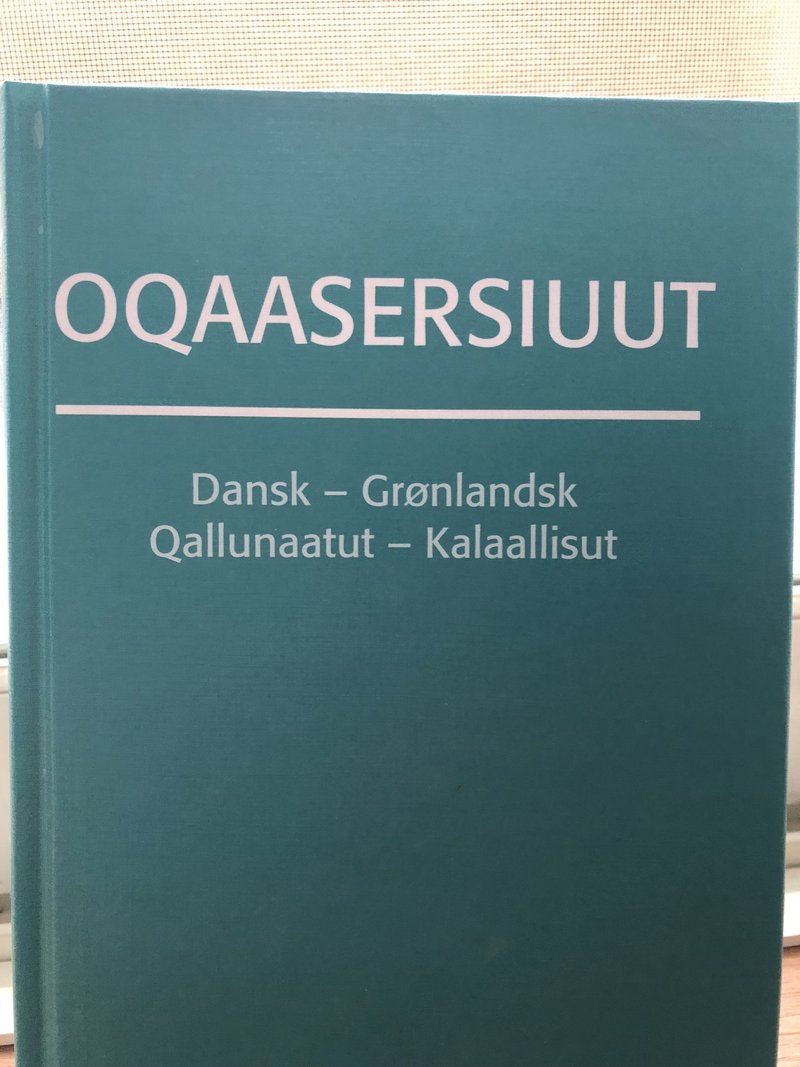
実際、それぞれのパーツが何を表しているかはチェックできる。しかし、英語などと大きな違う点はすべての単語が合体してしまっている点だろう。それがグリーンランド語にしろイヌクティトゥット語にしろ、単純な文章比較で読み解けない理由につながる。
例えばこの文章は次のようなパーツから成り立っている。
illinniavik = 学校
-muuq- =〜へ行く
-tunga = (私:一人称単数の語尾)
この部分の肝は"illuniavik"の語尾の"k"が後続する"muuq"の頭文字と子音同化を起こして、"illuniavim-"という形になってしまうことだ。単純な文であればいいが、長い文章になればなるほど、この切れ目を確認することと子音の同化現象を見定めていくことが肝心になってくる。
では逆に否定にする場合はどうするのだろうか。「私は学校へ行かない」というパターンである。文法上のルールに従えば、次のような長い文章になる。
Illinniavimmuunngittunga*
一応、*をつけた。私もネイティブではないし、文法間違いしている可能性があるからだ。しかしながら、文法上の規則に従えば、上のような文ができるはずだ。
ここでもまた、パーツが合体する際に語尾の子音を変更してくっついている。
Illinniavi(k)-muu(q)-nngit-tunga
( )は子音が同化していることを表している。このような細かい変化が、長ければ長いほど続き、話が長ければ長いほど、文が長くなる。
数の概念
すでに「つぶやき」で書いたことだが、イヌクティトゥット語には一つを表す単数と三つ以上を表す複数に加え、二つということを表すためだけに使われる形が存在する。
文法用語では「双数」という。
例えば私たちが使っている「イヌイット」という単語が典型的な例である。私たちは日本語で「イヌイットが一人、イグルーの前にいた」と言うかもしれない。しかし、イヌイットはイヌクティトゥット語で複数形なのである。
作り方はシンプルで語末の子音を落として、"-it"をくっつけるだけ。"inuit"の単数形は「イヌック("inuk")」だ。カナダを訪れた人が英語でイヌイットの人に"an Inuk"で話せれば、「こいつは少し教養があるぞ」と見なされるかもしれない。
では、上記のイラストのようにイヌイットが二人いる場合はどうなるのかというと「イヌーク」になる。語末の子音を落として、長母音化し"-k"をつける。これで完成になる。
豊富な新造語?
さて、イヌクティトゥット語の未来は明るいのだろうか。例えばアイヌ語の新造語が巷にも増え始めてきたと思うのは最近だが、まだ最近のインターネット用語の定着や政府の官庁の名前などはアイヌ語として公式にはない。まあ「公式」も「非公式」も概念としてないとも言えるが。
何れにしても、その状態と比べると、イヌクティトゥット語は自前で作った新造語が目立つように感じる。例えば、次のような単語がある:
qangatasuuq = 飛行機
これは"qangata"という動詞に"-suuq"という接尾辞をつけて名詞化したものであるらしい。これに"-kkuvit"という「〜を保管する場所」を表す接尾辞をつけて、次のような単語を作る:
qangatasuukkuvit = 空港
次のような例もある:
kiinaujaq = お金
これに「〜の人」を表す"-liriji"という接尾辞と「〜をする集まり、団体」を表す"-kkut"という接尾辞をつけて、次のような単語を作る:
kiinajaulirijikkut = 金融庁、あるいはお金を扱う人達の団体
さて、このような単語はイヌクティトゥット語を学べるサイトから引用したものだが、yahoo!では全くヒットしない。googleでかろうじてカナダ先住民族文字を使うホームページのURLに含まれているからヒットする程度まで増える。
なので、私は次のように考える。イヌクティトゥット語はヌナブト準州の公用語になったばかりだから、近代語の語彙を揃えることとそれを州教育に取り入れて広めようとしている最中なのではないだろうか、と。
エスキモー語の未来
世界のいろいろな言語政策(法的に言語をどのように扱うべきかを定めた法律)では、まず標準語を作るところから始める。あるいは模範となる言語を標準語として定義付けする。しかし、その時により「美しい」標準語を作ろうと、外来語を排して「純粋な」単語を作り出そうとする一派と借用語を許容する一派に別れることがある。
私がネットで学んだイヌクティトゥット語もそのような性格の標準語ではないのかと思い巡らせる。つまり、実際のヌナブトの人たちが口にする単語とは異なる単語ではないのか、という疑心がある。しかし、これにはどちらの方法が正しいのか正解はないし、外部の民族が口すっぱく突っ込んでいく問題でもない。
でも、アラスカの厳しい自然の中で継承されてきた言語が「宇宙船」や「世界保健機関」、「モノのインターネット」みたいな難しい言葉を、全て自前のイヌックの言葉で言い表せられたらすごいなぁと思うんだ。
そういう言葉の持つ可能性を信じて、エスキモー語の未来をのぞいて見たい気持ちはある。
参考
Inuktut Tasaalanga: https://tusaalanga.ca
オススメ
オススメできる教科書は日本語で出版されていない。また、英語でも適した教科書があるかというとそれも心当たりがない。上記の"Inuktut Tasaalanga"がイヌクティトゥット語の構造を知るためには有益だろう。または学術論文にたよるなど、まだまだ敷居が高い言語ではある。
おそらくグリーンランド語に関する文献の方が多いのではなかろうか。カラーリット語から攻める場合は、デンマーク語文献を調べる方が近道かと思う。
Twitterもよろしく
Facebookもよろしく
資料や書籍の購入費に使います。海外から取り寄せたりします。そしてそこから読者の皆さんが活用できる情報をアウトプットします!
