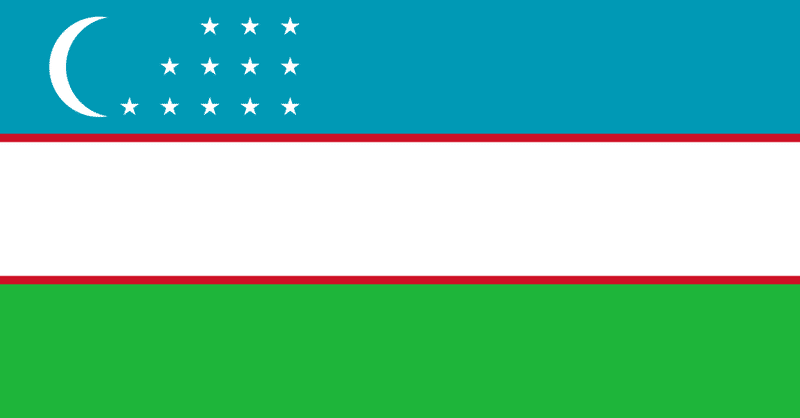
#18.ウズベク語
去年はウズベキスタンと関係が深まる年になった。
前田敦子さん主演でウズベキスタンが舞台の英語も公開されたし、テレビの旅番組でもウズベキスタンを旅をするというテーマが例年よりも多かったと思う。その縁もあってか、私の町でもウズベキスタンダンスのグループをお招きして、異文化交流イベントを開催したりした。
個人的に大きなことの一つもウズベキスタンと関係している。仕事休みを利用して、ウズベキスタンに一人で旅行に行ったのだ。現地ではウズベキスタンの知り合い達に力を借りたものの、初めてのウズベキスタンとタジキスタンの諸都市を一人で行き来したのは良い経験になった。
特に快適に感じたのが、ウズベキスタンで入国の際に必要なビザが日本人は免除されたことだ。また、旧ソ連式のレジストレーションカードも必要なく、明るい現地のウズベク人達やタジク系の人々に囲まれて、良い旅になったと思う。
心をつなぐ経験
「良い旅になった」と言えるのは一重に気さくな人々との出会い故だが、その気さくな人々と出会えた一番大きな要因は、何といっても「ウズベク語でのおしゃべり」だった。
ウズベキスタンは日本が無くした村社会的な性格を強く残しているのかもしれない。根本的にウズベキスタンの人は好奇心が強く、気さくだ。向こうから話しかけてくることもかなりある。
例えばバザールでは押しが強く言葉がお互い不完全でもぐいぐい話しかけてくる。ローカルバスに乗っている時、日本はみんな気にはなるけれど極力関わろうとしないようにする。でも、ウズベキスタンでローカル線のバスに乗ると一瞬で他の乗客全員の視線が集まっているのを背中越しに感じるくらい、ウズベキスタンの人は興味を隠さない。そして、誰かが外国人に話しかけると、バスを降りる頃には会話の輪がバス中に広がっている。
それに加え、ウズベキスタンは昔から、そして現在もウズベク人だけに止まらない、多種多様な民族が暮らす人種の坩堝のような国だ。そのため、ことばの問題に非常に重きが置かれているように感じる。
例えば日本生まれで日本育ちで日本語がしゃべれないという人は滅多にいないだろう。でも、ブハラに行くとウズベキスタンのブハラ生まれだが、家庭内ではタジク語のブハラ方言を話し、大学ではロシア語で授業を受ける、なんていう人もいる。客引きをしているロシア人のタクシー運転手の中にはソビエト時代の名残りか、ロシア語しかしゃべれない人もいる(そのため「グーグル翻訳」アプリを使って外国人旅行者を客引きしてくることもある)。
タシケントのような大きな都市は例外かもしれないが、多かれ少なかれどこ行っても、ウズベク語が話せれば旅がずっと楽になる。ウズベキスタンとタジキスタンの国境で国境警備隊の人の質問にウズベク語で回答したら、ものすごく喜ばれた。明らかに写真を撮ってはいけなさそうな国境中間地帯でも銃を持っている軍人のお兄さんに話しかけ、「ここ面白いから写真を撮りたい。いいか?」と聞くと、他の軍人と少し話した後に「いいよ」と返事がもらえたりする。それはウズベク語をしゃべる人への役得だ。
直訳できる喜び
国境を通るときに「ロシア語はしゃべれますか?」と警備員に受付のガラス越しに聞かれた。私は「少ししゃべれるけれど、文法が全然違うから苦手」と答えた。
実はウズベク語は日本語と文法がそれなりに似ている。ウズベク語は日本語と同様、SOVの順番の言語だ。かつ、動詞が日本語の用言と同じように、連用形や連体形などに変化する。これはウズベク語が、というよりもテュルク系言語全体に言えることであるが、思いついた日本語をウズベク語に単語を置き換えるだけで、それなりに理解される文章が作れる。これは英語では絶対にできないことだ。
ウズベク語は日本語と同様、典型的な膠着語だ。つまり、前置詞や後置詞を多様する言葉というよりも、単語そのものにパーツをくっつけて、文の中の単語の役割を明確にするタイプの言語であるといえる。ただし、ウズベク語は後置詞も多用するが、日本語で考える人にとってウズベク語に訳す際に大きな障害にはならない。
例えば次のような文を作ってみた:
Buxoroda yashayatgan kishilarning hayoti haqida gapirayapsizmi?
(ブハラに住んでいる人たちの生き方について話しているんですか?)
これはほとんど日本語と逐語訳とほぼ同じになると思う。
Buxoro-da :ブハラーに
yash-ayatgan:住んでーいる(現在進行の連体形)
kishi-lar-ning:人ーたちーの
hayot-i:生き方(+修飾されていることを表す"i"がついている)
haqida:〜について
gapira-yap-siz-mi?:話してーいるー(あなたが)のですーか?
上を見て頂いて分かるように、ほとんど日本語と同じようになる。丸々一文がほぼ日本語と対応するということは、英語や文明・文化的に近い中国語でもほとんど起こらないことだろう。
ウズベク語に近いことば
しかし、ウズベク語は文法的に日本語に似ているが、親類関係は証明されていない。
では、どの言葉がウズベク語に最も近いかというと、それはウイグル語だと思う。
すでにこのウイグル語の記事でウズベク語との近さについては言及している。興味がある方はこちらもお読み頂きたい。
しかし、遠かれ近かれ、中央アジアの言葉のほとんどがお互いに親族関係にある。中央アジアはタジキスタンを除き、すべてテュルク語系言語の国だ。したがって、お互いの言葉を100%分かるわけではないが、言葉が違っても何となくお互いの言っていることが分かることが非常に多いように思う。しかし、お互いに正書法や書き言葉が違うし、自分のニュアンスが完璧に伝わるという確信を持ってしゃべれるわけでもないので、何か別の共通の言葉が必要になってくる。そこで昔から学ばれているロシア語が族際語として登場するわけだ。
ところで、最近は「飛行機」という単語から中央アジアのそれぞれの国の考え方が見えてこないか、というような投稿をした。
中央アジアの言葉の中でも、ウズベク語はロシア語からの借用語を使う傾向にあると思う。
黒田龍之介先生の『世界の言語入門』の「ウズベク語」のページでは、お知り合いのウズベク人がウズベク語にロシア語が多すぎるとぼやく、というところがある。上記の投稿の"samolyot"だけでなく、”sivilizatsiya(文明)"や"militsiya(警察)"のように、近代的な高級語彙にまだまだロシア語は残り続けている。トルコの言語政策のように無理やり語彙を開発して使わせない限り、ロシア語からの語彙は残り続けるだろう。もっとも、ロシア語の語彙を今更排除し、言語の純化を掲げたところで、何の意味もないのではないかと思うが。
イレギュラーなウズベク語
個人的にはウズベク語はオススメしたい言葉だ。理由は「ウズベキスタンファンだから」等、個人的な理由はある。しかし、何よりもテュルク諸語の文法的特徴の一つである「母音調和」がウズベク語の標準語にない、というところが最大のオススメポイントだろう。
テュルク系言語の母音にはざっくりと言って「二つの母音のグループ」があり、しかも「派閥抗争」がある。例えば、トルコ語では、次のようなグループに分かれる:
グループA:A I U O
グループB:E İ Ü Ö
トルコ語には単語の中で使われる母音を必ずどちらかの母音のグループで統一するという基本ルールがある。これを言語学的には「母音調和」という。トルコ語の全ての単語がこのルールに従っているわけではないが、単語に格助詞のようなパーツをくっつけるとき、格助詞の母音を何にするかはこのルールに準じることになっている。
ありがたいことに、そして興味深いことに。ウズベク語にはこの母音調和がない。母音の関係性を気にしないのだ。
なのでテュルク系言語の初心者によくある「この単語の母音はどちらのグループになるんだろう」や「間違って違う母音のグループの格助詞を書き足した」などのミス。そのような初歩的なミスをする可能性が、なんとウズベク語では「ゼロ」になるのだ!
終わりに
ウズベク語は日本ではまだまだマイナーな言語かもしれない。しかし、母音の細かい点を気にせず、ある程度文法を学べば、日本語と同じ感覚で文をスラスラ作れるようになるのは、SOV語順の膠着語を話すウズベク人と日本人だから可能になることだ。これは日本語を母語にしている人への大きな特権だろう。
オススメ
...と今までオススメということでウズベク語について書いてきた。しかしながら、優れたウズベク語の教科書や文法書はほとんど入手困難になっている。入手できる機会があったら絶対にゲットしないと絶対に後悔するだろう。
今手に入手しやすいのが『大学のウズベク語』と『簡明ウズベク語文法』、『ウズベク語簡易文法便覧』だろう。しかし、いずれも文法書なので、基本的に怒涛の文法ラッシュになる。
総合的に勉強できるのは『ウズベク語文法・会話入門』と『ウズベク語初級ーウズベキスタンへの招待』だ。手に入りやすく読みやすいという意味では『大学のウズベク語』を読んでみてはどうだろうか。
Twitterもよろしく
Facebookもよろしく
資料や書籍の購入費に使います。海外から取り寄せたりします。そしてそこから読者の皆さんが活用できる情報をアウトプットします!
