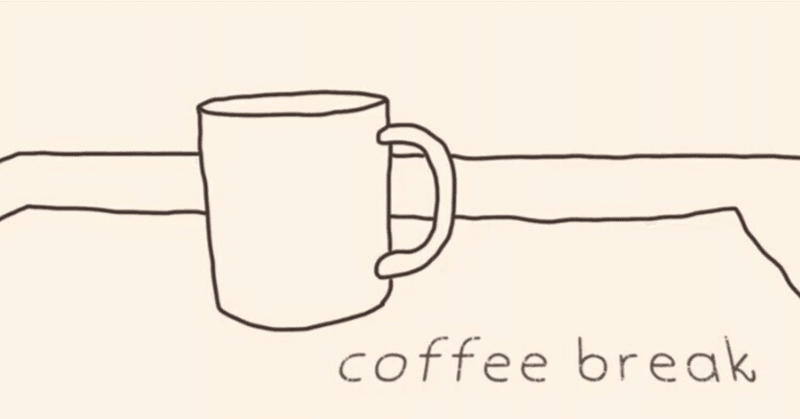
6月下旬のイベントの開催報告
こんにちは。6月に開催したイベントの開催報告を簡単に書きます。
1.BARイベント
こちらのBARイベントですが、お酒に音楽に詩に酔いしれることができました。
音楽についてはフランク・ザッパ氏や灰野敬二氏の音楽を鑑賞してみました。
曲の感想を話したり、タイトルやアーティスト情報からこのような曲ではないか?と推測してみたりしました。どの曲もはっきりとしたメロディラインや、歌詞があるわけではなくさまざまな音や声の組み合わせで、たしかに「奇妙な音楽」だと納得された方が多かったです。
詩については、難解とされる現代詩を中心に読みました。必ずしも散文的な理解ができなかったり、作者の主張や意図、意味が必ずしもすぐわからない作品を中心に鑑賞しました。店主の作品の朗読シーンをご覧いただきます。
この会に特に結論があったわけではありませんが、表面的な意味を超えた言葉にはならない想いがあることを実感しました。それを直接論理や理性を超えた世界で伝えられるのが詩だったり現代音楽だったりするのかなと思いました。
改めまして、こちらのイベントにご参加や告知に協力いただいた皆様、場所をお貸しいただいたBARエデン様、誠にありがとうございました。
— Poetry Factory(ポエトリーファクトリー)@負けの詩の投票お願い致します (@poetryfactory_t) June 21, 2023
写真はイベント終了時23時までお店にいてくださった方々です。
また、イベントをより良くしてこのような場を開きたいと思っております✨ pic.twitter.com/vk3NGs4TAs
2.西原大輔先生のオンライン講演会
西原先生の講演会は、8月から開催する西荻窪での対面講座の紹介を兼ねて開催しました。講座の詳細はこちらです。

西原先生のプロフィールです。

講座は、対談形式で進行させて頂きました。大きなトピックは3つです。
・詩の研究者の世界
研究と鑑賞の乖離や違いは?
研究者のポストについて
論文書くのは重要?
若い研究者の課題
・読者の世界
詩人はいるが読者はいないのは何故?
難解暗喩について
韻律と暗喩
人気詩人について
詩に教訓は必要?
国語教科書の役割について
入試と学校授業について
・詩のこれから
技法って大切ですか?
詩は何を語るのが良いか?
詩を普及するには?
(大衆)読者層も取り込むためには?
今回は聞き手の方もこだわりまして、Poetry Factory内部ではなく、文学部を経て、出版活動をされたり、学術研究に関連する仕事をされている方に依頼したのでとても先生の話を上手く引き出してくださいました。ご参加いただいた方の感想を記載します。
詩の魅力が素晴らしかったです。ところどころではっとさせられました。このような講演会をもっと開いてほしいです。聞き手の方もお疲れ様です。
今回だけの講演なので仕方がないが、少し浅く広くという印象でした。
私の周りの学生間でも詩は小説に比べて軽視されています。詩は短くて言葉を捏ねたものという認識があるようです(誰でも書ける)。現代で詩というものの復興があるとするならば、暗喩に頼る詩ではなく、言葉でロゴスとパトスの中間を縫うような(読みやすさと読みにくさの両立)詩しかないのではと感じました。本日は大変勉強になりました。
国語を正しく教えられる先生が極めて少ないことが、貧しい国語力で育った現代人の「悩み事」の根源なのだと思います。 守破離、の先ず守の教育をきちんとし、離れる楽しさを身につけることで自他共に認め合えるのではないでしょうか。 また、詩は大分下火になってしまっているという話がありましたが、これから姿形を変え、詩の多様性を求めて生まれ変わって続いていくと、わたしは思います。
確かに、詩は国語の授業で出会ってからそれきりという形になってしまっていました。私は残念ながら、東京の講座には参加できませんが、オンラインでも詩を読む機会をいただけましたら幸いです。
3.おわりに
いかがだったでしょうか?私たちはイベント会社というわけではないので、イベントは詩を広めたり、考えたりするための1手段です。それでも楽しいですし、今後も積極的に開催してまいりたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
