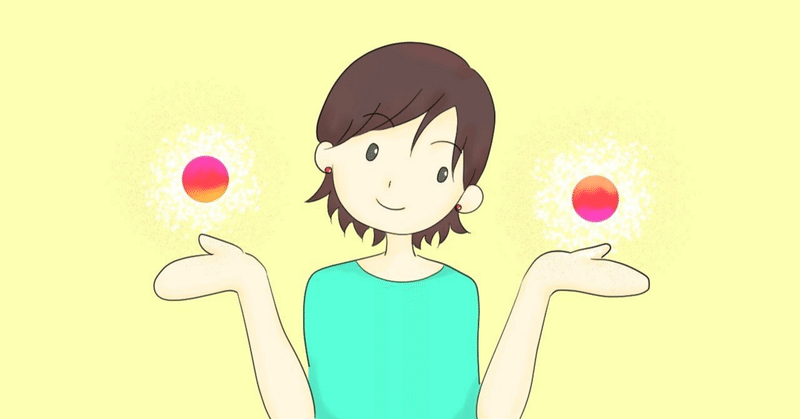
自分で考えられる子になってほしいの罠。自分で物事を決められる大人になるためにはどうしたらいい
【この記事は音声でもきけます。↓をクリック】
「今日の夕飯は何を食べたい?」
「今日は保育園(学校)で休み時間に何をして遊んだの?」
「寝る前に本を読んであげるけどどの本がいい?」
子どもとの日常生活の会話の中で何気ない質問をすることはたくさんあるでしょう。
「夕飯はハンバーグがいい」
とか
「休み時間はみんなで鬼ごっこした」
とか
「はらぺこ青虫読んでほしい」
とか
親の問いかけに子どもが笑顔で答えてくれたら嬉しいですよね。
でも、中には
「夕飯なにがいい」と聞かれても
言葉は理解できるし喋れるのに
返答をすることが苦手な子がいます。
もしかしたら、
頭の中で色々な食べ物は浮かぶけれど、どれもよくて決められない
とか
そもそも、食べ物というカテゴリーが大きすぎて食べたいものが絞れない
とか
食べ物(例えばカレー)のイメージは頭の中で浮かぶがその名前が出てこない
など色々な理由が考えられます。
質問に対して返答がなく無言であると悲しくなるし
物事を自分で考えて自分で決められるようになってほしいと思う親御さんの思いもあるでしょう。
大人になり、何か問題に出会った時に、自分で考え、決定して、実行していくという【自律】ができるようになってほしいですよね。
だけど、子どもの中にはそれが不得意な子もいます。
みんないろいろです。
質問に答えることが苦手な子には、まずは選択肢を与えてあげる。
質問内容を狭めてあげることが有効です。
「夕飯は何たべようか。ハンバーグ?お魚?」というように
子どもに選ばせるのです。
一見、親が選択肢を出しているため、親が主導で食べたいものを決めさせているように見えるかもしれません。
しかし、ハンバークかお魚かどちらにするかを決めるのは子どもです。
これも自分で考えてどちらかを決定しているのです。
どちらも嫌と言われたらそれもその子が自分で出した答え。
違う選択肢を再度与えてみましょう。
もし、ハンバーグかお魚どっちがいいか聞いても、それでも無言の場合は、
その子の嫌いなものを選択肢にいれて質問してみてください。
例えば、「野菜炒め(嫌いなもの)とオムライスどっちを食べる」と。
大抵の子は答えやすくなり、オムライスを自分で選択するでしょう。
自分で考えて、答えをだして、行動できるようになってほしい。
でも、それが難しい子にはまずは選択肢から選ばせることから始めるのも一つです。
大人が選択肢を出し続けていけば、子どもの頭の中に今まで出された選択肢が知識として蓄積されていきます。
そしたら、何か質問された時には、その頭の中にある選択肢のストックから自分で答えを引き出して答えることができるのです。
このやり方だって、1人で考えて答えを導きだしているのと一緒です。
自分の力で答えをだしてほしくて
「あなたはどうしたいの」とただただ問い続けることこそ
それが苦手な子にとっては苦痛でしかありません。
萎縮して話すこと自体を嫌になる子もでてくるかもしれません。
選択肢を与えるなど、答え方のレパートリーを教えて増やしていけるといいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
