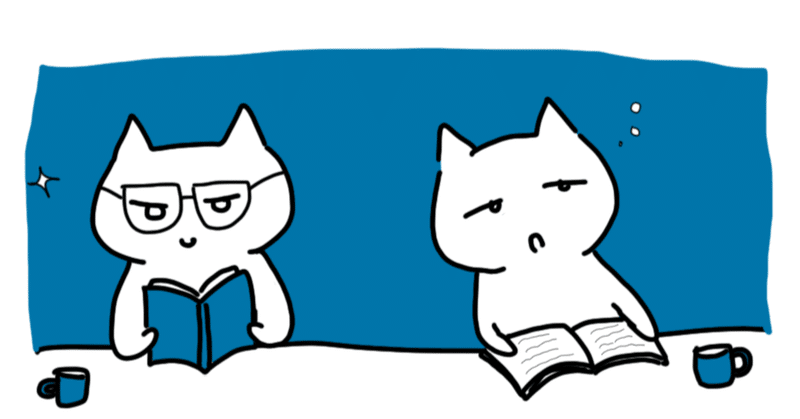
《詳細なカンニングペーパーを念入りに作っているうちに、試験中それが必要でなくなるほど既にその内容が頭に入ってしまっている》というのは本当だろうか? (試験の時間*再勉生活)
私のnote史上、最も長いタイトルです。でも、よくある笑い話ですよね。
のび太が試験の前日に一生懸命小さな字でカンニングペーパーを作っている。それを見たドラえもんが言います:
「のび太くーん、そんな苦労するよりも、ちゃんと勉強した方がよっぽど楽だと思うんだけど……」
ドラえもんは、ある意味正しく、ある意味では間違っている。
おそらくのび太は、明日の試験ではカンニングペーパーを見る必要がないほど、試験範囲の公式を暗記してしまっているかもしれません。
でも、《カンニングペーパーを作る》という極めて重要なプロジェクトがあったからこそ、のび太は全身全霊をそれに打ち込んだのです。
先日、古い書類を整理していたら、《再勉生活》時代に作った《cheater》つまりカンニングペーパーを発掘しました。
大きさはハガキより二回りほど小さい、その昔、図書館のインデックス・カードとして使われていた、3インチX5インチ(76.2×127 mm)のカードです。そこに裏表びっしりと公式や要点が書いてある。

といっても、《非合法》のものではありません。
《再勉時代》に受講した、セラミック材料について学ぶ講義の試験用に作ったものです。確か学部4年向けの講義でした。
担当の先生は、試験の1週間前に学生に告知しました。
「君たちは、試験会場に、3 by 5 のインデックスカードを1枚だけ持ち込むことが許される。その裏と表に何を書いてきてもいい。ただし、絶対に1枚だけだぞ!」
学生の間にはどよめきが起こりました。
私もさっそく、購買にカードを買いに行きました。
インデックスカードには青い横線が引いてあります。その間隔で文字を書いて行くのがよかろう、と考え、どの情報を入れるか考えました。
その判断のためには、試験範囲を一応「おさらい」せざるを得ません。
そして前日夜に、先を尖らせた鉛筆で慎重に書いていきました。


ぼんやり記憶しているのは、重要事項は1.5 枚程度、つまり表と裏の半分ぐらいで書き終え、後は適当に「あまり関係ないけど」的メモで埋めたことです。
確かに、このプロセスで要点は頭に入っており、いや、そもそもこんな複雑な公式を暗記する必要などはなく、試験には主に《考え方》を問う問題が出たと思います。
公式や要点を書き写す過程で、その《考え方》を辿っていたことになります。
従って ──
のび太は、
《カンニングペーパーを作る過程で、実はちゃんと勉強していた》
というのが、冒頭のドラえもん問題に対する答えなのでした。
この、
《規定のカンニングペーパーを持ち込ませる》
方策は、カンニングを取り締まるよりもはるかに有効だな、と思ったものです。
ただし、昨今の《コピペ文化》では、それすらも自作しない学生は、……残念ながらいるかもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
