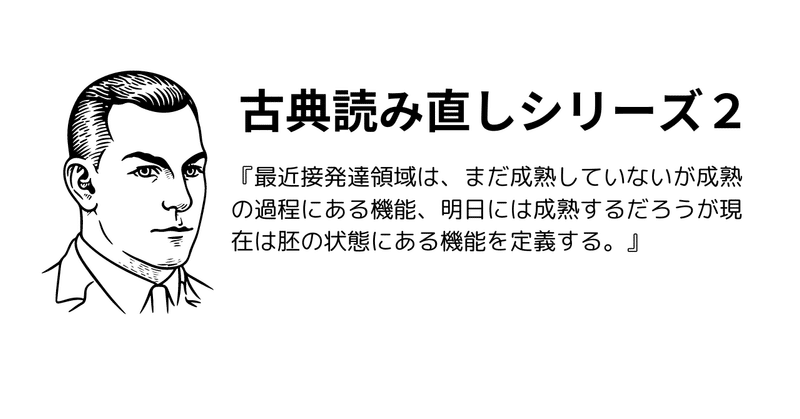
ヴィゴツキーに学ぶ、これからの教育のあり方
今回は、20世紀の偉大な心理学者の一人、レフ・ヴィゴツキーの理論について紹介したいと思います。
教育学や心理学を学ぶ学生にとって、ヴィゴツキーといえば、最近接発達領域やら足場理論やら、最近のイケている教育テクに満載なパワーワードの創造主ですね。
でも、じゃ本読んだことがありますかって聞かれたら、多くの人は目をそらしてしまうのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、ヴィゴツキーが人間の知能発達をどのように捉えていたのかを、彼の主著 "Mind in Society" と "Thought and Language" の内容をベースにわかりやすく解説していきます。心理学専攻の学生さんだけでなく、子育て中のお父さんお母さん、教育関係者の方々のお役に立てるような内容にしていきたいと思いますっ!
ヴィゴツキーは何を考えていたのか?
ヴィゴツキーは、人間の心理機能の発達を社会や文化との関わりから説明しようとしました。彼は、言語、論理的思考、意図的注意、記憶など、人間に特有の心理機能は、すべて社会的なやりとりを通して形成されると考えました。
特に、Thought and Languageという本の中に鮮明に書かれているのですが、私たちが言葉によって生み出す「意味」が重要と考えたんです。意味は、思考と言語を統合する役割を果たしているというんですね。
ヴィゴツキーによれば、子どもは大人や仲間とのコミュニケーションを通して、言葉の意味を内面化していきます。つまり、最初は気持ちを伝えたり、とりあえず使うだけだった言語が、徐々に内的な思考の道具へと変換されていくのです。この過程で、言語は思考を形作り、思考は言語を洗練させていくと考えました。
ヴィゴツキーは、この言語と思考の相互作用こそが、人間の意識の発達を促すカギだと考えたんですね。
前回、ピアジェの理論を紹介したんですけど、表にすると結構対照的なんですね。じゃ、何が決定的に違うのかというと
ピアジェが個人の能動的な構成を重視するのに対し、ヴィゴツキーは社会的相互作用を重視した
ってとこなんです。

ヴィゴツキー重要用語: 社会相互作用、最近接発達領域、内化
本文では出てくる順が違うのですが、この順の方がわかりやすいと思います。
先ほども書きましたが、基本、ヴィゴツキーは人間の知能発達は社会や文化との関わりにあると考えました。社会的相互作用は子どもの発達を促す重要なエンジンとして位置づけられています。
子供同士のやり取りでも大切ですが、大人は、子どもとの関わりを通して、子どもの発達を助ける重要な役割を担っているのです。
例えば、子どもが大人や仲間と一緒に問題解決をする際、最初は大人の助けを借りながらできることが徐々に一人でできるようになりますよね。
なんだろ、保育園・幼稚園児だったら算数の足し算引き算に取り組むときに大人がそっと助け舟をだしたりしますよね。ヴィゴツキーは、この時の大人と子どもの実際の能力の差、つまるところ、一人だったらできないけど他の人がいたらできる差を「最近接発達領域」と呼び、重要視しました。彼にとって教育の役割は、この領域を上手に刺激し、子どもの潜在的な発達可能性を引き出すことにあるのです。
また、ヴィゴツキーは、心理機能の発達を「内化」のプロセスとして説明しました。つまり、子どもは外的な社会的活動を内的な心理的活動へと変換させていくのです。例えば、大人と一緒に指差しをしながら数を数えることを通して、子どもは徐々に内的な計算能力を身につけていきます。他には、最初ぶつぶつ独り言を言って何かをやっていたのが、気がつくと言わなくなるとか。これは、言葉を使って自分の思考を表現していたのを内化したと考えられています。
The internalization of socially rooted and historically developed activities is the distinguishing feature of human psychology, the basis of the qualitative leap from animal to human psychology.
ちなみに、内化のプロセスが人間の心理の特質であり、動物から人間への質的飛躍をもたらしたとおっしゃっております。
まとめ 今日の教育への示唆 〜 scaffolding と協働学習
ヴィゴツキーの理論は、子どもの発達と学習を社会的文脈の中で捉える視点を提供しています。これは、従来の個人の能力に重点を置いた教育観とは大きく異なりますね。例えば習熟度別クラスとか・・・
ヴィゴツキー理論に基づけば、教育の役割は、学習者の最近接発達領域をうまく活用し、適切な助言や手がかりを与えながら、学習を導いていくことにあります。
具体的には、教師は子どもの現在の発達水準を把握した上で、少し背伸びをしないと届かないような課題を用意することが大切。
そして、子どもが徐々に自力で問題を解決できるように、適切なヒントや励ましを与えていく必要があります。この考え方に基づいた教え方をscaffolding (足場かけ)と呼ばれていますね。
また、最近接発達領域の考え方から、ヴィゴツキーは協働的な学習の重要性を指摘しました。子ども同士が協力して課題に取り組むことで、互いの理解を深め、新しいアイデアを生み出すことができるというのです。
先生は、このような協働的な学習が生まれるように、グループ活動の場を設定したり、子ども同士の対話を促したりする必要があります。決して放任ではありません。あしからず。
子どもの可能性を最大限に引き出すためには、一人一人の発達の特性を理解し、適切な働きかけが必要なんですね。だからこそ、ある教育者たちは年齢による輪切り教育はふさわしくないと考えました。ここから生まれた教え方がイエナプランなどにいかされています。最近都内でできたアクティビティ系小学校もこの流れかな。
今回の記事で紹介してきたように、ヴィゴツキーの理論は、今日の教育に重要な影響を与え続けているんですね〜。
関連記事
難しいメモ。ヴィゴツキーは当時はやっていた心理学にアンチの気持ち満載で研究を進めました。基本的な立場は
意識の心理学: 行動主義的立場を批判し、意識を心理学の中心的な研究対象とすべきだと主張。
文化-歴史的理論: 人間の心理的発達を、社会的・文化的な文脈の中で捉える必要性を説いた。
発生的方法: 心理的機能の起源と発達過程を解明することが重要だと考え、発生的(genetic)方法を提唱。
弁証法的方法: マルクス主義の影響を受け、心理学にも弁証法的方法を適用しようとした。
というものです。特に、マルクスからかなり影響を受け、弁証法的方法を用いて、心理的発達を固定的で静的なものではなく、ダイナミックで相互作用的なプロセスとして理解しようとしたんですね〜・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
