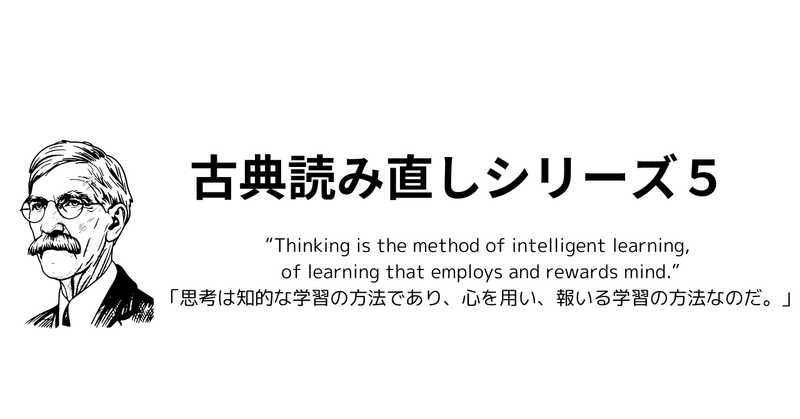
(続)未来を生き抜く子どもたちへ〜デューイ流 「考えること」 のトレーニング
chatGPTが登場して、急激に情報化が進展する現代社会。
今後どのような教育+子育てが最適解なのだろう
と悩んでいる人も多いのではないのでしょうか。
何を隠そう、私もその一人です。
手に職またはプログラミング、はたまた語学力か?
あれこれ未来を勝手に想定し、悶々としてしまいます。
しかし、
私たちは日々複雑怪奇な問題に直面しますが、そうした時に的確な判断を下し、問題を解決に導くことができるのは、鍛え上げられた思考力があればこそだったりします。
そこで、デューイ。
デューイは「反省的思考」という概念を提唱し、問題解決に向けて能動的に考えを巡らせるプロセスこそが、真の意味で思考力を高めると主張しました。さらに彼は、探究活動こそ、思考のトレーニングだと言っているのです。
彼は教育の究極的な目的が、子どもの思考力を育むことにあると考えました。そのために、暗記主義から脱却し、学習者自身が問題を探究し、試行錯誤する経験を積むことが不可欠だと主張しているのです。
前回の記事では彼の経験学習からの振り返りの大切さについて学びましたが、今回は彼の著書『How we think』(われわれはいかに思考するか)という全く知られていない+読まれていない本から、考えると何かということについて学んでいきたいと思います。
考えるとは?
デューイは考えること、つまり思考の重要性を3つの点から説明しています。
思考は、衝動的・習慣的な行動から脱却し、目的を持った行動を可能にする。
思考によって、人は自然の事象から意味を読み取り、将来を予測・計画できるようになる。
思考は、物事の価値や意味を変容させる。
この洞察は、私たちの日常生活や教育実践に重要な示唆を与えてくれます。
まず、思考力を育むことは、子どもたちが衝動や習慣に振り回されず、自分の行動を意図的にコントロールできるようになる上で不可欠です。目的を持って行動できる力は、将来の社会生活を送る上で重要ですよね。
また、身の回りの事柄から意味を読み取り、未来を見通す力は、激動の時代を生き抜くために欠かせません。単に情報を一方的に受け取るだけでなく、そこから隠された本質的な意味を汲み取り、先を予測する習慣とか思考パターンを身につけたいものです。
さらに、思考を通して物事の価値や意味を問い直す経験は、子どものたちの成長過程で人格形成に大きな影響を与えます。既成の価値観をそのまま受け入れるのではなく、自分の頭で吟味し、時には新しい意味を創造する。
思考力を通じて、子どもは自立的な人間へと成長していくとデューイは考えたのです。
ちなみに都内では2012年ぐらいから思考力を問う入試が流行っています。
反省的思考のプロセス
デューイによれば、思考は次のようなプロセスを経て進むそうです。
困難の発生
困難の明確化
解決策の示唆
示唆の合理的な展開(推論)
実験による確証と信念の形成
具体例でみていきましょう。私たちは1)困難や戸惑いに直面したとき、そこに問題があることを2)明確に認識しますね。例えば、新しく購入した家電の設定方法がわからないとき、「どうすれば正しく設定できるだろうか」という問題が浮かび上がるでしょう。
次に、その問題の原因や解決策について、3)仮説を立てます。先の例では、「取扱説明書を読めば設定方法がわかるのではないか」といった具合です。
さらに、その仮説に基づいて、4)論理的に筋道を立てて考えを進めていきます。「取扱説明書には製品の特徴が書かれているはずだ。それを理解すれば正しい設定ができそうだ」というように、推論を重ねていくのです。
最後に、実際に行動に移して、仮説や推論の妥当性を確かめます。つまり、本当に取扱説明書を読んで設定し、意図通りに家電が動くかどうかを検証するわけです。
しかし、デューイは探究の過程をこれらの「段階(steps)」として捉えることを否定しています。むしろこれらは、探究の過程で繰り返し現れる、知性的な思考の特質を表しているのです。つまり、行ったり来たり、ジワジワと進むと考えているんですね。
注)これは結構マニアックな議論になりますが、実は初版とのちに改訂ではこの箇所の記述がことなります。
探究とは思考トレーニングである
考える大切さはよくわかった、そのプロセスもわかった。
じゃ、どんすんの?
ってことになるのですが、デューイは子どもの思考力を育むトレーニングについてもちゃんと書いているんです。
さくっと要約すると、思考のトレーニングは生得的な能力に基づいて行われるべきだと主張しています。
具体的には、以下の3つの要素が重要だとしています。
示唆(suggestion): 思考において自然に生じるものであり、容易さ、範囲、深さなどの側面を見とる必要がある
好奇心(curiosity): 思考の素材を提供する最も重要な要因であり、教師はそれを守り、育てる必要がある
秩序立て(orderliness): 事実と示唆を組織化し、一貫した思考を生み出すもの。
まず、観察力を養うことです。五感を使って対象をじっくり観察する習慣をつけさせましょう。自然観察や人間観察から、問題発見の糸口を見つけられるようになります。
<参考>
また、好奇心を刺激することも大切です。子どもの「なぜ?」「どうして?」といった素朴な疑問を言葉にして共有し、一緒に考える姿勢を育みたいものです。
さらに、言語化のスキルを磨くのも忘れてはなりません。自分の考えを言葉で明確に表現する練習を重ねることで、思考はより論理的で説得力のあるものになっていきます。考えを文章や図表で整理してアウトプットする機会を設けるのもいいトレーニングになりますよね。
経験学習の重要性を論じたデューイ。その核心には
探究(inquiary)とは思考のトレーニング
だという揺るがない信念があるのでした。
そして探究活動には
考には時間的余裕が必要
学習者自身が問題を探究する責任を持つ
とも指摘しております・・・
ちょっとマニアック。
意味を理解することが思考の中核をなすと主張しているんですね。意味を中心に据える点は、パースらのプラグマティズムの影響を受けていると考えられます。特に、概念を問題解決のための道具と見なす発想は、パースの「アブダクション」の考え方と通じるものがあります。また、意味の獲得を実践的な反応と結びつける視点は、機能主義的言語獲得論の展開だと言えるでしょう。これが、のちにブルーナーに引き継がれていくんですけど・・・
まとめ
今から100年前にデューイが説いた反省的思考のプロセスは、まさに生涯学び続ける力を身につけるための道標となりそうですよね。
デューイの経験学習は学校現場での探究活動につながるだけでなく、一般的なPDCAサイクルとか、企業研修などで広く知られるコルブの経験学習モデルとかショーンの反省的実践(reflective practice)の基礎となりました。
さらに、これは本書よりも『学校と教育』に色濃く出ているのですが、デューイは教育信条として、思考力の育成を単なる技術の問題としてではなく、民主的な社会の礎として捉えていました。社会の一員として責任ある判断を下すことができる市民を育てること。それこそが、彼の教育の究極的な目標だったのです。
情報があふれ、常識が揺らぐ時代だからこそ、自ら問題を発見し、仮説を立て、論理的に考え、実践によって検証する。そうした思考の訓練を子どもの頃から積み重ねることで、将来どんな困難に直面しても、自分の頭で考え抜く力を身につけてた大人になってもらいたいものです。
子どもの無限の可能性を信じ、その思考力を丁寧に育んでいく。
彼の言葉は、時代を超えて私たちの心に迫ってきます。
教育の究極的な目的は、一人ひとりの子どもを、自立的に考え、責任ある判断を下せる大人へと導くことにあるのだと。そのメッセージは、変化の激しい現代社会を生きる私たち大人にこそ、突きつけられているのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
