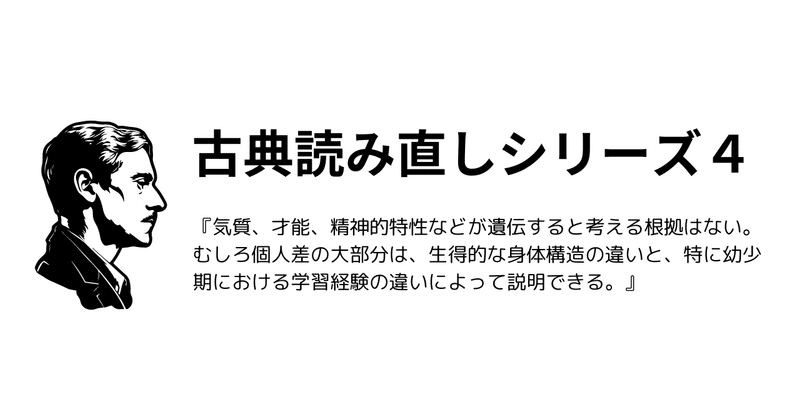
子育ての科学:行動主義の父・J.B.ワトソンから学ぶ
はじめに
ワトソン
シャーロックホームズのワトソンでもなく、IBMのワトソンでもなく、
キラキラ心理学・教育関係の本で今となっては役ただずみたいに書かれているワトソン
「みんな、そんなに俺のことが嫌いなのか」って声が聞こえてきそう。
しかし、そのJ. B. ワトソン。
今から約100年前、「行動主義」という画期的な理論を打ち立てました。
え、画期的?だって時代遅れじゃん、って言っているそこのあなた。
今回の記事では、アルバート赤ちゃん実験などから「怖い+やばいおじさん」みたいに誤解されている彼の研究を紹介しましょう。
(と言っても僕が読んだのは「行動主義宣言」(1913年)と巷では呼ばれている論文と著書『行動主義』(1924年)って本なので、その2つからワトソンが何をしようとしたのか、3分以内で読めるように書きますね。)
もちろん、100年以上も前の話なので、ワトソンの理論がそのまま通用するってことではありません。彼の主張は、現代の認知科学から見ると「それないでしょ」みたいなところ満載だからです。
しかーし、行動主義の核心、特に彼がやろうとしたことは、今でも子育ての指針になるはずです。(たぶん)
そもそもワトソンは何をしたかったのか
健康的な赤ちゃんを連れてきたら何にも育ててやる
I would feel perfectly confident in the ultimately favorable outcome of careful upbringing of a healthy, well-formed baby born of a long line of crooks, murderers and thieves, and prostitutes. Who has any evidence to the contrary?
とか
行動主義の立場から、人間に本能(instinct)は存在しない
As a corollary from this I wish to draw the conclusion that there is no such thing as an inheritance of capacity, talent, temperament, mental constitution and characteristics. These things again depend on training that goes on mainly in the cradle. The behaviorist would not say : "He inherits
his father's capacity or talent for being a fine swordsman.
みたいなサイキックな発言で有名な心理学者なんですが、ワトソンはそもそも何をしたかったのでしょうか。
実は、ワトソンもいきなりよくわからない発言を繰り返したのではなく、当時はやっていた心理学に、
もっと科学的に心理学しようぜ(大谷風)
と唱えたんですね。
当時の心理学、詳しく書くと1879年にドイツ人のWundt がライプツィヒ大学に世界初の心理学実験室を設立して、内観法(参加者に刺激を与えて感想を聞く)を用いて意識経験を分析することで心理学を確立しようとしました。
しかし、ワトソンは内観法の主観性と不確実性を批判し、もっと客観的で科学的な心理学、つまり測定可能・再現可能な心理学を模索しました。
内観法に依拠したふわっとした意識現象の研究ではなく科学をしたかったんですね。
ですから、彼は、人間の心を「意識」や「本能」といった目に見えないものでとらえるのではなく、観察可能な「行動」に着目すべきだと主張したのです。
ワトソンの考え方は確かに極端なところもありますが、子育てを科学的に考える上でも重要なヒントがあったりするんですよね。
例えば、子どもの行動は、単に「性格」で決まるのではなく、周囲からの働きかけによって作り出されるものとか。
これは今でも当てはまりますよね。子供がどんな行動をするのかって周りの友人からの影響大きいですよね。
ということで、ワトソンらが唱えた行動主義のから学びのヒントを考えてみたいと思います。
ヒント1: 行動のメカニズムを理解しよう
子どもの行動には、必ず原因があります。例えば、泣き止まない赤ちゃんに、ミルクを飲ませると泣き止んだとしましょう。すると、赤ちゃんは「泣く→ミルクがもらえる」という学習をします。これが、ワトソンの言う「古典的条件づけ」です。
例えば、3歳の男の子が犬を怖がるようになったとします。公園で大きな犬に吠えられた経験から、犬を見ると怖がって泣き出すようになってしまったのです。
この場合、犬(無条件刺激)と恐怖反応(無条件反応)が結びついてしまっています。これを解消するために、犬を安全な刺激と関連づける「脱感作(脱条件づけ)」を行うことができます。
具体的に、まずかわいい犬の写真を見せて、お気に入りのお菓子を食べてもらうところから始めます。「犬の写真を見る→お菓子がもらえる」という新しい視点(用語は連合)を形成します。そして、少しずつ写真から絵本、ぬいぐるみ、動画と、犬のリアル感を上げていきます。
そして最後は、実際の犬を遠くから見せて、徐々に近づけていきます。その際も、お菓子を食べてもらったり、楽しい遊びをしたりしながら、「犬=安全・楽しい」というイメージを築いていくのです。
このように、恐怖対象を安全な刺激や快刺激と関連づけていくことで、恐怖反応を和らげ、場合によっては消去することができます。これは「系統的脱感作法」と呼ばれる行動療法の一種で、ワトソンの古典的条件づけの原理を応用したものです。
またさらに行動主義の考えはさらに発展し、「オペラント条件づけ」というものも誕生しました。例えば、子どもがお片付けをしたら褒める、ご飯を残したら叱るといったように、行動の後に与える働きかけを変えることで、子どもの行動を望ましい方向に導くこともできます。このことについて別の記事で紹介しますね。
(注:オペラント条件付けはワトソンの後に登場するソーンダイクとかスキナーという研究者が開発しました)
何を言いたいのかというと、こうした報酬メカニズムを理解することで、子どもにやってほしい姿に対して適切に働きかけることができるようになるのです。子育ては、行動のメカニズムを味方につけることから始まると言っても過言ではありません。(しかし、子育て進行中・教育関係者は現実はそんなに甘くないってものよく知っています)
<参考:古典的条件付けとオペラント条件付けの違い>

ヒント2: 言葉の力を活用しよう
教育や子育ての中で、言葉は強力なツールになります。ワトソンは、言語を行動を制御するものとして重視しました。
ここから言えることは、例えば、頑張って片付けをしたら、「よくがんばったね!」と具体的に褒めると、「頑張ると褒められる」という連合が形成されるみたいな感じです。「あなたは頑張り屋さんだ」と子どもの特性を肯定することで、自尊心を高めることもできますね。
ただし、これはワトソンの理論の裏解釈ですが・・・
行動主義の立場からは、「意味」を観念の問題として扱う必要はない。
という激しいことも言っています。これは先の記事で紹介したヴィゴツキーの考えとは真逆ですね。
意味は、思考と言語を統合する役割を果たしている by ヴィゴツキー
ここがワトソンの行動主義理論の限界として理解することが必要です。
人は言葉に無意識に反応するわけではありません。感情を持ち意識を持っています。だからこそ、子ども自身の言葉を引き出すことが大切なんです。
うまくいかないことがあった時、「どうしてそう思ったの?」と尋ねたり、「そういう気持ちなのね」と共感したりすることで、子どもは自分の感情を言語化できるように手伝ったりするのが重要なんですね。
共感する言葉を用いるってのが行動主義という屍を乗り越えて私たちが学ぶべきことなんでしょう。
まとめ 子育てと教育を科学しよう
今からすると「えっ」と思ってしまうような主張をしているワトソン。
そんな彼から私たちが学ぶことなんてあるのでしょうか。あるんです。
それは、子育ての科学的な理解に大きく貢献したという点です。
現代の認知科学は、さらに新しい知見を加えています。ニューロフィードバックを用いた脳科学ベースの教育や認知心理学の成果を取り入れ、より効率的な学びを追求など・・・
またワトソンの行動の個人差を遺伝的要因のみに帰すのは早計だと警鐘を鳴らし、養育環境の重要性を説いた点は高く評価されてもいいでしょう。
確かに遺伝子で決まってしまうところもありますが、幼児のころからなるべく学びにふさわしい環境を整えようぜ、と働きかけた姿勢には共感を覚えますよね。
ワトソン先生から学べること。
それは子育て・教育情報が氾濫する現代において、それN1サンプルの事例だよね、それポジショントークだよね、みたいな煽り系メソッドに毎日のように出会います。
そこでワトソン。徹底的に子育てや教育を科学しましょう。どのようにすればうまく行くのか、うまくいかない原因はなんだったのか、考える必要があると教えてくれるのです。
日本においてはともすれば職人芸みたいになっている授業とかありますよね。でも、いい授業にはかならず核心や形式があるはずです。それをマスターすれば職人の域には達せないかもしれないけど、ヒットを量産できるはずです。実はここが日本における授業教授法の苦手なところですけど・・・
さらに人を育てるのは理論通りにはいきません。
なんなら、うまくいかないこと前提です。でも、そこから学ぶことも多いはず。学習者の行動を観察し、行動のメカニズムを理解する。そして、学び手一人ひとりに合った関わり方を模索する。
ワトソン先生は、子育てや教育は試行錯誤の連続ですが、学び続ける姿勢があれば、必ず道は開けると教えてくれているのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
