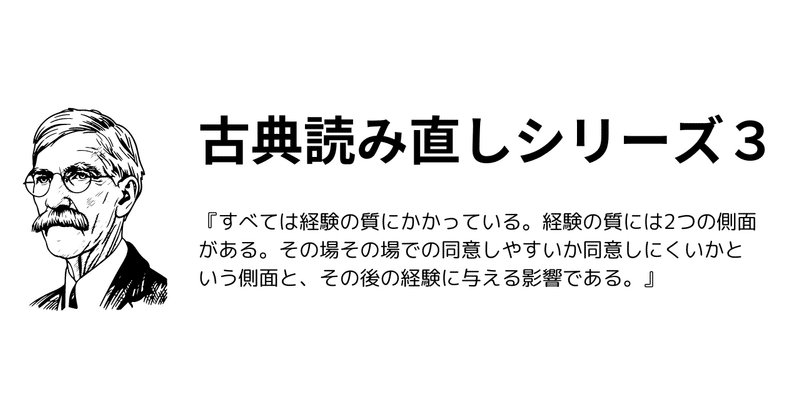
経験学習の本質とは?デューイに学ぶ「良質な学習経験」のヒント
昨今、教育現場や企業研修では経験学習の重要性が叫ばれています。対話主体学びや問題解決学習など、学習者の能動的な参加を促す教育方法への関心が高まっています。
しかし、体験学習とは単に学習者を何らかの活動に参加させればいいってものではありません。
そこで今回の記事は、Mr. 経験学習、20世紀初頭のアメリカの哲学者・教育者であるデューイの登場です。
デューイは、著書 "Experience and Education"(経験と教育)の中で、経験を通した学習の本質と意義について深い洞察を示しました。
本記事では、(主に)この "Experience and Education" に基づいて、経験学習の本質と意義について解説したいと思いますっ(力み)。
ところで、教育や心理学を学んでいる学生さんは授業で下の3つを(いやいや)読まされ、次の日には教育への熱意が冷めるかデューイという言葉を聞くのも嫌になってしまっているのではないでしょうか?
ということで、いきなり彼の思想を語る前に、そもそもこの人はなんでこんな経験学習重視になったのかってところから始めたいとおもます。
そして、デューイは今日の教育現場でも根強い人気を誇っているのですが、実際はめちゃ曲解されているんですよね・・・。
そもそもなんで経験学習なのか?
これを考える上で、当時のアメリカの状況を理解する必要があります。当時、20世紀初頭の米国では、
1 産業化と都市化の進展
2 移民の増加と社会の多様化
という社会構造がマジで変わりそう、という激動のなかにありました。
この記事は教育とか学びにフォーカスしているので政治的なことはさらっと触れるのですが、社会が変わりそうになると政治的な声も出てきます。
つまり、なんでもかんでもオートメーション・機械化されるようになると、人間とは?みたいな問いが出てくるもんです。そこで、主権とか主体性、権利という話になって、民主主義の理念に基づく社会の実現を目指す機運が高まり、教育もその一翼を担うものと位置付けられました。これをまるっと進歩主義思想と言ったりします。
あとは、ヨーロッパでも児童研究の発展 19世紀末から20世紀初頭にかけて、児童の発達や学習に関する心理学的研究が進展しました。例えば、フレーベルとかペスタロッチとかですね。ちなみに我らが宝『あんぱんまん』は1973年にフレーベル館刊行の雑誌に掲載れたものでございます。(駒込にあるフレーベル館社にはアンパンマン像があります。)
こんな時代背景のなかで、デューイは機械的な暗記を強いる旧来の教育を批判し、生徒の主体性を尊重した教育実践への転換を試みたのです。
今の日本社会ともかなり似ているので、そのことについて後日記事を書きます。
めちゃくちゃ誤解されているデューイの思想
たしかにデューイは経験学習を提唱しました。けれども但し書き付きなんです。
デューイの経験学習観の核心は、経験の連続性と相互作用の原則にあります。彼は、学習を単なる知識の獲得ではなく、経験の連続的な再構成の過程だと考えました。これは『学校と社会』のなかでも詳しく語られています。
経験の連続性とは、一つ一つの経験が過去の経験の上に積み重なり、未来の経験の質に影響を与えるという考え方です。したがって、教育的に価値のある経験とは、学習者の成長を促し、より豊かな未来の経験につながるものだということになります。
一方、経験の相互作用とは、学習者の内的な要因(態度、信念、知識など)と、環境の外的な要因(教材、教師、クラスメートなど)が互いに影響し合うことを指します。良い学習経験は、学習者の内的な要因と環境の外的な要因が適切に相互作用したときに生まれるのです。
ここ重要です。デューイは教育的に価値のある経験って言っているんですね。全ての経験が教育的とは限らないと指摘しているんです。
ある経験が学習者の成長を阻害したり、好奇心を損なったりする場合、それは非教育的な経験だと言えます。教師の役割は、学習者に教育的な経験を提供し、非教育的な経験を避けるような環境を設定することにあります。
さらに!
経験そのものを絶対視したわけではありません。経験を通して得た知識や技能が、体系的な教科内容と関連づけられ、意味づけられることが重要だと考えたのです。単なる活動主義に陥ることなく、経験の意味を捉え直し、反省的に検討することが求められます。
まとめると、
1 教育的に価値のある経験
2 経験を通して得た知識や技能が、体系的な教科内容と関連づけられ、意味づけられること(課外活動と授業内容が連動している必要あるってこと)
って言っているんですね。つまるところ、放任じゃないって、学生にやらせておわり、じゃないんですよ(何度も強調)。
どうでしょう?今の日本では結構、探究活動という名のもとにとりあえず外部団体に丸投げしておしまいって傾向多くないですか?
"Unless experience is so conceived that the result is a plan for deciding upon subject-matter, upon methods of instruction and discipline, and upon material equipment and social organization of the school, it is wholly in the air."
「経験というものは、その結果、教科の内容、指導と規律の方法、学校の物的設備と社会的組織について決定するための計画である、と考えられるのでなければ、まったく宙に浮いたものである」
まとめ: 本当に価値のある学習経験とは
わかります。
80年代の詰め込み教育からのゆとり教育失敗からの、じゃ、次はなんだ?って考えるの。
そこでいい塩梅に出てきたのが探究活動というこれまたフワッとした言葉だったんですよね。
しかし、デューイの経験学習の核心は、良質の学習経験を繰り返すというところなんですよね。
そして、この良質の学習経験を作り出すには、やっぱり先生が必要って言っているんです。ただし、教える側は知識の伝達者ではなく、学習経験の質を高める環境の設計者として専門性を高めなければいけないと。つまり、学習者の興味関心や発達段階を理解し、適切な教材や課題を選択・開発する力を身につける必要があるんですね。
デューイの経験学習論は、100年近く前に提唱されたものですが、その本質は色あせていません。学習者の経験の質を高め、成長を促すという教育の根本的な目的は、時代が変わっても変わらないからです。
良質の学習経験をいかにして子どもや学習者に提供できるか。
これは、親であれ、教育者であれ、研修の専門家であれ、決して避けては通れない、永遠の課題と言えるでしょう。
シリーズもの
関連のあるもの
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
