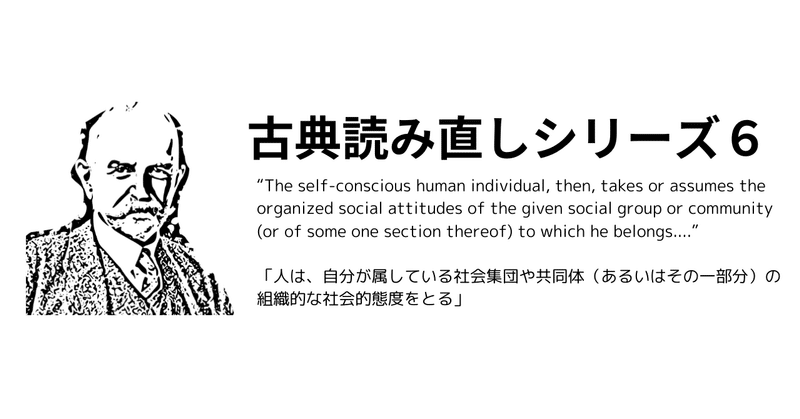
「地位が人をつくる」G.ミードの役割取得理論から学ぶ、子どもの成長と発達
地位が人をつくり、環境が人を育てる
「地位が人をつくり、環境が人を育てる」という故・野村監督の格言があります。
四番に据えれば、四番らしい風格や自信がみなぎってプレーにも好影響を与える。ヤクルト時代の古田敦也が好例。
この格言は、人間の成長と発達において社会的な役割や環境がいかに重要であるかを示唆しています。
実はこの考え、今から100年も前にG. H. ミードという社会心理学者・哲学者の著作"Mind, Self, Society"という本の中で展開された、社会的行動主義の理論とも深く関連しています。
ん、行動主義?今、行動主義という言葉にピクリと反応しましたね。
そう行動主義といえば、あの(今から考えると)とんでも論を展開したワトソン先生を思い出してしまいます。
しかし、ミードは、伝統的な行動主義の考え方では、人間の行動を十分に説明できないと考えました。彼は、人間の行動をより深く理解するには、社会的な相互作用に目を向ける必要があると主張したのです。
社会的な相互作用とか、成長する環境が重要という流れはデューイ先生に似ていますね。それもそのはず。ミードとデューイは大学の同僚で共同研究するほどお互いリスペクトしおておったそうです。
ミード先生の研究からめちゃくちゃ学ぶことが多いのですが、今回の記事では特に、彼の社会的行動主義の核心にある、「役割取得」という概念から、教育や子育て、そして学び成長することについて考えてみたいと思います。
人の気持ちになって考えてみる
役割取得とは、他者の態度や反応を想像し、取り入れながら、自分の行動を調整していくプロセスのことです。
よく言いますよね
人の気持ちになって考えてみろ
ってね。でも若干説明を加えると、人の気持ちになって考えてみるのと役割取得は違うんです。人の気持ちになって考えてみるというのは、あくまでも認知の問題でこれは(マニアックに話すと)「心の理論」というものになってくるんですね。
今回の役割取得というのは、あくまでも社会的な役割を取得することを通じて、自己を形成し、成長していくプロセスのことをさすのです。微妙に違いますね・・・。
さて、ここで、冒頭の格言を思い出してみましょう。
「地位が人をつくり、環境が人を育てる」というのは、まさに役割取得の重要性を表現しているのではないでしょうか。子どもは、家庭や学校、地域社会といった環境の中で、様々な役割を取得しながら成長していきます。親や教師、友達など、周囲の人々との関わり合いの中で、子どもは自分の役割を学び、社会性を身につけていくのです。
ミードの理論は、子育てを考えるうえでも重要な示唆を与えてくれますね。
子どもの成長を助けるには、役割取得を促進するような環境を用意することが大切なのです。本稿では、この概念を軸に、子どもの成長と社会性の発達について考察していきたいと思います。
役割取得と子どもの発達
子どもの成長において、「遊ぶこと」は非常に重要な意味を持っているっぽいんです。
役割取得とは、その状況に置かれた時に他者の態度や反応を想像し、取り入れることで、自分の行動を調整していくプロセスのことです。この何かの役をやることを通じて、社会性を身につけ、自己を形成していくのです。
でもよく考えたら、子どもってみんな役割取得してますよね。
例えば、ごっこ遊び。
何かの役割を模倣し、その人物の気持ちを想像することを学んでいます。例えば、お医者さんごっこをする子供は、患者役の友達の気持ちを考えながら、優しく接することを経験するでしょう(たぶん)。こうした遊びの経験は、子供の他者理解を深め、共感力を育てていくと言われています。
また、言語の発達も、役割取得に大きく関わっています。ミードは、言語を「有意味なシンボル」と呼びました。有意味なシンボルとは、自分と他者の両方に同じ反応を引き起こすシンボルのことです。子どもは、言語を通じて、他者の視点に立って物事を考えることを学びます。言葉を使ってコミュニケーションをとる経験は、子供の役割取得能力を大きく向上させるのです。
(実はここの考えを逆転・さらに発展させたのはBruner先生!)
家庭や学校など、子どもを取り巻く環境も、役割取得に大きな影響を与えます。親や教師との関わりの中で、子供は様々な役割を観察し、学んでいきます。大人が手本を示し、子供に多様な役割を経験させることは、子どもの社会性の発達を助けることにつながるっぽいです。
子どもは、その置かれた環境で自己を形成し、社会の中で生きていくために不可欠な能力を身につけ成長するらしい。遊びや言語、周囲の環境など、様々な要因が複雑に絡み合いながら、子どもの役割取得能力は発達していくのですね。
student-teacher method
例えばこんなこと
子どもたちの自己発達は、社会性の発達と密接に関連しています。
ミードは、自己を「I」と「me」の弁証法的な関係として説明しました。弁証法って聞くと、ヴィゴツキーにつながりそうですね。「I」は、自己の主体的な側面を表し、「me」は、他者の態度を取り入れた、客体的な側面を表しています。子供は、「I」と「me」の相互作用を通じて、自己を形成していくのです。
子どもの自己発達において、重要な役割を果たすのが「一般化された他者」の概念です。一般化された他者とは、社会的な規範や期待を表す、抽象的な他者のことです。子どもは、家庭や学校、地域社会など、様々な集団の中で、一般化された他者の態度を内面化していきます。つまり、社会の規範や価値観を自分の中に取り込み、社会性を身につけていくのです。
例えば、学校という集団の中で、子供は「よい生徒」としての一般化された他者の態度を学びます(この「よい」という定義は議論の余地がありそうですが・・・)。時間を守る、先生の話を聞く、宿題をきちんとするなど、学校生活というか社会生活に必要な規範を内面化することで、子どもは自己を形成し、社会性を発達させていくというのです。
これは私が今から12年も前にやっていた授業実践なのです。Student-Teacherという方法論です。
何をやっているのか、というと、
僕の代わりに先生やってよ
というものです。
授業の順番としては、ざっくりと
1)授業の目当てを提示
2)内容解説(10分超えてはダメ)
3)実践演習
4)ココ! 課題を理解し、早くできた人が先生になる
ポイントは、握手などして役割委譲の儀式をすること。儀式が重要。
ちなみに、僕は100均で買ってきた腕章に"master"と書かれた紙を入れてつけさせました。

5)先生役の生徒がわからない生徒に教えていく (<help>マークとして机の上に色付き紙コップとかを置いておくのもあり)

先生役の生徒が何人かを集めてコーナーを作って解説もあり。こういうのを使うと便利。窓とか壁に貼ってプチ授業するといい感じになるよ。
6)生徒はちょっとわからない生徒を教えて、先生である私は「本当にわからない」生徒にベッタリつく感じ。(←これめちゃくちゃ重要)先生は遊んでいるわけではありません。放置プレー厳禁。
7)まとめで授業おわり<雑>
ちなみに、こういうふうに「わかる」生徒と「わからない」生徒がミックスされているとヴィゴツキーのいう最近説発達領域が力を発揮し、ジグゾーとかがやりやすい。だから僕はあまり習熟度別っての好きじゃないんだよね。習熟度別やるんだったら、時にはミックスさせるクロスファンクショナルなクラス設計が重要。
ヴィゴツキーのもう一つの用語、MKO(More Knowledgeable Other)<自分よりちょっと知っている他人>というのもポイントっす。
ただし、自己の発達は、単に<こうあるべき>社会の規範を受動的に取り入れるだけではありません!ミードは、自己には創造的な側面もあると指摘しています。
上の例で言うと、あえて先生役を生徒にまかせることで、「わからない他人への共感」とか「わかりやすく伝えるって難しい」とかいろいろなこと感じるようになります。
生徒たちは、クラスメートの態度を内面化しながらも、同時に、自分なりの個性を発揮し、時には先生(上では私)の規範(教え方とかルール)に挑戦することもあるでしょう。こうした創造的な自己の表現が自己成長のエネルギーとなるんですね。
子どもの自己発達と社会性の発達は、<受け身>と<創造>の表裏一体の関係なんです。他者との関わり合いの中で、子どもは自分の役割を見出し、社会の一員としての自覚を深めていきます。同時に、自分らしさを大切にし、創造的な自己表現を試みることで、自己を確立していくのです。
まとめ
はい、ということでミードの社会的行動主義は、子どもの成長と発達を考えるうえで、重要な示唆を与えてくれます。
彼は人間の行動を理解するには、社会的な相互作用に目を向ける必要があると主張しました。特に、「役割取得」の概念は、子供の成長を考えるうえで、非常に有益な視点を提供してくれますね。
おさらいですが、役割取得とは、他者の態度や反応を想像し、取り入れることで、自分の行動を調整していくプロセスのことです。子どもは、遊びや言語、周囲の環境との関わり合いの中で、<自分とは>という理解をしていきます。
よくこれからの時代、先生は教えるだけでなく、ファシリテーター、コーチの役割をしなければならないって言われますね。
私は昔からこれに加えて、プロデューサーの役割も重要ですよって言っています。プロデューサーって聞くと、なんか作らなければならないのか!仕事増やすなって一瞬イラッとしますね。(すいません)
私が言っているプロデュースというのはめちゃ簡単で、上で紹介した「先生」になってもらうとか、そいうことです。なんでもいいんです。「生徒会長」でも「班長」でも。そいういう、役を用意してあげることがいいみたいと言っているのです。授業外では結構あるのですが、授業内でも役を作ってあげると授業内・外の境目が曖昧になっていい感じとなります。
子育てにも同じことが言えます。親としてできることは、役割取得を促進するような環境を用意することが大切です。遊びや対話を通じて、子供が多様な役割を経験できるようにしたり、家で「テーブルを拭く当番」とか役を与えたり。日常で豊かな言語環境を提供し、子供の言語発達を支えること。そして、子供の個性と社会性のバランスを大切にしながら、成長を見守ること。こうした点に配慮しながら、子供の成長を支えていくことが求められるでしょう。(かなーり理想論ですが・・・)私の場合、「テーブルを拭く当番」を割り当てているのにも関わらず、子どもに無視されてがっかりしたりしますがwww
いずれにせよ、ミードの社会的行動主義、子供の成長と発達を、社会的な相互作用の中で捉えるという視点は同意しちゃいますよね。
かの有名なシェイクスピアもいっています。
この世はすべて ひとつの舞台、男も女も 人はみな役者に過ぎぬ。
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players:
人生という舞台で、私たち一人一人は様々な「役」を演じる俳優・女優です。
子ども時代から大人になるまで、家庭、学校、職場など、様々な場面で「役」が与えられてきてますよね。
「役」を演じるとは、他者との関係性の中で自分の立ち位置を見つけ、期待される行動を取ることです。「役」を演じる機会が多いほど、私たちは多彩な経験を積み、社会という大きな舞台で活躍できる大人へと成長していくのです。
ミードの役割取得理論は、「役」を演じることが成長するための重要な要素となると説いています。
教育現場で教える者や子育て中の親、または会社で研修担当する者として、学び手がより多くの「役」を経験できるよう支援することが、彼らの成長を助ける鍵となるのですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
