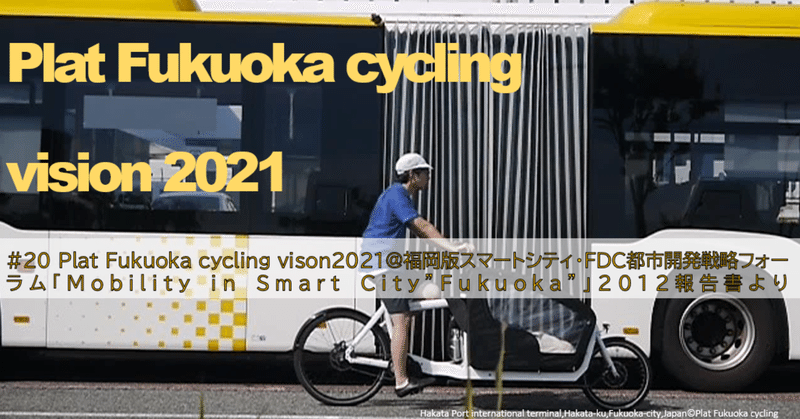
#20 Plat Fukuoka cycling vison2021@福岡版スマートシティ・FDC都市開発戦略フォーラム「Mobility in Smart City”Fukuoka”」2012報告書より
Plat Fukuoka cyclingは福岡がbicycle friendlyな都市(まち)となるための様々な提案を行っています。
bicycle friendlyというと「自転車にやさしい都市」となると思いますが、私は「自転車がやさしい都市」になってほしいと考えています。それは歩行者に対しても、バイクやバス、自家用車…つまりは都市に対して、自転車がやさしくできる都市でありたいと思うのです。
これまでのPlat Fukuoka cyclingは下記の目次よりリンクしていますので、ご覧ください。
0.Plat Fukuoka cycling vision
1.Copenhagenize Index2019を読む
2.Plat Fukuoka books&cycling guide
3.Plat Fukuoka cargobike style
4.Fecebook ページ
5.Instagramページ
6.twitterページ
7.Plat Fukuoka cyclingの本棚(リブライズ)
---------------------------------------------------------------------------------
当サイトで最も読まれている#07デンマーク・コペンハーゲンのスマートシティにて、デンマークでのスマートシティの定義「住みやすさと持続可能性、そして繁栄の実現を目的として、革新的なエコシステムに市民の参加を可能とするしくみを構築し、デジタルソリューションそのものよりも、市民にとって福祉と自足的な成長の手段」の1つとして、自転車の活用があり、行政が積極的にインフラ整備を行い、いまのデンマークのコペンハーゲンのような自転車都市が構築されているということお伝えしました。
Plat fukuoka cycling vison2021ではbicycle friendlyな都市となるための見通し(vision)、としてそのための戦略を考える連載になります。
これまでは、福岡以外の地域の記事や論考からの考察でしたが、今後は福岡という地域への考察をより深めていきます。
福岡の都市交通において、特質すべきはバス交通の充実です。福岡市が地下鉄を建設するまで、福岡市の主要な移動手段はバスでした(1)。
今回は、注目すべき「バス」と「自転車」に関する世界経済フォーラムの報告書に関する記事と、福岡市のシンクタンク的存在である福岡地域戦略推進協議会(以下「FDC」という。)が、設立草創期に実施したバスをはじめとした都市交通をテーマとした都市戦略ワークショップについて紹介しつつ、福岡に必要な都市戦略について考えます。
◯自転車とバスが担う都市交通の未来「Bicycles And Buses Will Be Future’s Dominant Modes Of Urban Mobility,Predict 346 Transport Experts」(Carl Reid『forbes(http://www.Forbes.com』2020.10.9)
Transport for Under Two Degreesプロジェクト( T4<2°プロジェクト)は、ドイツ政府が世界経済フォーラムなどと協力し、報告書をまとめています。今回の記事は、その報告についての記事になります。
---------------------------------------------------------------------------------
(以下はリンクサイト:https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/10/09/bikes-and-buses-will-be-futures-dominant-modes-of-urban-mobility-predict-346-transport-experts/?sh=6f7233871b03
の内容を知人で国際経験豊富な横田美香さんの協力の上で意訳しております。転載等する場合は本サイトのプライポリシーを参照ください)
Bicycles And Buses Will Be Future’s Dominant Modes Of Urban Mobility, Predict 346 Transport Experts
自転車とバス交通が将来の都市交通の主軸となるという346人の交通専門家の予測
世界経済フォーラムが支援する1つの重要な報告書は、地球全体の利益であるパリ協定の脱炭素化のためにも「交通変革」が起きなければならないと主張しています。Transport for Under Two Degreesプロジェクト( T4<2°プロジェクト)は、10月8日に、Way Forward(成功への道)報告書を発表し、世界中の政府が自動車への助成をやめ、代わりに、都市での「アクティブな交通」の魅力的な将来を見越して自転車道と広い歩道を建設する必要があると主張しました。
公共交通機関の利用についても促進する必要があり、ドイツ外務省が委託し、ベルリンを拠点とするシンクタンクAgoraVerkehrswendeと連邦コンサルタントサービスのGIZが作成したT4<2°プロジェクトを推進しています。
Way Forward(成功への道)ー2年間の道のりーはこれまでの調査と、企業、NGO、国および地方自治体を含む交通およびエネルギー部門の56カ国、346人の国際的専門家への新しい定性分析インタビューと追跡アンケートに基づいて作成されました。
ドイツ外務省のエネルギー及び気候政策担当ディレクターHinrich Thölken氏は報告書の序文で「調査が強調するように、交通部門における脱炭素化は重要であると同時に、技術の進歩と国際的なガバナンス構造を考えると実現可能」と強調しています。
・コロナウイルスによる影響について
Way Forward T4<2°報告書では、「COVID-19への対応は、モビリティセクターに体系的な変化の可能性を示している」とし、大規模なロックダウンにおける自動車の大幅な減少が、変化の可能性を示したことを認めています。
現在報告書は「交通分野のガバナンス構造をよりサスティナブルで、回復力があり、効率的で包括的なシステムに向けて調整する機会」であると追記され、世界中の政策立案者が交通システムの脱炭素化を検討すべき10項目の「重要な視点」に焦点をあてています。
その視点は、例えば太陽光や風力によるエネルギー転換によってのみ、交通分野の脱炭素化が実現可能というものなどで、全く目新しいものではありません。しかし、都市や農村部の移動が30年度どのようになるかという予測は、自動車に依存したままの人々にとっては衝撃的なものとなるでしょう。
専門家は、将来の都市での個人的な自動車の使用はサスティナブルなものではなく、政策立案者は都市環境から自動車を取り除くために法整備をする必要があると言います。これが実現された場合、専門家の大多数は、運輸部門の完全な脱炭素化が世紀半ばまでに可能であると信じています。
しかしながら、巧みな(技術的・法整備的などの)調整は忘れてください。専門家は技術的な解決策ではなく、人々が地球を破壊する交通モードをからの切り替えを余儀なくされるということに圧倒的に同意しています。
AgoraVerkehrswendeのディレクターであるChristianHochfeld氏はデジタル調査開始時に「社会問題に対する技術的解決策はありません」と述べています。声明の中で、「パリ(協定)の目標に準拠したビジネスモデルのみが、将来性がある」と付け加えました。
・ドローンの可能性について
専門家のほとんどは、燃料の使用を阻害するために燃料に対して税金を引き上げる必要があり、燃焼エンジンの段階的廃止も加速させる必要があると考えていますが、電気自動車やドローンが渋滞やその他の都市の問題を解決するとは考えていません。「ユニットまたは乗客1人あたりのエネルギー消費量が多いことを考えると、ドローンはニッチなテクノロジーであり続けるでしょう」と調査した専門家は述べています。
そして、報告書では、最初の緊急措置として「現在化石燃料補助金に費やされている公的資金の新たな方向づけをすること」を述べています。
また報告書では、気候変動に配慮した都市交通の重要な要素は「公共交通、アクティブな交通手段、シェアモビリティー及び、サスティナブルな都市計画」であり、加えて公共交通への投資とともに、自転車や歩くことを促進することを優先すべきと述べています。
・自動運転の自動車について
テスラの創業者の1人Elon Musk氏はいまは目を背けているが、世界の交通専門家は、自動運転車(AV)が2050年までに大量に普及するとは考えていない。さらに、政府は「都市のスプロール現象による自動運転車の輸送量とエネルギー需要の増加による潜在的な悪影響」を懸念し、自動運転車の使用の推奨をすべきでないとしている。
専門家によると、これは自動運転車に対する「政治的ガバナンスの必要性を証明している」ということであり、つまりは、特定のシナリオ以外の利用機会は法によって制限されるべきということです。
ある交通経済学の教授は「肝心なことは、人を運転席から出すだけでなく、車から連れ出すこと」と報告書で述べています。「新しいテクノロジーとモビリティ・ソリューションは、政策立案者がモビリティの行動様式の変化にも焦点を当てている場合にのみ、脱炭素化の可能性を最大限に引き出すことが可能」と専門家は強調します。 これは、「自動車のスペースを減らし、自動車を完全に禁止する、またはより効率的な交通モードを優先する」ことによってもたらされると報告書は述べています。
・モーターダム
『Fighting Traffic:The Dawn of the Motor Age in the American City』の著者でもあるPeter Norton氏は報告書発表時の基調講演の中で、氏は、1920年代から、自動車会社や自動車協会が30年間で都市の街路を占領したことを「モーターダム」と名づけ、それらが路面電車やバスなどの公共交通機関に勝利したのがどうかは定かではないと述べています。
そして、氏は「モーターダムは、多くの間違いを犯し、多くの行き詰りに遭遇しました。この間違い研究し、それらから学びを得ました。これは、世界史上最も成功した輸送革命でした。そして、私たちはそれらから学ぶことがたくさんあります。まず、エンジニアリング、政策、社会規範の変化を別々に追求することはできない。1人で追求されたそれぞれは、他の2人に打ち負かされます。3つすべてを統合し、一緒に追及する必要がある」と述べています。
バージニア大学工学社会学部歴史学の准教授は「私たちは変化を、制約や選択の喪失としてではなく、解放として、選択肢の拡大として提示していかなければならない。そして、再びサイクリングとウォーキングが優先されるべきとし、最も持続可能で包括的なモードは対応すつのが最も簡単で、少ない資金で対応できるものだ」と代表団に述べました。
T4<2°プロジェクト報告書では、バスやトラムは再評価され戻ってくる。そして先進国の専門家の82%、発展途上国の専門家の96%が、2050年の脱炭素化された都市の移動において、公共交通機関が支配的なモードになると報告しています。
自転車は2番目に重要な交通手段であり、専門家の50%は、30年内にほとんどの都市で自転車が主要な移動手段になり、またウォーキングは多くの人にとって、重要な移動手段であり続けるだろうと述べています。
また「交通問題以上に、サイクリングとウォーキングの両方が、人びとに大きな健康上の利点を提供し、いわゆる生活習慣病の社会的コストを下げることができ、持続可能な開発に大きく貢献するだろう」と報告書は述べています。
専門家は、「世界中のいくつかの都市が、道路と駐車スペースの両方で、自動車のスペースを減らし、より効率的で持続可能なモードに再配分し始めている」と前向きにとらえています。
Carlton Reid氏
(Forbes.com, The Guardian, BikeBiz.comライター
roadswerenotbuiltforcars.com, bikeboom.infoの編集者)
(意訳はここまで)
---------------------------------------------------------------------------------
この記事で、日本で進んでいるスマートシティにおける選択肢である自動運転やドローンといったものが、すでに欧米では、気候変動対策上必要とされておらず、むしろ規制の議論までされているのです。
記事のとおり、欧米でのスマートシティは公共交通を主軸したサスティナブルな都市計画と、加えて自転車や歩くことが優先されるまちづくりを取り入れていくということ(2)です。つまりは、これらが2050年における先進国の都市像の新たな定義であり、そうでない国は、発展途上国となるということを示しています。
気候変動対策は、単なる地球環境の維持という次元から、今後は国際的な駆け引きの上でも重要になってくることが予見されます(3)。これまでの先進国の定義が、気候変動対策で大きくシフトする時、それにいかに対応できるかが、今後の国際的な都市間競争で、重要になってくることがわかります。
では福岡でPlat Fukuoka cyclingがvisionとして上記の記事の指摘をどのように戦略として具現化していけばよいのか。ここで、福岡市で10年前に開催されていたひとつのフォーラム報告書を紐解くところから始めていこうと思います。
○FDC設立草創期に行われた『Master Class Fukuoka2012 Transportation&Mobility』にみるポスト・コロナの都市開発戦略
『Master Class Fukuoka2012 Transportation&Mobility』は、福岡地域戦略推進協議会(FDC)(4)と、欧州都市デザイン(Stadslab)というオランダのフォンティス大学の独立研究機関が欧州外で初めて展開して実現した共同研究プログラム(5)です。
設立間もないFDCとStadslabは2011年から、福岡の新たなビジョンと戦略の立案を行うべく、実務研修として、Master Classを開催。このMaster Classは2011・2012年の2回実施されています。
ここで、2011年7月の第1回のワークショップにて、福岡の都市開発の5つの原則と提案が明示されています。
福岡の都市開発の5つの原則
□Connectivity/つながり □Accessibility/たどりつきやすさ
□Legibility/わかりやすさ □Imageability/イメージのつかみやすさ
□Walkability/歩きやすさ
提案の3つのポイントと期待される効果
(1)福岡都市圏全域の移動(モビリティ)の質の統合
・鉄道、地下鉄、バス、水上交通の統合された「福岡版スマートシテ
ィ」における交通ネットワーク
→域外とのConnectivity/つながりの改善:福岡の優れた陸路、海路、
空路との接続の最大限の活用
(2)都市開発を誘導する公共交通軸の形成
・主要施設へのAccessibility/たどりつきやすさの向上と都心の成長の方
向づけ
→移動の質の向上:交通空白地や道路混雑の改善
(3)交通体系改善に向けた意思決定
・バス交通軸に限られた公共施設立地やインフラ整備
→都市開発の誘導:公共交通軸に沿った開発投資の集中と最適化
2012年のMaster Classでは、福岡の交通戦略におけるバス交通について、ストリートのデザインを含んだ提案が行われました。世界経済フォーラムの記事のとおり、将来の先進国は、公共交通が主軸となる必要を指摘しています。2012年のMaster Classの報告書には、福岡におけるバス交通の現状を下記のように分析しています。
我々の分析ならびに見解によると、福岡の公共交通ネットワークは、バスについて考え直すことで、市民にも来訪者にとっても、さらに効率的で、信頼性のある、快適なものにすることが可能である。西鉄がすばらしいバスのストックを有しており、福岡はバスの都市と自認しているかもしれない。しかし、逆に言うと、都市の規模と密度を考慮すると、路上のバスの多さ(6)は福岡の強みではなく、弱みを指し示している。
分析では、福岡の交通におけるバスの役割が、他都市を比較しても小さく、かつラッシュアワーの時間帯でも低い乗車率、そして、都心部でのバスの運行密度と郊外部でも大きな差はアンバランスであり、都心部の運行密度が高すぎることで、バス自体により交通交雑を発生させてしまっていると分析しています。その上で、Master Classでは下記の提案として、今後の福岡のバス交通の方向性を示しています。
市民と来訪者の両方に優しい、統合型の公共交通ネットワークを形成するため、幹線-枝線型にバスネットワークを再構築する
幹線・枝線の概念
・幹線:地区間のコネクティビティ向上(交通軸を走行)
・枝線:地区内のアクセシビリティを向上
・8本のバス交通軸による幹線-枝線バスネットワークの要点
(1)バス交通軸へのインフラ整備と公共交通優先制御
(2)運行の効率化によるバス走行台数の削減と走行速度改善
(3)ダイヤ調整、乗換施設の改善によるスムーズなの乗換
(4)バスネットワーク全体の運行改善と利用者満足度の向上
※バス交通軸(コリドー)はバス専用レーンないしはバス専用道を有し、バス優先の交通制御がなされる道路と定義。
※今回の提案は統合的な公共交通ネットワークへの改善に向けて、バス交通軸の概念を提案。路線の提案は次の課題。
提案はこれまでの各地から福岡都心部にくるバス路線を、途中の中継箇所で集約して、都心部に入るバスをバス渋滞のなく、一定間隔で定時制を確保し、効率的な運用のための全体スキームを示しています。報告書では、当時の福岡の幹線道路における1時間当たりのバス台数は60~70台程度、つまり、1分に1台バスが通過していることになり、過密であり、乗車率も低いことを課題視。バス幹線の集約で、都心の幹線道路の1時間当たりのバス台数を12台、つまり5分に1本の程度と効率的な運行が実現する。
我々の考えでは、都心部はバス専用道持つバスの軸線を走る8路線から10路線でカバーされうる。バスの軸を形成するための道路や交通制御の改善は、ITを活用した情報提供や十分な広さを持つバスの待合空間、自転車道、歩行空間の改善とともになされるべきである。また現在、自動車走行に供されている車線を片報告に1車線ずつ、バス専用道ないしはバス専用レーンへと転換されるべきであろう。空間に余裕のない場所やバス専用道以外に優先すべき施設が存在する区間については、例外的に考えることが必要であるが、現状の道路空間は、この改善を行うには十分であり、新たな用地の取得は必要としないと考えられる。
Covid−19により、日本全国の公共交通機関は利用者の大幅な減少と回復が遅れており、経営危機に直面しています。グループで日本一のバス保有台数の西鉄も状況は厳しく、不採算事業の撤退など経営の合理化を進めています。
福岡市の交通計画では、公共交通を主軸とする旨の明記(7)もあり、方向性は定まっています。一方で、抜本的な交通体系の見直しには、政治的な駆け引きにもなることもあるでしょう(8)。
○交通をめぐる政治的な駆け引きを乗り越えるためのリーダーの資質について『ストリートファイトー人間の街路を取り戻したニューヨーク市交通局長の闘い』(学芸出版社、2020.9)
Plat Fukuoka cycling vision2021@『ストリートファイトー人間の街路を取り戻したニューヨーク市交通局長の闘い』(学芸出版社、2020.9)よりにて、自転車レーンや自動車車線の削減などの政策での壮絶なメディアの反対などに対して、地域への地道な説明会や調整を指揮したニューヨークの交通局長サディク=カーン氏は、リーダーの資質についてこう記しています。
リーダーに求められる資質は、変化に伴って見舞われる批判の嵐に立ち向かう決心、度胸、気概である。(中略)何もしないことの理由は無限に存在することを、私は身をもって学んだ。しかし、何もしないことを許してはならない。私たちの都市が成長するために、リーダーや市民は機能不全に陥った街路を受け入れることはできないのだ。で、あれば、彼らは街路の変革のために闘わなければならない。言ってしまえば、その改革を勝ち取るための闘いは私たちの任務の一環に過ぎない。(9)
当時のニューヨークは、大富豪から市長となったブルーム・バーグ氏でした。ブルーム・バーグ市長がサディク=カーン氏を交通局長として採用したたのは、市長就任から6年目の2期目の2年目の時期でした。バーグ氏が市長でなかった場合、自転車レーンをめぐる駆け引きや、ストリートの改革などは、実現しなかったのかはわかりませんがブルーム・バーグ市長のこの言葉で締めようと思います。
「私は、行政局長たちに、政治カレンダーに従ってやるべきことをするように頼んではいない。正しいことをする、その一点のみ託している」(10)
この発言は市長として第3期の選挙を控え、タイムズスクエアとヘラルドスクエアのリノベーションの意思決定する際のやり取りとのことです。
「忖度」なることを一切排除し、正しいことをスピード感をもって進めたブルーム・バーグ市長らしい言葉です。
引き続き、Plat Fukuoka cyclingはPlat Fukuoka cycling visionとして、『Master Class Fukuoka2012 Transportation&Mobility』の本編の読解を進め、10年前に託された報告書を紐解いていき、福岡の進むべき方向を提案していきます○
---------------------------------------------------------------------------------
〈参考文献等〉
(1)福岡市は、1982[昭和56]年の地下鉄開業するまで、離島航路以外の交通事業はもっておらず、市内主要な交通手段であった路面電車とバスは西日本鉄道、つまり民間企業が担っていました。地下鉄開業後、現在は交通局として地下鉄事業のみ行っています。確かに福岡市の地下鉄は、市の移動手段の約17%(2021年3月『福岡市自転車活用推進計画』P7参照)を占めていますが、部署名に「交通」という名を関する組織が、たった17%の移動手段の事業しか行っていないことから、一部の交通手段を所感しているだけであって市の交通を担う局なのか、「地下鉄局」の方が、正しいようにも思います。
(2)#12Plat Fukuoka books&cycling guideコンパクトシティ政策を進める ドイツの都市・交通計画と自転車政策@かどや食堂にて、自動車に頼らないドイツの都市・交通計画にて、紹介しています。都市のこれ以上の拡張は、公共インフラの負担が増え、かつ不動産市場の供給が増えることで、既存エリアへの建物の共同化や高密度化を阻害し、密度の低い都市を形成することにつながります。これは都市政策全般に共通する課題で木下斉氏も「地方再生に求められる「供給抑制型成長戦略」(note2021.6.23)にて、指摘しています。自動運転やドローンは、公共交通がなくなった郊外住宅地や山間部の交通手段などの代替手段(一時的な救済)にはなりえる一方で、自動運転やドローンがあるから、都市政策として、都市を縮小していく政策プロセスの検討をする必要がないというような都市政策に至る危惧をも感じます。記事のとおり「政治的なガバナンス」がどこまで機能できるかが鍵となるでしょう。
(3)竹内昌義氏が「あり方委員会第4回を終えて。 中間の感想です。」(note2021.6.26)にて、住宅の省エネルギーとエネルギーの関係の話で、欧米諸国と中国との対立の中で、G7は中国の国際的な枠組みの弱点である温暖化対応クイックにできないことを念頭に、西側諸国はその優位性を常に示しつつ、対抗するだろうと述べています。そしてつまりはG7の一員である日本も、今後よりCO2の排出削減に対する外交的プレッシャーが高まることになる。現在の日本国内の経済界の顔色を伺いながらの内政的な政策を続けていると、いずれ国の経済するら犠牲にしなければ、国際的に生き残れない、つまり国といて生き残れなくなるだろうと述べています。
(4)FDC(福岡地域戦略推進協議会)は2011年に設立された産学官民で構成される福岡地域の成長戦略の策定から推進までを一貫して行う任意団体。FDCの成果と展望については、現事務局長の石丸修平 著『超成長都市「福岡」の秘密―世界が注目するイノベーションの仕組み』(日本経済新聞社、2020.2.18)にて、電動キックボードや連節バスについて記載されています。
(5)ワークショップは、Fontysのサイトhttps://fontys.edu/Stadslab-European-Urban-Design-Laboratory/Projects/2013-Fukuoka-Japan.htm。もしくは、FDCの都市開発戦略フォーラム|レポートにて公開されています。(6)鈴木文彦 著『西鉄バスのチャレンジ戦略』(交通新聞社新書2020.8.17)の本の帯に「今も昔もバスが数珠つなぎ・・・。その理由は?」というブラックジョークもありますが、西鉄バスの様々な経営戦略を読むことができます。
(7)福岡市の交通戦略として2015年に「福岡市総合交通戦略(福岡市地域公共交通網形成計画)」を策定しています。FDCはこの計画策定における協議会のメンバーとして参画しています。当時のプレスリリースはこちら。
当時のプレスリリースのリンクは切れてしまっていますが、福岡市の都市計画・都市交通のHPにて公開されています。
(8)『Master Class Fukuoka2012 Transportation&Mobility』の提案であるバス路線の拠点集約、幹線強化を実行した事例は、新潟市の新バスシステムです。公設民営方式で、市が幹線であるBRT乗継停留所、連節バスなどのハードを整備し、民間バス事業者が運営しています。乗継時間の短縮や、利用者への周知が図られ、新潟市内のバス利用者の減少に歯止めをかけ、増加に転じるなどプラスの成果の一方で、乗継の抵抗感や交通だけでなく都市戦略とのつなげ方で課題も見えた事例です。一時はBRT自体の存否を問う政治的な問題にも発展し、注目を集めました。この動きについて#03Plat Fukuoka books&cycling guideフランスの都市交通政策を読む@ボンジュール食堂で紹介した『なぜフランスの地方都市は』の著者ヴァイソン氏は、ブログにて、公共計画における自治体の向き合い方について、下記のように指摘しています。
ストラスブールの交通政策部長が「いつでもどこでも利害が対立するのが公共計画というものだから、明確な都市づくりのヴィジョンを持って、反対派に地道に説明する努力が必要だ」とおっしゃっていたのが、私の記憶に残っている。またその説明努力に、市長やトラム局長がこまめに公開討論や地区説明会に足を運んでおられていた。「住民は計画責任者の言葉を待っている」と。「ストラスブール市では一時期、本当にまちのどこかで毎日のように公開ヒヤリングがありました。」都市交通計画の殆どの整備及び運行資金に公金を投入するフランスと、日本では当然事情も異なるが、合意形成のあり方、反対意見の建設的な採用等、考えさせられることの多いインタビューであった。
https://www.fujii.fr/actualites/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e6%96%b0%e6%bd%9fbrt%e3%81%9d%e3%81%ae2/
と述べるように、リーダーによる責任ある説明を地道に行う努力が必要と述べています。どちらか言うと事前調整で動かしようのないほどプランが固まってから情報がオープンになりがちな日本ですが、意見の集め方から、市民とのコミュニケーションの方法まで、取り組めるかが、特に様々な利害や意見がある交通政策において求められると思います。
木下斉氏はnote読み放題聴き放題マガジン「狂犬の本音」2020年10月30日「公民連携時代、地域活性化を促進する上で求められる地方議員の立場と姿勢。」にて、議員(特に地方議員)こそ、パブリックコメントなどを含めた様々な機会に政策立案そして実行まで役割が期待されるべきと述べています。
(9)ジャネット・サディク=カーン氏、セス・ソロモノウ氏共著『ストリートファイトー人間の街路を取り戻したニューヨーク市交通局長の闘い』(学芸出版社、2020.9)P17「はじめに」より抜粋
(10)(8)P117「6章 生まれ変わったタイムズスクエアー歩行者空間化への闘い」より抜粋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
