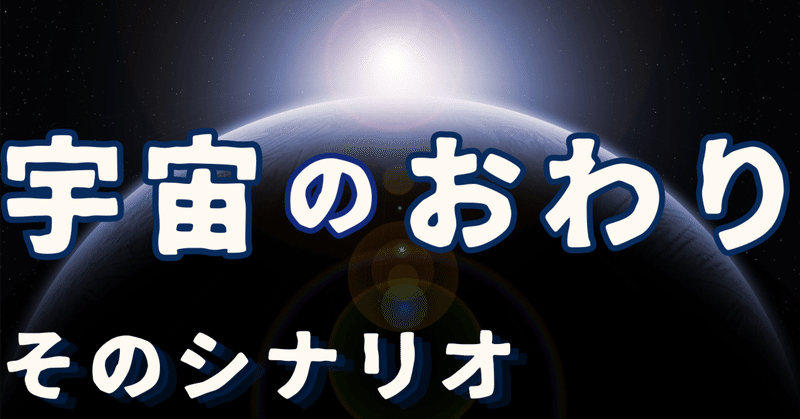
【解説】宇宙の終わり そのシナリオ
宇宙 その正確な大きさは 誰にもわからず
いまだに広がり続けていると言われています
そんな宇宙に いつかおわりはあるのでしょうかそれとも 永遠に存在しつづけるのでしょうか
もし宇宙が終わるとしたら...これにはいくつかの説があります今回は 宇宙のおわり そのシナリオ について
章ごとに話していきます
※動画版はこちら
1. 膨張する太陽
すべての星に終わりはあると考えられています
わたしたちが住む地球を明るく照らしつづける太陽
太陽は将来的に大きく膨れあがり
大きく膨れあがった太陽に 惑星は飲みこまれ
その後 太陽は燃えつき 死を迎える...そんな説があります
燃えさかる太陽のエネルギー源である水素
太陽の中心部にある水素は あと60億年ほどで尽きてしまうと考えられています
その後、重力による収縮によって中心部の温度が急激に上昇
これによって外側にあるガスが押し広げられ 大膨張がはじまるのです
20億年ほどかけて170倍ほどの大きさへ
この時の太陽の状態は「赤色巨星」と呼ばれています
水星と金星は飲み込まれてしまいます
膨張した太陽は地球まで届かないと予測されていますが
太陽の重力変動の影響によって 太陽系外に投げ出されてしまう可能性もあるようです
そこから20億年後
「赤色巨星」になった太陽は急激に収縮していき、現在の10倍程度の大きさまで戻っていきます
原因は中心部の温度が約1.5億℃に達し、ヘリウムが核融合反応を起こしはじめることです
この核融合反応で太陽の圧力は安定し
広がり続けていたガスは重力によって縮み
現在の10倍程度の大きさまで小さくなるのです
しかし 約1,2億年後
ヘリウムが燃えつきることによって 再び大膨張がはじまります
この時、太陽の大きさは現在の200倍から600倍になる可能性もあるといわれ
「漸近巨星分岐星」と呼ばれる状態になります
もし地球が太陽系外に投げ出されていなかった場合
太陽は地球を飲み込み 地球は終わりを迎えることになるでしょう
その後 太陽は膨張と収縮を何度も繰り返すと考えられています
その過程で 太陽を形づくってきたガスが宇宙空間に流れていくことで
太陽は小さくなり 地球程度の大きさの中心部だけが残されます
これが「白色矮星」と呼ばれる天体です
表面温度は1万℃を超え 白く輝くと同時に紫外線を大量放出します
この紫外線は周囲のガスをさまざまな色で輝かせます
このような天体を「惑星状星雲」と呼びます
どんな色で輝くのかは まだ解明されていません
しかし 輝く惑星状星雲は余熱で輝いているだけ
徐々に冷えていき 紫外線の放出は1万年程度で終わり
輝きを失ってしまうのです
残された白色矮星はさらに冷えていき
輝きをうしなったまま 宇宙空間に残されることになります
2. 闇に包まれる宇宙
アンドロメダ銀河と 天の川銀河
これらは数十個の銀河で構成された集団 「銀河群」 に属しています
約45億年後 ふたつの銀河は衝突、合体して ひとつの大きな銀河になると考えられています
この巨大銀河の重力は ほかの数十の銀河を引き寄せ
その結果 ひとつの「楕円形銀河」としてまとまっていきます
このような銀河の衝突、合体は 「銀河群」よりも大きい「銀河団」でも起きて
約1000億年後には ひとつの大きな「超楕円形銀河」へとまとまっていきます
この段階になると 超楕円形銀河からみえる範囲には ほかの銀河がひとつも存在せず
宇宙のなかで孤立すると考えられています
3. 恒星の世代交代の限界
自ら光を出して輝く天体は 恒星と呼ばれます
夜空にみえるほぼすべての星は恒星で 太陽も恒星のひとつです
そんな恒星にも いつかおわりが来ます
恒星のおわりには 大きく分けて2つのタイプがあります
1章でお話しした さまざまな色に輝く「惑星状星雲」を形成するタイプ
そして「超新星爆発」、いわゆるスーパーノヴァのタイプです
いずれも 恒星を形づくっていたガスが宇宙空間に広がり
それが新たな恒星の材料になり 恒星の世代交代がおこなわれます
しかし このような世代交代は永遠につづくことはありません
恒星の燃料が次第に宇宙から減っていくからです
燃料となる水素などの軽い元素がなければ
新たな恒星は生まれません
その結果 銀河は次第に輝きを失っていくのです
恒星は 質量が大きいほど寿命が短いそうです
例えば太陽の寿命は約100億年と考えられています
太陽の10倍の質量をもった重い恒星は 太陽よりもさらに強く輝き
3000万年程度で燃えつき おわりを迎えます
太陽と比べて8~50%の軽い恒星は 赤くて暗く、「赤色矮星」と呼ばれます
これらは宇宙で最も寿命が長く それは10兆年程度になると考えられています
やがて赤色矮星が銀河の輝きをにない だんだんと銀河は暗くなっていきます
最後には赤色矮星も終わりを迎え 宇宙は輝きを失ってしまうことになります
4. 消えていく天体と巨大化するブラックホール
恒星だけでなく 天体もいつかはなくなっていきます
銀河を構成する天体は つねに動いています
長い年月の間に まれに天体同士の接近遭遇が起こります
その影響で天体の軌道がかわり 一方は勢いをうしなって銀河の中心へ落ちていき
もう一方は勢いを得て銀河から離れていく、といったことが起きます
これが繰り返され 1垓(1超の1億倍)年後が経つ頃には
銀河から天体が消え去ってしまうのです
一般的に 銀河の中心には巨大なブラックホールが存在しています
その質量は太陽の100万倍から数百億倍にも達します
ブラックホールは落下した天体を飲み込み
その天体の質量の分だけ大きくなっていきます
銀河をはなれていった天体も いつかは消えていくと考えられています
天体を構成する原子にも寿命があるとされているからです
原子の中心には原子核があり 原子核は陽子と中性子の集合体です
陽子は安定している一方 中性子は不安定なため 単独だと15分程度で崩壊してしまいます
陽子はいつか崩壊する という仮説にもとづくと やがて中性子も崩壊し
天体を構成する原子が消滅していきます
陽子の崩壊には 1兆年の1兆倍の100億倍かかるという説もあり
これ以降にブラックホール以外のあらゆる天体や物体が消えていくと考えられています
5. ブラックホールの消滅
飲み込むものがなくなったブラックホールは 果たして同じ大きさのままでいられるのでしょうか?
実はそうではなく"蒸発"していくと考えられています
ブラックホールの蒸発とは
ブラックホールが光や電子を放出して少しずつ軽く 小さくなっていくことを意味します
これはスティーブン・ホーキンス(1942~2018)
によるミクロな観点での物理学「量子論」に基づいて理論的に予言されています
例えば炭などの物体は熱されると赤く光ります
これは「熱放射」と呼ばれる現象です
通常のブラックホールの温度はきわめて低いですが
とてつもなく長い時間を経て この熱放射のような現象によって蒸発が起きるとされているのです
蒸発していくブラックホールは だんだんと軽くなっていきます
軽くなればなるほど温度は上昇し 蒸発のスピードは加速していきます
そして最後には ものすごい勢いで光や素粒子を吐きだしたあとに消滅
これには10の100乗年ほどの時間がかかるとも言われています
蒸発した後 そこにはなにが残るのか
これには興味深い仮説もありますが それはまたいつか
あとがき
今回は 宇宙のおわりのシナリオ についてのお話でした
最後までご覧いただき ありがとうございました
個人で活動しております。 ご支援いただける方はぜひお願いいたします◎
