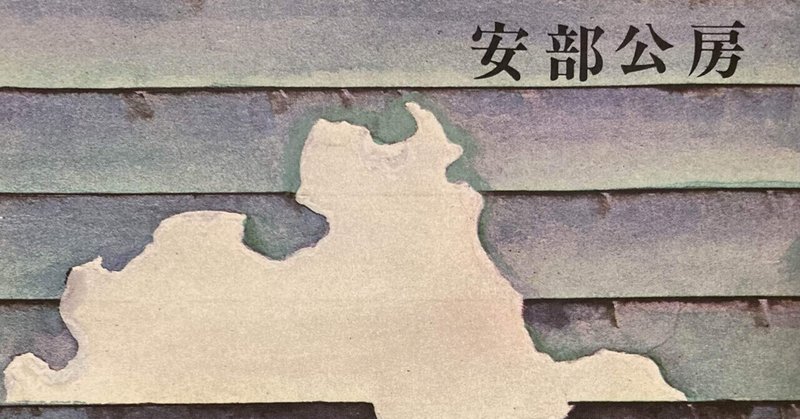
第四間氷期
"予言機械をもつことで、世界はますます連続的に、ちょうど鉱物の結晶のように静かで透明なものになると思いこんでいたのに、それはどうやら私の愚かさであったらしい"1959年発刊の本書は、万能の電子頭脳を巡る話から"日常・現在と未来の断絶"を描いた『日本で最初の本格的SF小説』
個人的に著者作は割と好きで読んできましたが、本書は未読だったので手にとってみました。
さて、そんな本書はアメリカ、ソ連が睨み合う『冷戦時代』作中では両国は核ミサイルや宇宙開発競争ではなく【万能の電子頭脳『予言機械』の開発競争】を繰り広げているのですが。そんな中で、日本で予言機械を研究開発しているも、成果不足から開発中止に追い込まれそうになっている博士『私』が、実験台として【平凡な人間を無作為に選んだ方が有用】だと考えて、ある中年男性を選んだことから【事態は意外な方向へと】向かっていくのですが。
まず、時代や『電子頭脳』といった設定、登場人物の台詞回しに【AIやロボットが当たり前に語られる】2022年の令和から眺めると、読み進める中で古臭さはやはり感じてしまいますが。それはそれで【レトロ感があって懐かしく、魅力的】だとも思いました。
また本書の中盤からはカレル・チャペックの『山椒魚戦争』を彷彿とさせる予想外の急展開となるわけですが(著者は絶対に既読だと思う)著者作は『いつも後半駆け足だな?』と感じた一方で、未来を現在から見て肯定的or否定的なイメージで判断する議論に【疑問や違和感を覚えた著者】が未来を予想できる『予言機械』をわざわざ登場させた上で【あえての断絶を描いた】本書。著者らしいユニークな実験小説だと思いました。
著者の実験小説ファンの方はもちろん、レトロ感ある日本SFとしてもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
