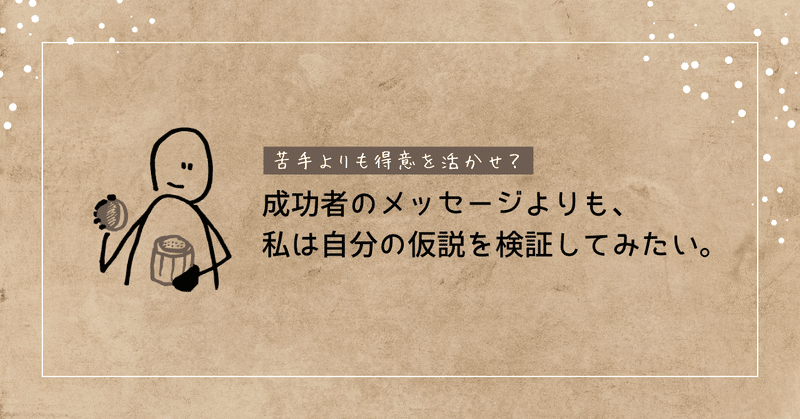
苦手よりも得意を活かせという成功者の助言より、まずは自分の仮説を検証してみたい
自分の得意なことは何なのか。
自己分析はもはや趣味なので、たくさん向き合ってきた。自分にはこんな一面がある、こんなことが評価される、自然にできる、結果が出せる、人に貢献できる。
あこがれる人に共通するのは、自分の強みを理解し、育て、得意なことで他者へ貢献し続けることで、自然と人に囲まれてることだった。
ウェルビーイングの研究でも、組織論の観点でも、自分の強みを理解し、活かすことは非常に重要であると明らかになっている。どの自己啓発本を読んでも自分の弱みに向き合ってもせいぜい平均にしかならないので、自分の強みを伸ばし続けることが大切だって言ってる。
きっと自分は、人と比較して
・相手のことをわかってあげる共感力がある
・話を構造化して、整理する力がある
・本人も気づかないような微妙な心の変化に気づく力がある
・ある程度、継続的に習慣化する力がある
・変化に対してポジティブに受け入れられる力がある
・大切なことはとことん丁寧に扱う力がある
・丁寧に振り返りを行い、改善し続ける力がある
・他者のことを素直にほめる力がある
・細かく、丁寧に対応し、進めていく力がある
・軸を持ちながらも、しっかりと方向転換する力がある
・自分の気持ちを伝え、人を巻き込む力がある
昔に比べ、自分の強みがすらすら出てくるようになった。
多分自己分析のワークの資料とか出せば、もっときれいに出てくるはず。それくらいここ最近は自分の強みを愛して生きてきた。
◎それでも自分はこれから「苦手」と向き合いたい….。
なぜなら、
①苦手には自分の願いのヒントが隠れているのではないか
②自分の根本的な自信には苦手を乗り越える経験が必要ではないか
という仮説が生まれたから。
自分が苦手なもの
・人と食事をすること
詳細は省くけど、小・中学生のころは給食の時間がすごく苦手だった。食べるのが遅いからという理由で、席は孤立させられたり、いつもみんなが外で遊んでいる間も一人食べていたり、三者面談は給食のトピックばかり。

そんな自分が今、料理に挑戦している。
きっかけはアフリカ村での生活。自分たちが食べるものは、自分たちで採取したり、地域の人に分けてもらう。毎日おいしいものが出てきて、食事に何時間も費やすこの日常を過去の苦しかった自分に届けたい。
・1on1で話すこと
TABIPPOの活動が終え、起きてる時間ずっとTABIPPOのことやってただろってくらい(少し盛った)だったので、活動が終えたときに何をすればいいかわからなくなった。

寂しさを埋めるため、そして次の一歩を考えるために1on1を始めた。はじめは話すことメモしたり、たくさん準備して臨むほど緊張。それが今では月平均3~5名程度伴走支援のお手伝いがあるのでびっくり。
・場をまとめる(目立つ)こと
給食の経験で、自分はこれ以上目立ってはいけないと思った。できるだけ迷惑をかけないように、人並みにできるようにならないといけない。集団主義の日本において、グループの平均を目指し、大多数を選び、常に普通を考え、目立つ行為を避けてきた。

そんな自分が実はファシリテーターとしての顔があります。少し前までは月2-5程度の場をオンライン/ オフラインともに作り、お金をいただいていました。
「苦手」って何だろう。
気づけば苦手なものが自分のアイデンティティになりつつある。
苦手なものは、人との関係をはぐくむきっかけ。
自分にはできないものと対峙したとき、自分は人の手を借りてどうにかしてきた。コミュニティの立ち上げ、無人島貸し切りでのリトリート、キャンピングカーでの協賛イベント、フィジーでのビジコン優勝等々、自分のレベルを超えた挑戦も多かった。
それは、自分のやりたいことを言い続けたことと、それを実現してくれる人と出会いに行き続けたことが大きかった。
苦手なものは、自分が本当は大切にしたいもの
すべてだとは思わないけど、苦手なものには自分の大切にしたいが隠れているのではないかと思っている。
例えば、人と深く話すこと。
普通でありたいと思っていた自分にとって、深いところまで心の中に入られるのを防ごうとした。でも、本当は人と心から分かり合いたいという願いからコーチとしての顔を持ちました。
例えば人と食事をすること。
当たり前に人と食事することがなかった自分にとって、食は苦しいもので決して楽しみではなかった。でも、本当は人と楽しく食卓を囲いたいという願いから最近料理にハマっています。
もしかしたら、苦手は「できない」から生まれるわけではないのかもしれない。
むしろ自分の欲求が強く、本当に大切にしたいもの。でも、世の中の当たり前と自分のこだわりがぶつかり、次第に苦手意識を感じるようになる。
この「苦手」と思っているものを乗り越えていく先に、真の自信があるのかもしれない。
少し余談
最近、DANROという対話のスクールに通い始めました。
第1回
内向き(内省好き)にも外向き(旅好き)にも目が向く自分は「何か」を探していることに気づきました。
第2回
自分の人生を推し進めていく「人」を捜し求めているのではないかと仮説が立ちました。
第3回
自分の目指すところには、自分の信じるものを貫く推進力と、何度でも方向転換する修正力を通じて、必要な出会いを生み続けることが必要ではないかとなりました。
そして今、自分の今信じるものを見つけるフェーズ。
それが今回の苦手なものには、自分が本当は大切にしたいものが隠されているのではないかという仮説です。
つまり
ざっくばらんに話したので要点をまとめると、
苦手=「できないこと」よりも、「大切なもの」のヒントが詰まったもの
自分が大切にしたいものが隠れているのに、多くの人がそこに向き合いきれない。だから、どこか生きずらさを感じるのかもしれない。
大前提、自分の得意を活かすことは間違っていないと思うし、基本正しいと思っている。でも、それで苦手と向き合わないのは、自分の大切にしたいことをどこかに置きながら日々過ごしているような感覚。
避けていたものリスト
◇苦手→好きになったものたち
・対話(現在スクールへ通ってる)
・場づくり(仕事も少しずつ)
・旅(年間100日以上旅人生活)
・朝活(朝型ブランディングされてる)
◇一歩踏み出したものたち
・海外(一歩目は踏み出した)
・読書(読み物リトリート実施)
・プレゼン(アワードで200名の前で)
・筋トレやストレッチ(緩くやっている)
◇最近力を入れ始めつつあるもの
・子供(最近よく遊んでる)
・食事(人にふるまえるように)
・表現(自分の表現方法を模索)
・パートナーシップ(そろそろ踏み出したい)
・教養学習(診断士勉強)


そして、この「苦手」と思っていたものも実は自分が本当に大切にしたいものだったんだと気づけること。それからだんだん好きになり、気づけば得意になっていく。
苦手だと思ってたものを乗り越えていく経験を重ねれば、自然と自分でも大丈夫。自分なら大丈夫って思えるかも。2024年に立てた目標も4か月経つことでかなり重なってきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
