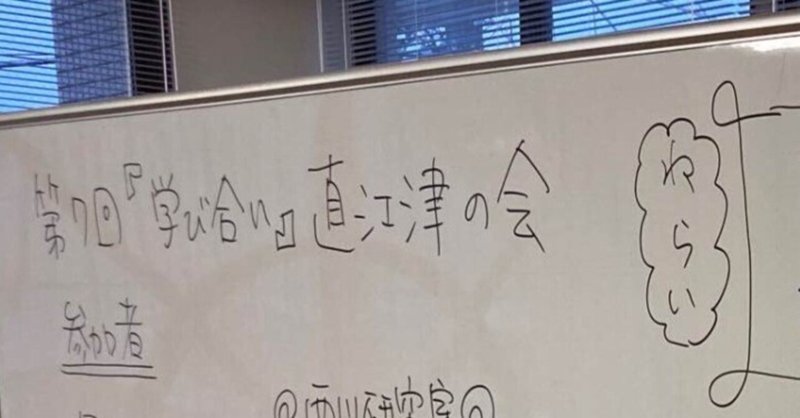
第7回『学び合い』直江津の会
学びの交流館がいっぱいだったのでレインボーセンターの第3会議室で開催しました。
話に花が咲き毎度のように時間が不足して終わりました。
最初は硬い雰囲気でしたが、それぞれの話に聞き入る感じで終了できてよかったなあと思います。
今回は西川研究室院生4人、OB1名、カウンセラー・コーチの方1名+私の7名でした。
参加者の一人のお話から様々な話題へと転換しました。
・学校の相談室では寄り添うべき「本当に困っている人」にアクセスが難しい。
・人がベールを被らないでいい、リラックスして、楽でいられる場所が必要。
・子どものためのフリースクール、大人のためのサードプレイス、と分けるのでなく、ごちゃ混ぜで自然体でいられる場所がより良いのではないか。
・それを設計する上では、学校法人は費用がかかりすぎるため、どのような形で実現していくのか知恵が必要。
・県内でも三条や安塚などで志を持ち活動されている人が大勢いる。
・そうした動きを具体化、加速させていく上では行政、そしてそれに影響する議会議員との繋がりが必要。
・地域性はそれぞれあり、保守的な地域では移住した人こそが地域を変える活動に尽力している。
・その時はやっている活動はもう遅い、先を見て提案する必要があるが、先を見るが故に理解されにくい部分もあり難しい。例えばyoutuberは最初は懐疑的な視線が多かったが、認知された今始めるには時期が遅すぎるようなこと。
・本気を伝えようとすれば伝わる、本気じゃなきゃ絶対に伝わらない。
・計画された偶発性理論を体現するには、自分が願っていることや思い描いていることを言葉にしていくことがかなり大切。
「歌いたい」と言っていた参加者の院生の一人はこの後、イベントに出かけて行って飛び込みで歌を歌い「夢」を一つ叶えました。
自分のコアはなんだろうかなあと皆さんのお話を聞きながら考えていましたが、「身近な地域コミュニティの居心地がベストの状態でない」ことが一つありそうだとわかりました。
これを一つ前進するための行動を考え、初めてみようというのが今日の私の大きな学びです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
